菅野 洋充(宅建士・リフォームスタイリスト)
社会に必要とされ人に役立つ企業を目指します
CLOSE
公開日:2024年7月9日
土地の価格は人が集まれば高くなる。こんにちは、REDS不動産流通システムの宅建士、宅建マイスターの菅野洋充です。
今回は、土地価格への影響が大きい東京近郊の新線、新駅に関する情報を書いていきます。

東京メトロ東西線に直通する第三セクター鉄道の東葉高速鉄道に、2028年度の予定で新駅が誕生します。
場所は「東海神駅」と「飯山満駅」の間で、この新駅周辺が土地区画整理事業および船橋市立医療センターの移転建て替え事業を中心とした「ふなばしメディカルタウン」構想のまちづくり地域となっています。
■ふなばしメディカルタウン構想(船橋市ホームページ)
土地利用計画図を見ると、中高層住宅地、低層住宅地もあり、宅地開発は期待される場所となることでしょう。現時点では宅地なども開発途中で、医療センターの移転開業は2027年度内予定とのことです。
JR東海道線の神奈川県内の新駅となる「村岡新駅(仮称)」は、ことしの5月に神奈川県・藤沢市・鎌倉市・JR東日本が協定を締結し、正式に駅設置が決定しました。この駅は「大船駅」と「藤沢駅」の間に設置予定で、本駅と湘南モノレールの「湘南深沢駅」の間は「村岡新駅周辺地区まちづくり」として開発予定となっています。
村岡新駅はもともとJRの貨物駅跡地で、湘南深沢駅西側の開発地はJR大船工場の跡地となっています。JR大船工場跡地は以前より開発計画がありましたが、正直なところ全く進んでいなかったため、この新駅開業により広大な遊休地を何とか開発したいという自治体とJRの思惑が感じられます。こちらの新駅は、2032年の開業を目指しているとのことです。
■東海道本線大船・藤沢間村岡新駅(仮称)設置に伴う工事等の施行に関する協定の締結について(PDF)
■村岡・深沢のまちづくり≪両地区一体のまちづくりと新駅設置≫(PDF)
有楽町線の豊洲駅は、2面4線構造になっています。もともと、この新線は、1972年の「都市交通審議会答申第15号」に8号線として豊洲から亀有までの計画が提案されたのが始まりとなっています。2022年に国交大臣の事業認可がおり、正式に事業化となりました。
豊洲駅と住吉駅の間の駅は「枝川駅(仮称)」「東陽町駅」「千石駅(仮称)」の3駅が設置される予定で、「東陽町駅」で東京メトロ東西線と乗り換えが可能になります。
「枝川駅(仮称)」は江東区枝川2丁目付近に、「千石駅(仮称)」は江東区千石2丁目付近に設置予定です。どちらの地区も、最寄り駅まで徒歩15分以上の鉄道空白地帯でしたので、周辺の不動産価格への影響は非常に大きいものと思われます。また、どちらも周辺は準工業地域ですので、マンションが多く建築される可能性があります。
■有楽町線延伸(豊洲・住吉間)及び南北線延伸(品川・白金高輪間)の鉄道事業許可を申請しました。
リニア中央新幹線の神奈川県駅(仮称)は、JR横浜線・京王相模原線「橋本駅」の南側で現在、建設工事中です。当初は2027年度開業予定だったのが、工期の大幅な遅れにより2027年度の開業を断念することがJR東海より発表されています。
すでに周辺では開発が進んでおり、タワーマンション建築や大規模な宅地開発がなされています。開業予定の延期が周辺地価に悪影響となっているかというと、どうやらそうでもなさそうです。
本駅が建設中の相模原市は、2010年に政令指定都市となり発展が続いています。橋本駅の隣にある相模原駅の北側に米軍基地がありますが、2014年に日本に一部返還され、2024年度中に土地利用計画が策定予定となっています。また、それに伴い、小田急多摩線の延伸計画も持ち上がっており、橋本駅から相模原駅にかけては、今後も発展が見込まれる地域と考えられます。
新駅建設は間違いなく周囲の不動産価格に影響を及ぼします。ただ、駅ができたばかりの時期は、商店や生活施設がまだ十分にない場合もあり、それほど便利でないという弱点もあります。
ただ、そういった時期であれば、まだ価格も大きく値上がりしていないことが多く、将来の資産価値向上を考えて住宅を購入されたいという方に向いているかもしれません。利便性が上がっていくと同時に不動産価格も上がってくるわけですので、そのあたりのバランスをどう考えるかは、それぞれのお考えによるかと思います。
REDSでは、そういった地域での不動産購入、売却のご依頼も、もちろん対応可能ですので、ぜひご利用をご検討ください。
公開日:2024年5月31日
REDS不動産流通システム、宅建士・宅建マイスターの菅野洋充です。
今回は、2024(令和6)年3月29日に「特定都市河川および特定都市河川流域」の指定を受けた「中川・綾瀬川」(埼玉県~東京都)について、流域周辺の不動産への影響を考えます。

(写真はイメージです)
「特定都市河川」とは、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき、国土交通大臣または都道府県知事が指定する河川のことです。
本法第二条にその定義があります。
“この法律において「特定都市河川」とは、都市部を流れる河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川をいう。以下同じ。)であって、その流域において著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあるにもかかわらず、河道又は洪水調節ダムの整備による浸水被害の防止が市街化の進展又は当該河川が接続する河川の状況若しくは当該都市部を流れる河川の周辺の地形その他の自然的条件の特殊性により困難なもののうち、国土交通大臣又は都道府県知事が次条の規定により区間を限って指定するものをいう。”
その川の周囲の都市化が進み、ダムや堤防などの一般的な治水事業のみでは洪水被害を防ぐことが難しく、さらなる治水対策が必要な川であると国や都道府県で指定された河川が「特定都市河川」です。
「特定都市河川流域」は「特定都市河川」の“流域”をさすわけですが、「流域」ってなんでしょうね。
コトバンクの説明文です。
“河川の流れに沿う地域。また、河川に流れ込む降水の降り集まる地域。集水地域。その河川の分水界に囲まれた地域。”
「その土地に雨が降ると○○川に流れ込むよ、というのが○○川流域」というわけです。ですので「特定都市河川」に水が流れ込む土地が「特定都市河川流域」として指定されます。
この法律によって「面積1000㎡以上の土地の雨水の浸透阻害行為」が制限されます。具体的には、以下のような行為を行う場合には都・県知事の許可が必要となります。
と、ここまでは足立区や埼玉県のホームページを見ればだいたいわかることを書きました。では、流域の宅地化が、どんな感じで進んだのかを八潮市を一例にて見てみましょう。
国土地理院地図で年代別の航空写真を見ることができます。これは1979(昭和54)年~1983(昭和58)年の間に撮られた、つくばエクスプレス「八潮駅」周辺の航空写真です。

見てのとおり、農地だらけです。昔は市街化調整区域だったと聞いています。綾瀬川が1980(昭和55)年から15年連続ワースト1の汚さとなったその最初の時期に撮られたものです。中川の水が茶色です。
続きまして、これは1984(昭和59)年~1986(昭和61)年の航空写真です。

首都高速6号三郷線が開通しています。でも周りは農地が多く、この頃から、都内から高速道路を使って運びやすくなったということで、産業廃棄物置場が増えてきたそうです。
そして、つくばエクスプレス開通して2年後になる2007(平成19)年の航空写真がこちら。

駅ができて、開発が進んでいく様子が見えます。農地はどんどん減っていきます。
そして最後に2019(令和元)年の航空写真です。

農地はどこ?って感じで、完全に市街化してしまいました。ちょっと緑が見えますが、区画整理事業地ですので、ここにもこれから建物が建っていきます。
と、八潮市南部の八潮駅周辺の開発の変遷をご覧いただきましたが、これ以外にも中川・綾瀬川流域では、例えば八潮駅と同じつくばエクスプレスの「六町駅」周辺や、JR武蔵野線「越谷レイクタウン」「吉川美南」「新三郷」などの大型宅地開発地があり、流域内で宅地化が急激に進んでいることがお分かりいただけると思います。
宅地化が進むと、表土が減ります。表土が減るということは、雨水が浸透する土地が減るということになります。そのため、下水道などの排水施設が十分でない場合に、大量の雨水を土に浸み込ませることができず、宅地からあふれた水で内水氾濫を起こすことになります。
こちらのページに、そういった過去の事例があります。
直近ですと2015(平成27)年に越谷市で大規模な床上浸水、道路冠水が起こっています。八潮市では豪雨のときにいつも冠水する交差点があり、冠水した交差点を自動車がのろのろと越えていく動画がSNSにアップされていたりします。
今回、中川・綾瀬川が特定都市河川に指定されたことにより、流域自治体で今年度に流域水害対策計画が策定されます。そして、中川・綾瀬川流域でこの法律が施行されるのは2025(令和7)年7月1日からとなります。施行後には前に説明した「雨水浸透阻害行為の許可」だけでなく、流域内の開発行為は流域水害対策計画に沿った形で行うことが求められます。
先に特定都市河川に指定されている「鶴見川」流域では、
が行われています。中川・綾瀬川流域も同じような形で、建築・開発時に雨水を土地から流出させない対策が求められるものと思われます。
八潮市南部では現在、下水道の整備が進められています。東京都隣接地区で何故か下水道の整備が遅れていましたが、もともと八潮の市街地は市役所周辺から整備されていて、現在整備している地区は八潮市のいちばん端にあるため整備が遅れていたものと思われます。
しかし、道路冠水がよく起こるのは、下水道が整備されているはずの古い市街地方面です。新しい開発地である八潮市南部には、洪水対策用の調節池などが数多く作られていて、下水道も最新の設備となっているため、冠水などの話を聞くことはありません。これは「越谷レイクタウン」についても同様です。
「市街化≒雨水浸透阻害行為」ではあると思いますが、きちんと対策をしたうえでの開発はむしろ水害対策になると私は思いますので、下水道だけでない最新の水害対策を備えた開発分譲地はより安全な住宅地になることと思います。
今回の指定をきっかけに、より安全で住みやすい土地となってくれると思いますので、皆さん、家を買うときは新しい開発地をご検討してみてはいかがでしょうか。
最終更新日:2024年5月1日
公開日:2024年4月23日
REDS不動産流通システム、宅建士・宅建マイスターの菅野洋充です。今回は昨今、世間をにぎわせている「クルド人問題」で揺れる埼玉県川口市で見られる事象について考えてみます。

先日、埼玉県の人口統計が出ました。埼玉県は人口が減っているようです。統計をみると、実は“自然増減”の「自然減」つまり出生者数に比べ死亡者数が多いことが原因とわかります。これは、いわゆる「少子高齢化」の影響であると考えられます。
「自然減」が多いのに対し、“社会増減”をみると埼玉県は転入超過で、他県から流入が比較的たくさんあることがわかります。「転入超過」つまり転出より転入の多い市区町村ランキング(さいたま市は区で分けてみます)は以下のとおりです。
1位:川口市
2位:さいたま市大宮区
3位:さいたま市緑区
4位:・さいたま市西区と朝霞市(同数)
※上記データの出典は、埼玉県ホームページ「埼玉県推計人口」より
川口市は現在、いわゆる「クルド人問題」が世間で騒がれていますが、それでも転入超過(出ていく方より引っ越してくる方が多い)です。その理由はどのようなものでしょうか。主な理由を4つ考えてみました。
川口市は荒川を挟んで東京都の足立区や北区に隣接しており、地理的に東京都心に近い位置にあります。市内には京浜東北線や、東京メトロ南北線に直通する埼玉高速鉄道が通っているため、東京都心へのアクセスが非常に便利です。これらの鉄道路線を利用することで、多くの職場や商業施設、文化施設へスムーズに移動できるため、通勤や日常の買い物、レジャーにも困りません。
このように〝ほぼほぼ東京〟にもかかわらず、川口市は東京都内の地域と比較して家賃や不動産価格がかなり安い傾向にあります。特に東京の中心部の高い家賃や不動産価格から逃れたいと考えている人々にとって、川口市は魅力的な選択肢です。そのため、都心からのアクセスが良好な一方で生活コストを抑えたいと考える人々が、移住を検討するケースが多く見られます。
このような利点により、川口市は東京都心に近接しながらも、より手頃な生活コストで生活できる場所として、多くの人に選ばれています。その結果、住宅需要が増加し、さまざまな居住地域や商業施設が発展しているのです。
川口市は、工業が盛んな地域として知られています。この市の用途地域に指定されている工業地域は約364.8ha、準工業地域は約1014.2ha、工業専用地域は約30haで、合計で約1409haにもなります。川口市全体の面積が61.97k㎡(6197ha)なので、市の約22%が工業関連の用途地域であることになります。
さらに、川口市は東京都に隣接しており、首都高や外環自動車道などの自動車交通網が発達しています。このため、倉庫や流通センターが多く設置され、就業機会が豊富です。日中の就業人口が増えることで、飲食業をはじめとしたサービス業も発展し、市内の経済活動がさらに活発になるという好循環が生まれています。
このような状況から、川口市は工業に加え、物流やサービス業が集まるビジネスの中心地としても機能しているのです。
川口市は外国籍居住者の割合が非常に高いことで知られています。川口市には多様な国籍のコミュニティが存在し、それぞれの文化や歴史が色濃く反映されています。
映画『キューポラのある街』で朝鮮帰国事業に関連するシーンが描かれていたように、川口市には歴史的に韓国・朝鮮系のコミュニティが根づいていました。その後、蕨駅近くの芝園団地で中国人コミュニティが発展、定着し、西川口駅西口は現在では「ガチ中華」で有名な街となりました。
最近ではクルド人と地元住民の軋轢が表面化しています。クルド人の国籍はトルコですが、川口市の外国人住民数をみると、多い順に以下のようになっています。
1位:中国 24193人
2位:ベトナム 4916人
3位:フィリピン 2892人
4位:韓国・朝鮮 2861人
5位:ネパール 1509人
6位:トルコ 1197人
※上記データの出典は、川口市ホームページ「川口市統計書」より
人数でみるとトルコ籍の人は中国籍の20分の1しかいないのですが、ちょっと悪目立ちしてしまっているというところかと思います。
ただ、ひとついえるのは、言葉の通じない外国で、同胞の人たちが集まるコミュニティというのは非常に重要だということです。言葉の壁や文化の違いを一緒になって乗り越え、支援し合える環境があることで、新しい国での生活が格段に楽になります。コミュニティが存在することで、新たに移住してくる人々が集まりやすくなるという好循環も生まれます。
今後も川口市は、外国人(特にアジア系の人たち)にとって故郷のような安心感を提供できる特別な場所でありつづけると思います。
川口市内には、JR京浜東北線・JR武蔵野線・埼玉高速鉄道という3路線の駅が計8か所(川口駅、西川口駅、東川口駅、川口元郷駅、南鳩ヶ谷駅、鳩ヶ谷駅、新井宿駅、戸塚安行駅)あります。また、市内にはありませんが、隣接して利用可能な駅として蕨駅、東浦和駅、南浦和駅があります。
京浜東北線・埼玉高速鉄道は南北の移動、武蔵野線は東西の移動を担っており、東京や埼玉北部だけでなく、東京市部や千葉方面にもつながっていて各方面からの移動も容易です。
また、市内の道路網も充実しており、首都高や外環自動車道が整備されたことにより都内だけでなく東北・常磐・関越方面への自動車移動の利便性も兼ね備えています。移動がしやすいことは、周囲の市町村だけでなく少し離れたところの住民も引っ越しを考えやすくなります。
川口市に人口流入が起こる原因を考えてきましたが、仕事、交通、コミュニティが地域発展に必要不可欠であることを示唆していると思います。人口が減っている自治体は、上記の3つについて、現状で足りないところがないか確認し直すことで、発展への道筋が探れるかもしれません。
公開日:2024年3月15日
REDS不動産流通システム、宅建マイスター・宅建士の菅野です。とうとう日銀総裁も認めるインフレ基調がやってまいりました。
▼NHK 日銀 植田総裁 “2%の物価目標少しずつ確度高まる”
▼NHK 日銀総裁 “今後も物価上昇続く デフレでなくインフレ状態”
今回はインフレ時に不動産を購入する場合の注意点と、インフレでどんどん不動産価格が上がっていく中、どうしたらできるだけ安く購入できるかを考えていきます。

インフレとは物価が上がっていき、相対的に貨幣価値が下がっていくことです。このため単純にお金を貯金していると、貯金したお金の価値はどんどん下がっていくことになります。例えば、2%の物価上昇率が続いた場合、100万円のものは10年後には122万円を出さないと買えないわけですが、100万円をタンス預金していた場合、貨幣価値は81.9%となり、約18%分も価値が目減りしてしまいます。
そのために人はお金を価値の下がらない、むしろ価値が上がってくれそうなものに変えようとします。インフレに強い資産として挙げられるのは、株や投資信託などの有価証券、外国債などの外貨建て資産、不動産や金などの現物資産、仮想通貨などといわれています。
そういったことで、インフレのリスクヘッジとして不動産を購入される方が増え、そのためにさらに不動産価格が上がるというスパイラルが起こっていくわけです。
インフレ基調下で不動産購入を検討する場合、以下の点に注意することが重要です。
1. 金利の変動に注意:インフレ時には中央銀行が金利を引き上げることが一般的です。これは、住宅ローンの利率も上がることを意味し、購入後の支払いが予想よりも高くなる可能性があります。金利の将来的な動向を考えて、固定金利と変動金利のどちらがより適しているかを検討することが大切です。金利がまだ低いうちに固定金利でローンを組むということも、今後は検討するに値すると思います。
2. 価格の適正性の判断:これは非常に難しいところですが、不動産価格が大幅に上昇している場合、その価格が適正であるかどうかを慎重に評価する必要があります。市場価格が将来的に下落するリスクを考慮し、長期的な視点で購入する価値があるかどうかを判断することが重要です。立地、環境、マンションのグレードや設備など、バリューのある物件を選ぶことも重要です。
3. インフレによる物価高騰の影響を考慮する:インフレは物価が上昇しますので、もちろん不動産の維持管理コストも上昇します。税金、保険、修繕費用などのコストが増加する可能性があるため、これらを将来の費用予測に含める必要があります。
4. 賃貸市場の状況を理解する:投資目的で不動産を購入する場合は、賃貸市場の動向を把握しておくことが大切です。インフレにより賃料が上昇する可能性があるものの、同時に空室率が高くなるリスクも考慮する必要があります。物件周辺の賃貸需要に関する情報は鵜の目鷹の目で確認することが必要です。
5. 流動性を確保する:不動産は流動性が低い資産です。将来的に資金が必要になった場合に素早く売却することが難しいかもしれません。資金をすべてつぎ込むのではなく、リスクヘッジとしての現金の用意はされておくのが吉です。
6. 専門家の意見を求める:不動産市場は複雑であり、地域によって異なる特性を持っています。不動産エージェントやFPなどの専門家に相談し、適切な判断を行うための支援を求めることが推奨されます。REDSではそれぞれの担当者が複数の資格をもち、お客様にさまざまなアドバイスを行うことが可能です。
7. 長期的な視野を持つ:不動産への投資は、一般に長期的な取り組みとなります。短期的な価格変動に一喜一憂するのではなく、長期的な価値の向上を見据えた判断を行うことが大切です。
正直なところ、インフレ時はあからさまな売り手市場となってしまいがちで、価格を安く買うというのは非常に難しいときであると言えます。そんな時期でもできるだけの努力をして、なるべく安く買いたいというのが人間心理かと思います。その努力のいくつかを書いていきます。
1. 穴場を探す:不動産市場は地域によって大きく異なります。広範囲にわたって市場調査を行い、価格がまだ比較的安定しているエリアや、価格が下落傾向にあるエリアを見つけ出すことが重要です。また、売りに出されてから時間が経過している物件は、価格交渉の余地がある場合が多いといえます。
2. 未公開物件を探す:まだ一般に公開されていない、いわゆる未公開物件を探すことも一つの方法です。これらの物件は競争が少ないため、より有利な価格で購入できる可能性があります。不動産エージェントに連絡を取り、こうした機会がないかを探ってみましょう。ただ、世間でいわれる「未公開物件」の99%は実は「未公開」でないこともご注意ください。本当の「未公開物件」に当たる確率は、非常に低いといえます。
3. 強固な資金計画を立てる:現金での購入または大きな頭金を用意することができれば、売主にとって魅力的な買い手となります。売主は、購入手続きがスムーズに進む現金購入者を好むことが多く、価格交渉において有利な立場に立てることがあります。また、現金はいちばん強いのですが、住宅ローン事前審査を自分の借りられる最大の金額で通しておくというのも一つの方法です。強い与信は交渉のための要素として持っておくと有利です。
4. 価格交渉に取り組む:売主の事情を把握し、売却を急いでいるかどうかを判断します。急いでいる売主であれば、価格交渉の余地があります。また、物件の問題点を指摘して価格を下げさせる戦略もある程度は有効ですが、やりすぎると売主の機嫌を損ねて逆に購入できなくなるような事態も起こりますので、注意が必要です。
5. 適切なタイミングを見極める:不動産市場には季節性があります。たとえば、梅雨時期(6~7月)や初冬(11~12月)は購入希望者が減少する傾向にあるため、売主が価格を下げる可能性が高くなります。市場の動向を注視し、購入のタイミングを見極めることが重要です。
6. 仲介手数料やその他の購入時費用を抑える:どうにも価格交渉がうまくいかないという場合は、仲介手数料だけでも抑えるしかありません。REDSを利用すれば、仲介手数料については必ず安くできます。また、それ以外に登記費用を抑えるため、比較的報酬の安い司法書士を使うなども検討するとよいでしょう。住宅ローンの諸費用については、最初に大きく支払うほうが、借入期間によっては安く済む可能性もありますので、住宅ローンに詳しいエージェントにご相談することをお勧めします。
REDSなら、経験と知識が豊富で交渉やアドバイスができるエージェントがいます。もちろん仲介手数料は必ず割引、最大無料ですので、それだけでも大きな節約になります。我田引水なブログではございますが、REDSはインフレ基調でもずっとお得でお客様本位を貫いてまいります。
公開日:2024年2月6日
REDS不動産流通システム宅建士、宅建マイスターの菅野です。今年2024年1月1日の午後4時10分、石川県能登地方(北緯37.5度、東経137.3度)の深さ16㎞(暫定)地点を震源とするマグニチュード7.6(暫定)、最大深度7を観測した地震が発生し、現在も被害が続いています。
※内閣府| 令和6年能登半島地震による被害状況等について
1月26日の時点で死者は236人、そのすべてが石川県で亡くなっています。まだ公式の発表はありませんが、死因は家屋倒壊による圧死が多くを占めているとの報道があります。この倒壊の原因として「キラーパルス」という聞き慣れない言葉が取りざたされています。「キラーパルス」とはいったい何なのでしょうか。また地震から家屋倒壊を防ぐにはどんな対策があるのでしょうか。

今回の報道で気になる記事があったのでリンクを貼ります。
「直接死」過去3番目の災害に、原因は「キラーパルス」 能登半島地震 – 産経ニュース
この「キラーパルス」というものが今回の家屋倒壊の甚大な被害につながっているそうなのです。
「キラーパルス」とは、地震の揺れの周期のうち、1〜2秒周期のやや短い震動のことを指します。この揺れの周期は、地震学において「やや短周期」と分類されていて、このような地震の揺れの周期が建物の固有周期に近いほど、建物が大きく揺れやすいとされています。この周期の揺れが、どうやら木造の低層家屋の固有周期に近づくと建物に「共振」が起こり、大きな揺れとなって家屋倒壊へとつながっていくようなのです。
地震の「周期」とは、地震波が1往復するのにかかる時間のことです(ちなみに、一定期間中に何度振幅があったかを示すのが「周波数」で、「周期」の逆数となります)。
一般的に、地震波の周期が長いほど揺れがゆっくりとした大きな揺れになります。このようなゆっくりした周期の振動を「長周期振動」といいます。逆に「キラーパルス」と呼ばれる周期の振動は「やや短周期」の振動となります。
地震の揺れにはさまざまな周期があり、それぞれの建物には「固有周期」と呼ばれる、特定の周期で最も大きく振動する性質があります。この固有周期は、建物の構造や素材によって異なります。一般的に、建物の高さが高くなるほど固有周期が長くなるとされています。
低層家屋は1~1.5秒の間の周期に共振するそうです。高層マンションなどは固有周期が4~7秒ほどあり、低層家屋とは逆に「長周期振動」によって共振するといわれています。
戻りますが、木造の低層家屋は、固有周期が1〜1.5秒の範囲にあることが多いため、地震による1〜2秒周期の「キラーパルス」が発生すると、これが家屋の固有周期と一致することがあります。この一致が起きると「共振」という現象が発生します。
共振は、建物が自然に持つ振動の振幅を増幅させ、これによって建物が大きく揺れることになります。この強い揺れが原因で、木造の低層家屋が倒壊する危険性が高まります。
簡単に言うと、地震の「キラーパルス」は、特定の周期の揺れであり、この揺れが建物の固有周期と一致すると、建物は非常に大きく揺れ、結果として倒壊につながるリスクが高まるということです。
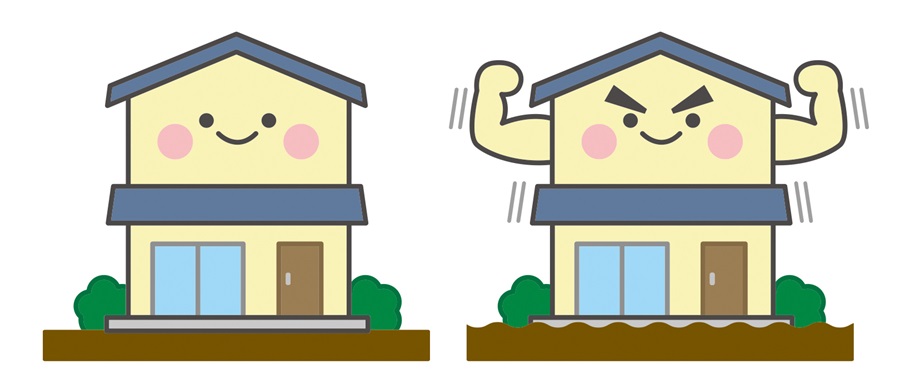
キラーパルスへの対策=地震への強靭化対策といえると思います。その主な対策を6つ紹介します。
日本の建築基準法では、耐震性能を3つの等級で評価しています。耐震等級3は最も高い等級で、耐震等級1の1.5倍の強度を持つ建物とされています。
耐震等級1(建築基準法で定められている最低限の耐震性能を満たす水準)とは、いわゆる「新耐震基準」のことで、
・数百年に一度程度の地震(震度6強から7程度=阪神・淡路大震災や2016年4月に発生した熊本地震クラスの揺れ)でも倒壊や崩壊はしない
・数十年に一度発生する地震(震度5程度)は住宅が損傷しない程度
の建物とされています。そのさらに1.5倍の強度をもつわけで、これには、強固な構造体や耐震性に優れた材料の使用などが必要となります。
ダンパーとは建物の揺れを減衰させる装置です。これらは建物の主要な構造部に取り付けられ、地震時の振動エネルギーを吸収し、建物の揺れを抑制します。ダンパーには液体を用いたもの、金属やゴムを用いたものなど、さまざまな種類があります。
制震テープとは、住宅の地震対策の一つで、地震の揺れを軽減するために柱や梁といった軸材と面材を接合する際に、間に挟むように貼る粘弾性体を厚さ1mm、幅30mmまたは100mmの両面テープ状に加工したものです。
制震テープは、高層ビルの制震装置に使用されている粘弾性体に着目し、両面テープ状にしたことで一般の木造住宅用で採用されるようになりました。制震テープは、柱の変位が起きたとき、柱や梁と面材との間に貼られたテープが変形して地震のエネルギーを吸収し、揺れを軽減する仕組みということです。制震テープは制震ダンパーと比較して施工性が高く、費用が安いという特徴があります。
既存の建物に対して耐震リフォームを行うことで、その耐震性を向上させることができます。これには、構造の強化、重量バランスの改善、耐震材料の使用などが含まれます。特に古い建物や耐震性が低い建物にはリフォームが必要かつ効果的です。
免震装置は、建物と地盤の間に設置され、地震の揺れが直接建物に伝わるのを防ぎます。この装置により、地震のエネルギーを直接吸収し、建物への影響を大幅に減少させることができます。免震装置は特に大規模な建物に適用されますが、現在では木造住宅用の免震ゴムというものもあるそうです。
地盤改良工事は、建物の下の地盤を強化することで、地震時の地盤の揺れを軽減します。地盤が弱い場所では、このような工事によって地震の影響を減少させ、建物の安定性を向上させることができます。ただ、現在建築物があるところでの地盤改良というのは難しいので、この場合には建物の移動や建て替えが必要となるでしょう。
「キラーパルス」と呼ばれるやや短周期の地震動は阪神淡路大震災でも観測され、2007年の能登半島地震で「キラーパルス」と呼ばれ注目されるようになりました。
新潟県中越地震(2004年)や新潟県中越沖地震(2007年)、熊本地震(2016年)でもこのキラーパルスが観測され、どの地震でも家屋倒壊の被害が大きい共通点があります(一方で、2011年の東日本大震災ではこのキラーパルスでの被害はあまり認知されておらず、津波による被害のほうが大きかったということです)。
古い木造家屋は今までに何度かの地震の揺れを受けダメージが蓄積されている可能性があります。そのため、新耐震基準で建てられた建物でも大地震で倒壊する可能性がないとはいえません。現行の建築基準(2000年基準)で建てられた建物ではない住宅に住まわれている場合は、建て替えや耐震リフォーム、お住み替えを検討されてはいかがでしょうか。
地震大国のニッポンで新築の不動産が人気である理由は、安全性や快適性が日進月歩で進化していることを皆様がご理解されているからなのだろうと思います。今回もお読みいただきありがとうございました。
公開日:2023年12月30日
REDSエージェント、宅建士、宅建マイスターの菅野洋充です。今年も皆様、大変お世話になりました。
突然ですが2024年1月より、お客様担当へ復帰することになりました。今までご連絡いただき担当できなかったお客様、大変お待たせいたしました。ぜひまたお声がけください。以前のように私が直接担当させていただきます。引き続きのご愛顧、どうぞよろしくお願いいたします!
今回はテレビドラマの「不動産監修」のお話です。

さて、NHKドラマ「正直不動産SPECIAL」「正直不動産2」が放送の運びとなりました。2022年放送の『正直不動産』はREDSにて不動産監修をさせていただいておりましたが、それとは別に、新春から放送する話題のドラマの不動産監修をさせていただいております。その名も
テレビ朝日金曜ナイトドラマ
『おっさんずラブ-リターンズ-』!!
前作は、田中圭さん演じるさえないサラリーマンの〝はるたん〟こと「春田創一」が、吉田鋼太郎さんが演じる部長「黒澤武蔵」と、林遣都さんの演じるデキる後輩「牧凌太」に言い寄られ男同士の三角関係になるという、いわゆる「ボーイズラブ(?)」のお話でした。
この皆さんが勤めているのが「天空不動産」という不動産会社で、今回もその続編で不動産業に関する細かい部分に助言させていただいております。
不動産業にかかる部分はあまりなく、だいたいは皆の恋愛関係や人間模様で話が進んでいくのですが、脚本を拝見すると非常におもしろいです。この脚本を書かれたのは徳尾浩司さんで、直近ではNHK夜ドラ『ミワさんなりすます』の脚本も書かれていて、妻と一緒に楽しく見させていただいていました。
天空不動産はREDSのような仲介会社ではなく、三井さんや住友さん野村さんのような総合デベロッパーのような大企業で、海外事業、ホテル事業や開発事業などもやっているようです。
当社REDSはリテール売買仲介にほぼ特化して営業しておりますが、天空不動産は何でもやっているようで、どうやら賃貸もやっているみたいでした。『正直不動産』の「登坂不動産」のような地場不動産業者で、営業担当者が賃貸も売買もやるっていうのは割とポピュラー(といっても、どの不動産業者もおおよそ売買担当と賃貸担当は分かれているもの)ですが、こういう規模の大きそうな総合不動産会社でなんでもやるっていうのは非常に珍しいです。お話なんで、両方できるほうが話は広がりますけどね。
あと、前回は弊社ではなくオープンハウスさんが監修されていたようで、新築戸建ての大規模分譲地現地販売の話や、最終的に土地から理想の家を建てよう、みたいな話があって、オープンハウスさんのカラーを感じるエピソードがたくさんありました。新入社員がタメ口だったりするのは、『正直不動産』でも出てきますよね。あんな感じの新人は正直、私の経験では見たことないのですが、結構いるものなのでしょうかね。
そして、前作の最初、主人公のはるたんが正直、こんなんでよくずっと勤めていられるな~と思っちゃうほどのダメダメ人間で、でもお人よしのいい人っていう、なんかすごい設定だなあと思いました。そして自分を思ってくれている相手(二人とも男ですが)と一緒に住むことで生活が改善していくっていうのが、身につまされるというか、なんというか自分が嫁さんと付き合いはじめたころのことを少し思い出させてくれるいいドラマだったなあ、という感想でした。
今回の『おっさんずラブ-リターンズ-』、じつは前回の続編としてつくられた映画「劇場版おっさんずラブ LOVE or DEAD」の続きから始まるのですが、さてどうなってしまうのか!
金曜ナイトドラマ「おっさんずラブ-リターンズ-」|テレビ朝日
この番組紹介サイトをみると、ファンには驚愕の現在が描かれています。
「はるたん」は東京第二営業所で係長になり、牧は映画で行ったシンガポールから帰国し別の部署、ホテルリゾート本部の課長に出世です。牧の元恋人の武川(眞島秀和)が部長になって、井浦新と三浦翔平が新キャストで、さらにこんがらがって何角関係になってしまうのか!?
居酒屋わんだほうの店主(児島一哉)と〝まいまい〟(伊藤修子)も結婚しているし、ちず(内田理央)はスピード婚からスピード離婚でシングルマザー? なんかすごい状況で物語が始まるようですが、みんな幸せでハッピーエンドだといいですね。このドラマは、多様性、ダイバーシティの象徴のようなお話ですが、こういった会社が今はどんどん増えていっているのかもしれません。
REDSにお問い合わせいただくお客様の中にはLGBTQと思しき方もいらっしゃるようですが、接客した限り、他のお客様との区別はできません。ただ、家を住宅ローンで買う場合、圧倒的に結婚しているほうが有利です。今はLGBTQのカップルに向けた住宅ローンを取り扱う銀行も増えてきており、中でも三井住友銀行では同性パートナーカップルでも夫婦連生団信に加入できるようです(詳しくはご相談ください)。
同性パートナーカップルの住宅ローンは、銀行によりそれぞれ要件が違うようです。もしご購入をご検討される同性カップルのお客様がいらっしゃるようでしたら、ぜひともREDSまでご相談ください。
最後に「おっさんずラブ-リターンズ-」は年明け2024年1月5日(金曜日)午後11時15分から、毎週金曜日にテレビ朝日系列にて放送予定です。REDSのロゴもエンドロールで流れますので、ぜひともご覧ください!!
公開日:2023年11月22日
REDSの宅建士・宅建マイスターの菅野洋充です。
旧耐震基準のマンションは都内のけっこう便利なところに多く存在します。リノベーション済みで、室内もきれいで、しかも新耐震基準のマンションより安くお求めになりやすい物件として、多く販売されています。今回は、そんな旧耐震基準のマンションを購入するときに確認しておきたいことを2つ、お伝えしようと思います。

「旧耐震基準建築のマンション」とはどのようなマンションを指すのでしょうか。これは1981(昭和56)年の建築基準法改正前の耐震基準で建築されたマンションのことを指します。詳しくいうと、昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建物のことを指し、これは建築確認の確認済証交付年月日がその日以前かどうかで判断します。この情報は、重要事項説明書に必ず記載されています。購入検討の際に、古めのマンションは確認しておくとよいでしょう。
旧耐震基準と新耐震基準の違いは以下のとおりです。
・旧耐震基準は、震度5強程度の地震でも建物が倒壊せず、破損したとしても補修することで生活が可能な構造基準
・新耐震基準は、震度6強~7程度の地震でも倒壊しないような構造基準
阪神淡路大震災や東日本大震災などの大地震を経験すると、旧耐震基準の心もとなさが分かるかと思います。
阪神淡路大震災の際に、旧耐震基準の建物が倒壊したにもかかわらず同じ地区の新耐震基準の建物が倒壊しなかったことで、耐震基準というものの重要性が世間一般に認識されました。その後、「耐震改修促進法」という法律が制定され、耐震診断がさまざまな旧耐震基準の建築物に義務付けられることとなりました。
マンションについては全てが耐震診断の義務を負っているわけではなく、地震災害時に通行を確保すべき道路のうち、特に重要な道路(特定緊急輸送道路)沿いの、その道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建物が対象となっています。
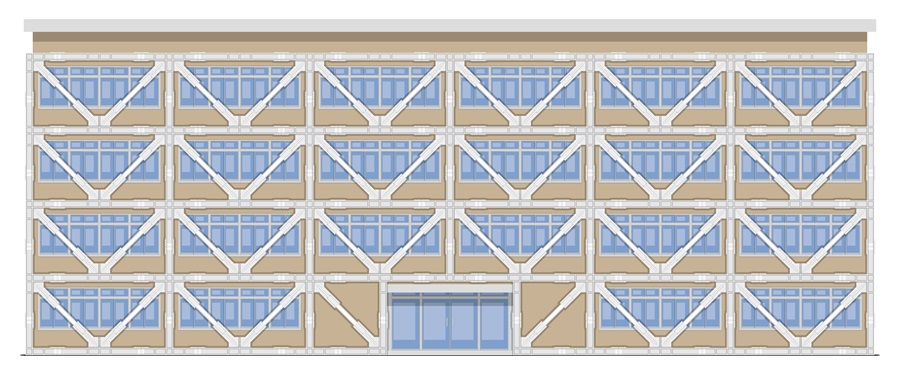
ズバリ、旧耐震基準で建築されたマンションは耐震性能が新耐震基準マンションに比べ低いため、耐震診断を行い、耐震補強することが必要です。耐震診断を行わずに耐震補強をすることはほぼないため、まずは耐震診断を行っているかを確認しましょう。さらに、耐震診断の結果を見て、どのような補強が行われている(もしくは行う予定がある)かも確認しましょう。
耐震補強がなされているマンションは、耐震基準適合証明の発行を受けることで新耐震基準のマンションと同様に住宅ローン減税などさまざまな税金の優遇措置を受けることができます。耐震基準適合証明は建築士さんに依頼することで発行が可能です。
耐震診断結果を見るときには、まず「Is値」に注目してください。
Is値(Seismic Index of Structure)は「(構造)耐震指標」と呼ばれる建物の耐震性の指標で、この値が0.6以上であれば耐震性能を満たすとされています(ちなみに文科省で定める学校の耐震指標は0.7以上となっています)。Is値が0.3未満の場合、大規模な地震で倒壊や崩壊する危険性が高いとされており、購入検討には十分な注意が必要です。
また、q値という水平方向の力に対する耐力指標にも注目してください。こちらの値が1.0以上でないと、倒壊や崩壊の危険性があるとされています。
旧耐震基準のマンションは建築後40年以上を経過しており、給排水管の劣化が進んでいる場合が多々あります。配管の更新工事がされているか否かというのは、生活のクオリティを大きく左右します。更新がされていない場合、水道からさびが出たり、あちこちで漏水が起こったりする懸念があります。室内がいくらきれいにリフォームされていても、漏水が起こったら一大事ですね。
ここで重要なのは「実際に共用部配管の更新を行っているか」ということです。〝磁石で水を活性〟うんぬんというような装置を付けてお茶を濁しているマンションは問題外ですし、非常に古い建物の場合、配管を躯体に埋め込んであって、そもそも配管の更新ができない構造のものもあります。そういったマンションは避けたほうがいいかもしれません。
旧耐震基準のまま耐震診断や耐震補強を行わないマンション、築後40年以上経過していて給排水管の更新を行っていないマンションは、管理組合の財務状況が厳しかったり、管理組合のガバナンスが機能していなかったりするため、購入を検討する際に注意が必要です。
また、旧耐震基準のマンションに住宅ローンの貸し出しを行わない銀行も昨今はあります。旧耐震基準のマンションに限ったことではありませんが、マンションの維持管理に最低限必要な修繕工事を行っているかどうかというのは、その後のマンションの資産価値に大きな影響を与えます。適切にマンションを維持管理しているかの判断基準としても、旧耐震マンションについては耐震診断・耐震補強の有無や給排水管の更新の有無を確認したうえで、購入のご判断をなされることをお勧めします。
公開日:2023年10月16日
REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの菅野です。今回は一戸建ての外壁材について調べてみました。
私の家は昭和末期建築の一戸建てで、外壁はモルタルの吹付タイル仕上げです。最近、ふと家の外壁を見上げたら出窓の下に雨筋汚れがくっきり見え、そろそろ2度目の塗り替えを検討するしかないか、と考えています。
最近の一戸建てはサイディングの外壁が一般的ですが、外壁材はいろいろな種類のものがあります。それぞれについて利点と欠点がありますので、一つずつ解説していきます。

モルタル塗り仕上げとは、外壁や内壁にセメントを主成分とするモルタルを塗布することで、その表面を仕上げる方法です。モルタルはセメント、砂、水などを混合して作られる建築材料であり、これを適切な厚さで塗布して固化させることで、壁の仕上げ面を形成します。適切な施工とメンテナンスが行われれば、モルタル塗り仕上げは非常に長持ちする耐久的な外壁仕上げとなります。
・非常に頑丈な材料であり、適切に施工されたモルタル塗りの壁は、長期間にわたってその性能を保持します。
・自然な風合いと質感を持ち、さまざまなデザインや質感の演出が可能です。
・サイディングのような継ぎ目やコーキングなどがなく劣化しにくいのもメリットです。
・手作業で行われることが多いため、施工者の技術や経験によって仕上がりの品質が変わることがあります。そして、そもそも左官職人が近年ではだいぶ減ってきており、施工できる人が少なくなってきています。
・ひび割れが生じやすいというのが最大の欠点です。地盤沈下や建物の動き、モルタルの収縮などの原因で、ひび割れが生じる可能性があります。
・比較的重たい材料であるため、建物の構造や基礎に負荷がかかります。
タイル張りとは、焼き物や天然石を利用したタイルを壁材として貼り付けていく施工方法です。タイル張りは技術を要する作業であり、専門的な技能や経験を持つ職人が必要です。タイル張りの外壁は、その美観と耐久性から多くの建物で選ばれていますが、施工やメンテナンスに関しては高い技術が求められます。
・タイルや石材は上品で高級な印象を与えます。
・非常に耐久性が高く、天候や時間の経過による劣化がそれほどありません。
・汚れにくく、また汚れがついても清掃が容易であるため、長期的なメンテナンスコストは比較的低めです。
・非燃性であり、防火性があります。
・多種多様なデザイン、色、質感があり、建物の外観をカスタマイズすることができます。
・タイルや石材、およびそれらを施工するための技術や材料は比較的高価であり、初期投資が高くなる傾向があります。
・重量があるため建物の構造や基礎に適切な対応が必要となります。特に既存の建物に後からタイルを張る場合、構造的な強化が必要な場合があります。
・タイル張りは技術を要する作業であり、専門的な技能や経験を持つ職人が必要です。
・地震や建物の沈下などの影響で、タイルにひび割れや剥がれが生じる可能性があります。
サイディングは板状の外壁材で、組み合わせながら外壁に貼っていくものです。サイディングはその素材や製造方法により、以下のようなものがあります。
・窯業系サイディング
・金属系サイディング
・樹脂系サイディング
・木質系サイディング
それぞれについて見ていきます。
窯業系サイディングとは、セメントに木質の繊維質を混ぜ板状に形成した外壁材で、窯で高熱にして仕上げるため“窯業系”と呼ばれます。サイディングのシェア約7割が窯業系サイディングです。圧倒的な使用率のため、さまざまな色や模様の商品が開発されています。窯業系サイディングは、その圧倒的シェアとデザイン、経済的な選択で多くの建物で利用されていますが、メンテナンスに関しては適切な頻度での施工が求められます。
・色やデザインのバリエーションが非常に多く、多種多様な好みに対応できます。
・比較的安価です。
・施工期間が短く済み、施工できる業者もたくさんあります。
・セメントを利用しているので耐火性に優れています。
・セメントを利用しているため重量があります。
・メンテナンス頻度多めです。素材はセメントで吸水性があるため定期的な塗装が必要。またサイディングの継ぎ目にシーリングが必要なため、シーリングの充填も5~10年ごとに必要です。
・セメントに熱を蓄積しやすい性質があるため、夏は夜まで暑くなりがちです。
屋根にも使用されるガルバリウム鋼板やステンレス鋼板を使用したサイディングで、実は芯材に断熱材を使用しています。そのデザイン性と耐久性からモダンな注文建築で多く利用されていますが、使用する地域や環境、建物の用途などによって適切な材料や処理を選択することが重要です。
・断熱性が高い:金属だけだと熱伝導率は高いと考えがちですが、金属系サイディングは芯材に断熱材を使用しており、しかも裏材にアルミラミネートが施された金属系サイディングは高い断熱性能を誇ります。
・軽い:窯業系に比べて軽量で、建物の耐震性にも大きく寄与します。
・モダンな見た目:これは好みですが、シンプルで現代的な外観となります。
・防水性があり凍害に強い:金属は水を吸わないため寒冷地の凍害対策としても有効です。
・錆びる、塩害に弱い:金属ですので、劣化すると錆びが発生しやすくなります。また、海の近くなどでは塩害の影響を受けやすいデメリットがあります。
・傷がつきやすい、へこみやすい:台風などで飛んできた石などで傷が簡単についてしまったりする欠点があります。塗装に傷がつくと、そこが錆びの原因となります。また、衝撃でへこみやすく、子供が壁に体当たりした跡がついてしまったりします。
・ちょっと高い:普及率がそれほど高くなく、単価も窯業系に比べると1.5倍くらいの費用感となります。
塩化ビニル樹脂を使用したサイディングです。アメリカでは広く普及していますが、日本ではかなりマイナーなサイディングです。樹脂系サイディングは、その軽さや耐候性、メンテナンスコストの面での利点がある一方で、少ない施工業者、デザイン性への考慮が必要です。ほぼフリーメンテナンスのため、業界であえて普及させないようにしているのでは?と穿った見方もしてしまいがちな感じです。
・とにかく軽い!重量が窯業系の約10分の1だそうで、耐震性に大きく寄与します
・シーリングが不要なのでシーリングのメンテナンスも不要です
・塗装が不要なので塗装のメンテナンスも不要です
・樹脂自体に色がついているので色落ちしにくい
・吸水性がないので凍害にも強い
・塩化ビニルは不燃材なので耐火性も問題なし
・全然普及していないので、扱っている業者が少ない
・全然普及していないので、選べる商品が少なくデザイン性に劣る
・全然普及していないので、施工費用が高くなりがち
木を使ったサイディングです。見た目は一番かっこよいです(個人の意見です)。その美観と温かみが魅力ですが、長期的なメンテナンスや耐久性の問題を考慮する必要があります。
・木質系サイディングは天然の木の質感を持っており、温かみと独特の風合いが得られます。この自然な外観は、多くの人々に愛されています
・木材の外壁は、高級な印象を与え、建物の価値を向上させる効果が期待できます
・木は再生可能な資源であり、適切に管理された森林からの木材を使用することで、環境にやさしいサスティナブルな選択となります
・木は良好な断熱性を持っており、冬は暖かく夏は涼しい室内環境を維持するのに役立ちます
・木質系サイディングは、他のサイディング材料に比べてメンテナンスが頻繁に必要です
・湿気や紫外線、虫害などの外部要因に影響を受けやすく、長期的には劣化が進む可能性があります
・高品質な木材や、防腐・耐候性を向上させるための特別な処理が施された木質系サイディングは高額です
・燃えやすいので防火地域、準防火地域はおろか法22条区域でも利用できない可能性があります
他にもALCとか石造り?とかもありますが、一般的でないので割愛します。自分がもし家を建てるとしたら、金属系サイディングか樹脂系サイディングを使ってみたいな、と思いました。近々、当社の工事課松本課長に相談して、自宅の外壁メンテナンスをしようと思います。その様子についても報告できたらよいなと思っております。
公開日:2023年9月12日
REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの菅野です。住宅ローンの選択で見落としがちなポイントについて今回書いてみます。
住宅ローンって、普通に考えると「借入金利が安ければよい」となりますが、果たして本当にそれだけなのでしょうか。金利が低ければ、返済額は低くなります。しかし、初期費用を合わせて考えると、金利が高い商品を選んだほうが全体の負担額が下がる場合がありますので、解説します。

住宅ローンの初期費用としてかかるものに以下の2つがあります。それぞれ解説します。
・(先払い)保証料
・融資事務手数料(ローン取扱手数料)
保証料とは、住宅ローンを借りるに当たって「保証会社」に支払うお金です。住宅ローンは基本的には保証人は不要です。その代わり、返済が滞ったときに保証会社が金融機関に代位弁済をおこないます。これは賃貸の保証会社と同じです。
このため、賃貸の保証会社と同じように「保証料」が必要となります。保証料は借入期間と借り入れ金額に応じて料金が決まっており、期間が長いほど、借り入れ金額が上がるほど高くなります。また、繰り上げ返済を行い、期間が短くなるとその期間分の保証料は払い戻されます。
融資事務手数料(ローン取扱手数料)とは、「銀行」に支払うお金です。名目は金融機関によっていろいろですが、借入期間にかかわらず一般的には融資金額の2.2%の料金となります。期間は関係ないため繰り上げ返済を行っても返戻金はありません。
これは「手数料」と称してはいますが、実質的には「前払利息」のようなものです。そのため、保証料型よりも金利を安くすることができます。
この違いについて、みずほ銀行さんのWebサイトで分かりやすい説明がありました。
みずほ銀行|保証料の支払方法
こちらのページでは3,000万円を借り入れたケースとなっていて、10年で全額繰上返済する場合には「保証料」が有利、35年借りっぱなしの場合には「ローン取扱手数料(融資手数料)」が有利となっています。
では実際のところ、何年くらいで分かれ目がくるのでしょうか。
今回は5,000万円を借り入れた場合で計算してみます。計算したのは、みずほ銀行さんのこのページです。
みずほ銀行|ネット住宅ローン返済額シミュレーション
【保証料前払いタイプ】変動金利0.425%
支払利息 107万8,600円+諸費用 76万200円=合計183万8,800円
【ローン取扱手数料タイプ】変動金利0.375%
支払利息 95万1,160円+諸費用 143万3,000円=合計238万4,160円
圧倒的に保証料前払いタイプのほうが、合計の費用は低いですね。
【保証料前払いタイプ】変動金利0.425%
支払利息 216万3,520円+諸費用 107万4,700円=合計323万8,220円
【ローン取扱手数料タイプ】変動金利0.375%
支払利息 190万6,240円+諸費用 143万3,000円=合計333万9,240円
20年でも、まだ保証料型のほうが総費用は低くなります。
【保証料前払いタイプ】変動金利0.425%
支払利息 271万1,500円+諸費用 119万5,700円=合計390万7,200円
【ローン取扱手数料タイプ】変動金利0.375%
支払利息 238万8,100円+諸費用 143万3,000円=合計382万1,100円
25年まで借りますと、ローン取扱手数料(融資手数料型)のほうが総費用は安くなります。今回のシミュレーションですと、だいたい22年くらいまでは保証料型のほうが有利です。
では、保証料金利上乗せ型(保証料を前払いしない方式)だと、どうなるでしょうか。
金利上乗せ型の場合、保証料を先払いしない分、保証料先払い型より金利が0.2プラスとなります。
借入期間10年 変動金利0.625%
支払利息 159万1,600円+諸費用 33万3,000円=合計192万4,600円
となり、すでに保証料先払い型より総費用が高くなってしまいます。
借入期間5年でも
【保証料先払い型】変動金利0.425%
支払利息 54万1,840円+諸費用 56万2,000円=合計110万3,840円
【保証料金利上乗せ型】変動金利0.625%
支払利息 79万8,280円+諸費用 33万3,000円=合計113万1,280円
このように、先払いしたほうが総額は安いのです。金利上乗せ型は初期費用をとにかく抑えないといけないという方以外には、あまりおすすめとは言えません。
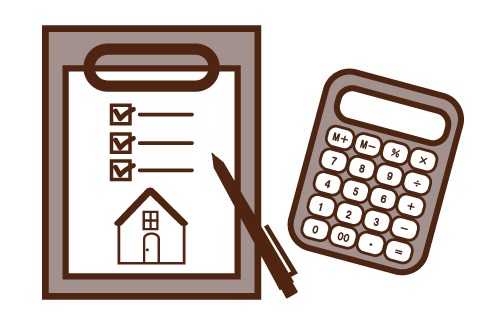
以上より、今回のシミュレーションですと
・二十数年以内に全額返済、もしくは売却する場合は「保証料前払い型」がおすすめ
・二十数年以上住む、早期返済もあまり検討しない方は「融資手数料型」がおすすめ
となります。ちなみに今回はみずほ銀行さんのシミュレーションですので、それ以外の金融機関を利用される場合に、今回のシミュレーションは当てはまらない場合があります。
昨今では短期譲渡所得となる取得から5年を超えた段階で住み替えをされる方も多くございます。そういった方にとっては「保証料先払い型」を検討するのがよろしいかと思われます。
一方、住宅ローンは団信(団体信用生命保険)に加入するのが一般的ですので、住宅ローンの借入額を生命保険的な扱いとして考え、繰り上げ返済をしない方も少なからずいらっしゃいます。そういった「終の棲家」として住宅を購入される方にとっては、金利を低く長く借りられるほうが有利ですので、「融資手数料型」をご利用されるほうがよいと思います。
また、ネット銀行など、そもそも住宅ローン商品に保証料先払い型のない金融機関も最近は増えています。保証料先払い型の住宅ローンはレガシーな金融機関(地銀、信金など)で取り扱いがあります。都市銀行では、みずほ銀行とりそな銀行、埼玉りそな銀行で取り扱っています。
今の時代、ネット銀行などで表示されている低い金利に惹かれてしまいますが、支払総額が重要ですので、検討する際には初期費用を含めたシミュレーションが必要です。お客様のライフプランにより選ぶべき住宅ローン商品は異なります。
ぜひともREDSのエージェントにご相談ください。経験豊富なREDSエージェントは、お客様に最適な住宅ローンを選ぶことが可能です。
公開日:2023年8月9日
REDSマーケティング担当の菅野です。先日、こんなことがありました。休みの朝8時くらいに急にピンポーンと玄関チャイムが鳴ったので、ドアフォンから出たら、「屋根瓦が飛んで落っこちそうですよ!」と言われました。

外にでると職人風の2人がいて、斜め向かいの屋根瓦を修理していたらこちらが見えて、一緒に修理できるがどうか、とのこと。
「うん? なんかの商法か?」と思い、その場では「知り合いがいるからそちらに頼みます。教えてくれてありがとうございます」とお断り申し上げ、当社の工事課松本課長に相談、屋根の業者さんを呼んで直してもらいました。
確かに、瓦が一つ外れて転がっていたそうです。「屋根」って、なかなか自分で見て確認するのが難しいので、本当に風とかで外れていたとしたら、教えてくれた2人の職人さんには申し訳なかったと思うのですが「いつどのように外れたのだろう」と、正直いまだに少し訝しい気持ちではあります。
とまあ、うちの家の屋根は瓦葺きだったことを今まであまり意識せずに住んでいたのですが、不動産仲介業に従事していますと、この「屋根材」は必ず重要事項説明書にて説明することだったりします。これが結構な種類があって、お客様に質問されることもたくさんありますので、今回まとめてみようと思います。
一般的に、登記簿に記載されている屋根材は以下のとおりです。
●瓦葺
●スレート葺(薄い石状のものを重ねていく)
●亜鉛メッキ鋼板葺(いわゆるトタン屋根)
●合金メッキ鋼板葺(ガルバリウム鋼板って聞いたことあります?)
●ステンレス鋼板葺(めっちゃ高いけどかなり丈夫でよい)
●ルーフィング葺(アスファルトシングルなどシートを敷いていくもの)
●陸屋根(屋上があるビル・マンションなど)
珍しいものとして以下のようなものもあります。
●草葺(茅葺きなど、あの白川郷のやつですね)
●板葺(木の板で葺いた屋根)
●銅板葺(お寺などで見かけます)
■瓦の分類にはいろいろある
瓦にはいろいろな種類があります。和瓦、洋瓦なんて分け方もあります。
素材でみると以下のようなものがあります。
●粘土瓦(焼き物の瓦全般)
●セメント瓦(セメントで塑性した瓦)
●金属瓦(金属製の瓦)
粘土瓦は以下の3つに分けられます。
・素焼瓦(釉薬を付けずに焼いた粘土瓦)
・陶器瓦(粘土瓦に釉薬を付けたもの)
・いぶし瓦(素焼きの瓦を燻して銀色になったもの)
以下、粘土瓦のメリット、デメリットを説明します。
粘土瓦のメリット
・紫外線に強く、耐久性が高い
スレートやアスファルトシングルなどは、紫外線にやられて約10年で色が褪せて塗装や吹き替えが必要とされています。また亜鉛メッキ鋼板葺などの金属屋根は時間に伴いどんどんさびていきます。しかし瓦は焼き物のため退色したりさびたりせず長持ちします。
・メンテナンスがほとんどいらない
割れたり飛んだりしなければ、基本的には放っておいてもOKなのが粘土瓦です。
・防火性に優れている
焼き物ですので、燃えません。不燃材として防火・準防火地域でも利用できます。
・通気性がよい
瓦は波を打っているように重ねて葺きます。この瓦の裏側に隙間があることで、通気性がよくなり屋根内の熱を逃がします。
・断熱性がある
焼き物の厚みのある瓦は、いわばお寿司屋さんの湯呑みのような感じで、太陽の熱をしっかり断熱してくれます。
粘土瓦のデメリット
・重い
なにより重いことがデメリットかもしれません。屋根の重みを支えるために、しっかりとした基礎や構造を作る必要があります。ただ、建築基準法に従って正しく建築すれば問題ありません。
・瓦職人さんが減っていること
メンテナンス不要とはいうものの、飛んだり割れたりすると修理が必要です。瓦屋根のメンテナンスは専門知識を持った職人さんの手が必要です。
ここで唐突ですが、「日本三大瓦」についての説明です。日本三大瓦とは「石州瓦」「三州瓦」「淡路瓦」の3つを指します。
石州瓦とは島根県の石見地方で生産されている瓦です。焼成温度が非常に高い(1200℃以上)ことが特徴で、雪(凍害)に強く、日本海側や東北、北海道などでよく使われているそうです。独特な赤茶色の瓦で、これは釉薬に鉄分を含んだ「来待石(きまちいし)」を使っているため。全国シェアで2割ほどを占めるそうです。
愛知県の三河地方で生産される瓦です。全国シェアは6割とトップを占めています。歴史も古く、奈良時代からあったようで、鎌倉時代に再建された東大寺の瓦にも使用されていたとか。鬼瓦を作る瓦職人「鬼師」は全国で70~80人ほどいて、そのうち50人が三州瓦の職人だそうです。もともとはいぶし瓦が有名でしたが、その後、塩を釉薬にした「塩焼瓦」を製造するようになり、今は釉薬を使った洋瓦も製造しているそうです。
兵庫県の淡路島で生産されている瓦です。きれいな銀色のいぶし瓦で、淡路島でとれる「なめ土」という細かい粒子の粘土がこのきれいないぶし瓦に合っているそうです。「いぶし銀」という言葉はこのいぶし瓦からきているそうです。飛鳥時代に日本に瓦製造技術が伝わったころから、淡路島には窯があったといいます。実際に淡路瓦として文献に出てくるのは慶長18年で、今ちょうどNHKでやっている大河ドラマ『どうする家康』の安土桃山時代からだそうです。
屋根について少し調べてみただけですが、瓦だけでも非常に奥深く、興味はつきません。ほかの屋根材についても、次回以降のブログで調べてみたいと思います。