川口 吉彦(宅建士・リフォームスタイリスト)
どんな小さな事でも何なりとお申し付けください。
CLOSE
公開日:2024年2月5日
REDSの宅建士・宅建マイスターの川口吉彦です。
新年元旦に襲った「能登半島地震」の甚大な被害が毎日報道で伝えられています。能登半島地震によりお亡くなりになられた方々にお悔やみ申しあげますとともに、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。また被災者の救済と被災地の復興支援のため尽力されている方々に深く敬意を表します。
被災地では相次ぐ余震と寒さの中、不安が募る状況が続いておられますが、皆様の安全と一日も早い復興を祈願してやみません。今回は、災害による不動産の損害を証明する「罹災証明書」について解説します。
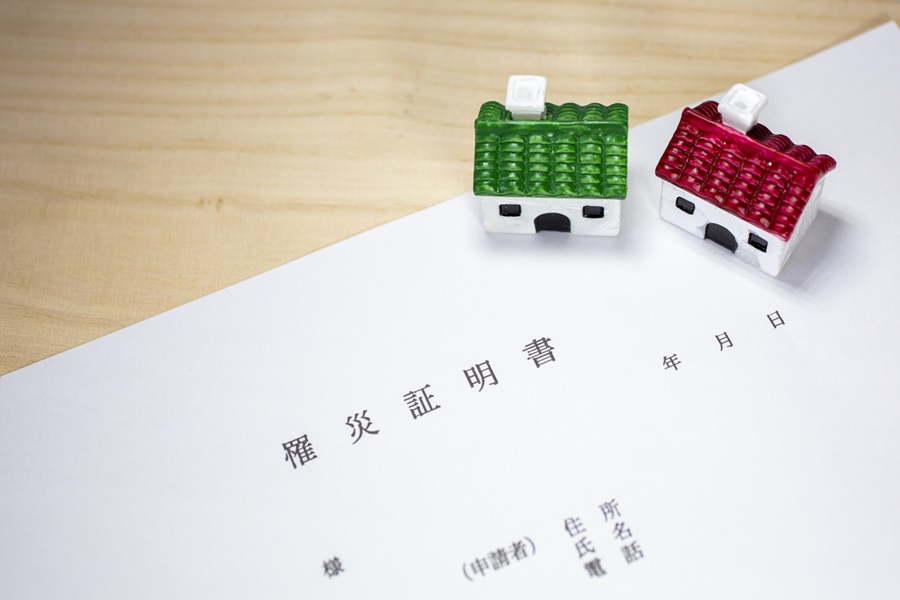
災害による不動産の損害については、罹災証明書が重要な役割を果たします。罹災証明書とは、自然災害による被害に遭った家屋の被害の程度を証明する書類で、市役所に交付してもらう必要があります。具体的には、以下のような内容が含まれます。
罹災証明書は、各市区町村(以下「自治体」といいます)が、災害の被害に遭われた方(以下「罹災者」といいます)の申請によって、お住まいの家屋の被害状況の調査を行い、その被害状況に応じて「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」を認定し、これを証明するものです。
罹災者が各種支援を受けるために必要となることが多いので、罹災者はできるだけ早く申請をした方がよいでしょう。
罹災証明書を自治体に発行してもらうことで、具体的にどのような支援を受けられるのでしょうか。自治体によって異なるので、詳細は各自治体に問い合わせるのがよいですが、一般的には以下のとおりです。
・公的支援:被害のあった家屋や土地の固定資産税や国民健康保険料が、一時的に減免または猶予される可能性があります。被災者生活再建支援金や義援金の支給も受けられます。公的書類の手数料が無料になります。仮設住宅や公営住宅への入居が優先的に認められます。災害復興住宅融資が受けられます。
・民間支援:金融機関が、有利な条件で融資を行ってくれる場合があります。私立学校などの授業料減免の可能性があります。災害保険の保険金を受給することができます。
罹災証明書を発行してもらうためには、以下の手続きが必要です。
・罹災証明書の発行を自治体に申請:罹災証明書の発行申請は、各自治体にて、当該家屋の所有者または居住者が行いますが、委任状があれば第三者でも代理で申請することができます。
・自治体の調査員が現場の被害状況を認定:この調査は国が定めた調査方法によって、各自治体から委嘱を受けた調査員が行います。
・自治体が罹災証明書を発行:一般的には「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」という区分に分けられて罹災の程度が認定されます。
・罹災届出証明書:罹災証明書はすぐに発行されるわけではありません。最低でも調査から1週間、場合によっては1カ月以上かかることもあります。急を要する場合もあるでしょう。そのようなときのために、罹災届出証明書というものがあります。
・被災証明書:また、家屋だけでなく、家財などにも損失があったことを証明しなければならない場合があるかもしれません。そのような時は被災証明書というものがあるとよいです。
また、災害(震災、風水害、火災等)によって所得税が軽減免除される制度もあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8004.htm
具体的には、以下の条件を満たす場合に所得税が軽減または免除されるようです。
(1)災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)がその時価の2分の1以上であること。
(2)災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下であること。
(3)その災害による損失額について雑損控除の適用を受けないこと。
所得金額に応じて、所得税の軽減または免除の額が決まります。具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1,000万円以下の方は所得税額の4分の1が軽減されます。
この軽減免除に代えて雑損控除の適用を受けることも可能です(雑損控除とは、災害や盗難、横領などによって資産に損害を受けた場合に適用される所得控除です)。具体的には、以下の条件を満たす場合に所得税が軽減されます。
(1)災害や盗難、横領などによって、生活に通常必要な資産に損害を受けたこと。
(2)損害を受けた資産が、納税者自身または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族(その年の総所得金額が48万円以下)が所有していること。
(3)損害を受けた資産が、棚卸資産もしくは事業用固定資産または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しないこと。
以上が災害による不動産と罹災証明書等についての基本的な情報です。
災害は予期せぬものですので、事前に罹災証明書について少しお調べしてご説明させていただきました。各々が理解しておくことは大切と思います。
公開日:2023年12月29日
不動産流通システムの川口吉彦です。いよいよ今年も残り僅かとなりました。年の瀬のお忙しい中、ご覧いただきまして誠にありがとうございます。
さて不動産売買における必要な宅建業法の知識は多岐にわたりますが、我々営業・業務に従事している者も知識不足とならないよう、日々精進を心がけております。そもそも不動産売買を行うための免許取得や従事することなど、今一度、不動産取引業の根幹としてその主要なポイントをまとめてみます。
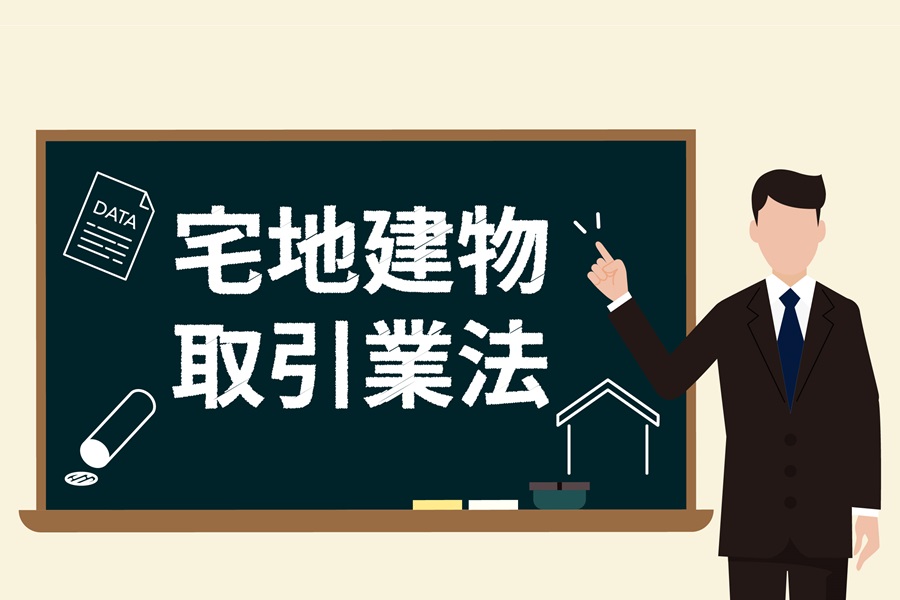
宅地建物取引業法(通称「宅建業法」)は、宅地建物取引業を営む者に対する免許制度を実施し、その事業に対する必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地および建物の取引の公正を確保することを目的としています。
宅地建物取引業を営む者は、免許を受けなければならず、免許を受けずに宅建業を営むことは無免許営業となり、罰則が科されます。
宅地建物取引業法に違反した場合、以下のような罰則が科される可能性があります。
1.監督処分:宅地建物取引業法に違反した場合、監督処分として「指示処分」「業務停止処分」「免許取消処分」が行われる可能性があります。
2.罰則:監督処分だけでなく、罰則も適用されます。悪質な場合は、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科」とされています。
3.両罰規定:宅建業者の代表者や従業員が違反行為を行って罰則を受けた場合、それらの者が務めている業者に対しても罰金刑が科されます。これを「両罰規定」といい、法人の場合、最高で「1億円」の罰金が科されます。
これらの罰則は、不動産業界における公正な取引を保証し、消費者を保護するためのものです。不動産業者として、これらの規定を遵守することは非常に重要です。
宅地建物取引業法に違反した具体的な事例は多岐にわたります。以下にいくつかの事例を挙げてみます。
1.無免許営業:静岡県で2002年10月頃に無免許の不動産業者が、原野約200㎡を290万円で販売した他、2004年7月頃に原野200㎡及び建物を約700万円で販売した事例があります。
2.説明義務違反:「賃料59,000円、管理費6,000円」との内容で2ヶ月半にわたり広告していたものの、広告後に賃料70,000円、管理費3,000円で賃貸借契約を結んでおり、実際には表示の賃料で取引する意思がなかった事例があります。
3.名義貸し責任:不動産業者が、宅地建物取引業保証協会に対して、同保証協会が十分な調査を行わず、同宅建業者に仲介取引に関する業務上の義務違反があるとして宅建業法64条の8第2項に基づく認証行為を行ったとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた事例があります。
これらの事例は、宅地建物取引業法の遵守が不動産取引における公正さを保つために重要であることを示しています。不動産業者は、法令遵守と公正な取引を常に心掛けるべきです。
以上のような知識が、不動産売買における業務において重要となります。これらの知識を深めることで、適切なアドバイスを提供し、クライアントの利益を守ることが可能となります。
さて、今年もたくさんの皆様から、弊社をご利用いただきました。誠にありがとうございます。
弊社では常時ご売却物件を募集しています。弊社の受任物件には、全て設備保証が付きますので、是非弊社エージェントへご相談ください。
不動産の売買をご検討中の方がお知り合いの方にいらっしゃいましたら、REDSご紹介制度をご利用ください。経験豊かなプロ集団が弊社のエージェントです。常にお客様の心に寄り添うよう尽力しています。
皆様、売る時も買う時も「どんな不動産も仲介手数料が全て割引!さらには無料も」のREDSをどうぞよろしくお願いいたします。
「さあ、不動産売買の仲介は“REDSでGO!”」「REDS不動産で検索」です。
本年は皆様からの数多いお問い合わせ、ご契約をいただき、誠にありがとうございました。また、ご契約後のアンケートでは、温かいお言葉、素敵なお言葉、励ましのお言葉、中にはお叱りなどもいただきました。本当にありがとうございました。お客様からの声は、私たちの反省や励みになります。来年も、なお一層より良いサービスを提供できるよう努めてまいります。
皆さま、どうぞ良いお年をお迎えください(改めて、新春お年玉キャンペーンでご連絡させていただきます)。
本年も誠にありがとうございました。どうぞ来年もよろしくお願いいたします。
公開日:2023年11月21日
皆様こんにちは、REDSの宅建士・宅建マイスターの川口です。今回は「不動産トラブルの事例とその対処方法」に関することをお伝えいたします。
不動産トラブルは、さまざまな原因や事情によって発生します。不動産取引に関わる売主・買主は、トラブルを未然に防ぐためにも、契約内容や法令上の制限などを十分に理解し、適正な取引を行うことが重要です。また、万一トラブルに巻き込まれた場合には、適切な対処方法を知ることが必要です。
具体的にどんなトラブルがあるのか、その対処方法を解説します。

土地や一戸建てを売買する際に、境界が不明確だったり、隣地との境界紛争が起きたりすることがあります。このようなトラブルを避けるには、売買前に境界を確定しておくことが必要です。また、売主は境界に関する情報を買主に告知する義務があります。境界が確定できない場合は、売主と買主の間で合意書を締結しておくことが重要です。一番は測量士に測量を依頼することをお勧めします。
土地の下に地下埋設物が残っていると、建築やリフォームの際に工事費用が増えたり、地盤が不安定になったりすることがあります。地下埋設物がある場合は、売主はその存在を買主に告知する義務があります。また、売買契約書で契約不適合責任の免責条項を設けることもできますが、一般的には売主による3か月間の責任負担があります。
建物に雨漏りや傾き、シロアリの発生などの物理的瑕疵があると、買主から損害賠償や契約解除を請求されることがあります。物理的瑕疵についても、売主はその存在を買主に付帯設備や告知表により説明する義務があります。また、売買契約書で契約不適合責任の免責条項を設けることができます。
売買契約書に記載された物件の内容と、実際の物件の現況が異なることがあります。例えば、面積や構造、設備などが著しく契約書と一致しない場合です。このような場合は契約不適合責任に抵触する場合があります。トラブルを避けるには、売買前に物件の現況を確認することにつきます。また、売主は現況と契約書の内容が一致しない場合は、買主にその旨を告知する義務があります。
不動産取引には、不動産業者が仲介や代理として関わることが多いです。不動産業者は、売主と買主の利益を公平に配慮し、適正な取引を行うことが求められます。しかし、中には、過失や不正によって売主や買主に損害を与える不動産業者もいます。
例えば、物件の情報を隠したり、虚偽の情報を提供したり、売買代金を横領したりします。このような業者によるトラブルを避けるには、不動産業者が信頼できる業者かどうか、実績はあるのかを確認するといいでしょう。
不動産業者に損害を受けた場合は、以下の対処方法があります。
・損害賠償の請求:不動産業者に対して損害賠償を請求することができます。損害賠償の額は、不動産業者の行為による物件の価値の減少分や売買代金の損失分などとなります。損害賠償の請求に対して不動産業者が応じない場合は、裁判所に訴えることができます。
・不動産業者の登録の取消しや業務停止の申し立て:不動産業者の過失や不正が重大なものである場合、不動産業者の登録の取消しや業務停止を当局に申し立てることができます。申し立ては、不動産業者の所在地の都道府県知事に対して行います。申し立てが認められると、登録の取消しや業務停止などの行政処分があります。
物件の引渡しとは、売主が買主に物件の所有権や占有権を移転することを指します。物件の引渡しは、通常は売買代金の全額支払いと同時に行われます。
一見、スムーズに行われる手続きのようですが、物件の引渡しでトラブルが発生する場合もあります。例えば、物件の引渡し日が遅れたり、物件の状態が悪化したり、物件に第三者が居住したりする場合です。このようなトラブルを避けるには、売買契約書に物件の引渡しに関する条件や責任を明確に記載することが必要です。
物件の引渡しでトラブルが発生した場合は、以下の対処方法があります。
・契約解除:トラブルが重大なものである場合、売主や買主は契約を解除することができます。ただし、契約解除には一定の手続きが必要で、相手方の同意がない場合は裁判所に申し立てる必要があります。また、契約解除によって売主や買主に損害が発生した場合は、相手方に損害賠償を請求することができます。
・損害賠償の請求:トラブルが軽微なものである場合、売主や買主は契約を維持しつつ、相手方に対して損害賠償を請求することができます。損害賠償の額は、物件の引渡しに関するトラブルによる物件の価値の減少分や利用損失分などとなります。損害賠償の請求に対して相手方が応じない場合は、裁判所に訴えることができます。
以上、不動産トラブルの事例と対処方法について、売買に関するものを紹介しました。不動産取引にはさまざまなリスクが伴いますので、契約内容や法令上の制限などを十分に理解し、適正な取引を行うことが重要です。また、万一トラブルに巻き込まれた場合には、不動産会社をはじめ弁護士などの専門家に相談することも必要です。
公開日:2023年10月15日
マンションと一戸建ての価値は、さまざまな要因によって変わるため、どちらが優れているとは一概には言えません。ただ、昨今の傾向としては、都市部のマンションでの値上がり率が戸建てより上昇しています。
マンションと戸建てという2つの異なる不動産タイプは、それぞれ一意の利点と制約を持っています。不動産の選択は、個々の好みや優先事項によって異なりますから、価値は立地、設備、メンテナンス、プライバシーなどの要因によって決まり、どちらがいいかは個人のニーズに合った選択になります。
あなたはマンション派、一戸建て派のどちらでしょうか。マンション住まいのメリットとデメリットをお伝えします。
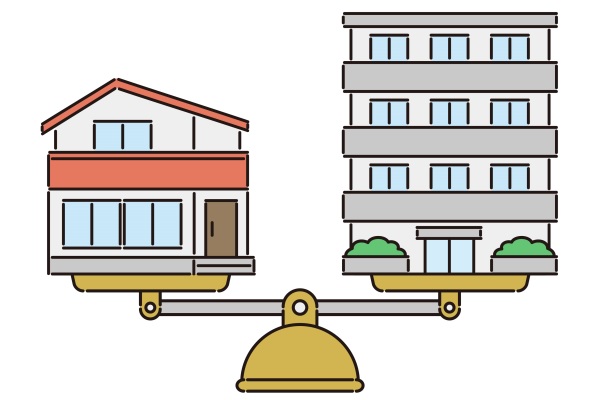
■立地の利便性
多くのマンションは都市部や交通アクセスの良い場所に位置しており、仕事、学校、ショップ、エンターテイメントへのアクセスが容易です。これにより、生活の便益が高まり、不動産価値は上昇します。
■共用施設
マンションは共用施設が充実していて、プール、ジム、駐車場などが整っているものがあります。これらは住民に利益をもたらし不動産価値を高める要因となります。
■セキュリティとメンテナンス
マンションは一般的にセキュリティ体制が整備されており、住民の安全が確保されています。また、共有部分のメンテナンスや修繕は管理会社によって行われるため、住人はそれに関する負担を軽減できます。
■コストの分散
マンションでは住戸や施設のメンテナンスコストを住民が分担するため、個々の負担が軽減されます。これは戸建てよりも経済的といえます。
■管理費と修繕積立金
マンションの住民は共有施設や建物のメンテナンスに関連する管理費や修繕積立金を支払わなければなりません。これらの費用は、戸建ての場合には所有者が単独で負担することが少ないため、総負担が高くなることがあります。
■プライバシー
マンションは複数の住戸が一つの建物内に共存するため、戸建てほどのプライバシーが得られないことがあります。共用の廊下やエレベーターを共有することから、他の住民との接触が避けられない場合もあり、隣人などとのトラブルや騒音などのプライバシーの問題が発生する可能性があります。
■その他
リフォーム工事やペットの飼育、駐車場、自転車置き場などに制限がある場合があります。また土地の所有権が共有のため自由に使えません。
■プライバシーと独立性
戸建ては隣人からの影響を受けにくく、プライバシーが確保されています。大きさにもよりますが庭や敷地も独占できるため、より自分のスペースを持てます。
■カスタマイズが自由
戸建て住宅を所有すると、内部および外部のデザインや改装を自由に行うことができます。部屋の配置や装飾、庭のカスタマイズなどを自分の好みに合わせて行えます。
■庭と屋外のスペース
戸建て住宅には一般的に広い庭やテラスが付属しており、庭でバーベキューをしたり庭いじりをしたりして楽しめます。ペットを飼う場合にも適しています。
■家族向け
多くの戸建て住宅は家族向けのレイアウトを持っており、多くの寝室や居住スペースが提供されています。複数の世代が一緒に住む場合もマンションよりは適しています。
■投資としての潜在的な価値
不動産市場の変動に応じて、戸建て住宅の価値が上昇する可能性があります。資産としての価値が増加することがあるため、将来的な資産形成にも役立つことがあります。
■維持費やメンテナンスの負担
自己所有の住宅は、自分で費用を出して建物と敷地のメンテナンスをしなければなりません。屋根、外壁、庭園、設備などの修繕や保守作業は所有者の責任です。また火災保険などの金額もマンションと比べて高いです。
■場所に依存
戸建て住宅の選択肢は、特定の場所に制限されることがあります。都市部では土地が限られており、高価であるため、選択肢が制約されることがあります。
■交通アクセス
都市部から離れた地方などの戸建ては、通勤やショッピング、エンターテイメントにアクセスする際にマイカー必要で、通勤時間が長くなることがあります。
■孤立感
戸建て住宅は隣人から遠い場所にあると、コミュニティからの孤立感を感じることがあります。マンションやアパートの場合、隣人との人間関係は希薄でも距離的に近いため、接触がより頻繁にあることがあります。
ところで、マンション価格が戸建てよりも上がっています。その理由はいくつかありますが、主な要因をいくつか挙げてみます。
■生活に便利な都市部に住みたい人が増加
大都市や都心部は就業機会やアメニティへのアクセス、交通の便などが魅力的であり、多くの人々が都市に住みたいと考えています。この都市部の住宅需要増加が、マンション市場の高騰につながっています。
■人口増加
人口が増加している地域(主に都市部)では、住宅の需要が高まっています。特に若い世代や単身世帯が増加しており、小規模な住宅ユニットであるマンションが選択肢として適しているため、需要が高まっています。
■土地の希少性
都市部では、土地の希少性が高まっています。土地供給が限られているため、新しい住宅プロジェクトは垂直方向に建設されることが多く、マンションの需要を高めています。
■建築コストの上昇
建設費用が上昇していることも、マンション価格の高騰に寄与しています。建築材料や労働力のコストが上昇し、それが住宅価格に反映されています。
■投資需要
不動産は安定した投資先と見なされており、投資家はマンション市場に資本を投入することがあります。こうして需要が高まると、価格は上昇します。
■住環境とアメニティ
最近の新しいマンションプロジェクトは、高品質の住環境と共用アメニティ(プール、ジム、コミュニティスペースなど)を提供する傾向があります。これらの施設は購買者に魅力的で、求める人が多くなると価格が高騰する要因になります。
■住宅ローン低金利
低金利の住宅ローンが利用可能な場合、住宅購入意欲が高まり、特にマンションはローンの制約が受けにくく需要が高まります。これは住宅価格を押し上げる一因となります。
以上、述べてきたように、都市部における需要の高まり、土地供給の制約、建設コストの上昇、投資家の関与などがマンション価格の高騰に寄与していることが背景にあります。ただし、不動産市場は複雑で、地域や時期によって異なる要因が影響を与えることに留意する必要があります。REDSエージェントにいつでもご相談ください。
最終更新日:2023年9月12日
公開日:2023年9月11日
REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの川口です。昨今下がる、下がると言われ続けている不動産相場ですが、特に都心部の23区などでは上昇傾向か、現状維持となっていて高騰ベースが続いています。
不動産業界は、日本の経済において重要な役割を果たしているのは言うまでもありません。2021年における市場規模は、不動産業・物品賃貸業全体でみると49兆円を超え、三井不動産や三菱地所、飯田グループホールディングスといった大企業がトップシェアを争っています。また、既存の不動産を取り扱う管理業や賃貸業などは、安定的に成長を続けています。
しかし、少子高齢化や人口減少などの国内問題、新型コロナウイルス感染症の流行などがあり、今後の成長には不透明感がつきまとう中、今後の不動産業界はどうなるのか、過去を振り返りながら考えてみましょう。

不動産業界は、過去30年の間に2度の大きな危機を経験しています。皆様もご承知のとおり(私も2度経験しております)それは、1990年の平成バブル崩壊と2008年のリーマンショックです。
平成バブル崩壊は、1990年代初頭に日本で起こった経済危機のことを指します。この危機は、1980年代後半に日本で起こったバブル景気の崩壊によって引き起こされました。バブル景気とは、株式や不動産を中心にした資産の過度な高騰と経済拡大の期間を指します。
内閣府の景気基準日付では、1991年3月から1993年10月までが景気後退期とされています。この期間は、第1次平成不況や複合不況とも呼ばれます。
バブル崩壊という現象は、単に景気循環における景気後退という面だけでなく、急激な信用収縮、土地や株の高値を維持してきた投機意欲の急激な減退、そして政策の錯誤が絡んでおり、1980年代後半には地価は異常な伸びを見せました。公示価格では北海道、東北、四国、九州など、1993年ごろまで地価が高騰していた地方都市もありました。しかし平成バブル崩壊より引き起こされたことで日本は最大の経済危機となり、この危機は不動産業界に深刻な影響を与えました。
特に当時の大蔵省から金融機関に対して行われた行政指導に「総量規制」というものがありました。この政策は、行き過ぎた不動産価格の高騰を沈静化させることを目的として、行政が個人でも法人に対しても、不動産契約を行う前に売主と買主とで価格の同意があったとしても行政は価格の調整を行いました。
これにより不動産売買の売主買主の思惑が外れ、売買契約が不履行になるケースが全国で多々見受けられました。このため予想をはるかに超えた急激な景気後退の打撃を日本経済にもたらし、いわゆるバブル崩壊の一因とされるほどの影響をもたらしました。この政策は、結果的に失敗に終わりました。
また都心部の不動産相場の下落は目に余るものがあり「土地神話」をも崩壊させました。土地神話とは、バブル崩壊前までは土地が永遠に価値を持ち続けるという考え方のことを指します。この考え方は、日本の不動産市場において長年にわたって支配的でしたが、このバブル崩壊により、その神話は崩れ去りました。
土地神話は、土地が不変の価値を持つという信念に基づいており、土地を購入することが安定した投資であるとされていました。しかし、実際には土地価格は変動するものであり、その価値は時代や経済状況によって変化します。現在では、土地神話は過去のものとされ、不動産投資においては慎重な判断が求められるようになっています。

次にリーマンショックは、2008年9月15日に米国の大手投資銀行であるリーマン・ブラザーズが経営破綻したことが引き金となり、世界金融危機および世界同時不況が発生した事象です。この危機は、住宅市場の悪化によるサブプライム住宅ローン危機がきっかけとなりました。
リーマン・ブラザーズは、1990年代以降の住宅バブルの波に乗ってサブプライムローンの積極的証券化を推し進めた結果、アメリカ五大投資銀行グループの第4位にまで上り詰めました。しかし、サブプライム住宅ローン危機による損失拡大により、2008年9月15日に経営破綻しました。この破綻劇は負債総額約6,000億ドル(約64兆円)という米国史上最大の企業倒産であり、世界連鎖的な信用収縮による金融危機を招くことに繋がりました。
日本でも、日経平均株価が大暴落を起こし、同年9月12日(金曜日)の終値は1万2,214円だったのが、10月28日には一時は6,000円台(6,994.90円)まで下落し、1982(昭和57年)年10月以来、26年ぶりの安値を記録しました。その結果、派遣切りや雇い止めが発生し、年末年始に年越し派遣村ができたほどです。
また法人に対しても金融機関から借入金の即時返済を求められ、いわゆる貸し剥がしも中小企業の倒産件数に拍車をかけたことは言うまでもありません。
一方で、現在は冒頭に申し上げましたように不動産市場の底堅さという点においては、特に都心部23区では上昇傾向か高値現状維持もうかがえます。しかし、都心賃貸の空室率は顕著に上昇傾向にあり、家賃の大幅値下げも見受けられます。
このように現在の日本の不動産市場は底堅さと弱さが入り交じるような姿をみせています。今後も変化し続けることが予想され、なお一層の注意が必要と思われます。
最終更新日:2023年8月9日
公開日:2023年8月8日
不動産業界は今後10年間でいくつかの問題点が起こるといわれています。その中で、「2030年問題」と呼ばれる2030年に国内で表面化する社会問題への対応も早期にしていかないとなりません。
2030年には、少子高齢化による人口減少や人口構造の変化により、雇用、年金制度などさまざまな影響が表面化すると予測されています。これらの問題が不動産業界にもどのような影響を及ぼすのか考えてみます。

2030年までに深刻化する社会問題として「少子高齢化・人口減少の進展」「空き家・空き地などの遊休不動産の増加・既存ストックの老朽化」「新技術の活用・浸透」などが挙げられます。
人口減少や少子高齢化により、住宅購入者が減少し、不動産価格が下落する可能性があります。また、地方の人口は大幅に減り、空き家問題や価格減少といった課題が現実のものになります。
空き家問題を解決するためには、空き家を賃貸住宅やシェアハウスとして貸し出すことなどがありますが、最近の取り組みで注目を集めているのが、空き家再生プロジェクト。空き家を再生し、地域ならではの景観を守るための取り組みです。例えば、NPO法人「尾道空き家再生プロジェクト」は、尾道市の山手地区にある空き家を再生し、地域活性化に取り組んでいます。
国土交通省による「空き家再生等推進事業」もあります。この事業は、居住環境の整備改善および地域の活性化に資するために、不良住宅、空き家住宅または空き建築物の除却および空き家住宅または空き建築物の活用を行うことを目的としています。
また、空き家を解体し、土地を売却することも一つの解決策です。さらに、自ら民泊などとして貸し出すことができますし、活用が難しそうであれば売却することなどが挙げられます。
また、不動産ストックを有効活用することも空き家問題の解決につながります。不動産ストックの有効活用とは、既存の不動産を効率的に活用することを指します。例えば、中古住宅の流通市場の環境整備、住宅リフォーム市場の環境整備、悪質リフォーム対策、公共賃貸ストックの計画的改善、マンション管理の適正化と建て替えの円滑化、既存オフィスビルの住宅への転用などが含まれます。
それに地方の不動産の活性化、適切で信頼される不動産取引、新規ニーズの開拓、提供するサービスの多面化、付加価値のある住まいの提案、若い世代への正しい不動産知識の継承などが挙げられます。
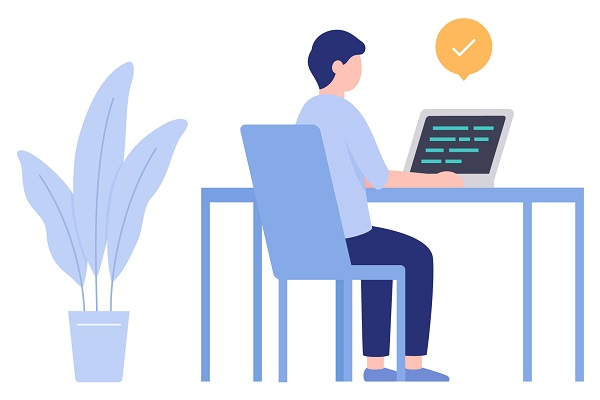
不動産業界においてIT化が進んでいないことも課題の一つです。慢性的な人手不足に悩まされている不動産業界では、DX推進により人手不足問題が解消され、労働環境が改善されることに期待が集まっています。
ここ数年、IT化を推進するために、いくつかの取り組みが進んでいます。例えば、契約の電子化や業務支援システムの導入、オンライン接客・内見の活用などが挙げられます。
契約の電子化とは、電子文書で不動産の売買契約をはじめとする手続きのことです。2021年にデジタル改革関連法が成立したことをきっかけに、法改正以前は主流だった紙の契約書に、インターネット上での電子文書が加わりました。契約の電子化によって、ペーパーレス化も図れます。
業務支援システムとは、賃貸管理や重要事項説明などの不動産業務を効率化するシステムのことです。ほかにも、物件に関する広告の掲載や家賃管理などの機能を搭載するシステムもあります。業務支援システムを導入すると物件情報や顧客情報、ビルメンテナンスなどの業務をシステム1つで管理できるようになります。システムの導入で業務を効率化できれば、不動産業界の課題である長時間労働や人手不足の解消も期待できるでしょう。
コロナ禍によって非接触による顧客対応が続き、新しい顧客体験の一環としてオンライン接客に取り組む企業も増えました。具体的には、物件の内見にVRを導入し、顧客がスマートフォンやパソコンの画面上でリアルタイムの内見ができるサービスなどです。これらを適切に活用することで、不動産業界におけるIT化を推進することができます。
IT化を進めるためには、目的の明確化と体制の構築が重要です。不動産会社に対する広いネットワークと深い信頼関係も必要です。これらの手段を適切に活用することで、不動産業界におけるIT化を推進することができます。
これらの取り組みは、不動産業界が直面する問題を解決し、持続可能な発展を実現するために重要です。今後も不動産業界は、社会的ニーズや環境変化に対応しながら、新しい取り組みを行っていくことと思います。
最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年6月6日
不動産売買仲介の中古マンション売買契約に付随する、付帯設備や告知事項のトラブルでは、どのようなケースが多く見受けられ、何に注意をして売買契約を進めればよいか、また購入の際の住宅ローンの概要を一般購入者の立場で考えてみました。
中古マンションの売買では、エアコン、キッチン、浴室、トイレなどの付帯設備が重要な要素です。
購入前に十分な点検を行わずに契約を進めると、故障や損傷が判明した後に高額な修理費用が発生する可能性があります。
注意点として、付帯設備の状態や機能性について明確に確認し、修理交換などの履歴をチェックすることが重要です。
売主は買い手に対して、建物や周辺環境に関する重要な情報を正確に提供する責任があります。
しかし、告知事項が不正確であったり隠蔽されていたりするケースもあります。
例えば、近隣トラブルや建物の法的問題などが隠されている場合、購入後に予想外の問題が生じる可能性があります。
購入者は契約前に重要事項説明書や契約書を詳細に確認し、特に法的な問題や近隣トラブル、修繕履歴などに関する情報を注意深くチェックする必要があり、疑問点等があれば、どんな小さなことでも遠慮せずに仲介業者に確認してみてください。
不動産売買には法的・技術的な専門知識が必要です。
信頼できる不動産エージェントや建築士などの専門家の助言を受けることで、契約書や重要事項説明書の内容や不動産の状態を適切に判断することができます。
購入前にマンションの内部と外部を詳細に点検し、付帯設備の状態を再確認します。
また、近隣環境や建物の法的な問題についても調査を行うことが重要です。
建物の状態を見るためには、建築士や施工業者、住宅診断士等の意見を聞くことも有益です。
契約書や重要事項説明書は注意深く読み、すべての項目や条件を理解してください。
特に付帯設備や告知事項に関する項目を重点的にチェックし、曖昧さや矛盾点がないか確認します。
質問や不明な点があれば、担当者に明確な回答を求めることも重要です。
不動産取引においては、購入者の保護を目的とした特約や条件を契約書に盛り込むことが可能かどうか仲介業者に確認するのも一考です。
例えば、付帯設備の保証期間や修理費用の負担などを検討しましょう。
専門家のアドバイスを受けながら、自身の利益を守るために追加保証などの措置を検討してみてください。
マンション購入は大きな責任となるため、情報収集と総合的な判断が重要です。
一括購入や投資目的での購入の場合は、将来的な市場動向や収益性も考慮されますが、住居系はご本人が自ら住まいとしての住処になります。
冷静な慎重さを持ちながら、自身の経済状況や将来の計画に合致するかどうかを考慮して決定しましょう。
特に住宅ローンを組む方は、仲介業者のアドバイスはもちろんですが、ご自身でもよく調べてみてください。
最終的には、自身の利益と将来の安定を考慮しながら、マンションの売買契約に進むかどうかを判断する必要があります。
以上の7点に気を付けることで、購入後の後悔やトラブルの大半は回避できることでしょう。
注意深く調査し、リスクを最小限に抑えるための対策を講じることで、より安心してマンション購入を行うことができます。

住宅ローンについてですが、皆さんがよく耳にする「変動金利と固定金利」の違いを簡単に説明すると、変動金利は金利が変動するため、金利が上昇すると返済額も上昇します。
一方、固定金利は金利が固定されるため、返済額が安定します。
ただし、固定金利の場合、金利が上昇しても返済額は変わらないため、金利が下がった場合には、他の銀行の住宅ローンの金利が下がっても、自分の住宅ローンの金利は下がらないというデメリットもあります。
また最近多く見受けられます「ネット系住宅ローン」と「銀行窓口の住宅ローン」の違いについてですが、ネット系住宅ローンはインターネット上で申し込みや手続きができるため、自宅にいながら手続きができるというメリットがあります。
また、金利が低い場合があるため、金利比較をすることが大切です。
一方、銀行窓口の住宅ローンは、担当者と直接話をすることができるため、細かい相談や質問にも対応してもらえます。
また、銀行窓口での手続きは手続きの進捗状況を確認しやすく、安心感があります。
住宅ローンの金利比較等については、インターネットで調べてみると、各銀行の住宅ローン金利比較や、新規借り入れ・借り換え時の支払いシミュレーション・計算、基礎知識やキャンペーン情報などが掲載されていますので、ぜひ参考にしてみてください。
また、住宅ローンには様々な種類があります。金利タイプや返済方法など、自分に合った住宅ローンを選ぶことが大切ですが、どちらが有利かは個人差があります。
ご自身のライフスタイルや将来的な収入などを考慮して、お選びください。
公開日:2023年3月25日
皆様こんにちは。
不動産業界では、ちょっとした人気を博した漫画【正直不動産】が、昨年はNNKテレビでドラマ化されたのは皆さまご存じでしょうか。
このドラマに弊社が「考察」を担当しました。ちゃんと字幕にも記載があったんですよね。
(また今年もスペシャル版があるそうです。)
正直不動産は、不動産業界の裏側や専門知識を面白く描いた漫画ドラマです。
主人公の永瀬(山P)は、正直すぎる性格で、お客さんに本音で物件を紹介します。
そのせいでトラブルに巻き込まれたり、上司に怒られたりしますが、次第にお客さんや部下の信頼を得ていく内容となっております。
また正直不動産は、不動産の契約や管理に関するリアルな情報が満載ですから、我々不動産業界でも、ちょっとした人気を博しております。
そしてドラマNHK正直不動産と、NHKの朝ドラで現在放映されています【舞い上がれ】の主人公(福原遥さん)が、両方の作品に出演していることです。
他にも福原遥さんの父親役の高橋克典さんが両方のドラマで共演していることです。舞い上がれでは、福原さんはヒロインの舞を、高橋さんは舞の父親の一平を演じています。正直不動産では、福原さんは不動産会社の社員の月下咲良を、高橋さんは月下の上司の登坂を演じています。
以上、うんちく話でした。

公開日:2023年2月18日
皆さまこんにちは。
日本の世の中も物騒になりました。
私の幼い頃の大昔は、玄関の鍵は掛けていませんでした。
泥棒も家人の留守中の「空き巣」狙いが主流と思っておりましたが、
最近では、みな様もニュース等でご存知のように、「強盗事件」に発展しています。
つい先日も弊社渋谷営業所から、約100m離れた渋谷警察署に強盗犯が逮捕されました。
報道車両等でごった返しておりました。
戸建てを中心に記憶では、中目黒のタワーマンションでも発生しました。
今や地方都心、戸建てマンション全くもってお構いなしです。
不動産の仲介を携わる身としては、防犯上のアドバイスも今後必須事項とつくづく実感しています。
特に戸建ての場合は、建物回りに防犯センセーの取り付けや、脚立等も置かないよう心掛ける事や、
泥棒が隠れられないようにする事も同様ですが、中には鍵を建物回りに隠している方も耳にします。
これは絶対にやめましょう!
そこで本日は防犯には欠かせない「鍵」について、少しお話させていただきます。
中古売買の場合、残代金決済時(所有権移転登記時)に売主様から買主様は鍵一式を受領します。
この時、売主様が使用していた鍵本数の一部を万一紛失していても、一般的に良しとされています。
当然ながら、買主様へは鍵の交換をしていただけるよう申し伝えます。
鍵のシリンダー(鍵穴)のみであれば、1~2万円位で交換可能です。(ディンプルキーは高価です。)
また万一免許証入り財布と一緒に鍵を落としてしまった、これはもう最悪ですね。
住所等が特定されますので、不用心この上ないです。
幸いに戻って来たとしても、鍵は一旦手元から離れたら早急に交換をしてください。
TVで鍵をご自身の集合ポスト(ダイアル鍵付き)の中に隠していたら、合鍵を作製されて、
帰宅時に鉢合わせをしたニュースが流れていました。
あと何年かしたら、外国並みに「ボディガード」が隣にいるようになるのでしょうか。
私には雇うお金がありません・・・・
どうぞ皆さま、用心、用心に越したことはありません。

公開日:2023年1月6日
新年あけましておめでとうございます。
昨年は大変お世話になりました。
皆さまお正月のお休みは如何でしたでしょうか。
心身共にリフレッシュされていれば最高ですね。
私は長野で正月を迎え、温泉三昧でした。
本年も引き続きのご愛顧、どうぞよろしくお願いいたします。
