藤ノ木 裕(宅建士・リフォームスタイリスト)
理想を現実に提案力を期待してください。
CLOSE
公開日:2024年4月25日
REDSエージェント、宅建士の藤ノ木裕です。今回は「位置指定道路」ついてお話ができればと思います。
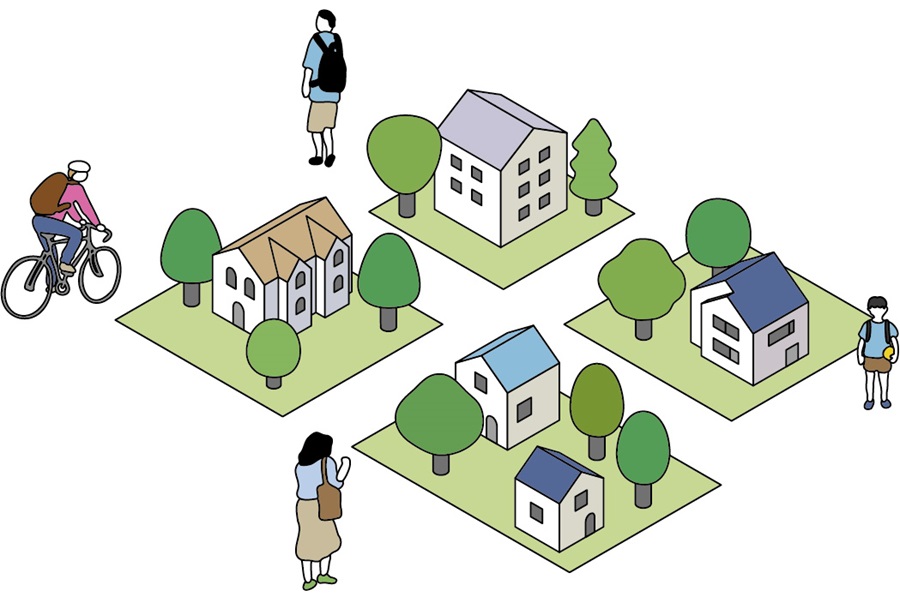
位置指定道路とは建築基準法上の道路として認められており、特定行政庁(地方公共団体)から指定を受けた幅員4m以上の私道です。建築基準法上、建築物の敷地は幅員(道路の幅)4m以上の道路に2m以上接しなければならないという接道要件を満たすための道路を指します。
位置指定道路にするには、幅員を4m以上にし、側溝を設け、路面を舗装するなどの要件を満たす必要があります。位置指定道路部分の土地所有者(不動産会社や土地を購入した人々)全員の合意が必要です。
位置指定道路でない私道に面した土地でも、建物を建てることが可能な場合があります。建築基準法の43条の但し書きにより、建築基準法上の道路でなくても建築が許される場合もあります。
他人の位置指定道路は通行できるのでしょうか。位置指定道路や公衆用道路を含む私道において、その土地の所有者以外の人には「通行権(通行できる権利)があるとは断定できない」と過去の裁判の判例で示されています。通行権は発生していない以上、土地の所有者から通行料を請求されることもあり得ます。
位置指定道路は、土地売買や建物の建設を検討する際に理解しておくべき重要なポイントです。
位置指定道路には、メリットとデメリットがあります。以下にそれぞれの詳細を説明します。
位置指定道路は、建築基準法上の接道義務を果たすために設定されます。建物を建てる際に、幅員4m以上の道路に接する必要がある場合、位置指定道路を利用することで接道義務を満たせます。土地の価値向上としての要件として、位置指定道路がある土地は、接道条件が整っているため、不動産の価値が高まります。建物を建てる際にも有利です。
都市計画や土地利用の規制緩和の要件として、位置指定道路がある土地は、都市計画や土地利用の規制が緩和されることがあります。建物の用途や規模に制限が少なくなる可能性があります。
位置指定道路は土地の一部を道路として指定しているため、固定資産税や都市計画税が発生する場合があることがデメリットかもしれません。
また、位置指定道路は私道の一種であり、通行権が発生していないことがあるのもデメリットです。他人が通行する際に通行料を請求される可能性があります。
このほか、位置指定道路は土地の一部を道路として指定するため、その部分は建物を建てることができません。土地の利用計画に影響を与えることがあります。
位置指定道路の設定にはどれくらい時間がかかるのか、一般的なステップを以下に示します。
1.申請と調査:まず、特定行政庁(都道府県知事や市町村)に位置指定道路の設定を申請します。行政機関は土地の現地調査を行い、設定可能かどうかを判断します。
↓
2.合意の取得:位置指定道路の設定には、土地所有者全員の合意が必要です。各所有者との調整や合意取得に時間がかかる場合があります。
↓
3.道路の整備:幅員を4m以上にし、側溝を設け、路面を舗装するなどの要件を満たすために、土地の一部を整備する必要があります。これには工事期間がかかります。
↓
4.指定の手続き:行政機関は位置指定道路の指定手続きを行います。これには書類の作成や審査が含まれます。
↓
5.公示と効力発生が必要:位置指定道路の指定が公示され、効力を持ちます。総じて、位置指定道路の設定には数カ月から半年以上かかることがあります。具体的な期間は地域や個別のケースにより異なりますので、行政機関と相談しながら進めることをおすすめします。
以上、位置指定道路について記載いたしました。
公開日:2024年3月18日
REDSエージェント、宅建士の藤ノ木裕です。今回はアスベスト調査義務化とその重要性についてお話ができればと思います。
令和4年4月1日から、建築物の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無を事前調査し、その結果を都道府県に報告することが義務づけられました。
アスベストは、かつて建物や工業施設の建材に使用されていた繊維状の鉱物です。その耐久性と耐火性から、過去には多くの建物で使用されていました。しかし、アスベストは健康に有害であり、呼吸器系の疾患や肺がんなどを引き起こす可能性があります。
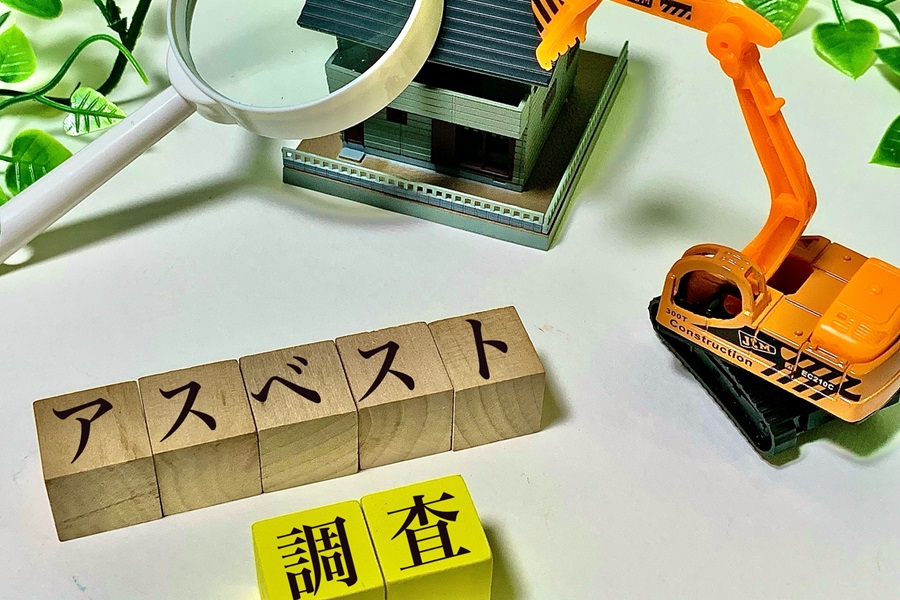
アスベスト調査はなぜ必要なのか、主な理由は以下のとおりです。
●健康リスクの評価について:アスベストが含まれている建材を特定し、適切な対策を講じることで、住民や作業者の健康リスクを最小限に抑えることができます。
●法的要件について:多くの国や地域でアスベスト調査が法的に義務付けられています。建物のオーナーや管理者は、法令を遵守するために調査を実施する必要があります。
●建物の改修と解体計画について:アスベストの有無を知ることで、建物の改修や解体計画を立てる際に適切な対応ができます。
アスベスト調査は、建物の安全性と住民の健康を守るために欠かせないもので、近年、多くの国でアスベスト調査の義務化が進展しています。建物の壁、天井、床、配管などの部位にアスベスト使用の有無が確認されるようになりました。
調査結果は公開され、住民や作業員に対して情報提供が行われています。建物のオーナーや管理者は、法的要件を遵守し、進んでアスベスト調査を実施するようにしましょう。
アスベスト調査の具体的な手順を説明します。以下は、アスベスト調査の基本的な流れです。
1.書面調査
2.現地での目視調査
3.試料採取
4.分析調査
5.調査報告書作成・提出
アスベスト除去工事には注意が必要です。以下にアスベスト除去での注意点を詳しく説明します。
1.専門業者に依頼する
2.工事現場の対策
3.アスベストの種類を理解する
4.含有の可能性のある建物を調査する
5.法的要件を遵守する
アスベスト除去の費用は、建物の規模やアスベストの含有量、工事のレベルによって異なります。以下は、アスベスト除去費用の相場と分類ごとの詳細です。
1.レベル1(発じん性が著しく高い)
発じん性とは粉じんの発生のしやすさを指しており、飛散性と同様の意味です。
2.レベル2(発じん性が高い)
3.レベル3(発じん性が比較的低い)
アスベスト除去工事には、事前調査や仮設工事、廃棄物処理などの費用も含まれます。具体的な費用は、建物の延床面積やアスベストの種類によって異なりますので、専門業者に見積もりを依頼することをおすすめします。
以上、アスベストについて記載いたしました。
公開日:2024年2月8日
REDSエージェント、宅建士の藤ノ木裕です。今回は、土地を購入して新築戸建てを建てる際の注意点について解説します。土地を所有していない方にとっては、土地の購入からスタートとなります。
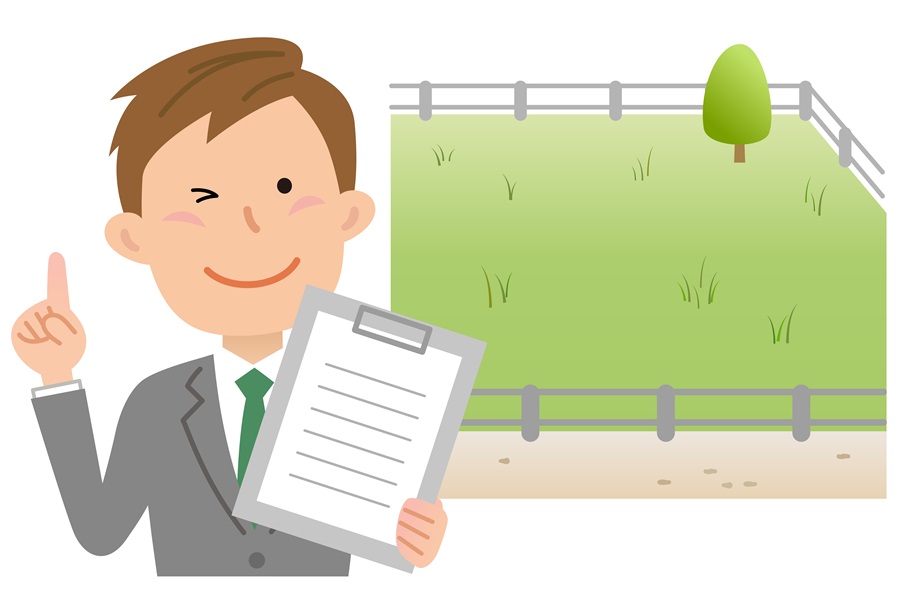
土地の選定については、以下のようなポイントに留意することが重要です。
土地には都市計画法に基づくさまざまな建築制限が存在します。代表的な制限は以下のとおりです。
・用途制限
・建蔽率・容積率
・日影制限
・宅地造成規制
こうした制限が土地に設定されている場合、望みどおりの家を建てられるかどうかは専門的な知識がなければ判断できません。そのため、土地を探す前に、土地の用途地域を理解することが大切です。
土地の条件には、以下のようなものがあります。
・最寄り駅までの距離などの交通の便
・医療施設や学校の有無、距離感
・スーパーやドラッグストアなどの周辺環境
・自然環境の多さ
・日当たり
・地盤の状態
これらの条件を確認することで、将来的に住む上でのストレスを減らすことができます。
土地にかかる法令などにより建物の高さや色、外観などが制限されることがあります。それにより、望みどおりの家を建てることができない場合があります。必ず、事前に、法令を確認することが大切です。あわせて、土地の形状によって、建物の形状や配置に制限が生じることがあります。
そのため、地積測量図などで土地の形状を確認することが大切です。土地の価格は、立地条件や周辺環境、土地の形状などによって大きく異なりますので、以上の点を踏まえ、土地を選ぶ際には、自分にとって最適な土地を選ぶようにしましょう。
住宅を建てる際には、ハウスメーカーの選び方が重要です。以下のポイントに留意することで、自分に合ったハウスメーカーを選ぶことができます。
ハウスメーカーによって得意とする工法が異なります。木造軸組、2×4(ツーバイフォー)、プレハブ工法、重量鉄骨造、鉄筋コンクリート造、ログハウスなどがあります。希望の工法について「これは絶対」というこだわりがある場合は、住宅メーカーが対応可能かどうか、商談前に資料請求や問い合わせをして確認してみましょう。
住宅メーカーの種類によって価格帯が変わってくるため、準備できる予算によって住宅メーカーを絞り込むことをおすすめします。予算の目安と候補の住宅メーカーは以下のとおりです。
●1,000万円台…ローコストハウスメーカー・工務店
●2,000万円台…ローコストハウスメーカー・工務店・大手ハウスメーカー
●3,000万円以上…工務店・大手ハウスメーカー
間取りやデザインのこだわりで選ぶ間取りや内外装のデザインを柔軟に決めたい場合は、工務店に絞り込んで依頼する業者を探してください。工務店の場合、規定の商品ラインナップがなく、建主の希望をヒアリングしながら設計に落とし込んでいくためアレンジの自由度が高いからです。
住宅メーカーによって保証・アフターサポートの内容が異なります。長期的に見て、安心して住めるように、保証・アフターサポートの内容を確認してから選びましょう。
住宅ローンを利用する際には、以下のような注意点があります。
住宅ローンの金利は、固定金利と変動金利の2種類があります。固定金利は、金利が変動しないため、返済期間中の金利リスクを回避できます。一方、変動金利は、金利が変動するため、返済期間中に金利が上昇する可能性があります。変動金利を選ぶ場合は、金利の変動に注意し、返済計画を立てることが大切です。
住宅ローンは、長期間にわたる返済が必要なため、借りすぎには注意が必要です。返済計画を立てる際には、自分たちの収入や支出をしっかりと把握し、無理のない返済計画を立てるようにしましょう。
住宅ローンを利用する際には、保証料が必要になる場合があります。保証料は、住宅ローンを借りる際に、金融機関が融資を行う際のリスクを補償するために必要な費用です。保証料は、金融機関によって異なるため、複数の金融機関を比較して、保証料の金額を確認することが大切です。
住宅ローンを返済する際には、繰り上げ返済ができる場合があります。繰り上げ返済とは、返済期間中に、元本を返済することです。繰り上げ返済を行うことで、返済期間を短縮することができます。ただし、繰り上げ返済には手数料がかかる場合があるため、事前に確認することが大切です。
フラット35は、住宅金融支援機構が提供する住宅ローンの一種です。フラット35は金利が安定しているため、返済期間中の金利リスクを回避できます。また、繰り上げ返済に対して手数料がかからないため、返済期間を短縮することができます。
フラット35を利用する際には、条件をよく確認し、自分たちに合った住宅ローンを選ぶようにしましょう。
以上、土地を購入する際のポイントを記載いたしました。
是非、街を歩かれる際には気になる土地に目を向けながら歩いてみてはいかがでしょう。
公開日:2024年1月1日
REDSエージェント、宅建士の藤ノ木裕です。今回は、家の外観を決める重要な要素のひとつとなるため、戸建てを購入されるときに気になる外壁材について解説します。

一般的に、外壁材の種類には、「窯業系」「金属系」「木質系」「樹脂系」「モルタル」「タイル」「ALC」の7つがあります。
外壁材の選び方には、「デザイン性」「機能性」「価格・予算」の3つのポイントがあります。
「デザイン性」については、外壁はもっとも目立つ部分のひとつで、外観の大部分を占めるため、家の印象を大きく左右します。
「機能性」については、外壁は使用する素材によって、機能性が大きく異なります。たとえば、白い壁は遮熱性が高く、夜には街灯の光を反射するので視認性も優れています。
「価格・予算」については、外壁素材は値段も幅広く、種類も豊富なため、目的に沿った素材を適切に選ぶ必要があります。
現在、街を歩き、目にすることが多い外壁材はサイディングでしょう。サイディングについて解説します。
サイディングが日本で初めて登場したのは1960年代のことです。それ以前は、国内ではモルタル壁が主流でしたが、住宅が洋風・高級志向になるにつれ、サイディングが主流になりました。
サイディングは、「窯業系サイディング」「金属系サイディング」「木質系サイディング」「樹脂系サイディング」の4つの種類があり、それぞれに特徴があります。
「窯業系サイディング」は、1974年に誕生し、現在では防火外壁材の代名詞のように使われています。デザインが豊富で、耐震性に優れています。
「金属系サイディング」は、1970年代に登場し、耐久性に優れているため、メンテナンスが必要ないことが特長です。
「木質系サイディング」は、自然な風合いがあり、断熱性に優れているため、近年注目されています。
「樹脂系サイディング」は、1980年代に登場し、耐久性に優れ、軽量で施工のしやすさに優れています。
サイディングがよく利用される理由は、以下のようなメリットがあるためです。
(1)初期費用が安い:サイディングは、他の外壁材に比べて初期費用を安く抑えられます。
(2)工期が短い:サイディングは、一定サイズの板を外壁に貼り付けていく方法で、工期は塗り壁より短いため、工事価格が安くなる可能性が高いです。
(3)デザイン性が高い:サイディングには窯業系、金属系、木質系、樹脂系それぞれに特徴がありデザイン力に変化がつけられます。
(4)防火性が高い:窯業系サイディングと金属系サイディングは防火性能に優れています。
サイディングのメンテナンス周期は、一般的には8~15年程度とされています。ただし、気候条件や使用状況によっても異なるため、定期的に点検することが重要です。塗装や張り替えで美しく保ちます。
サイディングの「再塗装」には、塗料の種類や塗装の厚み、塗装面積、塗装の技術力などによって、費用が異なります。一般的に、塗装の費用は、張り替えに比べて安価で、メンテナンス周期も長くなります。
サイディングの「張り替え」は、古いサイディングを剥がして新しいものに張り替えることで、外壁の劣化を防ぎます。メンテナンス方法によって、メンテナンス周期が異なるため、専門業者に相談することをおすすめします。
「窯業系サイディング」は、耐久性が高く、メンテナンス周期は10~15年程度とされています。一方、「木質系サイディング」は塗装が、剥がれたり、木材に多くの水分が含まれたりした状態で放置していると、外壁の劣化につながります。そのため、こまめなメンテナンスが必要で、メンテナンス費用もかかります。
近年、サイディングは耐久性やデザイン性が向上し、新しい種類のサイディングが登場しています。例えば、窯業系サイディングの中でも、30年間色あせしにくい保証付きの商品も登場しています。また、金属系サイディングには、サビに強い鋼板を使用した商品があり、耐食性が高く、塗装の必要がないため、メンテナンスが簡単になっています。木質系サイディングにも耐久性が高く、メンテナンスが簡単な商品が登場しています。
以上、外壁として支持が高いサイディングを記載いたしました。是非、街を歩かれる際には外壁に目を向けながら歩いてみてはいかがでしょう。
公開日:2023年11月24日
REDSエージェント、宅建士の藤ノ木です。今回は、防火地域と準防火地域についてお話しします。

防火地域と準防火地域という言葉をご存じでしょうか。火災の発生とその拡大を防ぐために設けられた地域です。これらの地域では、建築物の構造に一定の制限が設けられています。規制が厳しい順に並べると、防火地域>準防火地域>無指定地域となります。
防火地域では、地域内の建築物をほぼ完全に不燃化することによって火災からその地域を守り、または帯状に耐火建築物を並べることによって火災の拡大をせき止めるようにしています。この地域では、建築物の構造や材料に厳格な規制が設けられており、木造建築物の建設は原則として禁止されています。建築物の高さや密度、道路の幅などにも制限があり、万が一火災が発生した場合でもその影響は最小限に抑えられます。
一方、準防火地域については、防火地域ほど厳格な規制は設けられていませんが、それでも一定の防火性能を持つ建築物の建設が求められます。この地域では、木造建築物の建設は許可されていますが、その場合でも建築物の外壁や屋根には防火性能を持つ材料を使用することが求められます。
防火地域では、建築物の構造に対して厳格な規制が設けられています。具体的には、以下のような制限があります。
●建築物の構造制限:階数が3以上または延べ面積が100㎡以上の建築物は「耐火建築物」または「延焼防止建築物」でなければなりません。また、延べ面積が100㎡以下で2階建て以下の建築物は「準耐火建築物」または「準延焼防止建築物」以上の耐火性能が求められます。
●屋根の制限:防火地域内の建築物の屋根は、市街地の火災にともなう火の粉で延焼を受けないよう、特定の仕上げが必要です。
●外壁の開口部の制限:防火地域の延焼ライン内にある外壁の開口部(窓・扉・換気口など)は、20分間の遮炎性能を持つ防火設備が必要です。
準防火地域でも、建築物の構造に対して一定の制限が設けられています。具体的には、以下のような制限があります。
●建築物の構造制限:階数が4以上または延べ面積が1500㎡を超える建築物は「耐火建築物」または「延焼防止建築物」でなければなりません。また、階数が3で延べ面積が1500㎡以下の建築物または階数が2以下で延べ面積が500㎡を超え1500㎡以下の建築物は「準耐火建築物」または「準延焼防止建築物」以上の耐火性能が求められます。
●外壁・軒裏の制限:準防火地域内の建築物の外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分は防火構造とし、これに付属する高さ2mを超える門または塀で延焼のおそれのある部分を不燃材料で造りまたは覆わなければなりません。
耐火構造の建物を建築する際のメリットは以下のとおりです。
●火災リスクが低い:耐火構造の建物は、壁や床、梁や柱などの構造体が定められた耐火性能を持つため、火災が発生した場合でも被害を抑えることが可能です。
●火災保険料が安くなる:耐火性能が高い建物は、火災保険の保険料が優遇される可能性があります。
●防火地域に建築可能:耐火構造であれば、利便性の高い都市部の地域でも住居を構えられます。
●火災に強く燃え広がりにくい:耐火構造の住宅は燃えづらい材料を用いて建築するので、万が一火災に見舞われても退避するだけの時間を確保できます。
購入しようとしている土地や建物が防火地域・準防火地域にあるのか気になる方もいるでしょう。防火地域や準防火地域は、大きな自治体だとインターネットで調べることが可能です。小さな市町村で都市計画情報がネットに公開されていない場合には、役所に問い合わせれば確認できます。不動産会社に相談してみるのもいいでしょう。
公開日:2023年10月18日
REDSエージェント、宅建士の藤ノ木です。今回は、高さ制限や届出などの点で不動産とは切っても切れない関係にある景観法についてお話したいと思います。
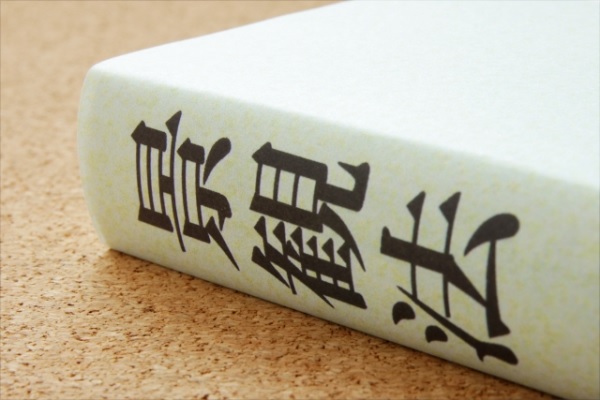
景観法とは、日本の都市、農山漁村などにおける良好な景観の形成を促進するために制定された法律です。直接に景観を規制する訳ではなく、地方自治体の景観に関する計画や条例、それに基づいて地域住民が締結する景観協定に実効性・法的強制力をもたせることを目指しています。
具体的には、以下のような内容が含まれています。
●地方公共団体が景観計画を策定し、その中で特別な配慮が必要な地域を指定します。
●指定された地域では、建築物の建設や改築、樹木の伐採などが行われる際には、事前に地方公共団体の許可が必要となります。
●地方公共団体は、その地域の特性や条件に応じて、建築物の形状や色彩、樹木の種類や配置など、景観に関する具体的な基準を定めます。
これらにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境創造及び個性的で活力ある地域社会実現を図り、国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的としています。
景観法は以下のような経緯で制定されました。
日本では高度成長期以降、全国どこへ行っても地域全体の調和や美観、伝統を軽視した住宅やビル、工場、護岸などの建築物・構造物が次々に建てられ、街並みや自然景観から調和や地域ごとの特色が失われていきました。一部の地方自治体では地域住民の要望に応え、景観条例を定めていましたが、法令に基づかない自主条例のため強制力がなく、建築確認の際に従う必要はないものでした。
1990年代頃から、ようやく国土交通省も自らが発注する公共工事において景観に対する配慮・調和を重視するようになりました。併せて「美しい国づくり政策大綱」を策定し(2003年7月)、景観法が2004年6月に公布され現在に至ります。
景観法があることによるメリットは主に以下の5点です。
(1)地域の特性を保護として、地域の自然や歴史、文化等と人々の生活や経済活動との調和を図り、地域の個性や特色を引き立てることで、良好な景観の形成を促進します。
(2)美しい国土の形成として、美しく風格のある国土の形成を目指しています。これにより、都市や地域が持つ美観を保つことができます。
(3)豊かな生活環境の創造として、潤いのある豊かな生活環境創造を目指しています。これにより、住民が快適に生活することができます。
(4)地域社会の活性化として、個性的で活力ある地域社会実現を図ります。これにより、地域社会が活性化し、地域経済が発展することが期待されます。
(5)国民生活の向上として、国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目指しています。

日本国内では、景観法の運用については各地方自治体が自主的に行っており、その厳格さは自治体により異なります。
具体的な自治体としては、北海道では以下のような例があります。
釧路市、北見市、千歳市、伊達市、富良野市、長沼町、栗山町、東神楽町、上富良野町、清里町、洞爺湖町、平取町、弟子屈町などは、景観行政団体となり統合条例を制定しています。一方で登別市や滝上町などは景観行政団体にならず、景観法を利用せずに自主条例を制定しています。これらの自治体ではそれぞれ独自の方法で景観を保全し、都市や地域の特性を維持しようとしています。
これらの自治体では、景観法と同様に、地域や都市の特性を維持し、良好な景観を形成することを目指しています。ただし、それぞれの自治体がどの程度厳格に法律を適用しているかは具体的な事例やデータに基づいて評価する必要があります。
日本以外の国でも景観法に類似した法律や制度が存在します。
イギリスでは個々の開発行為に対してディベロップメントプラン(Development Plan)と呼ばれる指標に基づいて規制が行われます。具体的な規制の例として、建造物の高さ規制が挙げられます。イギリスでは1930年代から都市を象徴する建造物をさまざまな所から眺めることができるように対象物と眺望点の高さ規制を行っています。
イタリアでは、文化財の保護に関する法律(1909年)がありましたが、この保護対象が景観を形成するもの(歴史的・芸術的価値を有する公園・庭園、眺望の美)にまで拡大されたことが景観規制の始まりといえます。1939年には、景観保全の重要な法律とされる文化財保護法(1939年法律第1089号)自然美保護法(同第1497号)が制定されました。
最後になりますが、景観について注目して見てみると、普段とはまた違った視点で街を楽しむことができると思います。古い街並みを訪れた際には、どういったところがいつもと違うのか見比べてみると面白いと思います。
公開日:2023年9月14日
REDSエージェント、宅建士の藤ノ木です。物件のご案内や契約時に説明することが多いのですが、建物面積を表示する方法として、「壁芯」(へきしん)と「内法」(うちのり)の2種類があります。
マンションの専有部分の登記上の床面積は、分譲マンションのパンフレット記載の床面積より小さくなっています。その理由が先の「壁芯」と「内法」。床面積の計算方法が異なるためです。住宅ローン控除や不動産取得税などの軽減措置を受ける際には絶対に知っておきたいこの面積の表示方法の違いについて、詳しく解説します。

「壁芯」は、壁の中心線により囲まれた部分の面積であり、分譲マンションの販売図面や戸建ての建物の登記簿で、面積を表示するときに利用されます。
壁の厚みの中心線を想定し、この中心線に囲まれた面積を床面積とするものを「壁芯面積(かべしんめんせき)」と呼んでいます。壁の中心線を「芯」というのですが、これは、主に建築設計業務で使用します。
「内法」は、内壁で囲まれた部分の面積であり、マンションの専有部分の面積を表示するときに利用されます。
「壁芯」で面積を出す考え方とは異なり、壁の内側の線を基準にした面積を床面積とする計算方法を「内法面積(うちのりめんせき)」と呼びます。実際に目に見える範囲で考えた広さともいえます。住む人の立場に立って考えれば、目に見えていて、実際に使える部分の面積が重要なため、こちらを重視する人が多いでしょう。
建築基準法では、床面積は「建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による」と定められています。つまり、建築基準法を根拠法とする建築設計に関係する場合の床面積の算出には「壁芯」を使う必要があるのです。
建物を建てる際には、監督官庁に対して「確認申請」という届け出が必要になります。この際にも「壁芯面積」で床面積を計算します。
建築確認で確認されるのは、申請された建物の設計が、建築基準法を始めとする関連法に違反していないかどうかという点です。実際に使える部屋の広さではなく、構造や周辺建物や環境との関係を調べるのが目的なので、「壁芯」で考えるのです。
これに対し、不動産登記法では、建築基準法と同じように、まず「建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分(壁芯)の水平投影面積」により算出しますが、マンションについては、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分(内法)の水平投影面積」で考えます。
ところが、マンションのパンフレットや広告に表示されている床面積はほとんどの場合、「壁芯面積」です。この理由は、まず面積を大きく表示できるためです。物件を購入する場合、合理的に考えると同じ価格で同じ条件であれば面積の大きさが判断基準となります。
また、物件を販売する立場からすれば、競合他社があるときには、自社だけ「内法面積」で表示すると誤解される可能性があります。そのため、面積の表示は「内法面積」ではなく、「壁芯面積」で表示されることが多いのです。
もう1つの理由は、建築確認の際には「内法面積」ではなく、「壁芯面積」がベースになっているためです。
住宅ローン控除や、不動産取得税・登録免許税の軽減措置を受けようとする場合には、床面積にとくに注意が必要です。
要件として、自己居住用であることなどの他に床面積が50㎡以上あることが基本になります。この際の面積算定に使われるのは、不動産取引に関わる床面積なので、「壁芯面積」ではなく、「内法面積」です。
たとえば、パンフレットで54㎡と記載されていても、登記面積としての「内法」面積が48.8㎡だったとします。この場合、優遇措置を受ける要件を満たしていないことになるのです。
優遇措置などで問題になる物件の「内法面積」の確認の仕方は、中古物件と新築物件で異なります。中古マンションなどを購入する際は、登記簿に記載された登記面積が「内法面積」になります。
一方で、新築マンションではこの方法で確認できないことがあります。最も簡単で確実な方法は、情報を把握している販売会社に確認することです。パンフレットなどに記載された面積だけで優遇措置の検討を進めるのではなく、販売会社に「内法面積」がいくらなのかを直接問い合わせて確認することが重要なのです。
内容を確認され物件探しをされてはいかがでしょうか。
最終更新日:2023年8月21日
公開日:2023年8月11日
お世話になっております。仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】のエージェント、宅建士の藤ノ木です。
本日はハザードマップのお話をします。ハザードマップとは、特定の地域での地震、洪水、崩壊、土砂災害、火山噴火などの自然災害が発生する可能性が高い地域を示したもので、多くの場合、自治体に問い合わせれば入手できます。

ハザードマップの役割については、下記の4つの用途で利用されます。
・リスクの可視化
・防災知識
・都市計画
・防災意識
それぞれ見ていきましょう。
ハザードマップは、地域での自然災害リスクを可視化し、理解するのに役立ちます。地震ハザードマップでは、警報や地震活動の予測を示し、ハザードマップではリスクの範囲や深さを示します。
ハザードマップは住民が必要な防災知識の基礎情報として活用されます。リスクが高い地域を特定し、避難経路や避難所の配置、建築基準の策定など、災害に備えるための具体的な対策が立てられます。
ハザードマップは、都市計画や土地利用の決定に影響を与えます。自然災害リスクが高い地域には、住宅や公共施設の建設が制限されるなど、適切な土地利用が促進されます。
ハザードマップによって、地域住民の災害リスクについての意識が高まります。自分や家族の安全を確保するためにリスクを冷静に考え、適切な行動をとることができるからです。
ハザードマップの作成にあたり、地形データ、気象データ、地質データ、過去の災害のデータなどが使用されます。科学的な分析やモデリングが行われ、専門家の知識と意見が統合された精度の高いものとなっています。こうして、地域特定の自然災害リスクに対処するための重要なツールとして広く活用されているのです。
ハザードマップは、地方自治体や自治体の防災部門や関連組織から提供され、ネット上でも確認することが可能です。市役所などに問い合わせれば、紙のマップを入手することもできるでしょう。
私の一番のおすすめは、国交省のハザードマップポータルサイトの「重ねるハザードマップ」です。「重ねるハザードマップ」ではなんと、さまざまな防災に役立つ情報を全国どこでもひとつの地図上に重ねて閲覧できます。
「重ねるハザードマップ」についての情報は下記のURLでご確認ください。
https://disaportal.gsi.go.jp/
調べたい住所を登録し検索すると「重ねるハザードマップ」を閲覧することができます。登録後、検索ボタンをクリックすると、住所検索した場所(代表点)における重ねるハザードマップが表示されます。
最初に重ねるハザードマップの白地図を見ることができます。赤枠の「現在地から探す」ボタンをクリックすることで、好みに応じて情報を重なったハザードマップを閲覧することができます。
災害はいつ起こるかわかりません。災害が発生しても落ち着いた行動が取れるように、災害時の心がまえを日頃から持っておくべきなのはいうまでもありません。そんなとき、ハザードマップを活用することで、予防策や備えができます。また、ハザードマップを参考に、地震や洪水、土砂災害などのリスクが低い地域を選び、住宅や事業所の建設や土地の購入することも肝要です。
また、ハザードマップで確認するだけでなく、実際に現地を歩いてみることもおすすめします。指定緊急避難場所や指定避難所への経路を、昼間と夜間それぞれ実際に歩いてみて確認しておきましょう。
このほか、地域で行われている避難訓練に参加されてみるのはいかがでしょうか。想定外の災害が発生した際、的確かつ冷静に対処するためには、「慣れ」が必要です。避難訓練を通して、起こり得るさまざまな災害・事件への対応力、安全に避難する力をしっかりと身につけていれば、不測の事態にも慌てることはないでしょう。防災意識を高めるためにも、防災訓練に取り組んでみてはいかがでしょうか。
最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年6月9日

不動産、特に中古住宅の売買に関しては、隣接する道路(前面道路)の幅員が非常に重要な要素となります。
幅員とは、道路の広さを示すもので、車道や歩道だけでなく、路肩、側溝、植樹帯、中央分離帯など、道路構造物全体の幅を含みます。
建物の敷地は道路に接している必要があり、その接した道路(前面道路)の幅員によって建築に制限が課されます。
前面道路とは、建築基準法で認定された道路で、建築するためには敷地が2m以上接していることが必須条件となります。
建物を建てられる敷地は最低でも1つの前面道路に接している必要があり、その幅員は通常4m以上あることが建築基準法で定められています。
前面道路の幅員が4メートル未満の場合は、原則として、道路中心線から2メートルの位置まで建築線(建築可能な敷地の境界線)を後退させる必要があり、これを「セットバック」といいます。道路中心線は、特定行政庁の指導に基づき決定されます。
セットバックが必要な土地は、売買対象面積よりも実際に建築可能な土地面積が狭くなるため、購入者にとっては注意が必要となり、売却する側はどれだけセットバックする必要があるか、購入者側に説明することが必要となります。
前面道路の幅員に応じて容積率が制限されることもあります。
「容積率」とは、建物の敷地面積に対して建築物が占める容積の割合を示す指標です。
都市計画では、建物の密度や周辺環境の保全、公共施設の確保などを考慮して、用途地域ごとに容積率の限度が定められています(指定容積率)。
前面道路の幅が狭い場合、その指定容積率からさらに制限されることがあります。
容積率が高い場合、同じ敷地面積でも、より多くの容積を持つ建物を建てることができ、これはより高さの高い建物が建築できることを意味します。
国や自治体は、容積率を適切に制限することによって、都市内の建物規模のバランスや環境保全を維持することが可能となります。
さらに、道路斜線制限により、建物の高さや容積に制限が生じる場合があります。
特に、建物の一部が道路に面している場合、天井の一部を斜めに下げなくてはならない場合があります。
これは、道路斜線制限の勾配に合わせて建物を配置する必要があるためです。
「道路斜線制限」とは、建物が道路に面している場合に適用される制度で、道路の勾配や傾斜に合わせて建物の高さに制限を設ける制限のことを指します。
この制限に基づき、建物の一部が道路に接している場合には、建物の一部を斜めに下げる必要が生じます。
これにより、建物と道路の高低差を調整し、隣接建物との均衡感や視覚的な調和を実現します。
道路斜線制限は景観保護や都市の景観に配慮するために設けられており、道路の勾配に合わせて建物を配置することで、周囲の景観や視覚的な調和を維持することができます。
以上から、中古住宅の売却に関しては、前面道路の幅員が重要な要素となります。
幅員が狭い場合、建築制限が課せられる可能性があり、容積率や道路斜線制限によって建物の高さや容積が制限される可能性があります。
売却時には、前面道路の幅員を確認し、建築制限に関する規制や条件を相手方に説明することが必要です。
前面道路の幅員が広い場合、以下のようなメリットがあります。
広い道路に面していることで、建物の配置に柔軟性が増します。また、道路斜線制限が比較的有利になるので、設計の自由度が上がります。
建物の位置を調整することで、日当たりや風通しの良さを最大限に活かすことができます。
敷地内のプランニングに余裕が生まれ、庭や駐車場の設置など住環境の質が向上します。
道路の広さはそのまま車の出入りの難易度につながり、建物の価値や魅力も向上する可能性があります。
建物が適切な距離を確保していることで、景観に調和し、プライバシーや防音効果も向上します。
幅員が狭い場合、建築制限が課せられる可能性があり、容積率や道路斜線制限によって建物の高さや容積が制限される可能性があります。
容積率や道路斜線制限は、都市計画や建築規制によって建物の高さや容積を制限することで、都市のまちづくりや景観保護、環境保全などの目的を達成するための仕組みです。
これにより、都市全体のバランスや美観、環境に配慮したまちづくりが実現されます。
以上より、不動産を売買するときに、前面道路の幅員を確認し、建築制限に関する規制や条件を理解することは重要であると思われます。
最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年5月7日
お世話になっております仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の藤ノ木です。
(独)住宅金融支援機構は28日、2022年度および23年1~3月の「フラット35」の申請戸数、実績戸数、実績金額を発表しました。
22年度は、買取型が申請戸数5万6,741戸(前年度比29.8%減)、実績戸数4万6,130戸(前年度比24.7%減)、実績金額は1兆5,091億円(同21.3%減)。保証型が申請戸数1万412戸(同24.9%減)、申請戸数8,290戸(同21.2%減)、実績金額2,390億円(同18.7%減)と、大幅な減少。
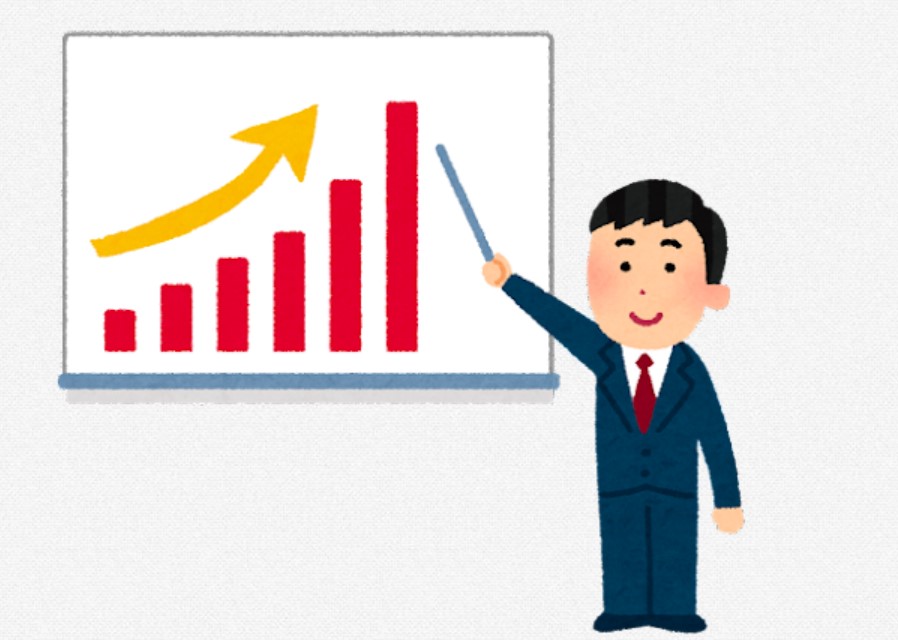
また、23年1~3月については、買取型が申請戸数1万247戸(同35.6%減)、実績戸数1万21戸(同30.4%減)、実績金額3,325億円(同27.8%減)。保証型は申請戸数1,816戸(同43.1%減)、実績戸数1,837戸(同35.9%減)、実績金額548億円(同32.1%減)とこちらも大幅減となりました。
ただフラット35のメリットは下記の様に多くあります。
・借入時点の金利で固定される
・ 保証料が不要
・ 所得に関する制限が明確
・ 団体信用生命保険が不加入で良い事
フラット35の実績低下は変動金利との金利の違いも大きいことと制度の利用のしづらさ感じております。
本来フラット35はご利用しやすい住宅ローンであり是非今後の改善を願うばかりです。