金谷 昭夫(宅建士・リフォームスタイリスト)
高く早く売却する方法をご提案致します。
CLOSE
公開日:2024年10月11日
REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの金谷昭夫です。
2024年10月より住宅ローンの金利が上昇することが発表され、これが家計や経済全体に与える影響は多岐にわたります。金利上昇に伴う影響を以下に記述いたしました。

(写真はイメージです)
住宅ローンの金利上昇は、住宅を購入する際の借り入れコストの増加を意味します。具体的には月々の返済額が増加するため、購入者の負担が大きくなります。
例えば、お借入金額が3,000万円で、変動金利の基準金利が2.475%の場合、元利均等払いの月々のお支払い額は10万6,846円となりますが、金利が0.15%上昇し2.625%の場合、月々のお支払いは10万9,269円となり、月額2,423円支払い額が増加します。そのため、金利上昇に伴い購入予算を見直しする必要も生じてきます。
変動金利で住宅ローンを借りている人々にとって、前述のとおり金利の上昇によって毎月の支払い額が増加します。日本においては、多くの住宅ローンが変動金利を採用しているため、金利上昇が直接的に家計に負担を与えます。
特に、生活費や子育てなど他の支出が重なる中で、ローンの返済額が増えることで、家計の余裕が圧迫される可能性があります。これにより、家計の消費余力が減少し、国内の消費全体にも影響を与えることが懸念されます。
一方、固定金利で借り入れを行っている人々は、契約時の金利がローン期間中に変わらないため、今回の金利上昇の影響を受けません。ただし、固定期間が終了した後に変動金利に移行する場合には、その時点での金利上昇が問題となるため、再度の資金計画が必要です。
金利の上昇は、住宅需要の低下を招く可能性があります。これは、借り入れコストの増加を理由に住宅購入が先延ばしにされるためです。
需要が減少すると、住宅価格の下落圧力がかかることが予想されます。不動産業者や建設業者にとっては、販売不振や在庫の増加といった問題が生じる可能性があります。また、住宅市場の低迷が続くと、不動産業界全体に悪影響を及ぼし、関連産業にも波及します。
一方で、投資目的で不動産を購入する層にとっては、価格の下落は逆に購入の好機となるかもしれません。金利上昇によりローンの利回りが低下するため、投資収益を見込むことが難しくなりますが、価格が下がれば、キャッシュで購入する投資家にとっては有利な状況が生まれる可能性もあります。
住宅ローン金利の上昇は、金融機関にとって利益率の改善につながる可能性があります。貸出金利が上昇すれば、融資から得られる利息収入が増加するため、銀行の収益が向上することが期待されます。
しかし、その一方で、金利上昇が過度に進むと、住宅ローンの借り入れが減少し、貸出残高が減少する恐れもあります。したがって、金融機関にとっては、金利上昇が収益にどう影響するかは需給バランスによるところが大きいといえます。
住宅ローン金利の上昇は、住宅購入を控えさせ、消費全体にも抑制効果を与える可能性があります。住宅を購入する際には、多くの関連消費(家具や家電、リフォームなど)が伴いますが、住宅購入が減少すれば、これらの消費も減少します。このような連鎖的な消費減少は、国内総生産(GDP)の伸びにブレーキをかける要因となり得ます。
住宅ローン金利の上昇は、政府や政策当局にとっても重要な課題です。住宅ローンは多くの国民にとって大きな支出項目であり、金利上昇によって生活が圧迫されれば、社会的な不満が高まる可能性があります。そのため、政府としては住宅支援政策や、住宅ローン控除といった減税措置を強化する必要が出てくるかもしれません。
さらに、日銀の金融政策にも影響が及ぶ可能性があります。日本は長らく低金利政策を続けてきましたが、物価上昇や景気回復の兆しを受けて金利の正常化が進む中、住宅ローン金利の動向は慎重に注視されるでしょう。政策金利の引き上げが過度に進めば、住宅市場や家計に対する悪影響が大きくなるため、慎重なバランスが求められます。
2024年10月からの住宅ローン金利の上昇は、家計や住宅市場、金融機関、そして経済全体に多大な影響を与えると考えられます。特に、変動金利での借り入れが多い日本では、家計への負担増加が顕著となり、消費の低迷や住宅市場の停滞が懸念されます。
一方で、金融機関にとっては利息収入の増加が期待されるものの、不良債権の増加リスクも同時に存在します。政府や日銀にとっては、金利上昇と経済成長のバランスを取ることが今後の課題となるでしょう。
住宅購入につきましても、金利の動向に応じて購入条件の見直しが必要になるかもしれません。不動産価格への影響につきましても、今後の動向に注視しながら、ご売却を検討されている方々も時期や売却価格等について適切にご検討いただくことが重要になると思われます。
ご購入、ご売却ともに最新の市況をお伝えいたしますので、お気軽に、REDS【株式会社 不動産流通システム】の金谷(カネヤ)までご相談ください。
公開日:2024年8月31日
REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの金谷昭夫です。
ワンルームマンションは、単身者向けの住宅として需要が高まっている一方で、地域社会への影響や周辺環境の悪化が懸念されています。特に、特定の地域への人口集中やごみの増加、騒音問題、地域コミュニティの希薄化が問題視されています。
こうしたことを受け、東京23区においてワンルームマンションを建築する場合には、各区で独自に規制が定められています。今回は各区でどんな規制が定められているのか解説します。

(写真はイメージです)
多くの区では、マンション1棟あたりのワンルームの戸数に制限が設けられています。ファミリータイプの間取りを一定割合確保することにより、単身者向けの住戸のみ増加することを規制することができます。この規制を少子高齢化のための施策としているところもあります。
ワンルームの最低専有面積を設定している規制が多く見られます。特定の間取りにのみ適用されるように見られますが、実際には「専有面積」が大きな基準となります。「1K」や「1LDK」、「2DK」などの間取りでも、専有面積が一定以下であればワンルームとみなされる可能性があります。これにより、過剰な過密化や住環境の悪化を防ぐことを目指しています。
このほか、管理人の駐在と管理人室の設置、駐輪場、駐車場の設置を義務づけているところもあります。
下記に主な行政区の現在の規制を記載しました。
今回抜粋させていただいた行政区は、利便性の高い地域が多く、単身者は立地に対してのニーズが高いのですが、それに合わせるだけではなく、地域によって偏りがないように、将来バランスよく人々が生活できる良好な住環境を目指し建築の規制が制定されました。
条例制定前の建築物には適用されておりませんが、今後建築される建築物には地域ごとに異なる規制が適用されますので、単身者用の方で自己居住用の物件購入をご検討されている皆様には、ぜひご参考にしていただければ幸いです。
23区内及びその近郊でお探しの方は、REDS【株式会社不動産流通システム】の金谷(カネヤ)までお気軽にご相談ください。
最終更新日:2024年7月25日
公開日:2024年7月24日
不動産流通システム【REDS】宅建士・宅建マイスターの金谷昭夫(カネヤアキオ)です。
最近の株式市場では、株価が史上最高値を更新するなど好調に推移しています。どこまで上昇するかが見えない動きに少し驚いています。
不動産の価格は、昔から株価に連動する傾向があります。不動産と株価は、経済の主要な投資対象であり、互いに影響を及ぼし合う複雑な関係にあり、それぞれの市場には独自の特徴があり、投資家や経済全体にさまざまな影響を与えます。
以下では、不動産と株価の基本的な概念、相互関係、影響要因、および投資としての考え方についてお話しさせていただきます。

不動産は、土地およびその上に建つ建物や構造物を指します。不動産投資は、主に不動産を所有することによって、その賃貸収入を得ることができることと、将来的に資産価値が上昇すれば売却することによる売買差益を得られる可能性があります。住宅用不動産、商業用不動産、工業用不動産など、さまざまな種類があります。
不動産の価値は、多くの要因によって左右されます。物件の個別要因である、地域や立地、敷地形状、敷地面積、建物規模、築年数、前面道路状況、インフラ整備、法規制のほかに、経済状況や金利などによっても変動します。
特に地域は、不動産の価値に大きな影響を与えます。都市部では、土地の需要が高く、価格も相対的に高額となっている地域が多くあります。都心部ではない地域でも、土地区画整理事業などにより、住みやすい街づくりが行われている地域では人気が高く、価値が上昇している地域もあります。
株価は、公開企業の株式が市場で取引される価格を指します。株式市場は、不動産市場とは異なり、流動性が高く、取引が頻繁に行われます。投資家は、企業の成長や利益に基づいて株式の価格が変動するため、売買差益を期待することができます。また、一部の企業は配当金を支払い、これも投資家にとっての収益源となります。
株価の変動要因には、企業の業績、経済指標、金利、政治情勢、国際情勢などがあります。特に、企業の決算発表や経済政策の変更は、株価に大きな影響を与えることがあります。
不動産と株価は、経済の異なる側面を反映しているため、必ずしも同じ方向に動くわけではありません。しかし、いくつかの共通要因が両市場に影響を与えることがあります。
金利は不動産と株価の両方に重要な影響を与えます。低金利の経済情勢では、不動産ローンのコストが低下し、住宅購入や不動産投資が活発化します。同時に、企業の借入コストも低下し、株式市場にとっても好材料となります。
逆に、高金利環境では、借入コストの増加が不動産市場と株式市場の両方に負の影響を及ぼします。
経済の好況期には、消費者の購買力が向上し、不動産価格と株価の両方が上昇する傾向があります。企業の収益も増加し、株価にプラスの影響を与えます。一方、経済の不況期には、不動産価格と株価の両方が低下することが一般的です。
最近では、株価の上昇幅が著しく、不動産価格が同じ上昇幅では推移していないように見受けられます。
戸建てや売地などと比較して、都心部の区分所有マンションの動きは、株価の動きに類似していて、新築時の購入した価格と最近中古で売却した価格を比較すると、ここ十数年は大幅な価格上昇が見られます。
過去にはない株価の動きに対し、今後の不動産価格との相関関係がどのように推移していくのか注視することが重要だと思われます。
不動産と株式は、それぞれ異なるリスクとリターンを持つため、投資家はこれらを組み合わせることで売買差益の分散を図ることができます。
不動産投資は、長期的な視点で安定した収益を得たい投資家に適しています。賃貸収入を得ることで、定期的なキャッシュフローを確保できます。また、所有する不動産によっては資産価値の上昇を期待できる可能性もあります。
反面、賃料や価格の下落が起こるリスクもあります。地域の経済状況や不動産市場の動向を注意深く注視することが重要です。
株式投資は、高い流動性と成長の可能性を持つため、リスクを許容できる投資家に適しています。企業の業績や市場の動向を分析し、適切なタイミングで売買を行うことが求められます。また、配当金を得ることで、追加の収益を得ることも可能です。
不動産と株価は、経済の異なる側面を反映しており、互いに影響を及ぼし合うことがあります。金利や経済状況は、両市場に共通の影響を与える要因です。投資家は、不動産と株式の特性を理解し、適切な投資戦略を立てることで、リスクを分散しつつ収益を最大化することができます。
不動産の大きな特徴は、一部の物件を除いてはほとんどの物件で資産がゼロにはならないという点です。不動産価格の上昇が賃料を上昇させ、そのため賃料収入が上昇した不動産も多くあります。
現在の低金利が続いている結果、収益性が高くなっている不動産も市場には出ています。不動産投資についても、ご興味がある方は、ぜひお問い合わせください。
公開日:2024年6月14日
REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの金谷昭夫です。
不動産のいわゆる「2025年問題」とは、日本において2025年に不動産市場や不動産に関連する社会問題が一挙に表面化する懸念を指す言葉です。特に注目される点を解説します。

日本は急速に高齢化が進んでおり、2025年には団塊の世代が75歳以上の高齢者となります。これにより、高齢者向けの住宅需要が増加し、逆に一般的な住宅の需要は減少する可能性があります。
都市部と地方で不動産価格の格差が広がる可能性も懸念されます。都市部では高齢者向けの住宅需要が増え、地価や住宅価格の上昇が続く可能性があります。一方で、地方では人口減少に伴う空き家の増加により、不動産価格が下落する可能性があります。
すでに社会問題となっている空き家問題がさらに深刻化すると予想されます。人口減少や都市部への人口集中により、地方の住宅はますます空き家となる一方で、都市部でも、高齢者が亡くなったり介護施設に移ったりすることにより、空き家が増加することが想定されます。
空き家となった家の処分についても円滑に行われる施策が必要となってきます。
高齢者の増加に伴い、相続による不動産の所有者の変動が頻繁に起こります。相続問題が複雑化することで、不動産の管理が困難になり、結果として市場に出回る物件の質や価格に影響が出る可能性があります。不動産相続の増加に伴う問題点は多岐にわたります。以下に主な問題点を挙げます。
不動産の評価額が上昇していると、相続税の負担が重くなることがあります。これにより、相続人が税金を支払うために不動産を売却せざるを得ない状況に陥ることがあります。
複数の相続人がいる場合、不動産が共有状態になることが一般的です。売却や管理には共有者全員の同意が必要となるため、意思決定が難しくなることがあります。また、共有者間で処分方法や利用方法について意見が一致しない場合、不動産の財産分与が円滑に行われない可能性があります。
すぐに処分方法が決まらない場合には、維持管理の責任や固定資産税、都市計画税等の税負担、建物の維持管理などに、経済的負担や労力を費やす必要があります。
相続による売却が増えることで、不動産市場に物件が供給過多となる可能性があります。これにより、地域によっては不動産価格が下がるなどの影響が出る場合があります。
不動産相続には多くの法律や手続きが関与し、それが煩雑であるため、相続が完了するまでに時間がかかることがあります。相続人が不動産に関する専門知識を持っていない場合、適切な手続きが行えない可能性もあります。
相続は家族間のトラブルを引き起こすことが少なくありません。相続財産の分割方法の意見の不一致が生じ、相続人間で意見が対立することがあります。
地方や過疎地域での不動産相続の場合、特有の問題が発生します。地方では不動産の買い手が少なく、売却が難しい場合があります。過疎地域では不動産の価値が低下し、相続財産としての価値が薄れることがあります。
不動産市場の変化に伴い、地価の変動が予想されます。都市部では依然として地価の高騰が続く一方で、地方の不動産価値は低下する可能性があります。これにより、資産価値の格差が広がることが懸念されています。
高齢化社会に対応するため、シニア向けのサービス付き高齢者向け住宅やバリアフリー住宅など、新しい居住形態への需要が高まります。建築物の内容のみならず、医療・介護サポートのための体制も整わなければなりません。また、社会的交流の促進のため、高齢者同士が交流できる共用スペースやレクリエーション施設を設置することも重要です。
国土交通省が進める「都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画」に基づき、高齢者や子育て世代にとって安心できる健康で快適な生活環境を実現し、財政面および経済面において持続可能な都市経営を可能とするために、医療・福祉施設、商業施設や住居がまとまって立地し、高齢者をはじめとする多くの住民が、公共交通によりこれらの生活利便施設にアクセスできる街づくり、すなわち福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直した「コンパクト・プラス・ネットワーク」が推進されています。
2025年問題は、人口動態の変化や社会経済の変動により、不動産市場に大きな影響を与えると予想されます。これに対応するためには、政府や企業、個人が連携して新しい需要に応じた不動産の供給や、空き家対策などの施策を進めることが求められます。
不動産の売買においても、それぞれの不動産会社が個別の事案にも的確に対応し、問題点を解決していくことが求められます。
公開日:2024年5月6日
REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの金谷昭夫です。
最近の不動産広告はインターネット広告での掲載が主流となっています。紙媒体で多いものは「売却物件を探しています」という、物件を宣伝する目的のものではなくて、売却の依頼を受ける目的として、不特定多数のマンションに投函されるケースがほとんどです。
今回は、物件情報の広告について法律に基づく基本的な決まりを解説させていただきます。
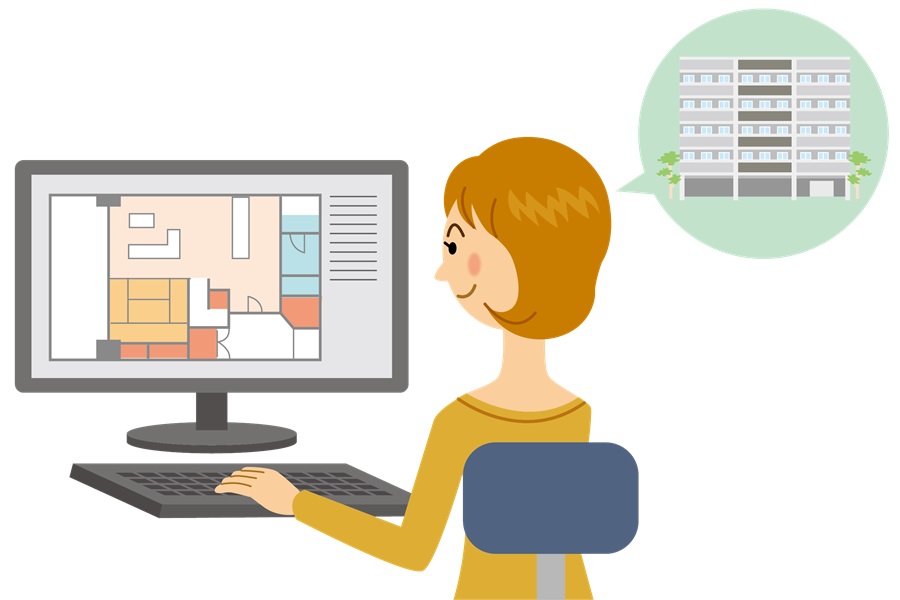
不動産広告は、宅建業法および不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)の2つのルールに従って行います。
宅建業法における広告に関する主な定めは、誇大広告の禁止、広告開始時期の制限、取引態様の明示の3つです。
宅建業者が広告をするときは、宅地・建物の所在、規模、形質、現在もしくは将来の利用の制限、環境・交通その他の利便、代金・借賃などの対価の額もしくはその支払方法、代金もしくは交換差金に関する金銭の貸借のあっせんについて、著しく事実に相違する表示をしてはなりません。
また実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示も禁止されます。これらの規制が、誇大広告の禁止です(宅建業法32条)。
この内容が、一番大きな問題となります。売り手側は、物件の内容をなるべく優れた表示となるように広告を行うものだからです。たとえばこんな調子です。
宅建業者は、宅地の造成または建物の建築に関する工事の完了前においては、工事に関し必要とされる開発許可や建築確認があった後でなければ、工事にかかる宅地・建物の売買その他の業務に関する広告をしてはなりません(同法33条)。未完成物件の売買は〝青田売り〟といわれますが、青田売りにおける広告は、広告開始時期の制限を受けるわけです。
一戸建ての場合は、更地の物件でも建築確認申請に基づき建築確認済証が発行されると「新築戸建」として広告表示を行って販売を開始することができます。ところが、建築確認の申請中もしくは申請も行っていないのにもかかわらず、「新築戸建」として広告を行っている業者も見受けられます。
土地のみで販売するより、〈土地+建物〉で販売するほうが、その取引に対して受領できる仲介手数料が多くなりますので、そのような目的で広告を行っている業者にはご注意ください。
宅建業者の取引への関与については、自らが契約当事者となる場合と、他人が当事者になる契約についての代理・媒介を行う場合があります。そこで、宅建業法では、宅建業者が宅地・建物の売買・交換・貸借に関する広告を行うには、自己が契約の当事者となって売買・交換を成立させるか、代理人として売買・交換・貸借を成立させるか、また媒介して売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(取引態様の別)を明示しなければならないものとされています(同法34条1項)。
取引態様は、インターネット広告でも、各ポータルサイトでも広告作成の入力項目として必須の項目となっております。
宅建業法が、不動産広告に関する基本的な禁止事項を定めているのに対し、表示規約では、「正しい広告はただ嘘(うそ)をつかないだけではなく、消費者が不動産を選ぶ場合に必要と考えられる事項を表示することだ」という立場から、不動産広告についてきめ細かいルールを定めています。
例えば、物件と各種施設までの距離・所要時間を表示することについては、徒歩時間は80mにつき1分として表示しなければなりません。広告における文字の大きさは、原則として7ポイント以上でなければならないという制約もあります。
不動産広告において、抽象的な用語を使用することによって、消費者に誤認を与える場合があります。そこで、消費者を誤認させる可能性のあるような一定の用語については、原則として使用が禁止されています。
使用が禁止される用語は、完全、完ぺき、絶対、日本一、抜群、当社だけ、特選、厳選、最高、最高級、格安、堀出、土地値、完売、など著しく人気が高く、売行きが良いことを意味する言葉などです。もっとも、その表示内容を裏付ける合理的な根拠がある場合には、使用は禁止されません。
具体例をご覧いただいても、時々見かけるワードかいくつかあったのではないでしょうか? 不動産の広告は、その物件の販売を目的としているだけではなく、その広告を見てお問い合わせをいただいたことをきっかけに、別の物件をご紹介する、いわゆる「集客」のための目的もあります。
広告ですので、好条件については積極的に記載をし、悪いことは極力記載しないように表示されているものが多いというのが実情です。
気になる物件がございましたら、広告掲載を行っている業者様以外に、客観的にコメントできる別の業者へ問い合わせることも有効な手段となりますので、広告をご覧になり、疑問点がございましたら、お気軽にREDS【株式会社 不動産流通システム】までお問い合わせください。
最終更新日:2024年3月31日
公開日:2024年3月30日
REDSエージェント、宅建士の金谷昭夫です。
マイホームを手に入れる方の中には、土地を購入して注文建築で家を建てる方々も多くいらっしゃいます。注文住宅を購入する際に、立地や価格、土地形状だけではなく、他に注意すべき点を説明いたします。
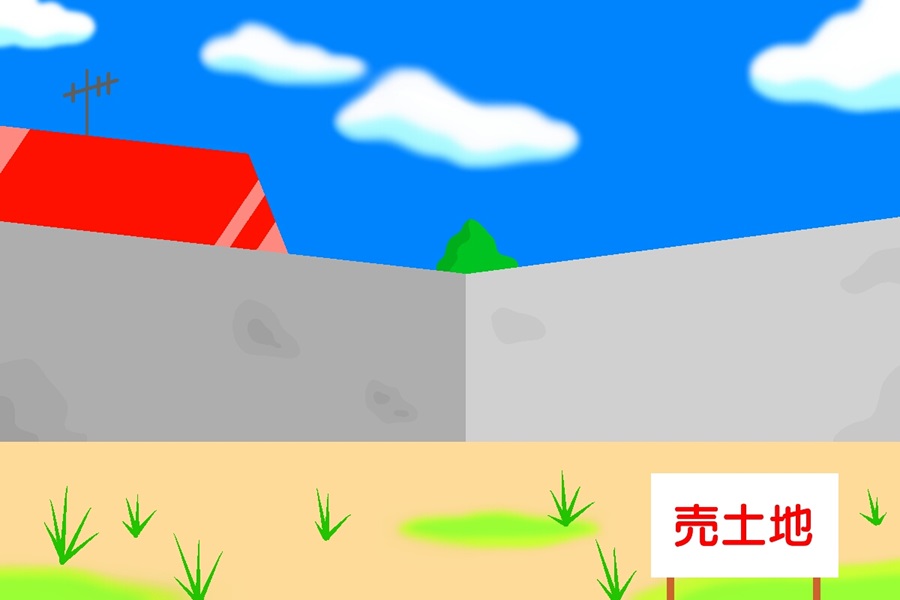
不動産の登記内容に「地目」という項目があります。地目の種類には「田」「畑」「宅地」「池沼」「山林」「公衆用道路」など、23種類の項目があります。
地目は変更されていることも多くあり、履歴は登記事項証明書にて確認できます。現況と必ず一致しているわけではありませんが、過去の土地としての利用用途が確認できる場合があります。
地目を見て推測できるのは、地盤の状況です。地盤の状況によっては地盤改良工事が必要になり、高額な費用が発生する場合もあります。
従前の建物の用途が店舗併用住宅や工場として利用されていた場合には、その種別によっては土壌汚染の可能性に注意しなければなりません。たとえばクリーニング屋の跡地や町工場があった土地は要注意です。
建物解体後に更地として販売している土地であれば、解体時に確認しているため、それほど心配はないのですが、これから建物を解体する場合は、解体後に地中から予想していない埋設物等が確認される場合も多くあります。過去に利用していた井戸や浄化槽、過去に建て替えをしたときに、旧建築物のくずやゴミが埋め戻されているようなこともあります。
売買契約時の際には、一定期間は売主の責任と負担にて除去する内容とするのが一般的ですが、契約内容についても事前確認をすることが重要です。
建築についての法制限については設計士に細かく確認をしていただくことになりますが、その敷地自体の状況もしくは隣接地の状況についての確認が重要です。
よく問題となるケースとしては下記のような内容です。
●塀(敷地内外ともに)が現行の基準に適合していない:塀の倒壊の恐れがあるため、塀の補修、再築造、建築する建物自体の補強が必要となり余分に費用がかかる場合があります。
●擁壁:高低差がある敷地で擁壁がある場合にも、塀と同様に注意が必要です。安全性の確認ができない場合、補修や再築造には多額な費用が生じますので、事前に構造の確認や現地の状況の確認が重要となります。
●越境:隣地からの越境物にも注意が必要です。隣地の建物の屋根が越境しているような場合もあり、越境している部分については建築対象面積から除外されてしまい、実際の敷地面積より有効面積が減少してしまう場合もあります。
市街化区域内では、その敷地の所在に対して用途地域が定められており、敷地に対して建築可能な用途や建築可能な建築物の面積(建ぺい率・容積率)、高さの制限などの定めがあります。
前面道路の幅員によっては、都市計画で定められた建築可能な延べ床面積の最大限度である容積率の制限があり、数値が少なくなる場合があります。また、道路幅の狭い敷地も、道路後退をしなければならない場合もあるため、事前確認が必要となります。
また、敷地の一部が都市計画道路線の上にある場合では、建築物の構造に制限がかかります。見た目が道路でも、実際には敷地の一部となっている場合もあります。都市計画以外でも地域によっては地区計画というものがあり、そちらが優先される場合があります。
地域によってはカーポートの設置が禁止されていたり、塀やフェンスの種類も制限があったりする地域もあります。新しく造られた大規模な住宅地などに多く見受けられます。
あまり馴染みがないかと思いますが、地域によっては「文化財保護法」に基づく、「埋蔵文化財包蔵地」に指定されている地域があります。この地域に該当した場合は、建築工事を行う際に事前調査が必要となります。
具体的には、建築を行う前に、事前に自治体で文化財や遺跡の試掘調査を行います。何も問題がないようであればそのまま工事を進めていく流れとなりますが、調査もしくは建築作業中に文化財や遺跡が発見された場合、作業を一時停止して文化財保護機関や専門家に連絡します。その後、文化財の発掘や保護作業が行われます。
このため、マンション棟の建築規模が大きい場合は一定期間工事が停止するために工期が大幅に遅れることもあります。ホームページ上で公開している自治体もありますが、主に昔から人が住んでいるような地域に多く存在しています。
その他にもいろいろと調査をしなければならない項目もたくさんありますが、信頼がある不動産業者にしっかりと調査をしていただき、ご検討いただくことが重要です。ご相談はREDS【株式会社 不動産流通システム】の金谷(カネヤ)までお気軽にお問い合わせください。
公開日:2024年2月21日
REDSエージェント、宅建士の金谷です。カーボンニュートラル(温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること)に向けて、さまざまな業界で取り組みが行われています。不動産業界でも同様で、住宅や建築物にも今後、さまざまな対応が行われます。カーボンニュートラル達成に向けて今後、住宅はどう変わっていくのか、解説します。

我が国では、地球温暖化の対策として「2050年カーボンニュートラル」の実現を目指しています。
カーボンニュートラルとは、人間の活動によって発生する温室効果ガスの排出量を削減し、残った排出量を吸収または補償することで、差し引きゼロになる状態を指します。カーボンニュートラルを達成するためには、再生可能エネルギーの導入、省エネルギーの促進、二酸化炭素の吸収手段の活用など、数多くの手段が必要です。
企業や自治体など社会全体で環境への負荷を削減し、再生可能エネルギーを利用することで実現に向かいます。不動産業界も積極的にかかわっており、「住宅」についても対策が取られることになります。具体的には環境改善に貢献する住宅を選んだ消費者にはメリットがある、ということになります。
2030年までに新築される住宅など建築物の省エネ基準がZEH、ZEB基準の水準の省エネ性能に引き上げられ、適合していることが義務づけられます。
ZEHは「ゼロ・エネルギー・ハウス」の略で、英語では「Zero Energy House」または「Net Zero Energy House」と呼ばれる概念です。ZEHは、建物が年間を通じて消費するエネルギーと、生成する再生可能エネルギーがほぼ同等である、または生成されたエネルギーが消費エネルギーを上回る建物を指します。
ZEHはまず、建物自体のエネルギー効率を向上させます。断熱性能の向上、高効率な冷暖房システムの採用、省エネ型の照明や家電の導入などが含まれます。さらに再生可能エネルギーの導入を重視します。太陽光発電など、建物が自己消費できる再生可能エネルギーの導入が一般的です。太陽光発電などで発生した余剰エネルギーを蓄電池などで貯蔵し、必要なときに利用する技術を導入することで、エネルギーの有効活用を図ります。
ZEBは、「Zero Energy Building」の略で、エネルギーの生成と消費がほぼ同じであるか、生成したエネルギーが消費を上回る建築物を指します。
また、再生可能エネルギー導入のため、新築住宅の6割に太陽光発電設備が導入されます。

木材は再生可能な天然資源であり、その生産・利用サイクルをすることで二酸化炭素の吸収と放出をバランスよく保つことができます。このため木造建築は環境への負荷が低いとされています。
木造住宅は軽量で施工が迅速であるため、省エネルギー性能や建築コストの削減にも寄与し、持続可能な社会を築くための一環として注目されています。
建築物省エネ法の改正に伴い、建築基準法の見直しも行われました。
(改定前)第一種低層住居専用地域等や高度地区においては、原則として都市計画に定められた高さの制限を超えてはならない。
(改定後)第一種低層住居専用地域等や高度地区における高さ制限について、屋外に面する部分の工事により高さ制限を超えることが構造上やむを得ない建築物に対する特例許可制度を創設。
(改定前)都市計画区域内においては、原則として都市計画により定められた容積率や建蔽率を超えてはならない。
(改定後)屋外に面する部分の工事により容積率や建蔽率制限を超えることが構造上やむを得ない建築物に対する特例許可制度を創設。
(改定前)建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可
(改定後)省令に定める基準に適合していれば、建築審査会の同意なく特定行政庁が認定
(改定前)住宅の居室にあっては、その床面積の1/7以上の大きさの採光に有効な開口部面積の確保が必要
(改定後)原則1/7以上としつつ、一定の条件の下で1/10以上まで必要な開口部の大きさを緩和
住宅ローン減税についても、脱炭素化に対応した住宅は減税の割合が高くなります。
長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅の種別で、それぞれ借入金額の上限が3段階に分かれていて、その種別によって、借入金額の上限がその他の控除対象の一般の住宅より高い水準となります(新築住宅、中古住宅ともに)。
今後、住宅の性能も上がることにより、建築コストも上昇することが考えられますので、新築住宅のご購入を希望される方は、金利の上昇が始まる前に、住宅のご購入をご検討されることをお勧めいたします。
公開日:2024年1月14日
REDSエージェント、宅建士の金谷昭夫です。
建築基準法に基づく用途地域は、都市計画において規定されています。建築基準法は、建物の安全性や衛生面などを定め、都市計画の一環として土地利用を管理するための法律です。今回は、建築基準法に基づく用途地域の中でも、「住居地域」に関して解説します。住居地域には低層と中高層とその他に分かれます。

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域は、主に住宅が建設されることを前提としています。住宅がこの地域の主たる用途となります。その特徴は以下のようなものになります。
高い建物の建設が規制されており、低層の建物が一般的です。これにより、住民の生活環境や景観を保護し、地域全体の開放感を維持します。
低層住居専用地域では、建物の高さや建ぺい率(敷地面積に対する建物の占有割合)などが法令で規制されています。これにより、一定の基準に従った低層の建築に制限されます。
低層住居専用地域は、住民の生活環境を向上させることを重視しています。低層建築により、日当たりや通風の向上、視覚的な快適さなどが促進されます。
商業や工業などの他の用途は制限され、住居が主体となっています。これにより、住宅地域としての静けさや安全性が確保されます。
低層住居専用地域は、周辺の自然環境や景観を尊重し、維持することが求められます。建物の高層化を制限することで、自然環境への影響を最小限に抑えます。
低層住居専用地域は一般的に住宅地域として穏やかな環境を提供し、住民の生活の質を向上させることを目的としています。
中高層住居専用地域では、高い建物が許可され、主にマンションや高層住宅が建設されます。この地域は住居が主たる用途とされており、商業や工業などほかの用途は制限されています。
高い建物の建設が許可されているため、建物の高さや容積率などの建築基準が規定されています。
中高層住居専用地域は、高層建築により土地の有効利用を図りつつ、住民の生活環境を向上させることを目的としています。
高層建築が多く存在することで、都市全体の景観が形成され、都市の発展と美観を両立させることが期待されます。
通常、中高層住居専用地域は交通インフラに近接していることが多く、アクセスがよいことも特徴の一つです。
一部のエリアでは、住居エリア内に商業施設も併設されることがあり、住民の利便性は高いと考えられます。中高層住居専用地域は都市部での高層住宅の需要に応え、都市の発展と住環境の向上を両立させるために計画されています。
住居地域では、主に住宅が建設されることが想定されています。商業や工業などの他の用途も一定の範囲で制限され、住居が主たる用途となります。
低層の住宅だけでなく、中高層の建物も一定の範囲内で建設が認められることが特徴です。建物の高さには一定の制限があります。
静かで住みやすい環境を提供することが重視されています。周辺の自然環境や景観を尊重し、住民の生活環境を向上させることが目的です。商業やサービス業などの施設も一定の範囲内で認められますが、主体は住宅です。商業施設は規模や種類に制限があります。
建物の高さや容積率、建ぺい率などの法令規制のもと、建築が行われます。
必要に応じて学校、公園、病院などの公共施設が配置され、住民の生活をサポートするインフラが整備されます。住居地域は、住宅地域としての静けさや安全性、快適な生活環境を確保するために整備されています。この地域においては、住民が穏やかな環境で生活できるようにさまざまな規制や計画が適用されます。
準住居地域でも住宅が主体となりますが、住宅だけでなく商業や事務所、サービス業などの施設も一定の範囲内で建設が認められる特徴があります。
住居と商業やサービス業が混在する地域であり、商業施設やオフィスビル、アパートなどが同じエリア内に建てられることがあります。
建物の高さや容積率、建ぺい率などの法令規制のもと、住宅と事業施設が調和する形で建築されるようになっています。
準住居地域では、住宅と商業・事業が調和し、住民にとって便利な生活環境を提供することが目指されます。
必要に応じて公共施設も配置され、地域の生活インフラを整備します。
居住用不動産購入の際に、環境面や利便性においてどのような点を重視するのが適しているのかは、都市計画のおける用途地域も重要となります。
物件をご紹介の際には、現地のご案内と合わせてご説明させていただきます。
公開日:2023年12月8日
REDSエージェント、宅建士の金谷昭夫です。土地区画整理事業は、都市や地域の土地利用を効率的かつ計画的に整備するための公共事業です。この事業は、道路、公園、住宅地、商業地などを適切に配置し、地域全体の機能を向上させ、住みやすい環境を構築することを目的としています。
要するに、住みやすい街づくりのために宅地や公共施設を整備する手法の一つなのですが、言葉は聞いたことがあっても実際にはどんなことが行われるのか、知らないという方も多いのではないでしょうか。今回は、土地区画整理事業の主な特徴や進行手順、影響について説明します。

土地区画整理事業は、公共性が重視され、地域全体のインフラや環境を向上させることを目指しています。これにより、地域全体の生活環境が向上し、住民の利便性が向上します。
土地区画整理は、都市計画と連携して行われることが一般的です。都市の発展計画や長期的なビジョンに基づいて、土地利用のあり方が計画的に整備されます。
土地区画整理事業では、地権者(土地の所有者)との協議が不可欠です。地権者との合意を基に土地の再編成が行われ、公正な補償が提供されるよう努められます。
土地区画整理事業では、交通インフラや公共施設、公園などの整備が行われ、地域全体の利便性や快適さが向上します。これにより、都市の機能が均等に分散されます。
土地区画整理事業は、環境に配慮されているため、緑地の確保や防災対策など、持続可能な開発が重視されます。
土地区画整理事業は、地域の発展計画や都市計画に基づいて検討され、事業計画が立案されます。地域のニーズや問題点が明確化され、解決策が検討されます。以下のような手順で行われることが多いでしょう。
土地の所有者や住民との協議が行われ、事業の内容や目的が説明されます。地権者の理解と協力が得られるように進めます。
土地区画整理の基本計画が策定されます。これには土地の再編成や新たな公共施設の配置、緑地の確保などが含まれます。
地域内の土地を地目ごとに整理し、新たな区画を設定します。これにより、効率的な土地利用が実現されます。
基本計画に基づき、具体的な実施設計が行われ、工事が開始されます。新しい道路や公共施設、住宅地の整備が進められます。
土地の所有者への補償が行われ、必要な場合は土地の移転が行われます。公正かつ円滑な補償の実施が求められます。
工事が完了すると、整備された地域が引き渡されます。これにより、新たな土地利用が可能となります。
土地区画整理により、地域全体が活性化し、新たな住民や事業者の誘致が期待されます。具体的にどんな影響があるでしょうか。
新たなインフラや公共施設を整備すたり、山林エリアや住宅地がないエリアを新たに整えることにより、整然とした街並みとなり、生活がしやすくなって不動産価値が向上することがあります。
道路や公園の整備により、住民の生活環境が改善されます。これにより、住みやすい地域が形成されます。
道路や交通インフラの整備により、交通の流れが改善され、通勤や通学がスムーズになります。
土地区画整理は環境への影響が懸念されることもあります。適切な環境への配慮が求められます。
土地区画整理事業では、借換地と保留地という言葉が出てきます。それぞれ解説します。
仮換地とは、土地区画整理事業の期間中に、対象地域の宅地の所有者などが「仮に」使用・収益できる土地のことをいいます。仮換地は、土地区画整理事業をスムーズに行うために事業の施行者が指定します。仮換地は、一般に将来そのまま換地となる予定の土地として定められます。換地とは、ほぼ工事が終った後に作成する換地計画において定められる土地です。したがって、事業途中では仮換地として扱われるのが一般的です。仮換地を購入すれば土地を使用収益できますのでマイホームを建てることも可能です。
保留地は、将来の開発や変更が計画されているが、現在はそのまま保持されている地域を指します。保留地は、将来の利用を見越して一時的に利用を差し控えている状態です。保留地では通常、所有権の変更は発生しません。現在の所有者が土地を維持しながら、将来の利用を見越して一時的に利用を保留している状態です。保留地を取得した場合、担保となる土地が存在しないため、住宅ローンを利用できる金融機関は極めて少なくなります。事前に金融機関への確認が必須となります。
土地区画整理事業では、元々所有していた土地と土地区画整理事業が完了した後に交換する土地との価値に差異が出ることがあります。その際には金銭にて精算を行うことになりますので、事業後に清算金が発生し、負担が生じる場合があることに留意しなければなりません。
このような土地の売買をご契約される場合には、お気軽にご相談ください。
公開日:2023年10月31日
REDSエージェント、宅建士の金谷です。今回は不動産調査における「地番」の重要性について解説します。
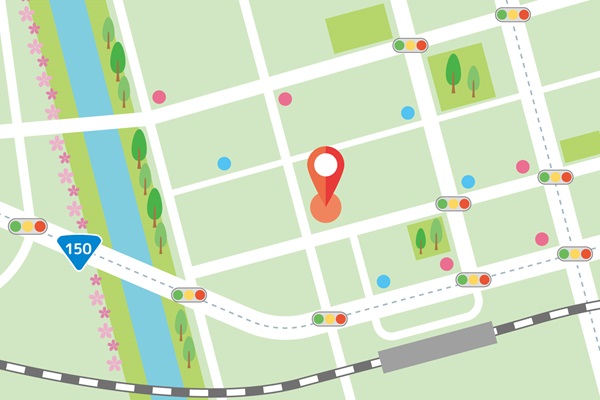
土地にはすべて地番という番号がつけられています。一方、住宅が建築されている土地には地番と住居表示と2つの番号がつけられていて混乱するかもしれません。住居表示は、日本における住所表示制度の一環であり、住居の位置を特定するための番地や番地外住居表示を含むシステムです。住居表示は以下のような特徴を持ちます。
●番地:住居表示における基本的な要素は番地です。番地は地域内の住居や建物が位置する特定の区画を示します。番地には地域の自治体が割り当てる番号があり、通常は道路や通りの両側に沿って連続しています。
●住居表示の要件:住居表示は法律によって定められ、建物や敷地などの所有者が、その建物や敷地について住居表示の申請を行うことが義務付けられています。この申請により、新しい建物が建設された場合や既存の建物に変更があった場合にも住居表示を更新する必要があります。
●住居表示の利点:住居表示は地域の住民や訪問者にとって、正確な住所の特定と位置情報の提供を可能にします。特に郵便配達や緊急サービスなどの公共サービスにおいて重要な役割を果たしています。
●地域ごとの適用:住居表示は地域ごとに適用されるため、地域によって表示の仕組みや規則が異なる場合があります。このため、地域の規制や法律を理解することが重要です。
地番は、日本における土地の位置を識別するための番号システムです。地番は以下のような特徴を持ちます。
●土地区画整理事業:土地区画整理事業の一環として、土地が区画され、各区画には地番が割り当てられます。これにより、土地所有者や行政機関は特定の土地の所有権や位置を識別することができます。
●建物との関連:地番は特定の建物や土地と関連付けられており、建物の所有者がその土地に関連する地番を持つことになります。
●地籍情報との関連:地番は地籍図や地図情報と関連付けられており、土地の所有権の登記や管理に利用されます。これにより、土地の境界や所有権の詳細を特定することができます。
不動産調査において地番の正確な把握は非常に重要です。なぜ地番が重要かを説明します。
●所有権確認:不動産の取引や所有権の確定において、地番は必要不可欠な要素です。正確な地番を持つことで、所有する土地の境界や位置を特定し、所有権を確認することができます。
●法的問題の回避:正確な地番の把握は、法的問題を回避するためにも重要です。隣接する土地との境界争いや所有権に関する紛争を未然に防ぐためには、正確な地番の把握が欠かせません。
●都市計画の確認:不動産調査では、地番を使用して都市計画や土地利用の規制を確認する必要があります。地番を通じて、不動産が属する地域の規制や制限を把握し、将来的な開発計画や利用可能性を判断することができます。
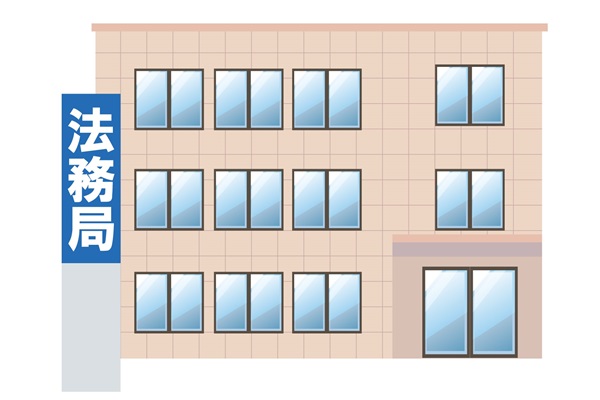
法務局は、土地の登記簿や登記情報を管理し、土地や不動産に関する情報を提供する機関です。土地所有者の確認を行う際には、法務局における登記情報を活用することが一般的です。以下に土地所有者の確認手続きの一般的な流れを示します。
●登記簿の閲覧申請:土地所有者の確認を行うためには、法務局に対して登記簿の閲覧申請を行います。法務局では登記簿を管理しており、土地の所有者や抵当権などの権利関係に関する情報が記載されています。
●登記簿の閲覧:登記簿の閲覧申請が承認されると、登記簿を閲覧することができます。登記簿には土地の所有者や権利関係、抵当権の有無などが記載されています。この情報を確認することで、現在の土地所有者を特定することができます。
●登記簿謄本の取得:登記簿謄本は登記簿の内容を複製した文書であり、法務局に対して申請することで取得することができます。登記簿謄本には土地の所有者や抵当権の登記情報が詳細に記載されており、土地所有者の確認に役立ちます。
以上の手続きにより、法務局にて土地所有者を確認することができます。不動産の登記情報は不動産取引や土地所有者の確認において重要な情報源となります。不動産売買を行う場合には、直近の日付で正確な情報を確認しましょう。