井原 直樹(宅建士・リフォームスタイリスト)
2023年ご売却契約数No.1・ご売却はお任せください。
CLOSE
公開日:2024年3月27日
REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの井原直樹です。2024年1月1日に発生した能登半島地震においては、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興をお祈りし、私も微力ながら地域経済にも貢献したく考えております。
今回の地震は、最大震度7の強い地震ではありましたが、最大震度7にも耐えうることを想定した「新耐震基準」の家屋に多数の倒壊が見られたことが印象的でした。

1981年6月の建築確認以降から、建築基準法による建物に要求される最低限満たすべき地震への耐性基準が大きく変わりました。それを「新耐震基準」といい、現在も適用されている基準です。
新耐震基準は、震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7に達する程度の大規模地震でも人命に危害を及ぼすような倒壊などの被害を免れることを建物に求める基準です。ちなみに、旧耐震基準は、震度5までの地震で倒壊・損傷しないというレベルでよしとされていました。
耐震基準とは、あくまで最低ラインを定めた基準になりますので、旧耐震基準建物が軒並み耐震性に劣るともいえません。極端な例では、法隆寺は1000年間もの間に地震で倒壊したことはありませんが、それだけの耐震性を有していたということです。
一方で、最低ラインを「震度6強から7でも倒壊しない」と定めた新耐震基準で建てられたはずの能登半島の建築物に多数の倒壊が見られたことが今回の焦点です。
今回、想定外の事態を受け、国土交通省は、被害状況や倒壊の原因などを詳細に調査することを目的に「令和6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会」を立ち上げました。
https://www.nilim.go.jp/lab/hbg/iinkai/notohantouzisinniinnkai/notoiinkai.html
詳細な原因については、委員会の調査結果が待たれるところです。そのため、あくまで一般論になりますが、こちらの3点が今回の原因ではないか、と挙げられています。
「2000年基準」というワードが出てきましたが、中古の木造住宅購入時には超重要ポイントなので、ぜひ覚えておいてください。
建築基準法の耐震基準は、1981年6月1日以降で新耐震基準が採用されました。これによって建物の耐震基準はとても厳しいものとなりました。この耐震基準の変化は有名ですが、実はその後も耐震基準がマイナーチェンジされていることはあまり知られていません。
特に重要な改正があったのが、2000年6月1日以降に建築確認申請する木造についての耐震基準で、これが「2000年基準」といわれます。「2000年基準」の主な改正点はこちらです。
以前は、地耐力調査は必須ではありませんでした。併せて品確法も改正され、分譲業者は地盤についても10年保証が義務付けられました。軟弱地盤は地盤改良工事をしたうえで、基礎工事を行うことになりました。
地盤がどのくらいの荷重に耐えられるか調査(地耐力調査)をしないで基礎工事を行うと、地盤が不同沈下(建物が不ぞろいに沈下を起こすこと)を起こし、建物が傾くためです。
以前から腕のよい設計士であれば、耐震性に考慮した配置バランスで設計がなされていましたが、建築確認ではノーチェックでした。南側には窓を多く設置するために筋交いの入った壁を減らし、逆に北側に耐力壁が偏った構造になりがちですが、阪神淡路大震災ではこのようなバランスの悪い偏った配置をした家がねじれて倒壊する例が少なくありませんでした。
木造住宅の柱の柱頭・柱脚(頭や根元部分)、筋交いの端部をそれぞれしっかり固定できるよう筋交いのサイズや部位によって固定する金物が指定されました。地震の際に柱、梁、筋交いが抜けてしまうと、構造耐力が満たせず、建物が倒壊してしまうためです。
このように、マイナーチェンジではありますが、非常に重要な改正が行われました。2000年基準を境に、耐震性には大きな差が出るでしょう。2000年基準を満たさない木造住宅は、「新耐震基準であっても、現行の耐震性ではない」ということを覚えておきましょう。
建築基準法で想定している耐震性とは、「大地震に一度だけ耐えて倒壊しない」ことですので、命に直結する最低ラインを示しているだけだといえます。
しかし、実際に被災した際には、こちらの3点が重要ではないでしょうか。
これらを評価した指標が「耐震等級」です。
〈等級1〉
建築基準法と同等の耐震性能。震度6強~7の地震でも、即倒壊はしない。ただし、大規模修繕や建て替えが必要となる可能性がある。等級1は建築基準法準拠で、必ず取得できる等級です。
〈等級2〉
建築基準法の1.25倍の耐震性能。震度6強~7の地震でも、一定の補修で住み続けられる。学校や避難所といった公共建築物レベル。
〈等級3〉
建築基準法の1.5倍の耐震性能。震度6強~7の地震でも、軽い補修で住み続けられる。消防署や警察署といった災害復興の拠点となる防災施設レベル。
耐震等級については、「住宅性能評価書」で証明されます。これまでは住宅性能評価書を取得していない新築戸建てもありましたが、住宅ローン控除の要件変更で必須になりましたので、これからはほぼすべての新築戸建てで耐震等級の確認ができます。
建物の耐震性がいくら優れようと、それだけでは自然災害には対処しきれません。
REDS宅建マイスターは、各種ハザード情報や、その土地の成り立ちをしっかり把握し、お客様にリスク情報を提供いたします。質の高い不動産売買は、経験豊富なREDS宅建マイスターへお任せください。
気になる物件があるお客様も、
ご売却をお考えのお客様も、
「トコトン安心・お得」な不動産売買をしたいなら!
お気軽に【REDS】宅建マイスター・井原までご相談ください!
メールはこちら
フリーコール 0800-100-6633
携帯電話 080-7564-4417
ご連絡はお気軽にどうぞ!
公開日:2024年2月18日
こんにちは。REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの井原です。
前回のブログでは、住宅ローン控除について深掘りしましたが、今回はその他の税制も含めてまとめて解説します(令和6年度税制改正の大綱をベースにしているため、内容が変更となる場合があります)。

住宅税制それぞれのテーマには、以下のような背景があります。
政府は2050年の脱炭素達成に向けて、エネルギー消費量の約14%を占める家庭部門での省エネに本腰を入れています。そのため断熱性が高い住宅や、太陽光発電設備を有したZEH住宅などに対して、手厚い支援をおこなっています。
背景にあるのは、岸田内閣の目玉政策でもある「異次元の少子化対策」と、「不動産価格の上昇」です。不動産価格は都心部だけでなく、郊外や地方都市でも上昇しており、特に若年層や子育て世帯にとっては購入しにくい状況が続いています。
その両方に対するアプローチとして、即効性の高い税制優遇や給付金などの形で、政府が後押ししてくれています。このような背景のもとに実施される、2024年の支援策を具体的に見ていきましょう。
住宅ローン控除とは、控除期間中は年末の住宅ローン残高の0.7%が、支払った所得税(住民税)から戻ってくる制度です。控除期間は最長13年間です。
例えば年末の住宅ローン残高4,000万円の場合は、28万円がその年の所得税(住民税)からキャッシュバックされるイメージで、節税効果は総額数百万円にのぼり、家を買う最大のメリットとも言えるでしょう。
デフォでもお得な住宅ローン控除が、子育て世帯・若者夫婦世帯についてはさらにパワーアップします。
子育て世帯・若者夫婦世帯とは、以下のいずれかが当てはまる世帯が対象です。
・19歳未満の子を有する世帯
・夫婦いずれかが40歳未満の世帯
※年齢の判定は居住開始年の年末時点となる見込みです。
最大還付額の違いはこちらです(新築住宅の場合)。
①認定住宅(認定長期優良住宅および認定低炭素住宅)
通常:409.5万円 → 子育て・若者夫婦世帯:455万円(+45.5万円)
②ZEH水準省エネ住宅
通常:318.5万円 → 子育て・若者夫婦世帯:409.5万円(+91万円)
③省エネ基準適合住宅
通常:273万円 → 子育て・若者夫婦世帯:364万円(+91万円)
このように、超パワーアップしていますが、来年以降の継続は全くの未定です。子育て・若者夫婦世帯に該当する方は、今年2024年を逃す手はないでしょう。年内入居が条件になるものと思われます。また、省エネ基準に適合しない住宅は、住宅ローン控除の対象外となりました(2024年以降に建築確認を受ける場合)。ハウスメーカーもしっかり対応していますので、ほとんどの物件で住宅ローン控除を受けることができますのでご安心ください。
では次は贈与の特例に行きましょう。
住宅取得資金贈与の特例とは、直系尊属から住宅購入資金の贈与を受けた場合に、500万円もしくは1,000万円分の贈与について、贈与税が非課税となる特例です。
この特例を使わない場合、年間110万円の基礎控除を超える部分について贈与税が課税され、年1,000万円の贈与を受けた場合の贈与税は177万円になります。それが無税になるとしたら非常にお得な制度です。
非課税枠1,000万円の対象物件は以下の3つです。
①省エネ性能がZEH水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6)以上
②耐震等級2以上or免震建築物
③高齢者等配慮対策等級3以上
①~③に該当しないものは500万円の非課税枠になります。
以下の注意点があります。
今回の改正で、新築住宅の省エネ基準は従来から1段階厳しくなり「ZEH水準以上」となりましたが、中古住宅の場合は従来と同じ省エネ基準(断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4)以上でこの特例を受けることができます。
細かい条件が定められています。
①直系尊属から贈与を受けること(叔父・叔母、配偶者の親などは対象外)
②贈与を受ける人の所得が年2,000万円以下であること
③居住開始前までに贈与を受けること
④贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住開始すること
⑤贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告書等を提出すること
⑥取得する住宅の床面積が50㎡以上(所得1,000万円以下の場合は40㎡以上)
これらをすべて満たす必要があります。
税に関する助言は税理士にしかできませんので、税務署に電話で聞いてみましょう! 無料で丁寧に教えてくれます。
次は、お金がもらえるうれしい補助金について見ていきましょう。
「子育てエコホーム支援事業」とは、子育て世帯と若者夫婦世帯の省エネ住宅購入を後押しする制度です。新築住宅で対象となるのは注文住宅と建売住宅で、補助金額は最大100万円/戸です。ここでも出ました「子育て世帯」×「若者夫婦世帯」への援助です。
2023年に施行された「こどもエコ住まい支援事業」が、年度途中で予算に達して早期終了してしまったことを受けて、今回の予算は約1,700億円から約2,100億円へと大きく上積みされました。
①子育て世帯
申請時点において、子を有する世帯。子とは2023年4月1日時点で18歳未満(2005年4月2日以降に生まれた子供)です。ただし、2024年3月末までに工事着手する場合においては、2022年4月1日時点で18歳未満(2004年4月2日以降に生まれた子供)が対象です。
②若者夫婦世帯
申請時点において夫婦であり、2023年4月1日時点で夫婦のいずれかが39歳以下(1983年4月2日以降生まれ)である世帯。ただし、2024年3月末までに工事着手する場合においては、2022年4月1時点でいずれかが39歳以下(1982年4月2日以降生まれ)の世帯が対象です。
補助金の額は以下のとおりです。
●長期優良住宅:100万円/戸
●ZEH住宅:80万円/戸
※市街化調整区域、土砂災害警戒区域または浸水想定区域については、それぞれ50万円、40万円に減額されます。
子育てエコホーム支援事業は、新築購入だけでなく、条件を満たしたリフォーム工事でも最大60万円の補助金が受けられます。REDSリフォームでもご提案させていただきます!
以上、解説してきたのは国による住宅制度です。これに加えて、都道府県や市町村が独自に実施している支援制度があります。
例えば東京都がおこなっている「東京ゼロエミ住宅導入促進事業」では、ZEH水準の新築戸建に対して最大50万円、太陽光発電設備の設置(3.6kw以下)に対して最大39万円の補助金が受けられますので、自治体の公式サイトで確認してみましょう!
2023年の「こどもエコ住まい支援事業」でも、3月に始まった申請が7月に予算に達し、追加予算が組まれたものの、それも2カ月で消化してしまい9月に申請が打ち切られました。子育て世帯への支援は年々手厚いものになっていますが、それだけ利用者も多く、早い時期に申込みが殺到する傾向があります。
「省エネ」×「子育て&若者夫婦」に該当する方は、できるだけ早い時期に申請できるよう検討を進めていきましょう!
2024年の不動産売買も、知識と経験豊富なREDS宅建マイスターへお任せください。
気になる物件があるお客様も、
ご売却をお考えのお客様も、
「トコトン安心・お得」な不動産売買をしたいなら!
お気軽に【REDS】宅建マイスター・井原までご相談ください!
メールはこちら
フリーコール 0800-100-6633
携帯電話 080-7564-4417
ご連絡はお気軽にどうぞ!
公開日:2024年1月11日
新年あけましておめでとうございます。REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの井原直樹です。
旧年中は本当にたくさんのお客様にご支持をいただきまして、お取扱高は20億円を超え、過去最高の実績となり、皆さまのお役に立つことができました。本当にありがとうございました。これからも、REDSのコスパの良い仲介サービスを通して、皆さまのお役に立つことをライフワークとして、一層頑張ってまいります。
2024年の注意点としては、住宅ローン控除の制度変更がありますので、まとめていきます。

年末の住宅ローン残高の0.7%分相当が、所得税・住民税から還付されることでおなじみの住宅ローン控除ですが、2024年1月から大きく変わることをご存じでしょうか。
特に、新築戸建てについては、省エネ基準に適合していることが必須要件になるうえ、控除上限も従来の制度に比べて減額されます。そのため、今後は今まで以上に制度を上手に活用することが求められるでしょう。
2023年までは、省エネ基準を満たしていない新築住宅であっても、最大で3,000万円×0.7%×13年間=273万円の控除を受けることができました。
2024年からは、なんと0円です。
※2023年中に建築確認申請し2024年6月までに竣工する場合は、最大140万円受けられる特例がありますが、一時的な経過措置です。
273万円が0円になってしまうとは、なかなかのインパクトですね。物件の選定時には、「2024年の住宅ローン控除に適合するか」を必ず確認しましょう!
省エネ基準適合住宅も従来に比べて、借入金の上限額は500万~1,000万円ほど減額されることになりました。
2023年までは、省エネ基準を満たした新築住宅であれば、最大で4,000万円×0.7%×13年間=364万円の控除を受けることができました。
2024年からは、最大で3,000万円×0.7%×13年間=273万円の控除となり、差額は91万円です。この91万円の減額分を取り戻すために、ペアローンや連帯債務を活用された方が有利になるケースも出てくるかと思います。
イメージとしては、2023年までは、ご主人様単独で4,000万円お借入の資金繰りをしていた方は、2024年は、ご主人様3,000万円+奥様1,000万円お借入の資金繰りで、あえてペアローンや連帯債務とした方が、お得になる可能性があります。
基本で付帯する団信は、ペアローンと連帯債務で違いがありますので、注意が必要です。
ペアローンの場合:各自の借り入れ分にしか付帯しませんので、一方の死亡や高度障害が起きた際に、双方の借入総額に対して保障をつける場合は、〈金利+0.18%程度〉の別途費用がかかります。
連帯債務の場合:主債務者に対して借入額総額の保障が付きます。主債務者ではない方にも保障をつける場合は、〈金利+0.18%程度〉の別途費用がかかります。
ペアローン、連帯債務のいずれの場合も、それぞれが単独でローンを組むことができる与信が求められますので、収入合算するだけのつもりでも、一定の勤務内容であることが必要です。
住宅ローン控除は、所得税&住民税からの還付になりますので、産休育休で所得が低い期間は、納税をしないので還付もありません。産休育休の期間や、未就業の期間が長期にわたる場合は、住宅ローン控除の恩恵を享受できない場合があります。
連帯債務の場合は、ローン契約が1件なので印紙代も1件分です。しかし、印紙代がかからない電子契約が多くなったので、それほど気にしなくてもよいかと思います。また、5,001万円以上の借入額の場合は、印紙代が連帯債務の場合は1件6万円に対して、ペアローンの場合は1件2万円×2件で4万円なので、かえって安くなります。
「連帯債務」と「連帯保証」は似ていますが全く違います。
「連帯債務」とは1つのローンに対して債務者が複数人いることを意味し、連帯債務者はそれぞれがローン全体に対して責任を負います。 連帯保証人と連帯債務者の大きな違いは、「連帯保証人は債務者ではない」という点です。 なので、連帯保証人は住宅ローン控除を受けらません。(借りた人がお金を返せない場合のみ、返済義務が生じます。)
収入合算でローンを組む際には必ず確認してください。
購入する不動産の所有権持ち分は、住宅ローン返済の負担率や、各自の借入額の比率や、各自の年収の比率により、案分した方が無難です。逸脱している場合は、税務署の判断により、贈与を問われる場合があります。
思い当たるご注意点を挙げましたが、ケースバイケースなので、お気軽にご相談ください。
今回の住宅ローン控除改正では、省エネ基準適合住宅だけでなく、認定住宅やZEH水準省エネ住宅も従来に比べて借入金の上限額が500万~1,000万円ほど減額されることになりました。
すでに行われた1%→0.7%の改定など、流れとしては縮小の傾向にありますので、気になる物件がある方は、お得な税制優遇があるうちにご検討を始めましょう!
2024年の不動産売買は、経験豊富なREDS宅建マイスターへお任せください。
気になる物件があるお客様も、
ご売却をお考えのお客様も、
「トコトン安心・お得」な不動産売買をしたいなら!
お気軽に【REDS】宅建マイスター・井原までご相談ください!
メールはこちら
フリーコール 0800-100-6633
携帯電話 080-7564-4417
ご連絡はお気軽にどうぞ!
公開日:2023年12月6日
REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの井原直樹です。2023年7月27日、長期金利の上限をコントロールする金融政策であるYCC(イールドカーブ・コントロール)の変更が発表されました。この変更で住宅ローンはどのような影響があったか、さらに予想されるインフレ下では住宅ローンはどのように計画すればいいのかについて解説します。

今回の日銀の政策変更の要点は、長期金利(10年物の国債利回り)に対する、金利操作(イールドカーブ・コントロール)の撤廃でした。
これまでは、長期金利の上限が0.5%を超えないように、日銀が国債を大量購入して金利を抑え込んでいました。ところが、今回の政策変更では「上限」を「めど」という表現に改め、おおむね1.0%までの一定の上昇を許容することにしたのです。
発表後、長期金利は一気に0.6%台まで上昇し、11月1日には0.97%にまで一時的に上昇しました。2013年5月以来、およそ10年5か月ぶりの水準まで上昇したことになったため、長く続いた金融緩和の終了への第一歩と受け止められ、金利の先高観が強まっています。
つまり、本来は今回のYCC撤廃とは関係がありませんが、短期金利をベースとした変動金利の住宅ローンについても「近々マイナス金利政策も解除されて、変動金利も上がるのではないか?」と考える方が増えました。
今回の政策変更は、固定金利型の住宅ローンである「フラット35」「10年以上の固定金利ローン」の金利上昇に直結します。
一方で、短期金利はマイナス金利政策を維持しているため、短期金利に連動する変動金利の住宅ローンについては、まだまだ超低金利の状態が続いています。その結果、住宅ローン金利の固定・変動の金利差がますます拡大し、変動金利を選択する方が依然として圧倒的に多い状況となっております。
先に述べたように、変動金利にも先高観があり、いつ金利は上昇するのか(マイナス金利政策が解除されるのか)、皆さん戦々恐々とされています。
日銀としては「賃金の上昇をともなう持続的・安定的な物価上昇」、つまり安定的なインフレが確認できれば、マイナス金利政策を解除するスタンスのようです。現在の物価上昇はコストプッシュ型の一時的なもので、マイナス金利政策を修正するのは時期尚早としていますが、2023年の春闘では賃上げ率が3.58%と約30年ぶりの高水準となったように、賃金上昇をともなった物価上昇の兆しも見えてきました。
30年以上続いたデフレからの脱却を果たした際には、変動金利も上昇してしまうという状況ですね。
上記を踏まえると、これから未体験のインフレ時代が到来するかもしれませんので、しっかり備えていきましょう。資金計画の基本や、インフレとの関係を考えていきます。
インフレとは物価や賃金の上昇というイメージがありますが、本質的には貨幣価値の下落です。極端なインフレの場合、物価が1年で2倍になったとすれば、貨幣価値は1年で半分になったと同じです。不動産を含むモノの価格は上がり、現金はその分目減りしたことになります。
そして住宅ローンなどの借入金も、借りた時点で元本が確定していますので、同様に目減りします。
日銀のインフレ目標は年2%で、「賃金の上昇をともなう持続的・安定的な物価上昇」を目指しています。日銀は、この先3年間の消費者物価の予測を発表しておりますので、見ていきましょう。
●2023年:+2.5%
●2024年:+1.9%
●2025年:+1.6%
仮に、こちらの予測どおりにインフレが進行した場合、2022年に5,000万円だった物件の価格はこちらになります。
●2023年:5,125万円
●2024年:5,222万円
●2025年:5,305万円
インフレ率だけで、3年間で305万円も上昇することになります。つまり、貨幣価値は3年間で約6%下がることになります。不動産の価格が上昇するとともに、預貯金や借入額などの貨幣価値は目減りするということがポイントです。
インフレ下ではモノの価格が上がり、貨幣価値が目減りするので、できるだけ早く貨幣を不動産などのモノに変えておいたほうがいいでしょう。ただ預金しているだけのお金があるなら、不動産や株などに変えておくことをおすすめします。
よく不動産を買うために、ローンを組むにあたって頭金を用意するべきか、それとも頭金なしで買うべきか、という議論があります。インフレが予想される現状では、「頭金を貯めてから買う」という考え方はおすすめできません。というのも、インフレ下では頭金を貯めている間に不動産価格は上がり、貨幣価値が目減りするからです。
次に、住宅ローンの返済期間と金利タイプについて考えてみましょう。今後インフレが継続すると仮定すれば、返済期間は長いほどお得になります。
仮に年率2%の物価上昇が続けば、現在1万円のモノは10年後に1万2,190円、20年後に1万4,859円、30年後に1万8,114円になります。逆に、現在の1万円の価値は、10年後に8,203円、20年後に6,730円、30年後に5,521円に下落します。つまり、現在の借入金1,000万円は30年後には約552万円の価値に目減りするので、返済期間が長い方がお得になります。
最近は50年間で返済可能な住宅ローンも登場しておりますので、インフレが続くと判断する場合には有用な選択肢になりますね。
ただし、インフレ継続に伴い、マイナス金利政策が解除され、金利上昇が年2%を超えてしまうと損になりますので、非常に悩ましいところです。
まとめると、インフレ対策に特化した資金経過はこちらです。
①余裕のある預貯金は頭金へ充当
②返済期間は最も長く(借入金利に注意)
③金利タイプは変動(金利上昇率に注意)
あくまで、今後も安定したインフレが数十年継続する前提です。将来の経済状況は予測できませんので、臨機応変に対応していきましょう。
将来の予測は難しいからこそ、堅実な資金計画を。家計全体の資産と借入のバランスと、ご自身のライフステージを考えることが大切です。
不動産購入は資産を保有することに伴い、負債やリスクも保有することになりますので、長期的な視点で安全性を点検する必要があります。
将来の経済予測は難しいですが、失敗しにくい物件の選定や、資金計画のアドバイスはできますので、経験豊富なREDS宅建マイスターへお任せください。
気になる物件があるお客様も、
ご売却をお考えのお客様も、
「トコトン安心・お得」な不動産売買をしたいなら!
お気軽に【REDS】宅建マイスター・井原までご相談ください!
メールはこちら
フリーコール 0800-100-6633
携帯電話 080-7564-4417
ご連絡はお気軽にどうぞ!
公開日:2023年10月28日
REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの井原です。
資産価値が維持しやすく節税効果もあるということで、タワーマンションは長らく富裕層に人気がありました。相続税の評価額が実勢価格を下回ることを利用して相続税を節税するために高層階を複数購入するケースも見られましたが、過度な節税の是正のために2024年1月から国税庁が新たな算定ルールを導入すると見られています。

富裕層がタワーマンションの、特に「高層階」を複数購入するケースが多いのは、希少性があるため資産価値を維持しやすいという不動産的な一面に加え、通常の20階建て未満の中低層マンションや一戸建てに比べて、相続税や固定資産税を節約できることが多かったためです。
多くのタワーマンション高層階が、はっきりと、節税目的に購入されていたのです。
しかし、こうしたケースは税の公平性に欠けるのではとの議論があり、固定資産税については2017年度の税制改正で是正されました。是正前の固定資産税は、高層階でも低層階でも専有面積が同じなら固定資産税が同額だったので、一般的には購入金額が高い高層階のほうが、低層階に比べて相対的に固定資産税がお得な状態でした。この点について、高層階になればなるほど固定資産税が高くなる仕組みが導入されたのです。
具体的には、2018年以降に建設されたタワーマンションが対象で、中間階は増減税なしとした上で、中間階から1階高くなるごとに0.256%ずつ増税されます。その一方で、1階ずつ低くなるごとに0.256%ずつ減税される仕組みになりました。
現在は2018年以降に建設されたタワーマンションに限られた話ですが、今後は全てのタワーマンションにも対象が拡大されるものと思われます。
来年から始まる新しい算定ルールでは、タワーマンションの相続税評価額と時価(売買価格)との間に、大幅な乖離が生じていることにメスが入ります。
現行制度では、相続税を計算する際に適用される相続財産の評価額は、現金ならそのままの価格(現金100万円=相続評価額100万円)であり、株式は時価で評価されています。
一方で、マンションをはじめとする不動産は、相続税評価額が主として用いられており、中低層のマンションでも、相続税評価額は実際の売買価格よりも3割程度は低く設定される傾向がありました。そのため、節税効果が期待できていたのです。
さらに、タワーマンションのように少ない敷地に対して、住戸数が非常に多い建物になると、一戸あたりの持ち分となる土地の面積が小さくなるため、中低層マンションにくらべて、更に相続税評価額が大幅に低くなる傾向にありました。このため節税のための不動産購入として非常に人気がありました。
来年からの新ルール(案)では、従来の相続税評価額に、マンションの築年数や部屋の階数などから国税庁が一定の根拠があると考える係数によって算出される「乖離率」を掛けて求められます。
この乖離率が1.67倍以上の場合、従来の相続税評価額に「乖離率と0.6」を掛けた価格で評価し、1.67倍未満であれば、従来の相続税評価額で評価されます。
なぜ1.67倍を境界線にしているのかといえば、「1.67倍の逆数が60%だから」というのが理由のようです。「従来の相続税評価額が60%を下回っているかどうか」という判定です。
つまり、「相続税評価額が実勢価格の60%を下回るのは許さない」という国税庁の意思が見て取れるわけです。
まずは「乖離率」の計算式を見てみましょう。
乖離率:A+B+C+D+3.220
〈A築年数〉=築年数×△0.033
〈B総階数指数〉=総階数÷33×0.239
〈C所在階数〉=専有部分の所在階×0.018
〈D敷地持ち分狭小度〉=土地持分面積÷専有床面積×△1.195
※「総階数指数」は1を超える場合は1で計算されます。
この計算式を見ると、築年数が浅く、マンション全体が超高層で、所有している階が高層階になればなるほど、敷地持ち分狭小度が小さくなればなるほど、乖離率は1.67倍を超えやすくなりますので、影響は大きくなるでしょう。
モデルケースで計算してみましょう。
〈従来の評価額3,600万円のマンション、築15年、28階建ての10階、74㎡の住戸で土地持分7㎡〉
いたって普通のマンションです。しかし、このケースの乖離率を計算すると、なんと「3」になります。
乖離率が1.67倍を超えている場合は、評価額=「従来の評価額×3.0×0.6」と計算されますので、従来の評価額が3,600万円だったとしても、新たな評価額では6,480万円になってしまいます。
法定相続人が1人であれば、相続税の基礎控除額が3,600万円あるので、マンション以外の相続財産がなければ、相続税はかかりません。しかし、相続税評価額が6,480万円になると、基礎控除の3,600万円を超えた部分の2,880万円が相続税対象額なります。
マンション以外の相続財産がなく、特例などがないとした場合、2,880万円に対する相続税はこちらになります。
2,880万円×15%=432万円
-50万円の控除額
382万円が相続税額になります。
相続税がかかるはずではなかったのが382万円になるのは非常に大きいものです。
国税庁の「マンションの相続税評価額と市場価格の乖離率の推移」によると、全国平均の乖離率は、2013年は1.75倍でしたが、2018年には2.34倍にまで上昇しているようです。
また、2018年時点で乖離率が2.0以上、つまり評価額が売買価格の半分以下になっていると思われるマンションの割合は全体の約65%を占めるようです。
「タワーマンションの相続には相続税がかかるもの」と肝に銘じておけば、後顧の憂いを断つ物件選定と、ライフプランニングができるのではないでしょうか。
2023年の不動産売買も、REDS宅建マイスターへお任せください。
気になる物件があるお客様も、
ご売却をお考えのお客様も、
「トコトン安心・お得」な不動産売買をしたいなら!
お気軽に【REDS】宅建マイスター・井原までご相談ください!
メールはこちら
フリーコール 0800-100-6633
携帯電話 080-7564-4417
ご連絡はお気軽にどうぞ!
公開日:2023年9月24日
こんにちは。
仲介手数料が必ず割引、更には無料のREDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの井原です。
表題の件、2024年の住宅ローン控除の適用条件が変更される予定です。今回は、その背景と、変更点についてお話しさせていただきます。

菅義偉前首相が「2050年カーボンニュートラルの実現」を2020年に宣言したように、世界は温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする方向へ向かっています。住宅・建築物においても、2050年にストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指すことになっていることから、その原動力となるように、今回の適用条件変更となったようです。
2024年以降は「省エネ基準」を満たさないと、新築住宅では住宅ローン減税を受けられません。
※住宅ローン減税は、住宅ローンを組んでマイホームを購入した人を対象にした減税措置で、一定の条件はあるものの、年末の住宅ローン残高の0.7%の金額を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間差し引くことができる制度です(詳しくは国交省HP等の公式情報をご覧ください)。
2023年内に新築住宅に入居した分については、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」であったとしても3,000万円を上限にして住宅ローン控除を受けることができますが、2024年以降、住宅ローン控除を受けるためには、省エネ基準に適合した住宅・建物であることが条件になります。
2023年末までに建築確認を受けている場合は、省エネ基準を満たしていなくても、2,000万円を上限にして住宅ローン控除を受けられました。
しかし、原則2024年以降入居分については、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」だと、住宅ローン控除が受けられなくなります。
ここまで劇的な条件変更がなされた背景は何でしょうか。最終エネルギー消費量の推移(出典:経済産業省資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」)を見ると、1990年比で最も削減が進んでいるのは「産業部門」で、2019年時点において15.7%減と順調に減少しているのに対して、「業務部門+家庭部門」を見ると、16.9%増と大幅増になっていることにあります。
そうしたデータを受け、住宅への太陽光パネルの設置について、「2030年には新築戸建住宅での太陽光発電設備の設置割合6割」「2050年には設置が合理的な住宅・建築物において太陽光発電設備の設置が一般的」となることを目標とする、と2021年に閣議決定された「エネルギー基本計画」に明記されました。
このような適用条件変更の背景により、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」に対する税制優遇措置をなくすに至りました。
2024年1月以降に建築確認を受ける新築住宅で、住宅ローン減税を受けるためには、【最低でも】省エネ基準に適合していなければなりません。
【最低でも】というのは、省エネ基準適合住宅の場合、住宅ローン減税の上限は3,000万円ですが、ZEH水準省エネ住宅になると3,500万円、さらに認定長期優良住宅・認定低炭素住宅になると4,500万円までに、上限額が増額される仕組みになっているからです。
このように差をつけている理由は、それぞれの基準を満たすためには建設コストが上がる分、住宅の価格が高額になるからで、それはこのような差があります。
◆最低基準の省エネ基準適合住宅
断熱等性能等級(外壁、窓を通しての熱の損失の防止を図るための断熱化による対策の程度を示す等級)4以上かつ一次エネルギー消費量等級(一次エネルギー消費量の削減のための対策の程度を示す等級)4以上の性能を有する住宅。
◆ZEH水準省エネ住宅
断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の性能を有する住宅。
「省エネ基準適合住宅」の証明書類は以下のいずれかが必要になります。
(1)建設住宅性能評価書の写し
※建設住宅性能評価書は、登録住宅性能評価機関が発行するもので、断熱等性能等級が4以上、一次エネルギー消費量等級が4以上であること。
(2)住宅省エネルギー性能証明書
登録住宅性能評価機関のほか、対象住宅の設計・工事監理等を実施した建築士による証明も可能で、前出の建設住宅性能評価書に比べると柔軟な対応が可能になっています。
2025年4月からは、原則としてすべての新築住宅・非住宅に対して省エネ基準への適合が義務付けられる予定です。そして、2030年にはZEH水準の省エネ性能の確保を目指すとあります。
将来的には、既存住宅であっても、省エネ基準に適合していない物件は税制優遇が受けられず、資産価値が下落しやすい状況が予見されます。省エネ基準適合については、資産価値を重視した物件選びには欠かせないポイントになっていくかもしれません。
2023年の不動産売買も、REDS宅建マイスターへお任せください。
気になる物件があるお客様も、
ご売却をお考えのお客様も、
「トコトン安心・お得」な不動産売買をしたいなら!
お気軽に【REDS】宅建マイスター・井原までご相談ください!
メールはこちら
フリーコール 0800-100-6633
携帯電話 080-7564-4417
ご連絡はお気軽にどうぞ!
最終更新日:2023年8月22日
公開日:2023年8月21日
こんにちは。仲介手数料が必ず割引、さらには無料のREDS宅建士、宅建マイスターの井原です。
表題の件、早速ではございますが、今回は主要なネット銀行系(auじぶん銀行、住信SBIネット銀行、楽天銀行、ソニー銀行、イオン銀行、PayPay銀行)での住宅ローンの特徴をまとめます。
これは個人の感想ですので、お含みおきくださいますようお願い申し上げます。また、審査基準については各金融機関から公表されておりませんので、個人の経験則になりますのでご容赦ください。
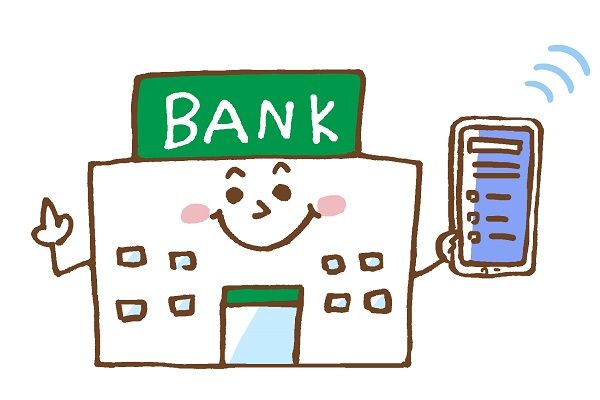
都市銀行、地銀信金系の場合は、審査結果に応じて金利も変わることが多いですが、ネット系銀行の場合は、審査通過イコール最優遇金利の適用、となることが多いです(そのため、審査も厳しい水準になります)。
団信については、都市銀行と地銀信金系は、金利上乗せなしでは基本の団信しか付帯しませんが、主要なネット銀行では無料で全疾病保障などが付帯します。
融資手数料、融資保証料はほとんどのネット系銀行でいずれも2.2%程度となっています。楽天銀行、イオン銀行は定額型もありますので、後記ご確認ください。
融資「手数料」と融資「保証料」の違いですが、融資手数料の場合は、早く返し終わっても、手数料は1円も戻ってきません。一方、融資保証料の場合は、場合によりますが、数十万円くらい戻ってくることがあります。この差は何かといいますと、「手数料」は文字どおりの手数料ですが、「保証料」は〇〇万円を〇〇年間借入することに対する保証を、銀行傘下の保証会社へ依頼するための費用です。
数年後に売却する可能性の高いお客様は、融資保証料型の方がお得になる場合が多いですので、要チェックです。
では、各行の詳細を見ていきましょう。
言わずと知れたネット銀行のパイオニア。
●無料で付帯される内容
・40歳未満の方:基本団信+全疾病保障+3大疾病(がん含む)50%保障
・40歳以上の方:基本団信+全疾病保障
●全疾病保障の適用条件
全疾病により「就労不能状態」となり、
・11回目の返済日まで、返済額が保険金として支払われる
・12カ月を経過した日の翌日0時まで就業不能状態が継続した場合、その時点のローン債務残高相当額が保険金として支払われる
「1年間の就労不能状態」が要件なので、かなりハードルは高いでしょう。しかし、入院ではなく「就労不能状態」というのがポイントです。自宅療養でも対象になる可能性があります。
私の体感値では、お客様からの人気No.1です。
●無料で付保される内容
・50歳以下の方:基本団信+全疾病保障+4大疾病(がん含む)50%保障
・51歳以上の方:基本団信+全疾病保障
●全疾病保障の適用条件
全疾病により「就労不能状態」となり、
・入院が連続して31日以上になった場合(以降、入院が継続して30日に達するごとに)毎月の住宅ローン返済額が無料
・入院が連続して180日以上になった場合、その時点のローン債務残高相当額が保険金として支払われる
住信SBIネット銀行に比べて、半分の入院期間で住宅ローン残債が0になります。しかし、「入院に限定」されますので、こちらの方がハードルは高いでしょう。住信SBIネット銀行は3大疾病保障であるに対して、auじぶん銀行の4大疾病保障は「腎疾患肝疾患」が加わっています。
団信内容は、auじぶん銀行と住信SBIネット銀行のハイブリッド! なんと、融資手数料はいくら借りても33万円の定額制となっています。
●無料で付保される内容
・基本団信+全疾病保障+がん診断で50%保障
●全疾病保障の適用条件
就労不能状態となり、
・毎月27日時点で、所定の就労不能状態が15日をこえて継続している場合、毎月の住宅ローン返済額を保障
・就労不能状態が1年を超えて継続した場合、その時点のローン債務残高相当額が保険金として支払われる
・「がん」と診断された場合、住宅ローン残高の50%相当額が保険金として支払われる
「がん団信50%は無料で付けたい! しかし、“入院半年”ではなく、“就労不能1年”の保障がほしい!」という方にはうってつけです。
以下、ネット銀行の審査について知っておきたいことを列挙します。
資本金が10億円・100億円に区分があるようです。1億円未満の企業は厳しい印象ですが、プライム上場企業の100%子会社であれば有利です。
ご年収は、400万円を区切りにお借入可能額が大きく変わります。
サラリーマンの場合、試用期間中は厳しくなりますが、大企業の場合は1カ月分の給与明細があればチャレンジ可能です。有利な状況に変わるのは、源泉徴収票に現勤務先からの丸1年分の収入が反映された状態です。
個人事業主、経営者、フリーランスの方は不可となることが多いです。
銀行によっては制限がありますが、産休前のご収入で審査が可能です。退職ではなく、ご勤務を継続していることが重要です。育休明けの場合、源泉徴収票の金額が低くても、フルタイム勤務時のご年収で審査可能な場合が多いので、ご安心ください。
非正規雇用の方は不可となることが多いです。
現居宅の家賃を経費計上している場合で、都市銀行でNGとなってしまった場合はチャンスありです。ご相談ください。
本来は現金で用意するべき諸費用ですが、ネット銀行の場合、本件(物件価格)と同じ金利で融資してくれます。都市銀行は物件が旧耐震物件の場合は、諸費用分の融資が難しい場合がありますが、一部のネット銀行では、ご本人の属性がよければ、難なく融資してくれます。
都市銀行系は投資懸念から、単身者のお客様には厳しいですが、ネット銀行では、ご本人の属性がよければ、難なく融資してくれます。
永住権がないお客様の場合、SBI新生銀行では配偶者が日本国籍であれば融資可能です。
これは一発アウトです。
1981年6月以前に、建築確認申請がされた物件を旧耐震基準物件といいます。耐震診断などを行い、現行の耐震基準に適合することの証明できる場合は、新耐震基準物件と同等に審査されます。旧耐震物件であっても、ネット銀行ではご本人の属性がよければ、難なく融資してくれます。
楽天銀行以外は不可です。定期借地権になると楽天銀行でも不可なので、借地権物件は都市銀行をメインにご検討ください。
マンションの場合は、壁芯(もしくは登記簿)30㎡~が基準です。一戸建ての場合は、土地が40㎡以上でないと融資不可です。
マンションの場合は、住信SBIネット銀行が登記簿25㎡以上で可能です。戸建ての場合、auじぶん銀行が土地30㎡以上で可能。またイオン銀行はマンション、戸建てともに、面積の要件がありません(←重要)ので、土地40㎡未満の狭小住宅で、低金利の住宅ローンをお使いいただく場合は、auじぶん銀行とイオン銀行の2択になります。
リフォームローンは基本的には不可ですので、ご希望の場合は都市銀行がいいと思います。
注文住宅は先に土地を購入し、後から建物を建築します。最大のポイントは、いつまでに「請負契約」が必要か(いつまでにハウスメーカーを決める必要があるか)です。というのも、いい土地はすぐに売れてしまいますので、早く土地を購入する必要がありますが、ハウスメーカーはゆっくり決めたいというご希望があるからです。
土地融資分の本申込み時までに請負契約が必要な場合が多く、ハウスメーカーをゆっくり決めたい方は、三井住友銀行がいいですね。ネット系銀行では、土地の本審査承認から建物完成が9カ月の猶予があるので、イオン銀行もいいと思います。
また、土地購入時に土地分の融資実行などの分割実行ができないので、つなぎ融資を利用する必要があります。
以上、思い当たる部分を列挙させていただきましたが、審査基準はまだまだございます。私たちは、これらの条件を踏まえて、お客様にベストなご提案をさせていただいておりますので、ご不明点は私にご質問いただいた方が早いかもしれません。
今回はネット系銀行に絞ってご説明させていただきました。
2023年の不動産売買も、REDS宅建マイスターへお任せください。気になる物件があるお客様も、ご売却をお考えのお客様も、「トコトン安心・お得」な不動産売買をしたいなら! お気軽に【REDS】宅建マイスター・井原までご相談ください!
メールはこちら
フリーコール 0800-100-6633
携帯電話 080-7564-4417
ご連絡はお気軽にどうぞ!
最終更新日:2023年8月9日
公開日:2023年6月19日
こんにちは。 仲介手数料が必ず割引、更には最大無料のREDS宅建士・宅建マイスターの井原です。
今回は都市銀行(三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行)での住宅ローンの特徴をまとめていきます。 これは個人の感想ですので、お含みおきください。 審査基準については各金融機関から公表されておりません。個人の経験則になりますのでご容赦ください。

事前に各項目をご説明します。
・金利
各行あまり変わらず、変動金利は0.375~1.075%。審査結果によりますが、自己資金の割合により変わることが多いのが現状です。
・団信
無料で付帯するのは、基本の団体信用生命保険(保険料無料・死亡と高度障害のみ保障)だけですので、ネット銀行と比べると見劣りします。別途、金利上乗せや保険料を支払うと、疾病保障を付保することができます。
・融資手数料、融資保証料
融資手数料型しか取り扱いがないのは、三菱UFJ銀行、三井住友銀行です。手数料の金額は、借入金額の2.2%です。
みずほ銀行、りそな銀行は、融資保証料型も選択することが可能です。多くの銀行が融資手数料型のみの取り扱いになりますので、これは貴重な選択肢です。融資保証料の金額は、融資手数料と大差ありませんが、以下の内容が異なります。
融資手数料は早く返し終わっても、手数料は1円も戻ってきません。一方、融資保証料は場合によりますが、数十万円戻ってくることがあります。
金額はいずれも同程度で借入金額の2.2%程度です。この差は何かというと「手数料」が文字どおり手数料なのに対し、「保証料」は〇〇万円を〇〇年間借入することに対する保証を、銀行傘下の保証会社へ依頼するための費用だからです。
仮に35年間の保証期間に対して、5年後に売却により完済したら、残りの期間分などに相当して返金があります。
元々、都市銀行などほぼすべての銀行が「保証料」として請求しておりましたが、長引く超低金利時代の影響か、ネット銀行を筆頭に、手数料のみ取り扱う金融機関が増えています。数年後に売却する可能性の高いお客様は、融資保証料型の方がお得になる場合が多いですので、要チェックです。
都市銀行の住宅ローン審査のポイントについて各項目ごとに解説します。
年収400万円を区切りに、借入可能額が大きく変わってきます。みずほ銀行は700万円以上で、さら大きく借りられるようです。
試用期間中は厳しくなりますが、大企業の場合は1か月分の給与明細があればチャレンジ可能です。源泉徴収票に現勤務先からの丸1年分の収入が反映された状態になると、非常に有利になります。
勤務先が中小企業でも問題ありませんが、帝国データバンクなどの企業データベースに登録がない企業の場合は、少し厳しくなります。また、フリーランスや親族経営企業の経営者には厳しい印象です。サラリーマン経営者の場合は、会社の決算内容は不問になることが多いです。自営業者でも安定的な高収入の場合にはチャンスがあり、個人で飲食店経営のお客様でも審査通過の実績があります。
銀行によっては制限がありますが、産休前のご収入で審査が可能です。退職ではなく、ご勤務を継続していることが重要です。育休明けのため、源泉徴収票の金額が低くても、多くの場合、フルタイム勤務時のご年収で審査可能ですので、ご安心ください。
収入合算やペアローンのお相手なら非正規雇用でもOKですが、それでも年収300万円以上が目安になります。主債務者になる場合は、源泉徴収票で丸1年のご収入が確認できないと厳しくなりますので、ご勤続は最低でも丸1年必要です。契約社員の場合は、雇用契約書が必要です。アルバイト雇用の場合は基本NGです。
一番のポイントは「現居宅の家賃を経費計上しているか」です。している場合は、購入しようとしている不動産も「住居兼自宅とするのでは?」と疑義がかかりますので、大きなマイナスになります。具体的には、経費計上している比率で物件価格から減額されてしまう場合があります。その場合は、都市銀行ほど厳しくないネット銀行などがお勧めです。株の売却益(損失)など、一過性の収入(損失)は、収入判定では考慮されません。
各銀行ともに、本件(物件価格)と同じ金利で融資してくれます。審査上で厳しくなるケースは、旧耐震基準(1981年6月以前に建築確認を受けた)物件と、「単身者」のお客様の場合です。旧耐震基準の物件を単身者のお客様が購入する場合、「頭金1割を必須」とする銀行もあります。
数年前のフラット35不正利用事件の時から、単身のお客様への審査が厳格化されています。「フラット35不正利用事件」とは、自宅として購入すると融資を受けて、実際には賃貸で運用するような不正利用が発覚した事件のことですが、事件の不正者に単身者が多かったことから、各銀行ともに単身者への融資基準を引き締めました。
購入する物件が50㎡未満の物件の場合も、居住用ではなく投資用に使うのではないかという懸念があるとして、審査が厳しくなる場合があります。その場合は、諸費用は借りられなかったり、頭金が必要だったり、金利が高かったりなどするケースがあります。こうした条件はありますが、銀行の中でも比較的、三菱UFJ銀行は寛容な印象があります。
日本で暮らす外国人の方で、永住権がない人でも、三菱UFJ銀行と三井住友銀行では審査可能です。ただし、単身の方は非常に審査が厳しく、大手企業にお勤めの場合のみチャレンジ可能です。上陸許可日から5年経過していることと、頭金2割以上を入れることが必須条件です。
住宅ローンを都市銀行で借りる場合、個人信用情報に問題がある(滞納歴など)と、一発アウトです。
1981年6月以前に、建築確認申請がされた物件を旧耐震基準物件といいます。耐震診断などを行い、現行の耐震基準に適合することの証明ができる物件は、新耐震基準物件と同等に審査されます。三菱UFJ銀行は旧耐震基準物件を、全く取り扱っていません。それ以外の3行は融資可能です。
借地権物件の場合、築年数の古い物件は注意が必要です。定期借地権の場合は、残存期間が上限になります。各行それぞれ基準がありますので、ご相談ください。マンションの場合のみ、三菱UFJ銀行は融資不可です。
マンションの場合は、壁芯(もしくは登記簿)30㎡以上が基準です。一戸建ての場合は、土地が40㎡以上でないと融資不可です。また、㎡数に関わらず、ワンルームの間取りの物件には三井住友銀行では融資不可です。
中古物件を買って、自分でリフォームされる場合、各銀行で、物件価格にリフォーム費用を上乗せして融資可能です。各行それぞれ基準がありますので、個別にご相談ください。三菱UFJ銀行とみずほ銀行では、収入とのバランスが合えば、上限額の設定はありません。
注文住宅は先に土地を購入し、後から建物を建築します。最大のポイントは、いつまでに「請負契約」が必要か(いつまでにハウスメーカーを決める必要があるか)です。というのも、いい土地はすぐに売れてしまいますので、早く土地を購入する必要がありますが、ハウスメーカーはゆっくり決めたいというご希望があるからです。
この場合は、三井住友銀行が最もお勧め。土地の購入(決済)から、建物着工までに半年程度の猶予が認められるからです。よって、土地決済からハウスメーカーを決定する請負契約までおおむね4~5か月程度の猶予があります。
以上、思い当たる部分を列挙させていただきましたが、審査基準はまだまだあります。REDSではこれらの条件を踏まえて、お客様にベストなご提案をさせていただいております。ご不明点はすぐに私にご質問いただいた方が早いかもしれません。
今回の住宅ローン解説は都市銀行に絞ってご説明させていただきました。次回は、ネット銀行をご説明いたしますので、どうぞご期待ください。
2023年の不動産売買も、REDS宅建マイスターへお任せください。
気になる物件があるお客様も、ご売却をお考えのお客様も、「トコトン安心・お得」な不動産売買をしたいなら!
お気軽に【REDS】宅建マイスター・井原までご相談ください!
メールはこちら
フリーコール 0800-100-6633
携帯電話 080-7564-4417
ご連絡はお気軽にどうぞ!
最終更新日:2023年6月30日
公開日:2023年4月24日
こんにちは。
仲介手数料が必ず割引、更には無料の
REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
このたび、REDSとauじぶん銀行が直接提携となりました。
これまでは代理店を経由したお取扱いしかできませんでしたが、
直接提携となり、金利は0.296%~でご利用いただけます!
しかも、auモバイル優遇割、じぶんでんき優遇割への加入不要で、この金利です。
直接提携でない場合は0.319%(キャンペーン金利)なので、REDSで仲介させていただくだけで更にお得になるという事ですね!
先日の住信SBIネット銀行の0.32%も驚愕でしたが、auじぶん銀行も追従してきました。
お客様合わせて、より良いご提案をさせていただきます。
気になる物件があるお客様も、
ご売却をお考えのお客様も、
お気軽に【REDS】宅建マイスター・井原までご相談ください!
ご連絡はお気軽にどうぞ!
最終更新日:2023年6月26日
公開日:2023年4月17日
こんにちは。
仲介手数料が必ず割引、更には無料の
REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
こちらは、贈与税がかからずに住宅資金の贈与を受けられる大変貴重なチャンスでしたが、
「今年で終わるのでは?」と囁かれています。
ちなみに、贈与税がかからずに贈与を受けるチャンスは、人生では非常に少ないです。
それは、国が「贈与税と相続税の一体化」を推進する姿勢を見せており、相続前の資金移動を許さない姿勢を強めています。
税制大綱より抜粋すると
・相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する
・贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では、家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある。
との事です。
また、毎年110万円の贈与に贈与税がかからない「暦年贈与」については、既に今年から見直しされています。
改正前
相続の3年以内に行われた暦年贈与は相続財産に含める
改正後
相続の7年以内に行われた暦年贈与は、総額から100万円を控除して相続財産に含める
一方で、これまで全然人気の無かった「相続時精算課税制度」については、
110万円の暦年贈与(的な控除枠)を新設して、「贈与税と相続税の一体化」に向けて破格の優遇をしています。
今後は相続時精算課税制度の利用は増えていくと思います。
受贈者が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、
贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、
一括して相続税として納税する制度です。
要するに、贈与時ではなく、相続時に一切を精算して、相続税を課税するという事ですね(名称そのまま)
国としては贈与税をなくして、相続税に一本化したい様ですので、
※こちらのブログは個人の備忘録ですので、正しくは税務署にお尋ねください。
気になる物件があるお客様も、
ご売却をお考えのお客様も、
お気軽に【REDS】宅建マイスター・井原までご相談ください!
ご連絡はお気軽にどうぞ!