津司 徳義(宅建士・リフォームスタイリスト)
客観的なデータを根拠にご提案させて頂きます。
CLOSE
公開日:2024年3月23日
REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの津司徳義です。
マイホーム購入は人生の中でも大きな買い物のひとつです。特に、近年は中古マンションの人気が高まっています。不動産市場における中古マンション価格の上昇が顕著で、購入した物件の資産価値がどんどんアップしているためです。
ただし、資産価値の高い物件、これから資産価値の向上が見込める物件を購入するには慎重な見極めが必要です。資産価値の維持、向上を期待できる物件を見つけるためのちょっとした知識のご紹介をさせていただきます。

中古マンション購入において、将来的に売却する際の価格を予測することは非常に重要です。その指標として、東京カンテイなどの不動産調査会社が提供するリセールバリューデータが役に立ちます。下記URLをご活用ください。
https://www.kantei.ne.jp/report/115RV_shuto.pdf
首都圏のリセールバリュー1位は六本木一丁目駅でリセールバリューは251.6%。10年後には新築分譲時の約2.5倍に値上がりするという計算になるとのことです。
2位は新御茶ノ水駅の208.1%、3位は代々木上原駅の192.0%、4位は神保町の188.2%、5位は新橋の179.5%と続きます。
上位30位までの駅の内訳をみると港区11駅、渋谷区と千代田区が5駅となっているようです。都心の駅が上位を占める中で22位には片瀬江ノ島駅の166.1%、26位の桜木町の164.5%と23区以外の駅も登場している点は興味深い現象です。
上記のリセールバリュー(価格維持率)は以下の計算式から算出しているとのことです。
◆リセールバリュー=中古流通時の価格÷新築分譲時の価格×100
10年住み続けた物件が、10年後に2倍の価格になっているなんて嬉しいですね。
ただ、リセールバリューデータはあくまでもエリア平均的な値であり、個別の物件によって価格は大きく異なります。そのため、個別の要因をしっかりと見極めることも重要になります。エリアの平均からどの程度上積みがあるか、減点があるかというような感じになります。計算式にすると下記のような感じです。
◆マンションの価格=エリアの価値+個別の価値
個別の要因には、以下のようなものが挙げられます。
これらの要因を総合的に判断することで、購入を検討している物件の将来的な価値をより正確に予測することができます。
個別の要因の見極めは、知識や経験が必要となるため、信頼できる専門家のサポートを受けることが重要です。
不動産会社には、マンション管理士、宅建士、ファイナンシャルプランナー、宅建マイスター、不動産コンサルティングマスターなどの資格を持つ専門家が在籍しています。これらの専門家に相談すれば、物件選びから購入後の資金計画まで、幅広いアドバイスを受けることができます。
優秀な営業担当者と物件探しをするのか、頼りない担当者とお住まい探しをするのかは意外に重要な成否の分かれ道になることも多いと思いますが、いかがでしょうか。
弊社REDSには非常に優秀な営業担当者が多数在籍しています。営業担当は100%宅建士かつ、多くの専門資格を保有しているエージェントが多いのが特長です。
一人当たりの資格保有数は全国トップレベルの不動産会社であることは間違いないかと思います。弊社では物件の提案も含めて購入後の資金計画や将来的な売却時のことまで考えた、トータル的なアドバイスを提供することができます。資産価値に関して少しだけ意識して物件探しをすることで将来大きな利益も見込めるかもしれません。
【ブログ筆者所有資格】
マンション管理士
管理業務主任者
2級FP
リフォームスタイリスト1級
国際不動産スペシャリスト
宅建マイスター
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
REDSは経験・知識豊富なエージェントの集団です。
しかも全員が宅建士、一人あたりの関連資格保有数も全国トップレベル。
さらに【仲介手数料最大無料、割引】のちょっとしたオマケ付きです。
不動産売買をお考えの際はぜひ弊社REDSへのお問い合わせください!
不動産プロ集団としての安心感を得ていただけると思います。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
公開日:2024年2月15日
REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの津司徳義です。
国土交通省による大注目の「令和5年度マンション総合調査」が2024年1月、終了しました! 調査結果の公表は5月から6月頃(予定) とのこと。
5年に1度の調査のため、結果からマンション住民、管理組合の管理意識の変化がうかがえる重要な調査です。マンション管理士としてはマンション管理に対する意識の変化を知る重要な調査となるためとても興味があります。
安心できるマンション生活には住民、管理組合の管理意識の向上は非常に重要な要素です。調査結果にもとづいたブログも今後掲載させていただきます。
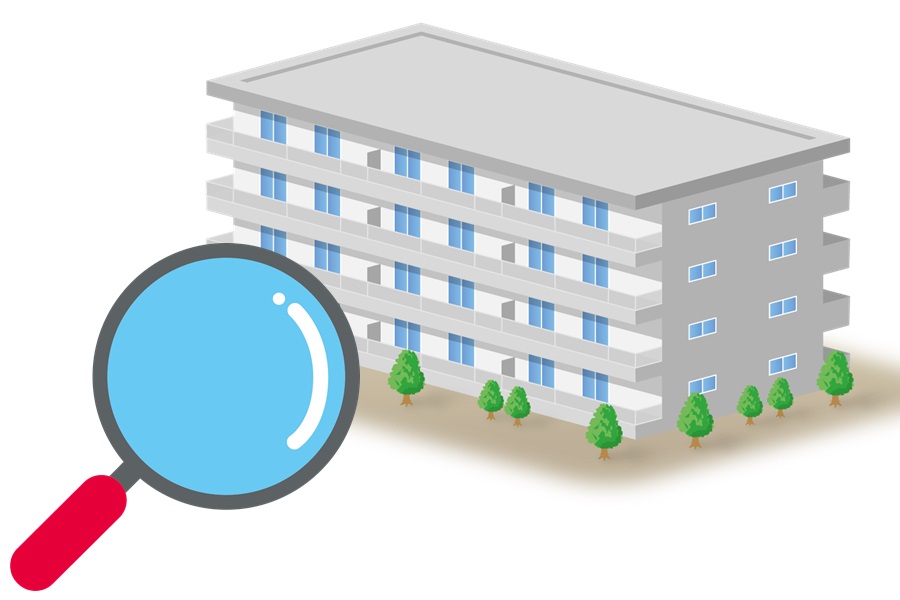
マンション総合調査で尋ねられる内容は以下のとおりです。管理組合向けの調査と区分所有者(住人)向けの調査に分かれています。
【管理組合向け調査】
1.マンションの概要について
2.マンション管理に関する国等の取組の認知度について(要注目)
3.管理組合の運営について(要注目)
4.管理規約の作成・改正及びその他への対応について
5.管理組合の経理について
6.長期修繕計画について(要注目)
7.修繕について
8.耐震・建替え等について
9.管理事務について
10.トラブルの発生状況について(要注目)
【区分所有者向け調査】
11.現在のお住まいについて(要注目)
12.管理組合活動への参加について(要注目)
13.マンションの管理に対する認識について(要注目)

特に今回、私が注目しているポイントは『マンション購入の際に考慮した項目』で「共用部分の維持管理状況」です。調査項目は多岐にわたるのですが、住民の管理意識の変化を最も確認しやすい項目です。
どんなに素晴らしい立地であっても、どんなに素晴らしいお部屋であっても「共用部分の維持管理状況」が良好でないと、物件の資産価値は大きく毀損されてしまう可能性があります。実はこの部分に対する購入者の意識は年々高まっており、今後も上昇し続けていくと予想していますが、結果が大いに気になります。
また、昭和55年度の21.7%から右肩上がりに上昇を続け前回調査では62.8%まで上昇した「永住意識」、こちらの数字にも注目しています。永住する方、売却する方どちらにとっても管理の良否は重要な課題です。
マンションの高経年化が進んでいく中で、国土交通省をはじめ、地方自治体もマンション管理の向上に力を入れている現状ですが、もっとも大事なことはやはりそこに住む住民の管理意識! 常にマンション管理の詳細を調査し、ご購入を検討されているお客様に説明している私としては、その結果がとても気になります。
ネットを通じてあらゆる情報の入手が容易になった昨今でも、マンションの管理状況を一般の方が把握することは非常に困難です。米国などではマンションの管理状況が公開されているような場合もあると聞いたことがあります。そして、内容が悪い場合には住宅ローンも難しい場合があるそうです。
日本でもマンションによっては管理内容を発信している「とても意識の高い管理組合」もちらほら見かけるようになりましたが、おそろしく少数派です。上記のような物件は購入に際して大きなメリットになります。マンション管理組合が資産価値の維持を目的に積極的に情報開示をしているととらえることができるからです。
外見からだけではまだまだ分かりにくいマンション管理の良否を知るためには、専門知識、経験豊富な不動産エージェントに相談するしかないというのが現状です。だからと言って、何の知識も持たずに信頼できる担当者を探すのも困難です。購入者側に自衛のための最低限の予備知識も必要になります。
私の過去のブログをご参照いただければ十分な予備知識をつけていただくことが可能です。最近はマンション管理に絞ってブログを掲載させていただいております。お時間の許す際にご覧いただけると幸いです。ある程度の知識を持つことで信頼できる不動産エージェントか否かを判断する基準を持つことはとても大切です。
もちろん物件購入時には必ず管理の良い物件を購入すべきということではありません。ただし、デメリットをあらかじめ知っておくことは重要です。また、管理は改善できるので、改善に向けた取り組みを行うためにも現状を把握していただきたいというのが私の考えです。
以上、マンション総合調査についてお伝えさせていただきました。マンション購入をお考えのみなさまは、一度ご覧になっていただいても良いかもしれません。現在は平成30年度のものまでが閲覧可能な状態です(令和6年2月1日現在)。
下記のURLから閲覧可能ですのでご興味のある方はご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000058.html
【ブログ筆者所有資格】
マンション管理士
管理業務主任者
2級FP
リフォームスタイリスト1級
国際不動産スペシャリスト
宅建マイスター
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
REDSは経験・知識豊富なエージェントの集団です。
しかも全員が宅建士、一人あたりの関連資格保有数も全国トップレベル。
さらに【仲介手数料最大無料、割引】のちょっとしたオマケ付きです。
不動産売買をお考えの際はぜひ弊社REDSへお問い合わせください!
不動産プロ集団としての安心を感じていただけると思います。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
公開日:2024年1月8日
不動産流通システムREDSエージェント、宅建士・宅建マイスター、津司徳義です。
今回は管理のいいマンションを見極める方法の上級編です。みなさまのマンション探しのお役に立てると嬉しいです。
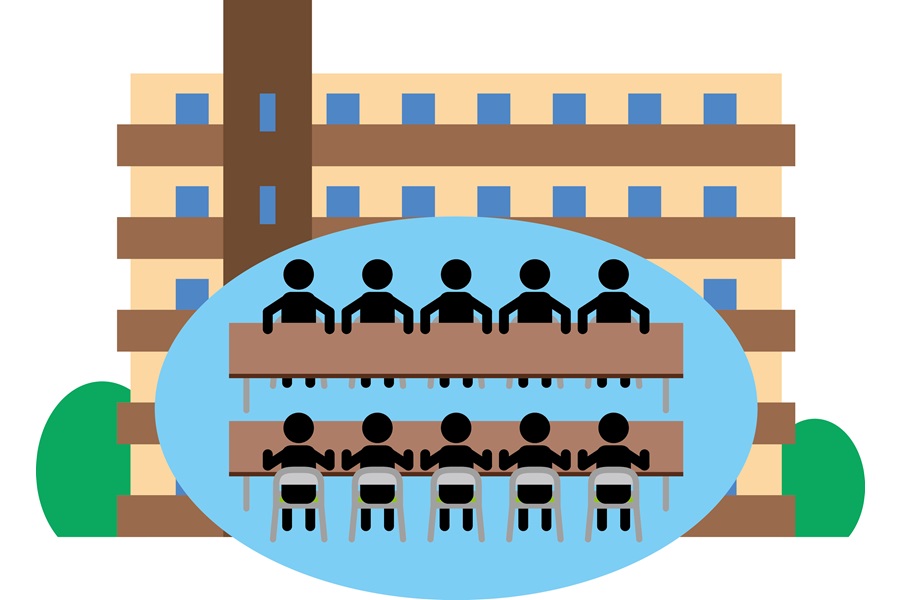
このブログの中でもたびたびご紹介させていただいていますが、マンション管理の良否は管理会社の良否ではなく、管理組合(住民)の管理に対する姿勢です。
管理に対する熱意を測る尺度として重要な指標となるのが、理事会の開催数です! 平均値は年3回程度、そこから回数が多いほど、より熱心であると推測することができます。年6回以上の開催であれば、管理がいいと期待が持てると考えられるでしょう!
管理に無頓着なマンションには、管理会社をあまり変更してきていません。変更をした履歴があるだけで、より優れた管理を求めているマンションである可能性が高まります。
管理会社を変更したことが分かる手がかりのひとつとして、大手ディベロッパーA社の物件なのに、違う系列の管理会社になっているような場合があります。こうした場合は変更履歴ありの可能性が高いといえます!
管理会社に管理を丸投げしている物件の大規模修繕の周期は12年であることが多くなっています。
なぜなら、多くの場合、大規模修繕工事も管理会社、施工会社(管理会社のグループ会社の場合が多い)の重要な収益源になっているケースが多いからです。
昨今この周期に関して大幅といっても過言ではない見直しがされています。これまで12年とされていた周期が15年だとか18年の周期でよいという方向性が打ち出されているのです。
この周期の長期化は昨今の大規模修繕における人件費、資材費の高騰を大幅に吸収できる重要な要因です。マンション財政に余裕があれば、12年に1回行うことにメリットはあります。半面、18年に1回と12年に1回では長期目線での支出には非常に大きな差額をもたらします。
管理に熱心な住民がいるマンションであれば、周期に対する見直しは当然行われるはずです。注意が必要な点としては、ずさんな管理で修繕資金の積み立てに苦労して、やりたい工事ができなかったという場合もあるので、その点は担当者に質問してみましょう。その返答により、あなたの担当者の力量を測ることにもつながります。納得のいく回答ができる担当者なのか否かは、お住まい探しの成否に直結する重要な要因になります。
管理組合の代表である理事の選任方法のほとんどは輪番制です。1年から2年の期間、理事を順番に担当するというものです。報酬もないことがほとんどですから、このような制度がとられることも当然かと思います。
一方、ごく少数の物件では立候補制、立候補制+輪番制が採用されているケースがあります。立候補制の場合はメリットがあると考えていいでしょう。立候補する住民の多くは管理意識が高い、またはマンション管理に対する専門知識があるケースがほとんどだからです。立候補の背景にはマンション管理の質を高め、資産価値の向上につなげたいという気持ちがあります。
実は多くのマンションで多くの理事が〝やっつけ仕事〟で理事会の運営を行うことが多い中、管理に対する意識が高く、専門知識も持ち合わせている理事が管理組合の中心にいることは大きなメリットになります。
築年数の経過しているマンションに限定されるチェック項目になりますが、照明をLEDに変更すると、昨今の電気代の上昇も吸収できるくらい支出の減少に貢献します。理事会で費用対効果を測定検証し、総会での議決を得て工事が実施されますが、意識の低い物件ではこのようなことは行われません。
管理に対する熱心さを測る、とても良い指標の一つではないかと思います。
マンションの総会は年に1回必ず開催されます。その総会議事録からマンションの管理に対する熱意を推測することもできます(※議事録の開示は見学前には難しい)。
その判断材料としては以下の項目が参考になります。
1.総会参加人数
2.議決権行使書の数
3.白紙委任状の数
目安ですが、1が過半数を超えることはありません。3割5分程度の参加があれば超熱心な組合と判断できます。2は7割程度の場合もあります。
一方、3が半数を超える場合は注意が必要かもしれません。しかし、2・3に関しては議案の内容にも左右されるので一概には定義することもできません。明らかに重要な議案に対して3の白紙委任状が3割を超えるような場合は注意が必要かもしれません。
今回のブログは上級編ということでいささかマニアックで、情報の入手が困難な場合もある内容も説明させていただきましたが、いかがでしょうか。
お住まいの購入は人生の中でも特に大きなイベントです。少しくらいマニアックになってみることも良いのではと思います。避けることができるリスクはできるだけ避けたいですよね? 今回のブログを通して、なるほど!と思っていただける内容があれば嬉しいです。
今回も御覧いただき誠にありがとうございます。
【ブログ筆者所有資格】
マンション管理士
管理業務主任者
2級FP
リフォームスタイリスト1級
国際不動産スペシャリスト
宅建マイスター
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
REDSは経験・知識豊富なエージェントの集団です。
しかも全員が宅建士、一人あたりの関連資格保有数も全国トップレベル。
さらに【仲介手数料最大無料、割引】のちょっとしたオマケ付きです。
不動産売買をお考えの際はぜひ弊社REDSへのお問い合わせください!
不動産プロ集団としての安心感を感じていただけると思います。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
公開日:2023年12月1日
REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの津司徳義です。弊社REDSが取材を受けた『日曜報道 THE PRIME』が2023年11月26日に放送されました。中古マンションの管理について踏み込んだ有益な放送内容だったと思います。このような形で放送される弊社の見解が、みなさまのお住まい探しの一助になれば非常に嬉しく思います。
今回は放送記念ということで、マンション管理の専門家である私が、マンション管理士としての視点から【管理の良いマンションを見極める方法】をご紹介します。

マンション管理の良否は物件選びの際の重要な判断要素です。管理の良否が資産価値の維持に大きな影響を与えるということが広く認知されていくことで、住環境の底上げにつながることは間違いありません。
今回は平成30年度マンション総合調査(国土交通省)の結果に基づいて説明します。調査はアンケート方式で行われ、その回収率は約40%とのこと。アンケートに答えるということ自体が、管理にしっかり取り組んでいるということになるので、すべてのマンションの実態よりは優等生的なデータになっている可能性もあるかもしれませんが、参考になる公的なデータです。
平成30(2018)年度マンション総合調査(国土交通省)の目的は以下のとおりです。以下、赤字はマンション総合調査よりの抜粋です。
マンション管理に関し、これまでに講じられてきた施策の効果の検証、必要となる施策の提示を行うための基礎的な資料を得ることを目的として、マンションの管理状況、マンション居住者の管理に対する意識等を調査した。
マンションの高経年化が進むなか、国はさまざまな施策を打ち出そうとしています。私が持つマンション管理士という資格もその一環で設けられたものです。国土交通省は真摯に住宅問題に取り組んでいると思います。
以下マンション総合調査からの項目抜粋
【マンション購入時に考慮した項目(新規調査項目)〔区4⑥〕】
「駅からの距離などの交通利便性」が72.6%で最も多く、次いで「間取り」が63.7%、「日常の買い物環境」が52.8%となっている。
【解説】
上記、上位項目は非常に重要な検討要因ですが、とても重要な要素が欠けています。それは管理の良否に関する要因です。以下が管理に対する意識調査です。
【⑦マンション選定時の入居後の共用部分の維持管理に対する考慮〔区5、区5①〕】
どの程度考慮したかについては、考慮した割合は41.7%であり、考慮しなかった割合57.2%を下回っている。考慮した事項については、「優良なマンション管理業者であること」が50.0%と最も多く、次いで「管理規約の内容が妥当であること」が43.0%、「管理費及び修繕積立金の額が十分であること」が41.8%となっている。
【解説】
「優良な管理業者であること」よりも「真剣な管理組合であること」が重要です。上記を理事の選任方法、理事会の開催数等である程度判断することが可能です。
「管理規約の内容が妥当であること」についてはそれほど注意する必要ないかと思います。なぜなら多くのマンションの管理規約は「マンション標準管理規約(国土交通省)」に準拠しているからです。気にする点としてはペット飼育の可否くらいでしょうか。
上記項目で最も重要なのは「管理費及び修繕積立金の額が十分であること」です。しかしながら、上記は正しい表記ではないかと思います。マンション管理士として上記文言を言い換えるとすれば「管理費及び修繕積立金の額が妥当であること」になります。
さらに「妥当とはどういうことか?」が問題になります。判断材料は以下のとおりです。
●新築時の修繕積立基金の有無、その内容。
●現在徴収している積立金の額(月の徴収額)
●現在の積立額(積み立てられている総額)
大規模修繕の周期、その内容はさまざまです。上記を総合的に判断することが管理の良否の判断に重要です。
【⑥現在の修繕積立金の積立方式(新規調査項目)〔管29⑥〕】
現在の修繕積立金の積立方式は、均等積立方式が41.4%、段階増額積立方式が43.4%となっている。完成年次別にみると、完成年次の新しいマンションほど段階増額積立方式となっている割合が多い。
【解説】
「均等積立方式」は国土交通省が推奨している積立方式です。そうであるにもかかわらず首都圏の築浅マンションでは少数派です。全国平均41.4%を大きく下回っているのが実感です。
非良心的(メリットもありますが)な「段階増額積立方式」が多くの新築・中古マンションで採用されていることが不動産業界の不健全な一面を象徴しているのかもしれません。明確な将来リスクを正確かつ、正直に説明できる担当者に相談することがリスク回避、失敗しないお住まい探しにつながります。
ご自身で管理内容をしっかり吟味できるお客様は少数派ではないでしょうか。信頼のできる担当者を探すことが重要ということになると思います。
【ブログ筆者所有資格】
マンション管理士
管理業務主任者
2級FP
リフォームスタイリスト1級
国際不動産スペシャリスト
宅建マイスター
宅地建物取引士
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
REDSは経験・知識豊富なエージェントの集団です。
しかも全員が宅建士、一人あたりの関連資格保有数も全国トップレベル。
さらに【仲介手数料最大無料、割引】のちょっとしたオマケ付きです。
不動産売買をお考えの際はぜひ弊社REDSへのお問い合わせください!
不動産プロ集団としての安心感を提供します。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
公開日:2023年10月25日
REDS不動産流通システム、マンション管理士・管理業務主任者・2級FP・国際不動産スペシャリスト・宅建マイスター・宅建士の津司です。今回は管理のいいマンションを購入するための必須事項について簡単にご説明させていただきます。
お住まい探しの際に失敗を防ぐためには自己防衛のための一定の知識が必要です。リスクの見極めを営業担当者に丸投げでは不安ですよね。そのようなみなさまのお役に立てれば幸いです。

「マンションは管理を買え!」とは昨今中古マンション購入時に非常に重要なキーワードです。今後もますます、その重要度は増していくことは間違いないのではないでしょうか。お住まい購入での失敗を防ぐには、管理の良否の確認は必須ポイントです。
以下にその注目ポイントを列挙させていただきますが、これらはあくまで一般論です。実際には個別の判断が必要で、信頼できるエージェントとのお住まい探しは重要ということになります。
■総戸数
少ないから一概にダメということではありませんが、マンションの総戸数は多いほうがいいでしょう。
■管理組合の理事の選任方法
輪番制より立候補制がいいでしょう。輪番半数に立候補半数とするところでも問題ありません。輪番制としているところは、管理会社都合を優先しているのかもしれません。
■理事会の開催数
開催数が多いほうが当然いいでしょう。多いとは何回程度で平均値が気になるところですが、後で解説します。
■管理費と修繕積立金の関係】
「管理費<修繕積立金」がよく、管理費は安いほどいいでしょう(極論です)。修繕積立金が低額な場合、注意が必要で、専有面積60㎡の場合は1万2,000円が分岐点です。修繕積立金の目安は㎡単価200円ですが、昨今の人件費、材料費の高騰で上昇傾向にあります。
■機械式駐車場
機械式駐車場は空きが少ないほうがよく、空き台数が多い場合は注意が必要です。
駐車場収入で、駐車場のメンテナンスが可能か否かが重要です。機械式駐車場の場合、修繕費として月額8,000円が目安です(国土交通省、マンションの修繕積立金のガイドライン)。つまり、機械式駐車場100区画の場合、メンテナンス費用として月額80万円が必要となります。
駐車料金1万円の場合、80台の利用があれば駐車場収入でメンテナンスが可能ですが、70台しかなければ月当たり10万円の補填が必要になります。
■共用施設
豪華すぎる場合は注意が必要です。維持修繕費用がマンション財政を圧迫する可能性があります。清潔感も大切。エントランスに入った瞬間の第一印象が大切です。管理がいいから、きれいに見えるのです。
■大規模修繕の周期
長期化傾向に準拠していることが望ましいといえます。これまでは12年が一般的でしたが、18年周期も十分可能です。資材、人件費の高騰がマンション財政を圧迫する可能性が高まる中で、修繕周期の延長は高騰分を相殺できる可能性が高いのです。
■ペット飼育の可否
ペット飼育可の方が資産価値は高くなります。ペットは家族。現状、大型犬の飼育をできる物件は皆無です。私見になりますが、規約を変更して大型犬を可とするだけで物件の資産価値は大きく上がると思います。購入希望者殺到は間違いありません。
規約の変更のハードルは低くはありませんが、物件購入した際に議案提出してもいいかもしれません。マンションの場合購入と同時に議決権を有する組合員になります。マンション規約を変更する権利を得ることができます。管理は住民の意識で変えることが可能です。
■外部専門家の利用状況
弁護士、建築士、マンション管理士などの外部専門家のアドバイスを受けていることが望ましいでしょう。
■管理会社の変更履歴
変更履歴があれば、管理意識の高い物件である可能性が高まります。変更により管理費の負担を下げることができます。理事会がマンション管理に熱心と判断する重要な要因です。いい管理は、熱心な理事会(住民)により成り立つということです。管理会社の良しあしよりも、理事会の取り組みの良否が重要です。
■掲示板の充実度、掲示内容
エントランスには、管理会社からの注意喚起、お知らせなどの張り紙があります。その内容は必ず確認してください。古いまま張り紙が放置されていないかなども管理の良否の重要な判断材料にすることができます。
以前、東京都S区のマンション掲示で『立小便禁止』の張り紙がありました。管理会社に問い合わせした際の説明は「3年前に、部外者が侵入してそのような事例がありました。今はありません」とのこと。
ただ、マンションの資産価値を大きく毀損するような掲示をし続けている管理会社はどうでしょうか? いい管理をできているとは思えないですよね。
以上が今回、買主様にとって有益な豆知識の共有です。
やや専門的な情報も入っているのですが、できるだけわかりやすく使える知識としてご紹介させていただきました。今後のお住まい探しのプラスになれば幸いです。
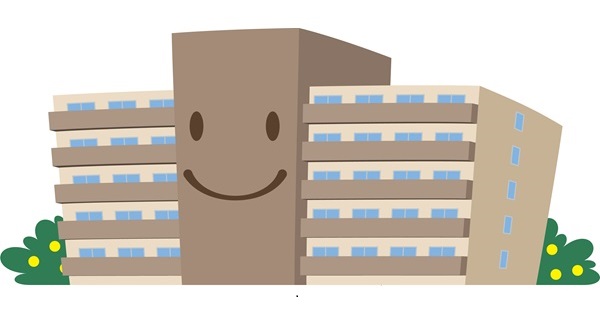
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
REDSは経験・知識豊富なエージェントの集団です。
しかも全員が宅建士、一人あたりの関連資格保有数も全国トップレベル。
さらに【仲介手数料最大無料、割引】のちょっとしたオマケ付きです。
不動産売買をお考えの際はぜひ弊社REDSへのお問い合わせください!
不動産プロ集団としての安心感を感じていただけると思います。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
公開日:2023年9月21日
最近の不動産価格上昇相場の中では、多くの買主様にとって新規物件は常に「この物件高いよね」と感じる状況が続いていると思います。今後の状況を予測するのも難しい状況ですね。
しかしながら、将来の相場変動についての不透明性はいつも同じです。この点も購入、売却を難しくしていますが、この不透明性はすべての相場に共通する難易度の高い問題です。
そこで、今回は最近の価格上昇をわかりやすく理解するため、とあるマンションの相場変動を例にご説明します。価格上昇の仕組みの理解を深めておくことは、正しい購入判断の一助になると考えています。
モデルを単純化することで、購入可否に対する正しい選択をするための基準を持っていただければ嬉しいというのが今回のブログの狙いです。以下は仮想事例ですが、直近の相場を参考にしています。

2019年3月にAマンションの別部屋の所有者が、同じく3階のお部屋を売りたいと思った時に「いくらで売りに出そうと思うか」、この点が重要です。
「1月に5,000万円で売れたなら、5,180万円で売り出してみよう!」
これは売主目線からすると当然ですよね! これが直近数年、都内で繰り返されてきました。
この場合、3か月で3.6%の上昇ということになります。直近の首都圏の不動産市場は、下値を固めるということが繰り返されています。
2019年6月に同じくAマンション別部屋の所有者が3階のお部屋を売りたいと考えたとき、「5,280万円で売ろう!」というのも普通ですよね! これも難なく売れました。
6か月で5.6%の上昇ということです。2019年9月に同じくAマンション別部屋の所有者が3階のお部屋を売りたいと考えたとき「5,480万円で売ろう!」となるのも普通ですよね!
9か月で9.6%の上昇ということです。2019年12月に同じく別のAマンション所有者が3階のお部屋を売りたいと考えたとき「5,680万円で売ろう!」となる、これも普通ですよね!
12か月で13.6%の上昇ということです。このような流れの繰り返しが、近年首都圏での不動産価格上昇の大きな要因の一つと考えられます。前年同月比で10%の価格上昇が認められた地域の場合、1年前は8,000万円だったお部屋が8,800万円で売りに出る。そしてこの価格で成約するというのが、近年の上昇相場の中で実際に起こっていることです。一般的な感覚からすると、「高すぎ」と感じてしまうと思いますし、この感覚は正常です。
以下は、直近の東京都区部のマンションの成約㎡単価前年同月比の推移です(公財東日本不動産流通機構のデータの引用)。
■中古マンション成約㎡単価の前年同月比(2021年5月)
東京都区部13.4%の上昇
↓
■中古マンション成約㎡単価の前年同月比(2022年5月)
東京都区部9.4%の上昇
↓
■中古マンション成約㎡単価の前年同月比(2023年5月)
東京都区部8.2%の上昇
今後この傾向がどのように推移していくかを予測することは非常に難しいですが、直近の上昇相場を具体的な数字でご確認いただければと思います。
例えば、2021年からお住まい探しを継続のお客様にとっては、購入意欲が削がれるほどの価格の変動ですが、相場の流れには逆らうことができないということです。直近の上昇相場の中で、過去の成約事例を重要な要因と考えると、多くの購入者が買えない状況が続いるといえるかもしれません。
しかし現実は、高くても売れるという状況に支えられ、上昇相場が継続しているということです。過去の成約事例を判断基準にする際には、あくまで過去の事例という意識をもって、そこからどの程度の上昇乖離があるかという観点からの検討が必要ということです。1年で10%の上昇が市場で形成されても適正相場、ということもありえるのです。
この点を踏まえて判断しなければ、なかなか新居の購入ができないということになってしまうのではないかと考えています。簡単な購入環境ではないと思いますが、そのような時こそ頼れる専門家に相談することが重要ではないでしょうか。相場を適切に理解することは、お住まい探しの成否に直結する重要な要因といって間違いないと思います。
最終更新日:2023年8月21日
公開日:2023年8月18日
REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの津司です。
マンションの資産価値を高める要因は多く、ブランド力、駅距離、周辺住環境、公立有名小学校の存在など、さまざまあります。今回ご紹介する注目要因は見逃されることが多いのですが、マンションの資産価値の下支えに大きく寄与する「マンションの管理」についてのお話です。

管理のいいマンションを買ったときの最も大きいメリットは、将来の売却時に高く売れる可能性が高まるということです。
他にも以下のようにさまざまなメリットがあります。
・管理のいいマンションは安心して生活ができる
・2022年4月からスタートした新制度(マンション管理適正評価制度)のもとでは、フラット35利用時に契約から5年間住宅ローンの金利が0.25%引き下げられる
・管理費、修繕積立金の計画がしっかりしているため、適正な月額ランニングコストを維持しやすい
大規模修繕時に住民からの一時金の徴収や、金融機関からの借り入れをするマンション、すなわち資金計画がしっかりしていないマンションは約21%(国土交通省・平成20年度マンション総合調査)もあるのですよ!
上記はメリットの一部ですが、やはり管理のいい物件を購入することはプラス面が大きいと思います。
デメリットもあります。それはマンション内での規則が厳しいという点が挙げられると思います。管理員さんが口うるさいことも多いです。洗濯物をバルコニーに干せないなんてこともあります。これらは管理のいい物件のデメリットかもしれません。
物件購入時に管理がいいことがすべてではありませんし、それはむしろ一部といってもよいでしょう。ですから、管理が思わしくない物件を買うことも選択肢として十分あり得ることだと思います。その他の条件がすべてよければ、管理面のマイナスを受け入れても良いことも多いはずです。
一方で管理は住民の意思によって、いい状態に変えていくことがいつでも可能です。楽な作業ではないでしょうが、実際に住民の皆様が管理の大切さを意識し優良管理物件へと導き、資産価値のアップに結びつけている事例も多いようです。
ですから、購入時に管理状態のいい点も悪い点も知っておくことが重要と私はいつも考えています。
それでは具体的に、管理のいいマンションとはどのようなマンションを指すのでしょうか。これには明確な定義はありませんが、マンション管理士としての私の視点からできるだけわかりやすく説明します。
まず【管理組合、理事会】と【管理会社】の違いを理解していただくことが重要です。【管理組合、理事会】とは住民が構成する組織です。一方、【管理会社】とは住民の委託を受けてマンション管理を行う営利団体。組織の母体が全く違うのです。
はっきり言えることは、マンション住民が【管理会社】に丸投げではいい管理を望めないということ、【管理組合、理事会】が管理に前向きに取り組んでいくことが重要ということです。
良質な【管理会社】が良質な管理をするというよりは、良質な【管理組合、理事会】が【管理会社】に良質な仕事をさせるということです。
いい【管理組合、理事会】を見分けるためには以下のポイントをチェックしましょう。
・理事会の開催数(年何回?)
・役員の選出方法(輪番制、立候補制、輪番、立候補併用制など)
・管理費と修繕積立金の金額割合の良否
・長期修繕計画の見直し履歴の有無
・管理会社の変更履歴の有無
・理事会における外部専門家の有無(大規模物件以上)
上記のような項目を精査することで【管理組合、理事会】の良否の概要を推測することは可能です。詳細な判断を外部からすることはとても難しいですが、購入時に良否の概要を知っておくだけでマンション購入の成否を大きく左右する判断材料を手に入れることができます。
少し専門的で恐縮ですが、不動産の価格は大きく3つの要因(それぞれ非常に細かく細分化されます)により決定づけられます。
(1)一般的要因(自然的要因、社会的要因、経済的要因及び行政的要因)
これは最も大きな要因です。例えば地質、地盤の状態だったり、貯蓄、消費、投資、国際収支の状態だったり。
(2)地域要因
これは中要因。エリアの相場とお考えください。たとえば「恵比寿駅周辺の基本的な相場はこの程度」というようなものです。
(3)個別的要因
これは小さな要因です。例えば築年数、設計・設備の機能性、耐震性・耐火性等の建物の性能、マンションの維持管理の状態のことです。
不動産の価格はこれらの3要因がそれぞれ結びついて最終的に決まるものとされています。今回のお話はこの(3)が優れた物件を買うことが将来の資産価値の下支えに大きく貢献するということです。価格を形成する要因は非常に多いのですが、維持管理の状態の占めるウェートは小さくなく、むしろとても重要です。
【維持管理の状態】の良否を見極める知識の差が、物件選択の成否に大きく影響するということです。
今回の記事では、【管理組合、理事会】の良否を見極めることがマンション購入時にはとても大切ということをお伝えしました。安心して生活をしたい、将来高く売れる物件を買いたいというような場合は、必須の要件です。今回のブログで物件の管理の重要性を少しでもご理解いただければ嬉しいです。
「マンションは管理を買え!」
このスローガンでのお住まい探しはみなさまに大きなメリットをもたらすはずです! 弊社REDSは不動産のプロ集団です。さらに、仲介手数料が他社よりも安くなるというちょっとしたオマケもつきます。不動産売買をお考えの方はぜひ弊社REDSまでお問合せください。
最終更新日:2023年6月25日
公開日:2023年6月16日
【仲介手数料最大無料】不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの津司徳義(つし のりよし)です。
私は不動産売買に役立つ資格を7つ取得しています。これらの資格はどういうものなのか、そしてどのようなお客様にメリットがあるのか、なぜこれらの資格を取得したのかについて説明します。
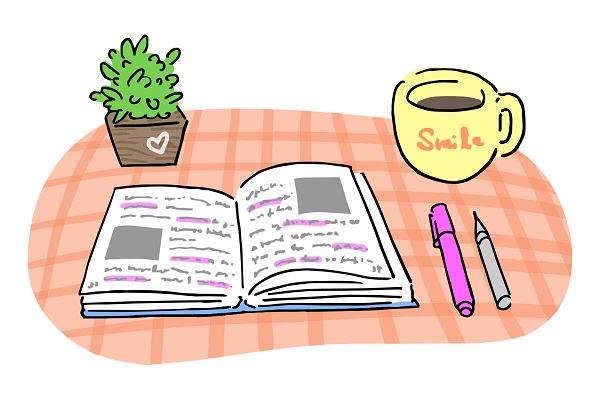
私の取得している資格は取得順に以下の7つです。
(1)宅地建物取引士(宅建士)
(2)3級ファイナンシャルプランナー
(3)2級ファイナンシャルプランナー
(4)マンション管理士
(5)管理業務主任者
(6)CIPS国際不動産スペシャリスト
(7)宅建マイスター
私は、不動産業界に携わる前は、まったく資格取得には興味がありませんでした。学生時代も、英検の資格を取得している同級生も多くいましたが、「入試本番で何点とるかがすべてでしょ」という考えでした。社会人になっても資格が必要となるような環境ではなかったので、特に資格取得に興味を持つこともありませんでした。
そんな私が不動産業界に携わり、比較的多くの資格を取得することにした理由は「お客様が契約後にトラブルに見舞われる可能性をできる限り取り除きたい」と考えたからです。
トラブルの要因は多様ですが、多くは担当者の知識不足に起因するといえるでしょう。経験により、その知識は増えていくことは間違いないですが、積極的に知識を増やしていくこともできるはずです。その最短の方法が資格取得だと考えました。
お客様が将来にトラブルを抱える可能性を最大限低くするために、私は積極的に知識を増やしていく方法として資格取得を選ぶことにしたのです。
では、私の持っている資格をそれぞれ解説します。
宅建士資格については、説明の必要がないと思います。タクシーの運転手さんにとっては2種免許のようなものです。不動産売買をお考えの方は、担当者が宅建士の資格を持っているのか必ず確認しましょう。資格がなくても優秀な方はもちろんいますが、やはりこの資格は必須ですよね。
こちらの資格も認知度がありますね。私は必要なお客様には専用のソフトを使い、それぞれのお客様のライフスタイルに合ったライフプラン表を作成させていただくこともあります。
ファイナンシャルプランナーとして感じることしては、住宅費にかける金額は収入から決めるのではなく、ライフスタイルによって決めるべきということでしょうか。900万円の収入があれば7,000万円の家の購入に問題がないとは一概に言えないことが多いと感じています。ライフプラン表の作成など、気になる方がいればお気軽にお声がけください。
こちらの資格は、認知度は低いですが、中古マンション購入をお考えの方にとっては非常に重要な資格です。
『マンションは管理を買え』という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。管理状況の良しあしを見極める専門知識を有する者が上記資格の取得者ということになります。特にマンション管理士は管理に関するコンサルティングを行う国家資格者。我々のような不動産仲介業者の中で上記資格を取得している担当は非常に希少です。
主な仕事はマンションの管理組会に対する助言、大規模修繕時のサポート、長期修繕計画策定のサポート、規約変更時のサポートなどです。マンション購入、売却の際には非常に重要なサポートをさせていただくことが可能です。マンション購入、売却をお考えのみなさまにはマンション管理士のサポートが必須といってもいいかもしれません。
こちらの資格も非常に認知度が低い資格で、かつあまりみなさまの役に立ちません(笑󠄀)。ビジネスができる程度に英語が話せれば役に立つのですが、残念ながらそれほどの英語力はありません。詳細は省略させていただきます。
こちらの資格も認知度は低いですが、不動産売買にかかわるすべてのお客様にとって非常に重要な資格です。一部記述式(半分くらい)なので受験者も少なく、結果として資格取得者も少ないのが現状です。
資格のコンセプトは『リスクを予見』し『トラブルを未然に防ぐ』というものです。特に『リスクを予見』の部分では「顕在化していないリスクを見逃さない」という点が重視されています。すべての不動産売買をご検討しているお客様にとって心強い資格といってよいでしょう。
私は令和5年度に受験しましたが、この年から『コンプライアンス意識の醸成』という内容も試験に付加され、合格後は『コンプライアンス遵守』についての誓約書も認定機関に提出しました。不動産取引に最も求められる『安心できる取引』についてもこの試験を通し、しっかりと学んでいますのでみなさまにとっては大きな安心材料として感じていただけると幸いです。
以上、私の所有資格についての簡単な説明をさせていただきましたが、『お客様が契約後にトラブルに見舞われる可能性をできる限り取り除くことが我々の仕事』という意識のもと資格取得に励んできました。
担当者の知識不足のために、大事な不動産売買で失敗をしてしまうなんてことは絶対に避けたいですよね。私もまだまだ勉強中(人生通して)ですが、私の知識でみなさまの不動産取引な安全性が高まるのであればとても嬉しく思います。
弊社REDSは不動産のプロ集団です。さらに仲介手数料が他社よりも安くなるというちょっとしたオマケもつきます。不動産売買をお考えの方はぜひ弊社REDSまでお問合せください。
最終更新日:2023年7月1日
公開日:2023年4月24日
【仲介手数料最大無料】不動産流通システムREDSマンション管理士・宅建士・宅建マイスター・2級FP・CIPS(国際不動産スペシャリスト)の津司徳義(つしのりよし)です。
今回は私の【自己紹介動画】を紹介させていただきます。
以下URLです。
https://www.youtube.com/watch?v=VRQA2r3eci8 
ざっくりな動画のため、REDSのメリット等の詳細はぜひお問い合わせください!
お住まい探しを、知識、経験、スキルの豊富な弊社エージェントすることでより良いお住まい探しの可能性を高めることができると考えます
お住まい探し、お住まいの売却をお考えの際はぜひ弊社REDSにお声がけください!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
REDSは経験・知識豊富なエージェントの集団です。
しかも全員が宅建士、一人あたりの関連資格保有数も全国トップレベル。
さらに【仲介手数料最大無料、割引】のちょっとしたオマケ付きです。

不動産売買をお考えの際はぜひ弊社REDSへのお問い合わせください!
不動産プロ集団としての安心感を感じていただけると思います。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
最終更新日:2023年6月26日
公開日:2023年4月17日
【仲介手数料最大無料】不動産流通システムREDSマンション管理士・宅建士・2級FP・CIPS(国際不動産スペシャリスト)の津司徳義(つしのりよし)です。
今回は弊社REDS不動産流通システムの隠れメニュー!についてのご紹介です。
それは➡お客様から営業担当の指名が出来るということ!

営業担当を指名できるというのは不動産業界では珍しいと思います。
めずらしいせいか
お客様から担当営業のご指名は思ったより多く入ります。
相性の良し悪しはお客様、担当営業の双方に意外に重要な要素かもしれません。
指名制度のご利用もご検討してみてください!
さらに嬉しいことにその指名した担当が万が一思ってたイメージと違う場合、弊社REDSでは担当変更も可能です。
REDSのHPでは各営業担当者のプロフィール、ブログ等が公開されています!
すべて確認して選択するというの難しいと思いますが、
何人かのプロフィール、ブログをチェックして担当者指名の制度を利用してみるのもより良いお住まい探しにつながるかもしれません。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
REDSは経験・知識豊富なエージェントの集団です。
しかも全員が宅建士、一人あたりの関連資格保有数も全国トップレベル。
さらに【仲介手数料最大無料、割引】のちょっとしたオマケ付きです。
不動産売買をお考えの際はぜひ弊社REDSへのお問い合わせください!
不動産プロ集団としての安心感を感じていただけると思います。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆