森山 賢治(宅建士・リフォームスタイリスト)
お客様のご要望に添ったご提案をいたします。
CLOSE
公開日:2024年6月19日
REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの森山賢治です。
建築基準法に定められた道路と敷地に関する規定、「接道義務」について今回は解説します。

接道義務とは、建築物の敷地が建築基準法に定められた道路に2m以上接していなければならないという決まりを指します。奥まった路地上の土地でも、道路に面する通路の間口が2m以上あることが求められます。
接道義務を満たしていない土地は原則として再建築不可となり、せっかく相続や購入で土地を手に入れても、家を建てることができません。
ただし、接道義務には例外もあります。接道義務の原則や例外を正しく理解することで、土地を賢く売ることや新しい家を建てることにも希望が持てます。
接道義務が必要な理由は主に2つあります。
接道義務は、地域の人々が暮らしやすいようにするだけではなく、安心して生活できるように法律で定められているのです。
接道義務には主に3つの例外が存在します。
1.建築基準法42条2項道路に該当する場合:これは「みなし道路」とも呼ばれ、建築基準法が定められる前から存在している道路や、すでに建物が立ち並んでいる場合などが該当します。この場合、道路の幅が4m未満でも例外とされ、建物を建てることが可能です。
2.建築基準法43条但し書き物件に該当する場合:建築基準法上の道路に接していない土地でも、「特定行政庁が建築審査会の同意を得て建築を許可した土地」は例外と認められます。ただし、この許可は1回の建物建築に限ります。したがって、許可を得た建物を壊して再建築するときには、再度43条但し書き物件の許可を得なければなりません。
3.都市計画区域・準都市計画区域外で建築する場合:接道義務は、都市計画区域・準都市計画区域内でしか適用されません。そのため、これらの区域外で建築するときには、接道義務を果たさなくても建物の建築が可能です。
これらの例外を理解することで、接道義務を満たしていない土地でも有効に活用することが可能になります
路地状敷地(旗竿地)における接道義務は、特に注意が必要な領域です。以下に主な注意事例を4つ挙げてみます。
1.部分的に借地をして接道要件を満たす事例:旗竿地(路地状敷地)の専用通路部分が幅員1.9mであれば、基本的には再建築不可の土地となります。しかし、隣接する地権者から幅10cm(以上)の土地を借りることで、建築確認を取ることが可能です。
2.敷地延長の通路部分を他人と共有している場合:敷地延長の通路部分が共有だった場合、共有持ち分にしか担保権を設定できないため、金融機関からは敬遠されやすいといえます。
3.通路部分は共有だが、仮に共有物分割したとしたら2m確保できる持ち分がある場合:4mの通路で、共有持ち分が1/2など、共有物分割(共有持ち分に従って敷地を分割して分け合う)したとした場合に、通路幅員を2m確保できる共有持ち分を持っているのであれば、その分割作業を実際にやるかやらないかは別として、取り扱いできる可能性は高まります。
4.通路部分のように見える部分が、建築基準法上の道路に指定されている場合:通路部分が、建築基準法上の道路に指定されている(位置指定道路)ならば、再建築可能であり、担保として取り扱えます。
路地状敷地(旗竿地)でも接道義務を満たす方法がいくつか存在します。主なものを3つ紹介します。
1.隣地の一部または全てを購入する:道路に接している通路の間口が2m未満の場合、建て替えることができません。そのため、隣の土地の一部または全てを購入し、接道義務を満たせば、建て替えることが可能です。
2.自分の土地と隣地の土地を交換する:たとえばAさんが接道義務違反の場合、隣人であるBさんの土地の一部を購入し、Aさんに全体を売却(またはBさんから全体を購入)し、AさんとBさんの土地を交換することで接道義務を満たすことが可能となります。
3.セットバックを行う:セットバックとは、道路の幅員が4m未満の2項道路の場合、道路の中心線から2mの線まで道路と敷地の境界線を後退させることで、幅員4mを確保する方法です。
これらの方法を理解することで、路地状敷地でも接道義務を満たすことが可能になります。ただし、具体的な建築計画を進める前に、各地方自治体の建築指導課などに問い合わせて確認しておくことをおすすめします。それぞれの地域によって、接道義務に関する具体的な規定や適用例が異なる場合があります。
不動産売買、不動産の価値判断には、接道義務は大変重要な事項になりますのでご注意ください。
公開日:2024年5月11日
REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの森山賢治です。
不動産の売買をする相手が知人や貸主、借主などですでに決まっている場合、不動産会社の介入なしで売買を締結した方が仲介手数料を節約できるため、省略してもいいものかとの相談がありました。不動産を個人間で売買する際の注意点を解説します。
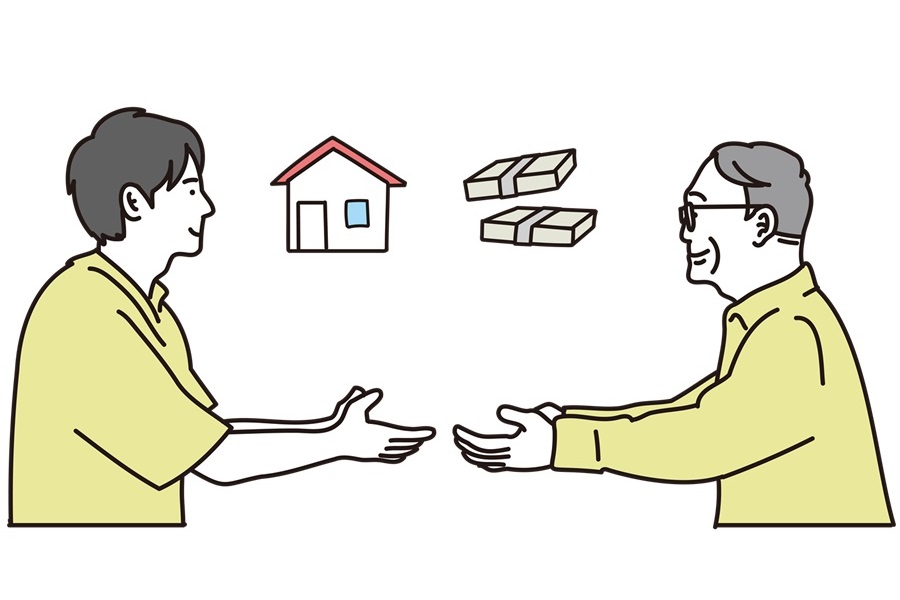
不動産を個人間売買する際の主な注意点は以下の8つです。
1.価格の適正性:不動産の価格は、物件の立地、築年数、建物の状態などにより大きく変動します。売買価格が適正かどうかを把握するためには、同じような条件の物件の相場を調査することが重要です。
2.契約書の確認:契約書は、売買の条件を明確にするための重要な文書です。契約書には、物件の詳細、価格、引渡し日、ペナルティなどが記載されています。専門家に契約書をチェックしてもらうことをお勧めします。
3.物件の状態の確認:建物の構造、設備の状態、近隣環境などを必ずチェックしましょう。可能であれば、専門家による建物診断を受けることをお勧めします。
4.登記簿謄本の確認:登記簿謄本には、物件の所有者や抵当権などの重要な情報が記載されています。これらの情報を確認し、問題がないかをチェックしましょう。
5.税金や手数料:不動産の売買には、固定資産税や登録免許税、仲介手数料など、さまざまな費用が発生します。これらの費用を事前に確認し、予算内に収まるかを確認しましょう。
6.法律的な手続き:不動産の売買は、法律的な手続きが伴います。たとえば、売買契約の締結、登記の変更などです。これらの手続きは専門的な知識を必要とするため、専門家(弁護士や司法書士など)に依頼することをお勧めします。
7.物件の評価:物件の価値を正確に把握するためには、専門的な評価が必要です。不動産鑑定士による物件評価を受けることで、物件の適正な価格を知ることができます。
8.ローンの確認:不動産の購入には大きな金額が必要となります。ローンの金利や返済計画をしっかりと確認し、自身の経済状況に合った計画を立てることが重要です。
特に4の登記簿謄本の確認について、さらに詳しく説明します。次の9つのステップで登記簿を確認しましょう。
1.所有者の確認:登記簿謄本には物件の所有者が記載されています。売主が実際に所有権を持っていることを確認します。「甲区」の所有権に関する事項から確認ができます。
2.抵当権の確認:抵当権が設定されている場合、その詳細が登記簿謄本に記載されています。抵当権が残っている場合、売買価格以上の債権額がある場合は特に注意が必要です。
3.仮登記、差押の確認:抹消されていない仮登記はまだ効力があります。余白部分に本登記がされますと、この仮登記以降に本物件に受付された登記はすべて抹消されます。また、差押登記の後に所有権移転登記をすることは可能ですが、競売、公売手続き後、買受人が現れた場合、この差押登記以降に受付された登記はすべて抹消されます。事前に仮登記、差押登記を抹消する段取りを整えたうえで進めないとトラブルに発展してしまいます。
4.根抵当権の確認:根抵当権が設定されている場合、現時点で被担保債権の額がゼロであっても、根抵当取引が続いているのであれば、売買契約後も借り入れが行われる可能性もあります。したがって、売買代金が極度額の金額以上であっても、根抵当権者と債務者との取引内容によっては、根抵当権を解除できない場合があります。
5.地役権の確認:地役権が設定されている場合、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供することになり、他の土地に利用されていることになります。地役権は容易に抹消ができませんので容認できることか確認が必要です。
6.地目の確認:地目は土地の利用目的を示しています(例:宅地、田、畑など)。土地の利用制限を理解するために重要です。例えば地目が「田」「畑」の場合、現況が宅地であったとしても、所有権移転登記を行うに当たっては、農地法5条などの届出受理書もしくは許可書が必要になります。事前に取得しておかないと当日所有権移転ができなくなるため注意が必要です。
7.面積の確認:土地や建物の面積が登記簿謄本に記載されています。実際の面積と一致しているか確認します。増改築などの理由により、登記簿上の床面積と現況の床面積が異なる場合、金融機関から現況に合わせるように求められることがあります。土地家屋調査士に依頼をして現況に合わせて登記をするか、または増改築部分を解体するかになりますが、どちらにしても時間と費用が発生します。事前に取り決めが必要になります。
8.権利種類の確認:所有権以外にも、地上権や賃借権などの権利が存在します。これらの権利が設定されている場合、その詳細を確認します。地上権は地主の承諾を得なくても第三者に譲渡できますが、賃借権の譲渡には地主の承諾が必要です。事前に費用などの確認が必要です。
9.登記の日付と内容:登記の日付と内容を確認し、物件の過去の取引履歴を把握します。
今回は、個人間売買の注意点と、特に登記簿謄本について詳しくご説明しました。安易な個人間売買はトラブル発生のもとになります。個人間売買といえども、信頼のできる業者に依頼をされたほうがいいでしょう。
弊社は全エージェントが宅地建物取引士ですので安心してご依頼くださいませ。しかも「仲介手数料割引~最大無料」で対応させていただきます。
公開日:2024年4月4日
REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの森山賢治です。
高低差のある土地で、側面の土が崩れるのを防ぐために設置される壁状の構造物を擁壁といいます。この擁壁がある不動産の売買において、最も重要なのは安全性です。擁壁の安全性が不動産売買にどう影響するのか解説します。
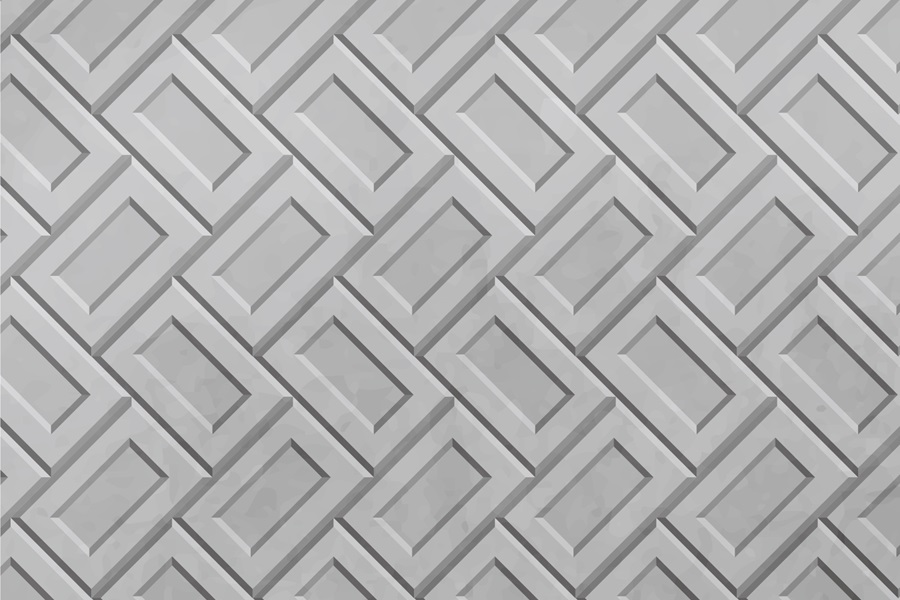
擁壁の安全性が不動産売買に与える影響について、主なポイントは以下の4点です。
1.安全な擁壁は売却への影響はない
国が定めた基準に従って設計・施工された擁壁は、大地震や豪雨で崩壊することはまずありません。安全性が確認された擁壁がある家や土地は、擁壁自体がマイナス要因になることはなく、相場どおりの価格で売却できます。
2.安全性が確認できない擁壁は売却価格に影響する
擁壁の安全性が確認できない場合、災害時の不安が払拭できないため、売却価格に影響します。特に、2000年以前に建てられた家の擁壁は、安全性が確認できないケースが多く存在しています。
3.擁壁の下の敷地でも売却に影響がある
他人地の擁壁であっても、売却に大きく影響を及ぼすことがあります。擁壁の高さによって建て替えの可能性が異なります。
4.検査済証だけでは安心ができないケースがある
検査済証は、検査をした時点の適合性を証明したものであり、売却時の適合性を保証するものではありません。経年劣化や法改正による影響も考慮する必要があります。
擁壁に関連する法律・法令には以下の3つがあります。
1.宅地造成等規制法
宅地造成等規制法は、盛土や擁壁などの土木工事に伴う崩壊や土砂の流出による災害を防止するための規制を行うものです。特定の高さを超える擁壁については、許可や確認申請が必要とされています。
2.建築基準法
建築基準法においても、擁壁に関する規定があり、擁壁の設置や安全性について、法律で定められています。
3.地方公共団体の条例
地域ごとに「がけ条例」と呼ばれる条例が定められています。これにより、擁壁の安全性や設置条件が具体的に規定されています。
宅地造成は、建物を建てたり駐車場を設置したりするために森林などを地均し(じならし)することです。すでに建物が建てられている土地や、駐車場や資材置き場が設置されている土地を再び地均しすることでもあります。
崖崩れや土砂災害が心配される区域内で乱暴な宅地造成が行われれば、大雨の際に土砂災害が発生し、多くの人命が失われるおそれがあります。このため、宅地造成等規制法では、崖崩れや土砂災害が心配される区域を「宅地造成工事規制区域」と呼び、同区域内で一定の範囲を超える宅地造成を行う際は、都道府県知事などの許可が必要であると規定しています。
許可を必要とする宅地造成は、切土(斜面を削る工事)により、高さが2mを超える崖(角度が30度を超える斜面)ができる宅地造成のほか、盛土(土を盛る工事)により、高さが1mを超える崖(角度が30度を超える斜面)ができる宅地造成、切土と盛土を同時に行うことにより、高さが2mを超える崖(角度が30度を超える斜面)ができる宅地造成があります。また、切土や盛土の有無にかかわらず、500㎡を超える宅地造成を行う場合もあります。
適切な工事が行われた場合、都道府県知事などが現場を検査し、検査済証が発行されます。適切に行われなかった場合は許可が取り消され、工事のやり直しを請求されます。
建築基準法において、擁壁は「法19条4項:敷地の安全に関する規定」と「法40条:地方公共団体の条例による制限の附加(通称:がけ条例)」で規定されています。
擁壁の高さが2mを超える場合、確認申請が必要です(施行令138条)。高さが2m以下の擁壁は、がけ条例も適用されず、建築基準法の具体的な規制はかかりません。
構造の規定としては、鉄筋コンクリート造、石造、その他これらに類する腐食しない材料を用いなければなりません。石造の擁壁については、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること、擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜き穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜き穴の周辺に砂利などを詰めることが決められています。
擁壁のある不動産を売買する場合、以下6つの注意点を考慮することが重要です。
1.擁壁の安全性を確認する
擁壁が安全であることを確認しましょう。国の基準を遵守して設計・施工された擁壁は、大地震や豪雨で崩壊することはほとんどありません。擁壁の検査済証を確認し、安全性が確認されたものであることを確認してください。
2.擁壁の高さに注意
高さが2mを超える擁壁は、開発許可や宅造許可、建築確認申請が必要です。これらの手続きを遵守しましょう。高さが1mを超える擁壁を築造する場合も、同様に申請が必要です。
3.擁壁の所有者になるリスクを理解する
擁壁の所有者になると、擁壁の安全性を維持する責任が発生します。擁壁の瑕疵担保責任を理解しましょう。
4.地質を考慮する
地盤の安息角(土を積み上げたときに崩れることなく安定を保つ斜面の最大角度)内に基礎を設けることで、擁壁が決壊しても建物への影響を最小限に抑えられます。地質によって建て替えの可能性が異なることを理解してください。
5.検査済証だけでなく実際の状態も確認する
検査済証だけでなく、実際の擁壁の状態も確認しましょう。経年劣化や欠陥がないかをチェックします。
6.売却価格に影響を与える可能性を理解する
安全性が確認できない擁壁は、売却価格に影響を与える可能性があります。購入者は工事費用を差し引いた金額での購入を希望することが考えられます。安全性につきましては専門家に相談し、慎重に擁壁の状態を確認し、売買を進めることが重要になります。
公開日:2024年2月25日
REDSエージェント、宅建士の森山賢治です。違反建築物と既存不適格建築物の違いをご存じでしょうか? 「どっちもダメなんじゃないの?」とつい考えてしまいますが、両者には大きな違いがあります。

違反建築物とは、建築基準法や都市計画法などに定められた規定や条件に違反して建てられた建築物のことを指します。具体的には以下のような状況が考えられます。
●法令上求められる基準に違反している建築物:例えば、建築物が占める面積(建築面積)の敷地面積に対する割合を示す建ぺい率や、建物の延べ面積の敷地面積に対する割合を示す容積率、防火規制、用途制限などの基準に違反している場合です。
●手続に関する規制への違反がある建築物:例えば、建築した建物の構造・仕様が建築確認申請の際に提出した図面と異なる場合や、建築基準法6条1項各号に掲げられた建物の建築にあたって必要な手続きを踏まなかった場合です。
違反建築物は、安全面や衛生面、防災の観点から問題がある可能性が高く、その所有者自身も危険にさらされるおそれがあるばかりでなく、採光・通風・防火・避難・衛生などに不都合が生じ、周辺住民などにもさまざまな面で不利益を及ぼす可能性があります。
既存不適格建築物とは、建築当時の建築基準法令には適合していたものの、建築後の法改正や用途地域の変更によって、法令に適合しなくなった建物のことを指し、違反建築物とは区別されます。
既存不適格建築物については、現行の建築基準法令の規定は適用されず、原則として、増改築・大規模修繕・大規模模様替えなどを実施する際に、現行の規定に適合させればよいとされています。ただし、政令の範囲内で行われる増築、改築等や軽微な修繕・模様替えなどを行う場合は、適合させる必要はありません。つまり、現行の建築基準法令に合わせるためだけに、既存不適格建築物に対して改築などの対処をする必要はないのです。
違反建築の具体的な事例としては以下のようなものがあります。
●建ぺい率オーバー:建築基準法では、敷地面積に対する建築面積の割合(建ぺい率)が定められています。しかし、この建ぺい率を超えて建築した場合、違反建築となります。例えば、建築確認申請とは異なる建築や増築、敷地の一部の売却などがなされるケースがあります。
●採光不良:建築基準法では、居室面積の1/7以上の開口部(窓)を設けることが求められています。しかし、隣地の建物との間が狭いことによって採光不良となるケースがあります。
●違法増築:10㎡を超える面積の増築には建築確認申請が必要です。しかし、この確認申請を行わずに増築を行ってしまった場合、それは違法増築となります。
これらの違反は、建築基準法や都市計画法などの法令に違反しているため、行政からの是正命令や使用制限などの指導の対象となります。また、違反建築物を購入した場合、ローンの取得が難しくなる、売却が困難になるなどのリスクもあります。不動産を購入する際には、物件が違反建築でないかをしっかり確認しましょう。
違反建築物かどうかは、以下の方法によって確認できます。
●建築確認申請書類の確認:建築確認申請書類は、建築主が建築物を建てる際に、建築基準法に適合していることを確認するために提出するものです。この書類には、建築物の設計図や仕様、構造計算書などが含まれており、これらの内容が現状の建築物と一致しているかを確認することで、違反建築物かどうかを判断することができます。
●建築確認済証の確認:建築確認済証は、建築確認申請が行政から確認され、建築が許可されたことを示す証明書です。この証明書がある場合、その建築物は法令に適合していると認められています。ただし、建築確認済証があっても、その後の改築や増築が適切に行われていない場合、違反建築物となる可能性があります。
●専門家の意見を求める:建築士や不動産鑑定士などの専門家に相談し、建築物の適法性を確認することも有効です。専門家は、建築基準法や都市計画法などの法令を理解しており、違反建築物かどうかを判断するための知識と経験を持っています。
●行政への問い合わせ:建築物が所在する自治体の建築指導課などに問い合わせ、建築確認申請の有無や内容を確認するのもいいでしょう。ただし、個人情報保護法などの関係で、所有者以外の者が詳細な情報を得ることは難しい場合があります。
これらの方法を用いて違反建築物かどうかを調査することができますが、専門的な知識が必要な場合もあるため、不明な点があれば専門家に相談することをお勧めします。
違反建築物を購入すると、どんないいことや悪いことがあるのでしょうか。
●価格:違反建築物は法律に適合していないため、不動産市場では一般的に低価格で取引されます。そのため、初期投資を抑えることが可能です。
●収益性:違反建築物はしばしば法定以上の面積を有しているため、法に適合した建築物よりも多くの家賃収入を得ることが可能です。
●安全性:違反建築物は建築基準法に適合していないため、建物の構造的な安全性や機能性が確保されていない可能性があります。これは、災害時に特に問題となり得ます。
●行政指導:違反建築物は行政から指導を受ける可能性があり、使用制限がかかることもあります。最悪の場合、使用禁止の命令が下される可能性もあります。
●融資の問題:違反建築物の購入に対する金融機関の融資(住宅ローン)は厳しいとされています。そのため、ローンが利用できない可能性があります。
●売却の難易度:違反建築物はその性質上、売却が難しいといえます。特に、金融機関の融資が難しいため、購入希望者が限られてしまうでしょう。
ただ、違反建築物を購入する場合、その違法性を改善することができれば、融資も通りやすくなり、売却という出口も見えてくる可能性があります。ただし、そのためには改善に必要な費用や手間を考慮に入れる必要があります。
不動産は高額商品ですから、信頼のできる業者に依頼をしての物件選択が不可欠です。弊社REDSは全エージェントが宅地建物取引士ですので安心してご依頼をくださいませ。
公開日:2024年1月22日
REDSエージェント、宅建士の森山です。日銀の金融政策の見直しで、長期金利に続き短期金利も上昇する可能性が出てきており、住宅ローンの金利はどれくらい上がるのか、家を買うことを検討しているみなさまの中には気になる方も多いのではないでしょうか。
住宅ローンの金利タイプには変動型と固定型があります。それぞれについて解説します。

変動金利型の住宅ローンは一般的には半年ごとに金利が見直され、金利の動きによって返済額が変わる可能性があります。
●メリット:金利が低ければ利息が少なくなるため、借り入れ当初の返済金額を低く抑えることができます。また、金利が下がれば返済額も減少します。
●デメリット:金利が上昇すると返済額が増加します。また、返済計画が立てにくいという点もあります。
固定金利型の住宅ローンは、一定期間(全期間固定金利型)または借り入れから特定の期間(固定期間選択型)の間、金利が変わらず、返済額も一定です。
●メリット:金利が上昇しても返済額は変わらないため、金利上昇の影響を受けず、返済計画が立てやすいです。
●デメリット:変動金利型に比べて金利が高めに設定されているため、毎月の返済額が高くなり、借入可能額が少なくなる可能性があります。
どちらの金利タイプを選ぶかは、個々の金利観、ライフスタイル、リスク許容度などによります。それぞれの特徴を理解した上で、自身の状況に最も適した選択をすることが重要です。また、金利動向を定期的にチェックし、必要に応じて金利タイプを変更することも選択肢に入れておきましょう。
住宅ローンを借りる際には、保証料と融資手数料という2つの費用が発生することがあります。それぞれの役割と違いについて説明します。
保証料は、借り手が返済できなくなった場合に、保証会社が返済を肩代わりするための費用です。保証料は、借入額と返済期間によって変わります。また、保証料には一括前払い型と金利上乗せ型の2種類があります。
融資手数料は、住宅ローンを借り入れる際の手続きの報酬として金融機関へ支払う費用です。「定率型」と「定額型」の2種類に分けられます。定率型では、住宅ローンの借入金額に対して一定の利率を掛けた金額を支払います。定額型では、手数料を数万円程度の少額に抑えられますが、かわりに借入金利が年0.2%ほど上乗せされるのが一般的です。
これらの費用は、金融機関によって異なります。大手銀行や地方銀行では、保証料の支払いが必要ですが、事務手数料は3万~5万円程度と定額です。一方、ネット銀行では、保証料が不要である代わりに、事務手数料は借入金額の2.2%程度もしくは数十万円の定額に設定されています。最近では大手銀行でも保証料型ではなく手数料型が増えてきました。
これらの特徴を理解し、自身の状況に合った住宅ローンを選ぶことが重要です。
住宅ローンの返済方法には主に「元利均等返済」と「元金均等返済」の2つがあります。
元利均等返済とは毎月の返済額が一定になる返済方式です。返済額は一定ですが、その内訳は、返済が進むほど元金が減るので利息額は減っていき、その分元金の返済額が増えていきます。
●メリット:毎月の返済額が一定なので資金計画が立てやすい。初期の返済額を少なくすることができる。
●デメリット:元金均等返済に比べて総返済額が多くなる。借入金の減り方が遅い。
元利均等返済とは毎月の元金部分の金額を一定にし、それに利息部分を上乗せして返済していく方法です。元金部分と利息部分を合計した返済額は、初回が最も多く、返済が進むにつれて、少なくなっていきます。
●メリット:返済額は返済期間に応じて少なくなる。元利均等返済に比べて、総返済額を少なくすることができる。
●デメリット:返済開始当初の返済額が多く、返済負担が大きい。借入時に必要な収入も高くなるため、借入可能額が少なくなる場合がある。
これらの特性を理解し、自身のライフスタイルや将来の収入予測などを考慮に入れて、最適な返済方法を選ぶことが重要です。具体的なシミュレーションを行うことで、どの返済方法が自身に適しているかを見極めることができます。
住宅ローンの団体信用生命保険(団信)は、住宅ローン契約者が死亡または高度障害状態になった場合に、住宅ローンの残債をゼロにする保険です。以下に詳細を説明します。
住宅ローン利用者が死亡または高度障害の状態になった場合に保険が適用され、住宅ローンの残高を支払う必要がなくなります。団信に加入することにより、死亡または高度障害の状態になった場合に残りの住宅ローンの返済を免除され、家族はそのまま住宅に住み続けることができます。
団信に加入できるのは、新規の住宅ローン契約者または借り換えを行う人です。加入後に団信のプランを途中変更することはできません。健康状態によっては加入できない場合もあります。
団信の保険料は金融機関が負担しますが、一般的に、団信の保険料相当額は住宅ローンの金利に含まれています。これらの特性を理解し、自身のライフスタイルや将来の収入予測などを考慮に入れて、最適な返済方法を選ぶことが重要です。具体的なシミュレーションを行うことで、どの返済方法が自身に適しているかを見極めることができます。
住宅ローンにはさまざまな種類があります。信頼のできる不動産業者に依頼をして、お客様それぞれに最適な住宅ローンの選択が不可欠です。
弊社は全エージェントが宅地建物取引士ですので、安心してご依頼くださいませ。
公開日:2023年12月13日
REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの森山賢治です。土地の売買をするとき、その土地が軟弱地盤であるかどうか知っておく必要があります。その理由について解説します。

土地の売買契約後に地盤の軟弱性が発覚した場合、売主は契約不適合責任に基づいて買主に損害賠償を請求される可能性があります。売主は、地盤の軟弱性を知らなかった場合や、その原因に責任がない場合でも、責任を免れない場合が多いです。
なぜなら売主は契約の目的を達成できるような状態で土地を売却しなければならないためです。仮に軟弱な地盤だった場合、買主が建物を建てる予定だったならば目的を達成することができていないことになります。
地盤の軟弱だと、建物の不同沈下や傾斜などの損傷を受ける恐れがあります。また、地盤改良工事を行う必要がある場合、その費用は数百万円程度と高額になることがあります。
地盤の軟弱性は、売買契約締結時に隠れた瑕疵として認められる場合がありますが、その判断は個別の事情によって異なります。買主が地盤の軟弱性を一定程度認識していた場合や、売主が地盤の軟弱性を明確に告知した場合は、隠れた瑕疵とは認められない場合があります。
軟弱地盤とは、土木・建築構造物の支持層には適さない、泥や多量の水を含んだ常に柔らかい粘土や未固結の軟らかい砂から成る地盤の総称です。軟弱地盤には以下のような種類があります。
●有機質土・高有機質土(腐植土):植物の遺体や分解物が堆積した土で、水分や空気を多く含みます。圧縮性が高く、沈下や液状化の危険性があります。
●N値3以下の粘性土:N値とは、地盤の強度を示す値で、標準貫入試験で測定します。N値が3以下の粘性土は、水分を多く含み、圧縮性が高く、沈下や液状化の危険性があります。
●N値5以下の砂質土:N値が5以下の砂質土は、水の移動が容易に行える大粒の土で、地震時には液状化現象が起こりやすいです。
●海成堆積物・埋立地:海岸平野での海成堆積物や埋立地は、粘性土や砂質土が混ざった不均質な地盤で、沈下や液状化の危険性があります。
●腐植土:谷底に形成された腐植土は、有機物が多く含まれた黒色の土で、水分を多く含みます。圧縮性が高く、沈下や液状化の危険性があります。
最終的には専門家の調査によることとなりますが、現地を注意深く観察することや、公開されている資料を利用することで軟弱地盤かどうかを見分けることができます。
まず、売主から水はけの良しあし、過去の水害などについて確認します。近隣からもヒアリングする必要があります。郷土資料などによっても過去の自然災害を確認できます。
次に現地を観察することで軟弱地盤の可能性を推測することができます。
①建物や塀に傾きはないか、基礎が沈下していないか、擁壁の状況はどうか
②水はけが良いか悪いか
③水田や自然の池がある公園が近隣にあるか
④堤防や水門、調整池(調節池)・ため池などの人工構造物の存在
⑤近隣に傾いた塀がある、基礎や外壁に亀裂のある家が多い
また、一般に入手できる資料としては次のものがあります。
①ハザードマップ:水害ハザードマップ、液状化マップ
②古地図:対象土地が過去にどのような使われ方をしていたかを確認できます。
③年代別航空写真:対象土地がどのような変遷をしているかを確認できます。
④地質図(日本シームレス地図):地表付近の地層や岩体を、その種類や年代等によって区別して、それらの分布や重なりが分かるようにした地図です。
⑤土地条件図(国土地理院):防災対策や土地利用・土地保全・地域開発等の計画策定に必要な、土地の自然条件に関する基礎資料を提供する目的で、昭和30年代から実施している土地条件調査の成果を基に、主に地形分類(山地、台地、段丘、低地、水部、人工地形等)について示したものです。ハザードマップ作成の基礎資料として使われています。
⑥治水地形分類図(国土地理院):治水対策を進めることを目的に、国が管理する河川の流域のうち主に平野部を対象として、扇状地、自然堤防、旧河道、後背湿地の詳細な地形分類および堤防の河川工作物当を表示している主題図です。
⑦ボーリング柱状図:各自治体のHPで公開されており、軟弱地盤を判断する資料として活用できます。
調査によって軟弱地盤であると分かったとき、主な対処方法は以下のようなものがあります。
●地盤調査を行う:地盤の強度や改良の必要性を調べるために、専門の業者に依頼するか、不動産会社に相談しましょう。
●地盤補強工事を行う:地盤が弱いと判断された場合は、地盤を強化する工事を行う必要があります。地盤補強工事には、柱状改良工法、小口径鋼管工法、既製コンクリートパイル工法、表層改良工法などがあります。
●地盤の状態や改良の費用を明示する:地盤が弱いことを知っている場合は、売主は買主にその事実を告知する義務があります。また、地盤改良の必要性や費用の負担についても、売買契約の前に明確に合意しておくことが望ましいでしょう。
軟弱地盤はその物件ごとにさまざまな問題がありますので、よりきめ細かな調査が必要になります。信頼のできる業者に依頼をしての売買が不可欠です。弊社は全エージェントが宅地建物取引士ですので安心してご依頼をくださいませ。
公開日:2023年11月4日
REDSエージェント、宅建士の森山です。今回は不動産の差押(差押え、差し押さえ)や仮差押(差し押さえ)について解説します。

不動産の差押とは、債権者が債務者の不動産を裁判所の命令で保全する(債務者が売買できなくする)手続きです。差押がなされると、その不動産は競売や公売にかけられて、その代金が債権の弁済に充てられます。
これに対し、不動産の仮差押とは、債権者が債務者の不動産を裁判所の命令で仮に保全する手続きです。仮差押がなされると、その不動産は処分できなくなります。仮差押は、正式な裁判による債務名義(確定判決などの強制執行の根拠となる文書)を取得する前に行うことができるため、債権の回収を確実にするための有効な手段です。
不動産の差押、仮差押は一般的には以下のような場合に発生します。
●債務者が債務を履行しない場合。例えば、売買代金や借金の返済が滞っている場合など。
●債務者が財産を散逸させるおそれがある場合。例えば、不動産を売却したり、第三者に移転したりしようとしている場合など。
●債務者が破産や民事再生などの法的整理手続きに入った場合。この場合、債権者は自分の優先順位を確保するために差押や仮差押を行うことができます。
差押や仮差押の登記があるということは、その不動産に関して金銭的なトラブルや所有権の紛争がある可能性が高いことを意味します。そのため、以下の点に留意してください。
●差押や仮差押の登記がある不動産は、そのままでは売買できません。登記を抹消するためには、保全処分を申し立てた債権者による取り下げや和解などが必要です。その際には、債権者に対して一定の金額を支払うことが多いでしょう。
●差押や仮差押の登記を抹消する前に売買契約を締結する場合は、登記の抹消を売買の実行前提条件とすることや、その他のリスクを防止するための条項を適切に盛り込むことが必要です。そのため、売買契約書は弁護士などにチェックしてもらうことをお勧めします。
●差押や仮差押の登記があるまま不動産を決済した場合は、後日強制執行によって所有権を失ってしまうリスクがあります。その場合には、第三者弁済や契約解除などの可能性を検討する必要があります。また、更地の場合は、登記が抹消されるまで建築に着手しない方がよいでしょう。
差押や仮差押の登記があるということは、その不動産に関して金銭的なトラブルや所有権の紛争がある可能性が高いため、売買にあたっては、これらの登記の抹消が必要となることは上記で説明したとおりです。
差押と仮差押の登記の抹消方法は、以下のように分けられます。
●民間による差押え・仮差押え:直接法務局に対して、抹消登記を申請することはできません。裁判所に対して、差押などの取り下げ書を提出すると、裁判所から法務局に対して抹消登記が嘱託されます。この方法は債権者の協力が必要であり、残債務を弁済するか、別に担保を提供するかなど債権者に納得してもらう必要があります。
●行政による差押・仮差押:直接法務局に対して、抹消登記を申請します。通常、行政が抹消登記嘱託書(申請書)を作成してきますので、それを司法書士が預かって、登記申請します。
不動産が差押えられると、競売や公売にかけられて、その代金が債権の弁済に充てられます。債務者が債権者に対して財産を担保として提供する権利を抵当権といい、抵当権が設定されると、その財産は債務者の所有のままですが、債務不履行の場合は債権者が強制的に売却して、その代金を債権の弁済に充てることができます。
国民が税金を納めない場合、滞納処分として税務当局が財産を差し押さえることができます。差押え物件の抵当権と滞納している税金の優劣は、一般的には以下のように決まります。
抵当権の設定登記日が税金の法定納期限よりも前であれば、抵当権が税金に優先します。つまり、差押え物件が売却された場合、先に抵当権者に支払われて、残りが税務当局に支払われます。
抵当権の設定登記日が税金の法定納期限よりも後であれば、税金が抵当権に優先します。つまり、差押え物件が売却された場合、先に税務当局に支払われて、残りが抵当権者に支払われます。
※売主の残債務の確認を行う場合は、登記されている担保権の確認だけではなく、税金の滞納有無と納期限についても確認する必要があります。
差押、仮差押は物件ごとにさまざまな問題がありますので、よりきめ細かな調査が必要になります。信頼のできる不動産業者に依頼をして売買することが不可欠です。
弊社REDSは全エージェントが宅地建物取引士ですので安心してご依頼をくださいませ。
公開日:2023年10月1日
REDSエージェント、宅建士の森山です。建物を建てるために購入した土地の「地中」から、前に建っていた家の基礎部分やコンクリートの塊、ガラス、杭、ガラ、埋設管、古井戸、防空壕などの「障害物」が発見されることがあります。これらの「障害物」を地中障害物と呼びます。
土地を売却する際、地中障害物を曖昧なまま売買し、地中障害物が建物建築の支障となった場合、売主は契約不適合責任を負い、除去費用や損害賠償を請求される恐れがあります。地中障害物が建物建築の支障とならなくても、通常の土壌処理以上の費用がかかる場合には、売主に処理費用の支払義務が認められる場合があります。
地中障害物にまつわる調査や撤去方法、トラブルの回避方法について解説します。

地中に障害物があった場合、ケースごとに対応が必要です。
■地下に埋められた水道管やガス管、電線などが工事の支障となる場合
→移設や切断などの対応が必要です。
■基礎杭(建物の基礎を支えるために地中に打ち込まれた杭)が工事の支障となる場合
→切断や抜去などの対応が必要です。
■埋土中のコンクリート塊などのがれき類(過去の建築廃材や解体残材で、処分費用を節約するために地中に埋められたもの)が工事の支障となる場合
→掘り起こして撤去する必要があります。
■古いタイヤや衣類、産業廃棄物、医療廃棄物などの不法投棄されたゴミが工事の支障となる場合
→掘り起こして撤去、特に感染性廃棄物は特別管理産業廃棄物として処理する必要があります。
■転石(自然発生的に地中に存在する岩石)が工事の支障となる場合
→掘り起こして撤去する必要があります。
■空洞(地中に自然発生的にできた空間や、過去の採掘跡)が工事の支障となる場合
→埋め戻すか補強する必要があります。
■過去に使用されていた井戸や浄化槽、便槽などが工事の支障となる場合
→掘り起こして撤去、または、穴埋めする土を補充する必要があります。
地中障害物が出てきたとき、初動の調査としてどのようなものがあるでしょうか。
まず、土地所有者に対して聞き取り調査を行います。旧建物、井戸、浄化槽などの図面の資料、解体にかかる書類の提供を求め、旧建物の基礎や杭、井戸、浄化槽が撤去されているか、残置のままかどうかを調査します。また、現所有者が対象土地を取得したときの重要事項説明書や売買契約書も、地中障害物が存するかどうかを確認できる資料となります。
土地の歴史や周辺環境に関する図面や資料を調べることで、地中障害物の存在の可能性や種類を推測します。
土地の表面や周辺の状況を目視で確認することで、地中障害物の存在の兆候や影響を探します。
土地の一部を掘削することで、地中障害物の具体的な位置や深さ、材質などを確認します。試掘は、最も確実な方法ですが、費用や時間がかかり、土地に傷跡を残します。
電磁波を地中に送信し、反射波を受信することで、地中障害物の位置や深さ、形状などを画像化します。レーダー探査は、破壊することなく広範囲を効率よく探査できる利点がありますが、土質や障害物の種類によっては探査精度が低下する欠点もあります。
電磁誘導法、磁気探査法、レイリー波探査法などの各種物理探査法を用いて、地中障害物の位置や深さ、材質などを測定します。これらの方法は、レーダー探査と併用することで探査精度を向上させることができます。
地中障害物の存在が判明すると、必ず売主とトラブルになります。売買契約を締結する前にトラブルを予防するにはどうすればいいでしょうか。
推進工事(非開削工法)の前に、図面照査や現地確認、試掘やレーダー探査などで、地中障害物の情報をできるだけ詳しく把握しておくといいでしょう。障害物が発見された場合は、その除去や回避の方法を検討し、費用や工期などの影響を評価します。
売主と買主の間で、地中障害物が発見された場合の責任分担や対処方法を明確に定めることが望ましいです。例えば、地中障害物の除去費用や損害賠償の請求ができることや、契約の解除ができることなどを規定しておくことが有効でしょう。
では、地中障害物が出てきてトラブルになった場合の対処方法について解説します。
土地の地下に障害物が存在することが原因で、契約内容に適合しない場合、売主は「契約不適合責任」を負います。また、不動産業者は「信義則上の調査義務」や「宅地建物取引業法上の説明義務」を負います。これらの責任を追及することで、障害物の除去や回避の方法と費用、損害賠償などを請求することができます。
推進工事中に予期せぬ障害物に遭遇した場合は、掘進機で障害物を切削・取り込み・排出することで対処できます。掘進機による切削除去方式は、掘進機で障害物を切削できることはもちろんのこと、切削した障害物を掘進機内に確実に取り込めることが重要です。
地中障害物問題はその物件ごとにさまざまな問題がありますので、よりきめ細かな調査が必要になります。
信頼のできる業者に依頼をしての売買が不可欠です。弊社は全エージェントが宅地建物取引士ですので安心してご依頼くださいませ。
最終更新日:2023年9月4日
公開日:2023年8月29日
REDSエージェント、宅建マイスターの森山です。
隣地境界が曖昧なまま土地を売買すると、将来の売却や建設などが困難になることがあります。また、境界を明示せずに売買すると、買主と隣地の所有者の間で紛争が起こる可能性があります。このほか、道路の接道義務がはたせず、最悪のケースでは再建築不可になる可能性もあります。
こういった事態にならないようにどうするべきか、トラブルになってしまった場合にどのように解決するかを説明いたします。

土地売買には具体的に以下のようなトラブルがあります。
・隣地の建物の屋根や雨樋が越境していた
・境界確定を行っていなかったために、土地を売却しようとしたら、隣家の車庫や塀が自分の土地に侵入していることが判明した
・かなり前に境界杭の設置、隣地との立会いをしたが、隣地所有者が当時と代わっていたため、境界の場所に相違がでた
・道路(水路)との境界が不明確なことにより、建築時における役所との見解の相違が出た
これらのトラブルは、境界確定や境界標の維持管理を怠ったり、無断で越境したりすることで起こります。土地建物売買では、契約前に必ず境界確認を行い、隣地所有者との合意を得ることが重要です。隣地所有者とトラブルになると将来数十年にわたってもめ続けることもあります。
隣地境界トラブルが起きたとき、それを解決する方法は以下のとおりです。
お互いに話せば解決する場合もあります。境界線の位置や越境物の有無などを確認し、合意できるかどうかを試みましょう。
境界トラブル解決のためには、正確に土地を測量し、隣地境界線を明確にすることが必要です。土地家屋調査士は、専門的な知識と技術を持っていますので、信頼できる測量結果を提供してくれます。
筆界特定制度とは、法務局が土地家屋調査士に依頼して、隣接する土地の境界線を特定する制度です。この制度を利用すると、法務局が発行する筆界特定書が証拠となりますので、裁判になった場合でも有利になります。
境界紛争解決センターとは、日本弁護士連合会が設置した民間の紛争解決機関です。専門家が中立的な立場で仲裁や調停を行い、双方の合意に基づいて解決を図ります。ADR機関とは、裁判以外の方法で紛争を解決する機関の総称です。
話し合いや仲裁などで解決できなかった場合は、最終的には裁判に訴えることもできます。裁判では、証拠や法律に基づいて判断されますが、時間や費用がかかりますし、関係が悪化する可能性もあります。裁判に訴える前には、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
※どれも一長一短があります。状況や目的に応じて、最適な方法を選択する必要があります。
土地の売買契約前に境界トラブルにならないための予防方法は以下のようなものがあります。
境界標とは、土地の境界線を示す目印のことです。境界標があれば、土地の形や面積を確認しやすくなりますし、隣地とのトラブルも防げます。境界標は、土地家屋調査士に依頼して設置(埋設)することができます。
境界立会いとは、売主と買主が一緒になって、土地の境界線を確認することです。境界立会いを行うことで、売買契約前に土地の状況を把握できますし、後からトラブルが起きても対処しやすくなります。境界立会いは、土地家屋調査士や弁護士などの専門家に立ち会ってもらうことが望ましいです。
境界明示義務とは、売主が買主に対して土地の境界を明示することが義務付けられていることです。境界明示義務を怠ると、売買契約が無効になったり、損害賠償を請求されたりする可能性があります。境界明示義務は、売買契約書に記載するか、別途書面で行うことが一般的です。
※どれも重要です。土地の売買契約前には、必ずこれらの方法を実施してください。
※旗竿地の場合、特に敷地延長部分の境界は注意が必要です。
旗竿地とは、公道に接する間口が極端に狭く、細長く延びる敷地の先に、周りを他人の土地に囲まれた敷地のことです。
旗竿地は、敷地延長の最も狭い位置で、2メートル以上の幅を確保する必要があります。最も狭い位置というのが要注意になります。測量図と実際の幅が異なる場合は、建築基準法や条例による制限や影響がある可能性があります。また、売買時には、測量図と実際の敷地面積が一致しないことで、契約解除や減額請求などのトラブルになる恐れもあります。
測量図で2メートルの確保ができていても実際には満たしていない部分があるかもしれません。最悪、再建築不可となりますので、旗竿地をご購入する際には、間口はもちろんですが、敷地延長部分の全てにおいて2メートルを確保できているか必ず測って確認ください!!
隣地境界問題はその物件ごとにさまざまな問題がありますので、よりきめ細かな調査が必要になります。信頼のできる業者に依頼をしての売買が不可欠です。
弊社は全エージェントが宅地建物取引士ですので安心してご依頼をくださいませ。
公開日:2023年7月21日
REDSエージェント、宅建士の森山です。先日、区画整理地内の新築戸建ての売買を仲介しました。その際、お客様から区画整理についての説明を求められましたので、参考までにブログでも説明をさせていただきます。

区画整理事業とは、都市計画区域内の土地において宅地の利用増進および公共施設の整備改善を図るため、土地の区画形質の変更および公共施設の新設や変更をする事業です。土地区画整理事業により、土地の所在・地番・地目・面積が変わるため、表題部の登記内容が大幅に変更されます。
区画整理地には仮換地と保留地があります。区画整理事業中に元の土地所有者が、新しい土地を割り当てられる土地を換地といいます。
仮換地は、換地処分を行う前に「仮」に換地を指定することをいいます。保留地は、区画整理事業を実施した際に、事業主体が取得する宅地のことを指します。保留地は所有権がなく、仮換地は移り住むものに所有権が移行しているので売買は自由です。
仮換地のメリットとしては、区画整理事業が完了する前に売却することができるため、現金化が容易であることや、区画整理事業後に価格が上昇する可能性があるため、その上昇分を得られることです。
一方、デメリットとしては、区画整理事業後に価格が下落する可能性もあるため、そのリスクを負うことになります。
保留地のメリットとしては、区画整理事業後に価格が上昇する可能性があるため、その上昇分を得られることや、区画整理事業後に住みやすくなったり周辺環境がよくなったりするため、住環境の改善が期待できることです。
一方、デメリットとしては、区画整理事業後に価格が下落する可能性もあるため、そのリスクを負うことになります。
※保留地は所有権がなく、抵当権を設定できないため、ローンで利用できる金融機関が制限される可能性があります。
※保留地については、区画整理事業が完了した段階で登記簿が作成され、事業施行者名義で初めて保留地の保存登記が行われます。そのため、保留地では、区画整理事業が完了するまでは転売ができない場合もあります。
区画整理地内での土地取引にはどんな注意点があるのでしょうか。
工事期間中の土地売買は禁止も
区画整理地内では、工事期間中の土地売買は禁止されることがあります。また、事業後の制約がかかることがあります(高さ、最低限度面積など)。
また、土地の位置や面積が変わることがあります。過去の売買では約1キロ離れた場所に移動した土地もありました。方位や道路幅が変更になったり、旗竿地が整形地に変更になったり、といったこともありました。
土地清算金が発生することも
従前地と仮換地の面積により土地清算金が発生する可能性があります。区画整理地内の土地清算金とは、土地区画整理事業の換地により「従前の土地」と「換地」との間に評価上の不均衡が生じることがありますが、この不均衡を解消するためにやりとり(徴収や交付)される金銭のことをいいます。清算金は、区画整理前と後で生じた土地の価格差を埋め合わせるためのお金です。過去の売買では換地後に約600万円の徴収ありの土地がありました。
不動産取引においては、売買契約書において清算金の負担を売主、買主どちらにするか明記することが重要です。従前地と仮換地の面積があまり変わらない場合は要注意です。変わらない場合は徴収の可能性が高く、反対に大幅に減った場合は交付の可能性が高くなります。
売買価格に大幅な差も
使用収益の開始時期の差により、売買価格に大幅な差が生じる恐れがあります。区画整理地計画段階での土地も以前売買をおこないました。計画段階では使用収益が開始されていないため、いつから建築できるのかが不明でした。
仮換地予定図はあったのですが、そちらにはまだ家が建っており、立ち退きが済んでいませんでした。そのため、使用収益が開始された仮換地と違い、大幅に売買価格が下がってしまいました。
移転、移築に関する補償金について見こみ違いとなったことも
区画整理地計画段階での中古戸建も以前売買をおこないました。すでに建物等の取得価格、建物等の移転費用、建物等の再建築費用などから補償金が算定されていました。
中古戸建を購入してリフォームをおこなう予定でしたが、すでに補償金の算定が終わっているため、今後数千万円かけても補償金の対象にならないことが判明しました。
区画整理完了まで地目変更できない
区画整理地内のマンション売買についても、区画整理が完了するまで地目変更ができません。駅前のマンションでも登記簿上の地目が「農地」になっている場合は、売買するたびに農地転用届が必要になります。
換地処分後の登記手続き停止について
区画整理によって換地処分された登記簿が残り、従前の登記簿は閉鎖されます。換地処分の公告日の翌日から区画整理登記の完了までの期間は、施行区域内の土地及び建物に関する登記手続きは一時的に(3~4カ月の期間)停止されます。このため売買契約締結後、引渡しまでの間に換地処分がおこなわれますと登記が約3~4カ月できなくなりますので、その期間は引渡しができなくなります。
区画整理地内の物件はその物件ごとにさまざまな規制がありますので、よりきめ細かな調査が必要になります。区画整理地内の物件売買は、信頼のできる業者への依頼が不可欠です。REDSは全エージェントが宅地建物取引士ですので、安心してご依頼くださいませ。