木村 康幸(宅建士・リフォームスタイリスト)
クライアント様の利益のために素早く動きます。
CLOSE
公開日:2024年9月16日
REDSエージェント、宅建士の木村康幸です。今回は不動産業界の悪しき慣行として行われてきたいわゆる「不動産の囲い込み」が、国による処分対象となりそうだという「朗報」について解説します。
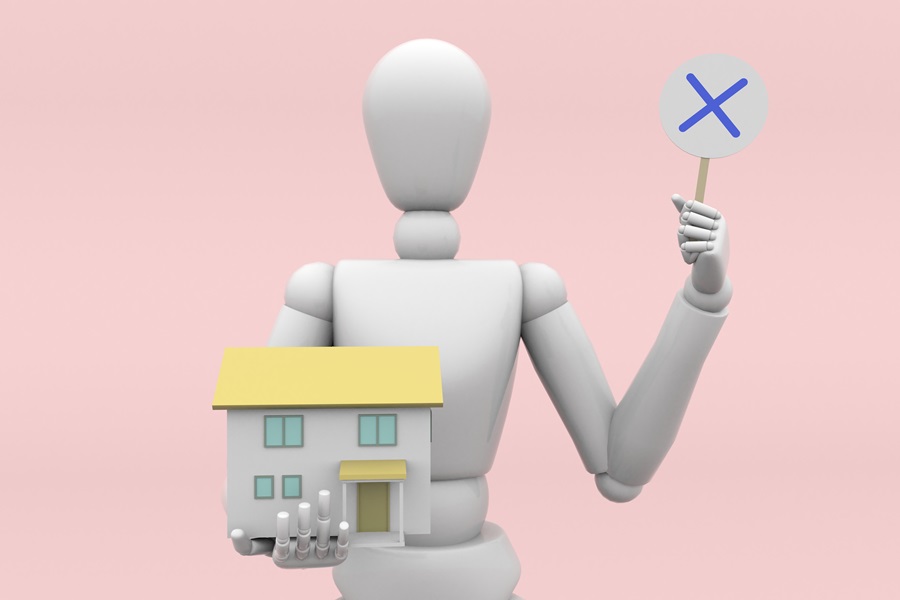
(写真はイメージです)
不動産における「囲い込み」とは、自社で「両手仲介」を実現したいがために、売却依頼を受けた物件の情報を市場に公開しないという不動産業界の商慣習のことを指します。
「両手仲介」とは、売買の依頼を受け、相手方を他の不動産会社を介さずに見つけることができた場合に、依頼元と相手方の両方から、仲介手数料をもらえることをいいます。
他の不動産会社が介在する片手仲介に比べて、収益は単純計算で2倍となるため、不動産会社の多くは両手仲介を目指して、自社の顧客網やネット媒体などによる広告でお客さんを探すことに注力しています。
ただ、そもそも売主と買主は「高く売りたい」「安く買いたい」という利益が相反する立場にあります。このように、双方の依頼を受けたという立場になる「両手仲介」は、ともすれば、売主・買主という依頼者の利益よりも、不動産会社の利益を優先することになります。消費者を置き去りにした行為ともいえるでしょう。
不動産会社が、より収益の多い「両手仲介」を執拗(しつよう)に目指すがために、売主から売却の依頼を受けた不動産物件を、他の不動産会社に取り扱わせないようにする行為のことを、不動産会社では、「囲い込み」(不動産・物件の囲い込み)といいます。
弊社ホームページをご参照ください。
◆クリーニングをするとウソをつく
N社:弊社のサービスで住んだまま室内クリーニングをいたします。売主様は土日しかお休みがないため、今週末、来週末でクリーニングしますので内見は3週間目以降ですね。
私:買主様リフォームを考えていますので、クリーニング不要です。
N社:売主様の意向です。売主様が汚れた室内を見られたくないと言っています。
(この期間はN社のお客様には内見させています。そして「申し込みあり」になります)
2024年8月29日の日経新聞に、国道交通省が囲い込みを処分するという内容の報道をしていました。以下、抜粋して引用します。
《不動産仲介業者による「囲い込み」が後を絶たない。売却依頼のあった物件を他社に紹介せず、売り手と買い手の双方から仲介手数料を取ろうとする行為だ。国土交通省は宅地建物取引業法の通達を改正し、2025年から囲い込みを確認すれば是正の指示処分の対象とする。物件の売却依頼を受け不動産業者は公的なデータベース「レインズ」に物件情報を載せ、取引状況を公表しなければならない。取引状況は「公開中」「書面による購入申し込みあり」など3段階で表示でき、囲い込む場合は「申し込みあり」と偽るケースが多いという。
「申し込みあり」とした場合、物件の購入希望をもつ顧客をかかえる不動産業者を遠ざけることができる。売却依頼を受けた業者は自ら買い手を探して成約させることができ、売買の両者から手数料を得られる。手数料は法律に基づく告示で「売買価格の3%プラス6万円」が上限の目安となっている。囲い込みが問題となっているのは、購入希望をもつ顧客が現れても、自社で買い手を探そうとするあまりに売却が遅れることがあるためだ。
高値での購入希望者が現れても、自社で受けた購入希望を優先しようとするために、低い価格での売却を迫られることもある。物件保有者の利益を損ねている可能性が指摘されている。国交省は取引の透明性を高めるため、宅建業法の解釈や運用に関する通達を6月末に改正し、囲い込みは処分対象だという見解を明確にした。
レインズへの登録内容に虚偽があることがわかれば処分する方針だ。こうした取り決めを2025年1月に施行する。発覚した場合は、宅建業法に基づく是正や再発防止の指示処分の対象となる。従来は発覚時の罰則が明確ではなく、囲い込みを許すもとになっていた。ある不動産業者の担当者は「大手でも、購入申し込みがないにもかかわらず、申し込みがあるとウソをついて内見を断るケースがある」と話す。レインズに関しては、仲介業者が売却を希望する物件の価格や面積、間取りなどを入力して掲載し、買い手側が検索できる仕組みとなっている。取引状況は必須の登録項目となっている。近年の住宅価格の高騰を受け、新築に比べて安価な中古住宅を選ぶ消費者は増えている。
内閣府の24年度の経済財政白書は住宅の着工戸数と中古住宅の取得戸数から中古の割合を試算しており、2022年度は約30%と10年前の約15%から上昇している。》
REDS 不動産流通システムの木村です。
宅地建物取引士・管理業務主任者・リフォームスタイリスト
(お気軽にお電話・メールにてお問い合わせください)
携帯電話:090-9815-3411
E-Mail:ya.kimura@red-sys.jp
公開日:2024年8月8日
REDSエージェント、宅建士の木村康幸です。
今回は、閑静な住宅街(第一種低層住居専用地域)についてのお話です。

第一種低層住居専用地域は、13種類ある用途地域のなかで最も建築制限が厳しい地域です。敷地の有効利用性がとても低いエリアで、それゆえいわゆる「閑静な住宅街」とされるエリアは、第一種低層住居専用地域が多いのです。
全体的に隣地との空間が広くゆったりしたエリアです。建ぺい率と容積率の制限が厳しく、高さ制限も10mか12mです。広めの敷地に平屋建てや2階建ての住宅が建ち並ぶエリアです。
第一種低層住居専用地域は全国的に以下のような制限があります。
建ぺい率が50%、容積率100%、土地面積100㎡の場合で考えると、建築できる建物は概算で1階に50㎡、2階に50㎡の2階建てになります。
両隣や近隣の住宅も同じ条件ですので、両隣との空間があり、採光・風通り・景観が良好で、ゆったりと静かな環境です。
第一種低層住居専用地域はこんな方々にお勧めのエリアです。
一方、第一種低層住居専用地域にはデメリットもあります。このエリアには大型のスーパーマーケットなどはつくれません。またコンビニエンスストアも条件をクリアする必要があります。。
以上のように、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるものを「用途地域」と呼びます。第一種低層住居専用地域を含め、以下のとおり13種類があります。
●第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域で建築物の高さが10mや12mなどに制限されています。戸建てだけでなく低層マンションも建てられます。一方、店舗は床面積の合計が50㎡以下であれば可能ですが、この規模では一般的なコンビニは建てられません。建物の種類としては、戸建て住宅のほか賃貸住宅やマンション、小中学校ならOKです。
●第二種低層住居専用地域
高さの制限は第一種低層住居専用地域と同様です。一方、建物の種類は床面積150㎡までの店舗が可能になるため、第一種低層住居専用地域で可能な建物に加え、コンビニや飲食店が建てられます。
●第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域です。建物の高さ制限はありません。
●第二種中高層住居専用地域
建物の種類は第一種中高層住居専用地域で可能な建物に加えて、2階建て以内&床面積1500㎡以下の店舗や事務所が建てられます。
●第一種住居地域
住宅の環境を守るための地域です。住宅以外は上記の第一種・第二種中高層住居専用地域で可能な建物に加えて、3000㎡までの店舗や事務所、ホテルが建てられます。
●第二種住居地域
主に住宅の環境を守るための地域です。第一種住居地域で可能な建物に加えて、ボウリング場やスケート場、また床面積1万㎡以下ならパチンコ屋やカラオケボックスなども建てられます。
●田園住居地域
平成30(2018)年4月に都市計画法上の新たな規制の仕組みとして導入され、田園住居地域という住居系の用途地域が追加されました。田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定められる地域・農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域です。
●準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。国道や幹線道路沿いが指定されることが多く、第二種住居地域で可能な建物に加えて、車庫や倉庫、作業場の床面積が150㎡以下の自動車修理工場、客席部分200㎡未満の劇場や映画館などが建てられます。
●近隣商業地域
準住居地域よりさらに制限が緩和され、店舗や事務所、劇場や映画館などに床面積の制限がありません。
●商業地域
映画館、飲食店、百貨店などが集まることを目的とした地域です。風俗施設や小規模な工場も認められています。ターミナル駅の周辺部などが指定されることが多いです。
●準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設が立地する地域です。危険性や環境悪化が大きい工場を除き、ほとんどの工場が建てられます。住宅やホテル、ボウリング場、映画館、病院、教育施設なども建てられます。
●工業地域
どんな工場でも建てられる地域です。高層マンション・住宅や店舗も建てられますが、ホテルや映画館、病院、教育施設などは建てられません。湾岸地域が指定されていることが多く、その場合たいていは高層マンションが建ちます。そのため高層階から海や街を眺める生活を送りたいという人には向いています。
●工業専用地域
工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅は建てられません。
(上記用途地域の種別と概要はSUUMOより抜粋)
REDS 不動産流通システムの木村です。
宅地建物取引士・管理業務主任者・リフォームスタイリスト
(お気軽にお電話・メールにてお問い合わせください)
携帯電話:090-9815-3411
E-Mail:ya.kimura@red-sys.jp
公開日:2024年6月30日
REDSエージェント、宅建士の木村康幸です。
ここ数年の住宅価格の高騰や住宅ローン控除の兼ね合いなど、さまざまなご理由でペアローンを活用するご家庭が増えています。ペアローンの場合、おふたりのどちらかに万一のことがあった場合、通常の団体信用生命保険で保障されるのは、その方が主契約者となる住宅ローンのみです。
一方、連生団体信用生命保険付住宅ローンに加入していれば、連帯債務でお借り入れされるおふたりのどちらかに万一のことがあった場合でも、ローン残高が保険でまかなわれて0円となります。住宅ローンの残高が残りませんので、家族の暮らしをしっかりと支えることができます。
今回は、この連生団体信用生命保険付住宅ローンについて解説します。

2024年6月15日現在で、4大銀行(三井住友銀行・みずほ銀行・三菱UFJ銀行・りそな銀行)で、連生団体信用生命保険の取り扱いがあるのは、三井住友銀行のみです。
三井住友銀行には、連生団体信用生命保険(商品名:クロスサポート)という保険があります。住宅ローン金利プラス年0.18%で利用できます。
参考:三井住友銀行|クロスサポート
日本経済新聞(2024年3月14日)によると、りそな銀行と埼玉りそな銀行も2024年10月から、がんと診断された際などに本人と配偶者が抱えるローンの残高をゼロにするペアローン向け団信の提供を始めるそうです。住宅価格の高騰に伴うペアローンによる高額借り入れの増加に対応するということです。
フラット35が展開する「デュエット(ペア連生団信)」とは、連帯債務者であるご夫婦で加入することができる制度です。ご夫婦のどちらか一方の加入者が死亡または所定の高度障害状態になった場合には、住宅の持ち分や返済額にかかわらず、残りの住宅ローンが全額弁済され、ローンの返済義務は残りません。
また、「デュエット」を利用できるご夫婦には、戸籍上の夫婦のほか、婚約関係にある方、内縁関係にある方、同性パートナーの方を含みます。
※3大疾病付機構団信でのご利用はできません。また、返済途中でのデュエットへの変更はできません。
※令和5年10月1日に「夫婦連生団信」から「ペア連生団信」に名称変更。住宅ローン金利プラス年0.18%でご利用いただけます。
参考:住宅金融支援機構|フラット35
PayPay銀行は、住宅ローンのペアローン向け団体信用生命保険として、ご夫婦などペアのおふたりのいずれかに万一のことが起こった場合、両方の住宅ローン借入残高の合計額※を保険金としてお支払いする「ペアローン向け全疾病保障付き連生団体信用生命保険(以下、ペアローン連生団信)」の取り扱いを2024年6月1日から開始しました。
※保障内容により、両者の住宅ローン借入残高の合計または月々の返済額の合計が保険金額となります。
従来のペアローンの団体信用生命保険は、ご夫婦などペアのおふたりのいずれかに万一のことが起こった場合も、もう一方のペアの方の返済は継続されますが、「ペアローン連生団信」は、万一のことが起こった場合、おふたりの住宅ローン借入残高がゼロになります。
参考:PayPay銀行株式会社|銀行初! 6月1日よりペアローンの「連生団体信用生命保険」取扱開始
群馬銀行にも夫婦連生団信付住宅ローンがあります。
夫婦でひとつのお借入をする住宅ローンで、夫婦のどちらか一方が死亡または所定の高度障害状態、余命6か月以内になった場合、保険金で住宅ローンが全額返済されます。
夫婦連生団信付住宅ローンは変動金利0.7%です。
参考:群馬銀行|夫婦連生団信付住宅ローン
2024年6月15日現在情報です。金利や商品内容等は変更になる可能性があります。
公開日:2024年5月20日
REDSエージェント、宅建士の木村康幸です。
住宅ローンの借入金額を伸ばす方法として収入合算があります。収入合算とペアローンは具体的に何が違うのでしょうか。連帯債務型と連帯保証型の違いについても解説します

夫婦や親子などの収入を合算して住宅ローンの審査にチャレンジすることを収入合算といいます。1人の収入では希望する金額を借りられないときなどに用いる手段です。収入合算できる要件は金融機関によって異なりますが、通常は同居していることや、配偶者や親子などの関係にあることが求められます。
収入合算でローンを借りるとき、ひとつのタイプに「連帯債務型」があります。連帯債務型では、一方が「主債務者」、もう一方が「連帯債務者」となります。主債務者も連帯債務者も同等に住宅ローンの債務を負うことがポイントです。
例えば、自分自身の年収だけでは希望額を借りられないとき、収入のある配偶者を連帯債務者として収入を合算すると、希望額を借りられるようになる場合があります。配偶者以外も連帯債務者になることができ、連帯債務者の基準は金融機関によって異なります。
収入合算の方法には「連帯債務型」のほかに「連帯保証型」というタイプもあります。いずれかが債務者になり、他方が連帯保証人になる方法で、債務者がローンを返済できなくなったときは、連帯保証人に返済義務が生じます。
ペアローンとは、一定の収入のある同居親族と一緒に、それぞれが主たる債務者として住宅ローンを組む方法です。それぞれが連帯保証人となります。同一物件に対して、2本の住宅ローンを組むのが収入合算との大きな違いです。
ペアローンを組むことができるのは夫婦、親子のほか、金融機関によっては同居予定の婚約者(入籍後に入籍を証明する書類の提出が必要になる場合も)、同性パートナー(公正証書などの提出が必要になる場合も)も認められます。
ペアローンでは各債務者がお互いの連帯保証人を務めるため、万が一、相手が返済できなくなった場合、自分の債務に加え相手方の債務も負うことになります。
ペアローンでは債務者のいずれも団体信用生命保険への加入が可能です。住宅ローン控除も、両債務者が対象となるため、所得税や住民税の節税ができます。
住宅ローンを連帯債務型にするメリットとデメリットを解説します。
住宅ローンを連帯債務で借りると、主債務者単独よりも多額を借りられる場合があり、理想の住宅を購入しやすくなります。また、連帯債務の場合、主債務者だけでなく連帯債務者も住宅ローン控除を受けられます。住宅や借入期間などの条件を満たしていれば、所得税や住民税の節税が可能です。
ペアローンは各債務者がローン契約を結ぶため、契約は2つとなりますが、連帯債務型の住宅ローンでは契約は1つのみです。印紙代なども1つの契約分のみ請求されるため、諸費用を抑えられます。
連帯債務者が病気やケガ、産休などで収入が減ったときでも、返済が免除されるわけではないので、貯金や就業不能保険などで備える必要があります。
また、団体信用生命保険は、主債務者のみが加入し、連帯債務者は加入できないことが一般的です。連帯債務者が団体信用生命保険に加入できないと、連帯債務者が死亡、所定の高度障害などの状態になった場合でも、住宅ローンは全額残り、主債務者の負担が増えてしまうことが考えられます。
金融機関によっては「連生団信」と呼ばれる主債務者・連帯債務者共に加入できる団体信用生命保険を取り扱っている金融機関もあります。「連生団信」は借入金利に保険料が上乗せされることが多いです。本来、主債務者が支払うべき住宅ローンの返済額を連帯債務者が支払うと、贈与税の対象になる場合があったり、主債務者と連帯債務者のいずれかが退職などにより収入のない状態になると、借り換えができなかったりするため注意しましょう。
次はペアローンのメリットとデメリットを解説します。
連帯債務型の住宅ローンとは異なり、ペアローンでは2人が債務者となり、それぞれが住宅ローン契約を結びます。ペアローンを利用すると、2人のうち片方が単独で住宅ローンを組む場合と比べると、多額を借りられるようになる点は連帯債務型の住宅ローンと同じです。
また、個別に住宅ローンを組むため、返済期間や金利タイプ(固定金利や変動金利、固定期間限定型など)を自由に設定できる点もメリットです。「夫は妻より10年早く退職するので返済期間も10年短くする」など、個人の生活にあわせた住宅ローンの組み立てが可能です。
両方が住宅ローン控除を利用でき、団体信用生命保険に加入できる点もメリットです。節税できるだけでなく、死亡や高度障害状態などの万が一のときにも備えられます。
ペアローンはそれぞれが個別にローンを組む契約のため、印紙代などの諸費用が2名分発生します。連帯債務型の住宅ローンと比べると、諸費用が割高になる点にご注意ください(電子契約の場合は印紙代がかかりません)。
また、ペアローンでは2名とも団体信用生命保険に加入できますが、一方に万が一のことが起こった場合、もう片方の返済義務は継続されます。
参考ページ(auじぶん銀行)
https://www.jibunbank.co.jp/column/article/00421/
公開日:2024年4月14日
REDSエージェント、宅建士の木村康幸です。
住宅ローンに申し込む際に、一般的には、契約者が死亡するなどしたときに残債の支払いが免除される「団体信用生命保険(団信)」への加入が必要となります。
住宅ローンの事前審査で承認が取れているにもかかわらず、住宅ローンの本審査で否決されてしまうケースのなかに、団体信用生命保険へ加入ができないことが理由である場合が多々あります。
団体信用生命保険にはいくつか種類があります。保障が適用される範囲が広いタイプもあるので、より安心感を得たい方は保障範囲の広さで選ぶのもよいでしょう。今回はこの団体信用生命保険(団信)について解説します。

団体信用生命保険(団信)とは、銀行などを保険契約者および保険金受取人、住宅ローン利用者を被保険者とする保険契約です。住宅ローンの利用者が死亡、または所定の高度障害状態になったときに保険が適用され、生命保険会社が債務残高相当分の保険金を保険金受取人である銀行などに支払い、銀行などはその保険金を債務の返済に充当します。
一般の生命保険では、死亡した際には保険金が遺族に支払われます。一方、団体信用生命保険では、保険会社が住宅ローンの引受先である銀行へ保険金を支払うという点が、一般の生命保険と異なる特徴です。
住宅ローン利用者が、団体信用生命保険の保険適用の条件を満たすと、住宅ローンの借入残高が0円になり、完済した状態になります。なお、団体信用生命保険の保障期間はローンの返済期間と同じで、ローンを完済すると、保障と団体信用生命保険の契約も終了します。
一般的な団体信用生命保険には、住宅ローン利用者が死亡したときの「死亡保障」と、高度障害状態になったときの「高度障害保障」が備わっています。
近年は死亡保障と高度障害保障に加えて、がんによって所定の状態になった場合に保険が適用される「がん保障」や、3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)によって所定の状態になった場合に保険が適用される「3大疾病保障」タイプもあります。
所定の状態が何を指すかは団体信用生命保険の種類によって異なるため、必ず契約前に確認しておく必要があります。例えば、がん保障のある団信では、がんと診断されると保険が適用されるものもあります。また、特定の疾病で入院することや、就業できない状態が一定期間続くことで保障が適用されるものもあります。
住宅ローン利用者は、家庭の中で中心的な稼ぎ手(一家の大黒柱)となっていることが多いため、死亡や就業不能状態になると家庭の収入が大幅に減り、返済が難しくなることも少なくありません。しかし、団体信用生命保険に加入していると、住宅ローン利用者に万が一のことがあったときに、団体信用生命保険の保険適用条件を満たしていれば住宅ローンが完済した状態になるため、住居を確保することができます。
一般的な生命保険では、被保険者に万が一のことがあったときは、受取人になっている方に保険金が支払われます。被保険者が死亡したときに保険適用となる生命保険であれば、受取人に指定された方が受け取ります。
団体信用生命保険に加入せずに一般的な生命保険に加入していた場合、被保険者が死亡、もしくはその他の保険適用の条件となる状態になったときに現金は受け取れますが、住宅ローンの支払いは残ります。保険金が住宅ローンの借入残高よりも多ければいいのですが、そうではない場合は残った住宅ローンを返済し続けていかなくてはなりません。
また、一般の生命保険は、保険料が保険金にほぼ比例しているという点にも注意が必要です。住宅ローンでは数千万円単位で利用するケースが一般的なため、生命保険金だけで住宅ローン借入額を充当しようとすると、返済をしながら高額な保険料を毎月支払うことになります。とはいえ、現金で保険金を受け取れるという点は、団体信用生命保険にはない一般的な生命保険ならではのメリットです。
住宅ローン利用者に万が一のことがあったときのためにも、団体信用生命保険と生命保険の両方を検討するといいでしょう。団体信用生命保険で返済を解消し、一般的な生命保険である程度の生活費や子どもの教育費に備えるということを想定しておけば、将来的な不安が軽減される可能性があります。
三菱UFJ銀行の住宅ローンで、利用できる団信を例に解説していきます。
https://www.bk.mufg.jp/kariru/jutaku/column/008/index.html
一般的な団信は金利上乗せ型と呼ばれるもので、一般団信部分の保険料は金融機関が支払い、上乗せした金利が適用されることで契約します。保険料分高くなり、月々の返済額にも反映されることになります。しかし、なかには保険料として別途支払うタイプの団信もあります。
三菱UFJ銀行の「7大疾病保障付住宅ローン ビッグ&セブン〈Plus〉 」では金利上乗せ型の団信もありますが、「安心の保険料タイプ(保険料支払型)」の団信では返済とは別に団信保険料を支払います。
https://www.bk.mufg.jp/kariru/jutaku/kanren/bigseven.html
「安心の保険料タイプ(保険料支払型)」の団信を選択すると、いかなる業務にも従事できない状態が30日を超えて継続した場合、毎月のローン返済額を補償し、1年と30日を超えて継続した場合は、ローン残高はなくなります。
金利上乗せ型はローン利用者の条件にかかわらず、一律の金利が上乗せされますが、保険料支払い型の保険料は性別や年齢によって変わる点は注意してください。また、加入時の保険料は定額ではなく、ローン利用者の年齢によって保険料が変化します。
団体信用生命保険の内容は各金融機関それぞれに特徴がありますので、ご自身にあったプランをみつけてください。
公開日:2024年3月8日
2024年2月より、フラット35のローン商品「子育てプラス」が、いよいよスタートされました。概要は下記になります。
◎子供の人数等に応じて金利引き下げ
◎金利引き下げ幅を最大▲1%
4月にマイナス金利の解除を予測するエコノミストが多数おり、金利上昇に敏感なお客様は金利上昇リスクを念頭におき始めています。住宅ローンの選択肢のひとつとして「フラット35」新制度、子育てプラスをご紹介させていただきます。
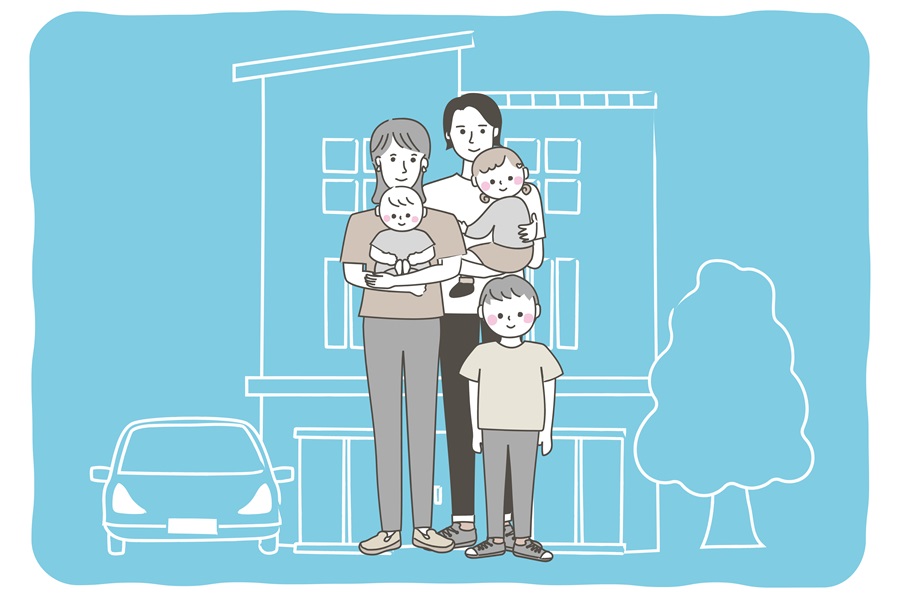
【フラット35】子育てプラスを新設し、子育て世帯※1、または若年夫婦世帯※2に対して全国一律で子供の人数等に応じて一定期間借入金利を引き下げます(【フラット35】Sなどの他の金利引き下げメニューとも併用できます)。
新しいポイント制度を導入し、金利引下げ幅を従来の最大年▲0.5%から最大年▲1.0%に拡充します。
※1 借入申込時に子供(実子、養子、継子および孫をいい、胎児を含みます。ただし、孫の場合はお客さまとの同居が必要です。また、別居している子供の場合は、お客さまが親権を有していることが必要です)を有しており、年齢が借入申込年度の4月1日において18歳未満である世帯をいいます。
※2 借入申込時に夫婦(法律婚、同性パートナーおよび事実婚の関係をいいます。なお、婚約状態の方は対象外です)であり、夫婦のいずれかが借入申込年度の4月1日において40歳未満である世帯をいいます。
*借入申込後から資金実行までの間に、上記の条件を満たした場合に対象となります。詳しくは取り扱い金融機関にお問い合わせください。
*お客さまが自ら居住する住宅、セカンドハウスとして居住する住宅またはお客さまの親族が居住(※)する住宅を建設・購入する場合が対象です。
※お客さまの親族が居住する場合は、融資対象住宅に入居する方が子供を有する場合または若年夫婦に該当し、かつ、連帯債務者となる場合のみご利用いただけます。
*【フラット35】子育てプラスは、借り換え融資にはご利用いただけません。
以下では【フラット35】子育てプラスの単独適用があった場合の金利引下げ幅等を記載しています。【フラット35】Sなど他の金利引下げメニューと併用する場合の金利引下げ幅については、ポイント早見表をご覧ください。
1.若い夫婦世帯または子供1人の場合 金利引下げ期間は【当初5年間】 金利引下げ幅【年▲0.25%】
2.子供2人の場合 金利引下げ期間は【当初5年間】 金利引下げ幅【年▲0.5%】
3.子供3人の場合 金利引下げ期間は【当初5年間】 金利引下げ幅【年▲0.75%】
*子供の人数に応じてポイントが加算されていく仕組みです。ポイント制度の詳細はポイント早見表をご覧ください。
*上記では【フラット35】子育てプラスのみのポイントの適用があった場合の金利引下げ期間および金利引下げ幅を記載しています。
民営化に伴い、住宅金融公庫は「独立行政法人住宅金融支援機構」に生まれ変わりました。フラット35とは同機構が展開している住宅ローンの名称です。そのときどきの金利で変動することなく進んでいく固定金利タイプになります。全期間固定金利ですので、金利上昇リスクを気にせず安定した資金計画がたてられます。
ただし、2024年2月20日現在では各銀行の変動金利、約0.3~0.9%に対してフラット35の固定金利は1.82%~1.96%ですので金利差が大きいのも事実です。
フラット35は投資用に使用してはいけません。公式ページでは下記の注意勧告がなされています。
“【フラット35】は第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金には、ご利用いただけません”
機構は申込ご本人またはご親族の方が実際に住んでいるかどうか定期的に確認しているそうです。これまで、不動産投資セミナー、不動産投資専門会社からの勧誘を通じて【フラット35】を投資用物件の取得に不適正に利用した事例が確認されています。悪質な勧誘によって、【フラット35】の不適正利用に巻き込まれないよう、ご注意ください。
また、居住用の住宅ローンを利用して投資用物件の取得を勧誘するウェブサイトも存在するようです。ご注意くださいませ。
不動産売買の経費削減は【REDS】不動産流通システムにお任せ下さい。
エージェント全員が宅地建物取引士です。
★★仲介手数料を法定上限額では頂きません。割引〜最大無料です。★★
成約価格が5,000万円以上だと仲介手数料半額確定〜最大無料になります。
不動産売買のご用命は、【REDS】不動産流通システム 木村までお願いいたします。
公開日:2024年1月30日
REDSエージェント、宅建士の木村です。
相続登記が義務化されます。2024(令和6)年4月1日より相続登記義務化制度が開始されます。正当な理由がないのに相続登記の申請をしないとペナルティもあるようですので、注意が必要です。

(1)相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、早めに相続登記の申請をしましょう。
※ 相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本などの資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなどは正当な理由です。
相続登記がされないため、不動産登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった不動産相続登記が義務化されることになりました。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。法務局に申請する必要があります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記をする必要があります。
相続人の間で早めに遺産分割協議の話し合いを行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に、不動産相続登記をする必要があります。
早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続き(※)を法務局でとって、義務を果たすこともできます。相続人申告登記は、戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する、簡易な手続きです。
◆遺産分割の話し合いがまとまった場合→遺産分割の結果に基づく不動産相続登記を行います。不動産の相続を知った日から3年以内にする必要があります。
◆早期に遺産分割をすることが困難な場合→「相続人申告登記」を行う。
※ 令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9年3月31日までに不動産相続登記申請を行う必要があります。
土地の相続などの際に所有者についての登記が行われないなどの理由で、誰が所有者なのか分からない土地が増えています。あるいは、所有者は分かっていてもその所在が不明で所有者に連絡がつかない土地のことです。所有者が不明の土地の面積は、九州の土地面積よりも広いと言われています。このような管理されずに放置された所有者不明の土地は、周辺の環境や治安の悪化を招いたり、防災対策や開発などの妨げになったりしています。
そこで、こうした所有者不明土地をなくすため、令和3年4月に、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本法制の見直しが行われました。
所有者不明土地が生じる主な原因としては、
●土地の相続の際に登記の名義変更が行われないこと
●所有者が転居したときに住所変更の登記が行われないこと
などがあげられます。
所有者が分からない状態が続くと、土地の管理がきちんと行われないまま放置され、周辺の環境や治安の悪化を招き、近隣住民に不安を与えることになります。
また、土砂崩れなどの防災対策のための工事が必要な場所であっても、所有者が分からないために、工事を進めることができず、危険な状態が続いてしまったり、公共事業や市街地開発などのための用地買い取り交渉ができず、土地の有効活用の妨げになったりします。
上記のような理由から相続登記義務化制度が開始されます。
参考ページ
東京法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202203/2.html
公開日:2023年12月22日
REDSエージェント、宅建士の木村康幸です。
家族構成の変化や転勤、高齢化、移住などで住み替えを考えているお客様は多いと思いますが、住宅ローンを抱えた状態で新しく住宅購入できるのか、不安になる方も多いでしょう。売却と購入が、ほぼ同時期にできれば理想的ですが、なかなか想定どおりにはいきません。
今回は住み替えのコツについて解説します。

住宅ローンは原則として、1世帯につき1軒の住宅に対して利用するのが前提です。原則的に二重の住宅ローンは難しいです。同じ銀行で住宅ローンの組み換え、もしくは完済して他の銀行で新規に住宅ローンを組み直します。ほとんどの場合で、新規融資の条件に現在の住宅ローンの完済が入ります。
2軒目のローンとして「セカンドハウスローン」や「親族居住用住宅ローン」があります。銀行により名称が違います。銀行には独自の返済比率があり、購入が先の場合、ご自宅が売れるまでの間、銀行によっては短期間の二重ローンを認めてくれる場合もあります。
契約から引き渡しまで、期間は少し長めに想定しておきましょう。通常、居住中の物件では契約から引き渡しまでが2~3か月くらいですが、3~6か月いただいて、その間に物件を探します。その期間内に住み替え先の物件が見つかればいいのですが、見つからない場合は、一時的に賃貸物件への仮住まいも視野に入れなくてはなりません。引き渡し期日までに引き渡さないと契約違反になってしまうからです。
さらに引き渡し猶予を7日くらい見ておくといいでしょう。引き渡し猶予とは、売買代金の支払い清算が終わってから数日間、引き渡しを待ってもらうことです。通常は1週間から10日程度です。ただし、引き渡し猶予の特約が契約書に記載されていると銀行によっては融資が受けられませんので注意が必要です。
住み替えには、金銭的にゆとりがあれば気に入った物件を先に購入して、引っ越し後、自宅をゆっくり売却していくという方法もあります。二重ローンの支払いにも耐えられるゆとりが必要です。
銀行によっては、6か月くらい新規住宅ローンの金利だけの支払いで元金支払いを待ってくれる場合もあります。
購入と売却がほぼ同時となった場合、下記のような特約を記載します。購入したのはいいのですが、万が一、自宅売却の契約が崩れた場合の備えです。お金が入ってこなくなるので購入できなくなります。
1.買主はその所有する所在:新宿区西新宿一丁目●●番地●● 家屋番号:西新宿一丁目●●番●●の●● 建物の名称:●●マンシヨンを売却し、その売却代金を本物件の売買代金に充当するため、令和5年12月18日付不動産売買契約(以下「買い替え契約」という。)を締結済ですが、買主の責に帰さない事由により買い替え契約が解除された場合、あるいは買主の責に帰さない事由により売買代金の入金が遅延し、かつ入金日が未定である場合には、本物件の所有権移転登記の時期までは、買主は本契約を無条件にて解除することができるものとします。
2.前項により本契約が解除された場合、売主は買主に対し、受領済の金員を無利息にて速やかに返還しなければなりません。
―――――――――――――――
次に、売却したのはいいが、万が一、新規購入の契約が崩れた場合の備え。引き渡し猶予付き。新規購入の契約が崩れると住む場所がなくなってしまうためです。
1.売主は本物件の買い替え先として、所在:大田区区山王一丁目●●番地● 家屋番号:山王一丁目●●番●の●● 建物の名称:●●第二マンシヨンを購入するため、令和5年12月18日付不動産売買契約(以下「買い替え契約」という。)を締結済ですが、売主の責に帰さない事由により買い替え契約が解除された場合には、本物件の所有権移転登記の時期までは、売主は本契約を無条件にて解除することができるものとします。
2.前項により本契約が解除された場合、売主は買主に対し、受領済の金員を無利息にて速やかに返還しなければなりません。
3.買主は、売主に対して、本物件の引き渡しを売買代金支払い日の翌日から7日間猶予するものとする。また、猶予期間中、売主は本物件の管理責任を負い、猶予期間中に天災地変等の不可抗力によって本物件の全部又は一部が滅失もしくは毀損したときは、その損失は売主負担とする。なお、固定資産税等の負担は上記引渡日をもって区分し、その前日までの分を売主負担、引き渡し以降の分を買主負担とする。
住み替えに関するご相談はぜひREDSまでご相談ください。
公開日:2023年11月15日
REDSエージェント、宅建士の木村です。戸建てを購入する際、家の前を走る道路についていろいろと決まりがあることを初めて知ったという方も多いかもしれません。道路には建築基準法と道路法の2つの法律が関係しています。今回は道路について建築基準法と道路法の両面から解説します。

建築基準法では、道路と建築物との間における一定の関係が定められています。これには、道路の幅員や、道路と建築物の距離、道路の拡幅などに関する規定が含まれています。以下に、建築基準法における道路に関する主な規定を詳しく説明します。
大原則として、幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられません。この道路について建築基準法では7つ規定されています。
建築基準法42条1項1号道路は、基本的に道路幅員4m以上です。国・都道府県・市町村が管理しています。
建築基準法42条1項2号道路も基本的に道路幅員は4m以上で、都市計画法により定められた道路になります。都市計画法とは、土地利用、建築基準、交通インフラ、環境保全などに関する規制や方針を設け、都市や地域の発展を適切に調整し、公共の福祉を確保することを目的としています。
建築基準法42条1項3号道路とは、建築基準法施行時の昭和25年11月23日以前に都市計画区域の指定を受けていた地域で、その日にすでに幅員4m以上あった道路のことです。既存道路とも呼ばれます。
建築基準法42条1項4号道路とは、現在は道路ではなく、これから造られる計画段階の道路のことです。道路幅員は4m以上で、2年以内に事業の執行が予定されているものとして特定行政庁が指定したものです。
建築基準法42条1項5号道路とは、建築基準法施行時の昭和25年11月23日以降に民間が申請を行い造った道路で位置指定を受けた道路です。通称、位置指定道路と呼ばれています。
建築基準法42条2項道路の道路幅員は4m未満です。建築基準法施行時の昭和25年11月23日に、すでにあった道路です。建物が密集しており建て替えの際には、セットバックが必要な道路です。
一般的には、道路の中心線から水平距離2mの範囲をセットバックするか、道路の片側が崖地や川などである場合には、その側の道路境界線から水平距離4mの範囲をセットバックすることになります。
建築基準法42条3項道路は、道路幅員は4m未満で建築基準法施行時の昭和25年11月23日に、すでにあった道路です。建物が密集しておりセットバック不可能な道路です。
特定行政庁は、土地の状況により、やむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については2m未満1.35m以上の範囲内において、同項に規定するがけ地などの境界線からの水平距離については4m未満2.7m以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。水平距離指定道路とも言われます。

日本の道路法(道路交通法)には、道路に関する詳細な規定が含まれています。
■高速自動車道(高速道路)
自動車専用の高速道路で、通常、高速自動車道法に基づいて管理されています。高速道路は、最高速度制限、車線規制、出入口の規則などが厳格に定められています。
■一般国道
一般国道法に基づいて管理され、都市間や県を結ぶ幹線道路です。一般国道も速度制限や交通規制が適用されます。
■都道
都道法に基づいて都道府県が管理する道路です。都市内や都市間の地域を結びます。
■県道
県道法に基づいて都道府県が管理する道路で、都道と市町村道の中間に位置します。
■市町村道
市町村が管理する地域内の道路です。市町村道法に基づいて規定があります。
道路の設計と建設は、厳格な規格と基準に従って行われます。これには道路の幅、カーブの設計、標識や信号の配置、歩道や自転車道の設置などが含まれます。
■速度制限
道路ごとに異なる速度制限が設定されており、高速道路では最高速度が通常100km/hまたは80km/hで、一般国道や都道、市町村道では一般的に40km/hから60km/hまでが一般的です。
■交通規制
道路法では、車線規制、通行止め、駐車規制などの交通規制についても規定されており、これらの規則を守ることが求められます。
■道路標識・信号
道路標識と信号は、交通の安全と秩序を維持するために道路上に配置されています。これらの標識や信号を守ることが法律で義務付けられています。
■交通事故と保険
道路での交通事故に関する法的規定と、自動車保険の義務についても道路法に記載されています。交通事故が発生した場合、事故処理や保険の適用に関する詳細な規定が適用されます。
日本の道路法は、道路の安全と交通秩序の維持を目的としており、道路利用者に対して責任と義務を課す法律です。詳細な規則については、日本の交通法規に直接アクセスし、最新の情報を確認することが重要です。
公開日:2023年10月11日
REDSエージェント、宅建士の木村です。
宅地建物取引士(以下、宅建士)は、不動産取引における専門家であり、幅広い業務を担当します。1つの事務所に5人に1人以上在籍する必要があり、足りなくなったら2週間以内に補充しなければならないという不動産会社にとってはマストな存在でもあります(REDSはエージェント全員が宅建士なので、そうしたルールとは無関係です)。
そんな宅建士は日々、具体的にどんな仕事をしているのかを、REDS不動産流通システムの木村が改めて説明いたします(今回は購入希望のお客様に対してのお仕事内容です)。
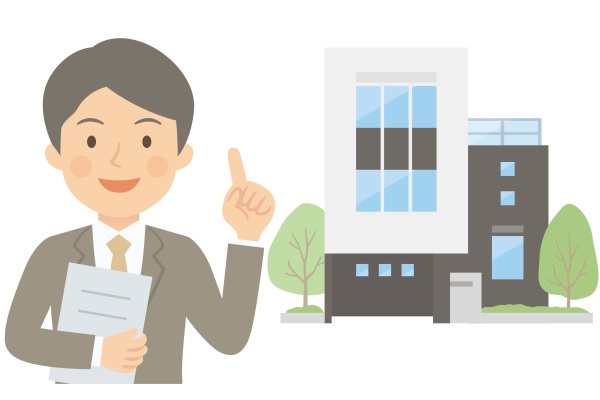
購入希望のお客様に対してさまざまな仕事を提供し、彼らが適切な不動産物件を見つけ、スムーズに取引を進められるようにサポートします。以下、宅建士が購入希望のお客様に対して行う主な仕事を順を追って紹介します。
購入希望のお客様の要望や予算に合った不動産物件を見つけるために、市場で紹介可能な物件のリサーチを行います。地域、価格帯、広さ、間取り、設備、築年数、駅までの距離、駐車スペースの有無などの諸条件をお客様に念入りにヒアリングをして適切な物件候補を特定し、購入希望のお客様に提案します。
購入希望のお客様と一緒に希望物件の内見に行きます。売り物件の中には売主様が居住中の物件が多々ありますので、事前の予約、日程調整が不可欠です。例えばお客様が3物件の内見を希望された場合、効率よく回るために日時を調整するのも宅建士の仕事です。
物件の内部と外部を評価し、お客様に物件の状態や魅力を説明します。住宅の場合、部屋の間取りや設備、修繕が必要な場合の見積もりなどを提供します。土地の場合、地盤状態や土地利用の可能性についてアドバイスを提供します。いいところばかりではなく、悪いところも伝えてお客様に判断を任せる宅建士のほうが良心的であることはいうまでもありません。
その時点での不動産市場の状況やトレンドに関する情報をお客様に理解していただきます。地域ごとの価格傾向や需要供給バランス、将来の成長ポテンシャルなどについて説明します。ただし5年後とか10年後といった根拠のない個別物件の価格予想はいたしません。
購入希望のお客様が特定の物件に興味を持った場合、契約条件や価格交渉の支援を提供します。売主様との交渉において、適切な価格や契約条件で購入するためのアドバイスを提供し、最善の取引条件を実現します。
不動産取引に必要な契約書を作成し、お客様に説明します。売買契約書・重要事項説明書は取引条件や法的責任を定める重要な文書です。契約書の内容や法的な意味についてお客様にわかりやすく解説し、必要に応じて修正や調整を行います。また物件ごとに慎重に調査を進め作成します。
不動産取引における法的問題やリスクに関するアドバイスを提供します。例えば、土地利用規制や建築基準法、不動産登記に関する法的事項などについて説明します。お客様が法的な責任を理解し、購入に向けて適切な手続きを実施できるようにサポートします。
お客様が不動産を購入するために融資(住宅ローン)を受ける必要がある場合、不動産会社は金融機関との連絡や融資手続きをサポートします。審査を通過するためのアドバイスをしたり、資金調達が難航するお客様にはさまざまな金融機関をご紹介したりして、ご希望に添えるように全力を尽くします。
物件の状態を確認するために、法務局や役所も回って物件を調査します。マンションの場合は管理会社を通じて最新の管理規約や重要事項の調査報告書を取得して、大規模修繕工事の履歴や予定、積立金に不足はないか、管理費や積立金の値上げ予定の有無、マンション全体での管理費や積立金滞納額を調べます。事件や事故、火災や自殺の事象はないかヒアリングも行います。
取引が最終的に成立し、売買契約を締結する際には、クロージング手続きのサポートに入ります。不動産の所有権の移転手続きや抵当権設定の登記手続きについてもサポートします。
不動産の購入後も、お客様に必要な情報やサポートを提供します。例えば、住宅ローンの返済計画や火災保険・地震保険の選定についてもアドバイスします。
宅地建物取引士は、購入希望のお客様の不動産取引を円滑に進めるために、専門知識と経験を活用して支援します。また、購入希望のお客様のニーズや目標を理解し、最適な不動産取引戦略を提供する役割を果たします。宅建業法では1つの事務所には5人に1人の配置でよいとされていますが、REDSはエージェント全員が宅建士です。ぜひご相談ください。