畑中 隼一郎(宅建士・リフォームスタイリスト)
迅速・丁寧な対応を心掛けて参ります。
CLOSE
公開日:2024年6月27日
REDSエージェント、宅建士の畑中隼一郎です。
マイホームを買おうと思ったときに、多くの人が悩むのが「マンションと戸建て住宅どちらがいいのか」ということでしょう。
マイホームと戸建てにはどちらもメリット・デメリットがあり、かかる費用や住みやすさ、立地環境なども変わってきます。迷ったときに、どこで判断するか比較するポイントを知っておくことが大切です。今回は、マンションと戸建て住宅のどっちがいいか、チェックすべきポイントについてご紹介します。

いきなり結論めいたことを言ってしまいますが、「絶対にマンションの方がいい!」「戸建ての方が得だ!」という答えはありません。
なぜなら、両方ともメリット・デメリットがあり、買う人が何を重視するのかによってどちらが向いているかは変わってくるからです。どちらにすべきか悩んでいる場合は、どの部分を重視するか、どこが気になるかを整理して比較してみると決めやすいでしょう。
マンションと戸建て住宅では、比較するポイントがいくつかあります。購入後のライフスタイルのイメージや、お金のシミュレーションをしながら比較してみるとわかりやすいでしょう。
マイホームの購入で一番気になるのが「費用」。費用といっても最初にかかる「物件価格」だけでなく、住み続けている間にかかる「維持費」や「税金」なども含めて比較する必要があります。それぞれの費用について解説します。
マンションの物件価格は首都圏を中心に上がり続けており、戸建て住宅よりも平均価格が高い状況となっています。物件価格は立地条件や築年数によっても大きく変わるので、さまざまな条件で幅広く探してみましょう。
マンションの場合、毎月管理費や修繕積立費がかかります。車を所有する場合は駐車場代も継続的な費用になるので、軽く考えてはいけません。基本的には管理費や修繕積立費が、物件の手入れやメンテンス費用になります。
戸建て住宅の場合は、マンションのように毎月決まった額を支払う維持費がありません。ただし、家は劣化するものなので、定期的なメンテナンスが必要です。一度にまとまった金額を用意するのは大変なので、計画して貯蓄しておくようにしましょう。
そして、マンションと戸建て住宅ともに、毎年固定資産税がかかります。固定資産税は、土地と建物の両方にかかる税金です。土地に対する税金は、広さに応じて算出されます。建物に対する税金は、建物評価額が高いほど高くなります。マンションは鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造のため耐用年数が長く、戸建て住宅よりも税金が高くなる傾向です。
マンションはワンフロアで生活ができて生活動線が整っています。セキュリティが完備されているケースが多いため、安心して住める環境です。
一方、戸建て住宅は2階、3階と建てられるため、マンションよりも床面積が広くとりやすく、居住空間は広くなります。バルコニーや庭などを確保しやすいのも戸建て住宅なので、何を重視して物件を選ぶか決めておきましょう。
不動産は、物件価値や土地の価値、立地環境の価値など、さまざまな評価を基に資産価値が決まります。
特に差が出やすいのは建物の耐用年数です。マンションは耐用年数が長いので、資産価値の維持に有利です。立地条件もマンションのほうが駅から近い好立地に建ちやすいので、戸建て住宅よりも資産価値が高くなりやすいでしょう。
マンションか戸建て住宅、どちらが自分に向いているか、以下のチェックポイントで確認しましょう。
マンションの大まかな特徴は、ワンフロアでの生活や立地環境がよい物件が多いことです。セキュリティも完備され、共用部分は管理会社による清掃やメンテナンスがあるため、自分で行う必要はほぼありません。
戸建て住宅の大まかな特徴は、広い面積を確保しやすく、静かな住宅街でも生活音や声で近隣に迷惑をかけにくいことです。プライバシー性があり、庭が欲しい方や駐車場を敷地内に欲しい方にもおすすめです。
マイホームを購入する際、マンションと戸建て住宅で悩んだときに、どちらが正解ということはありません。どこを重視して、どこが自分にとってメリットに感じるかというのが大きなポイントです。
最初はマンションに住んで、子どもができたら戸建てに引っ越すというケースもたくさんあります。現状と将来的な部分をイメージして考えるといいでしょう。
公開日:2024年5月19日
REDSエージェント、宅建士の畑中隼一郎です。
戸建てのマイホームを購入する際、注文住宅と建売住宅のどちらにすべきか、悩む方も多いのではないでしょうか。注文住宅と建売住宅では、それぞれで特徴が異なるので、よく理解して決めなくてはいけません。注文住宅と建売住宅、それぞれのメリットやデメリット、特徴についてご紹介します。

注文住宅は、自分の理想を形にできる家づくりができます。自分の好きな土地を見つけ、そこに理想のマイホームを建てられます。建物の構造から始まり、間取りやデザイン、使用する材質や設備なども自分で決めて家づくりを進めます。このため、こだわりがつまった理想の住まい空間を実現できます。
注文住宅の大きなメリットは以下の3つです。
注文住宅は、自分で好きな土地を探すところから始まります。土地から自分の好きな場所を選べるのは、注文住宅ならではのメリットでしょう。
土地が決まった後は、図面や施工など構造やデザインに関わる部分まで決められます。建てる工程まで見られるので、土台となる基礎から細かい部分の構造まで確認することが可能です。
注文住宅の大きなデメリットは以下の3つです。
注文住宅は自由度が高い反面、完成まで時間と労力がかかります。気になる土地が見つからなければ、その分時間もかかってしまい、入居まで1年を過ぎることもよくあります。このため、最初の段階で完成後の住宅イメージが付きにくいのも注文住宅のデメリットです。
そして、注文住宅は費用が高くなりやすいこともデメリットかもしれません。間取りや設備などに高品質なものを取り入れればその分高くなります。また、土地の地盤や設計の変更などによって、完成までに費用が上がってしまうことも珍しくありません。
決められた土地の上に決められた建物が建つ予定のものを購入するのが建売住宅です。完成前だとしても図面や完成後のイメージを見て購入を決められますし、完成後の物件を販売しているケースもあります。
建売住宅の大きなメリットは以下の3つです。
建売住宅はすでに完成している場合や、建設が始まっている状態のものが多く、早めに入居できることがメリットです。また、コスト面が抑えられており注文住宅よりも費用が安く済むでしょう。
建売住宅の大きなデメリットは以下の3つとなります。
建売住宅は、間取りやデザインがほとんど決まっているので、自分の思いどおりに選べないことがデメリットです。敷地内で複数の物件を販売することが多く、同じような建物が建ち並ぶなかのひとつのため、個性が乏しいと感じるかもしれません。また、まとまった土地を活用するため、駅から少し離れた立地になりやすいことも覚えておきましょう。
注文住宅と建売住宅は、これまで解説したようにメリット・デメリットが異なるため、特徴をよく理解して選ばなくてはいけません。選ぶ基準やポイントを解説します。
住宅購入で何よりも大切なのが予算を決めることです。無理をした予算の決め方は生活を苦しめてしまう可能性があるので、余裕を持った予算決めをしなくてはいけません。
予算を決めることは家づくりのスタートです。資金計画や返済シミュレーションを考慮した上で、長期的な目線で考えるようにしましょう。
家づくりは、すべてを叶えようと思うと、予算がいくらあっても足りません。住宅購入で決めるべきポイントは、予算、立地、間取り、デザイン、設備など多くの項目があります。この中から優先順位をつけておくと判断しやすくなります。
一例ではありますが、デザインは妥協できるけど予算を抑えたい場合は、建売住宅の選択がおすすめです。一方、こだわりたいデザインがあり、予算に多少幅を持てる場合には、注文住宅の選択も検討できるでしょう。このように優先順位や重視するポイントを整理しておくと、スムーズな選択がしやすくなります。
注文住宅と建売住宅を選ぶ際には、メリット・デメリットを把握した上で、どこを重視するかによって決めることが大切です。長く住む住宅の購入になるため、長期的な計画やライフスタイルをイメージして考えるようにしましょう。
公開日:2024年4月11日
REDSエージェント、宅建士の畑中隼一郞です。
子育て世代が新しい家を探す際、家族の安全や子供の成長に適した環境こそ何よりも重視することでしょう。今回は、子育て世代が考慮すべき安全で快適な住まいの条件を6つ挙げ、詳しく説明します。
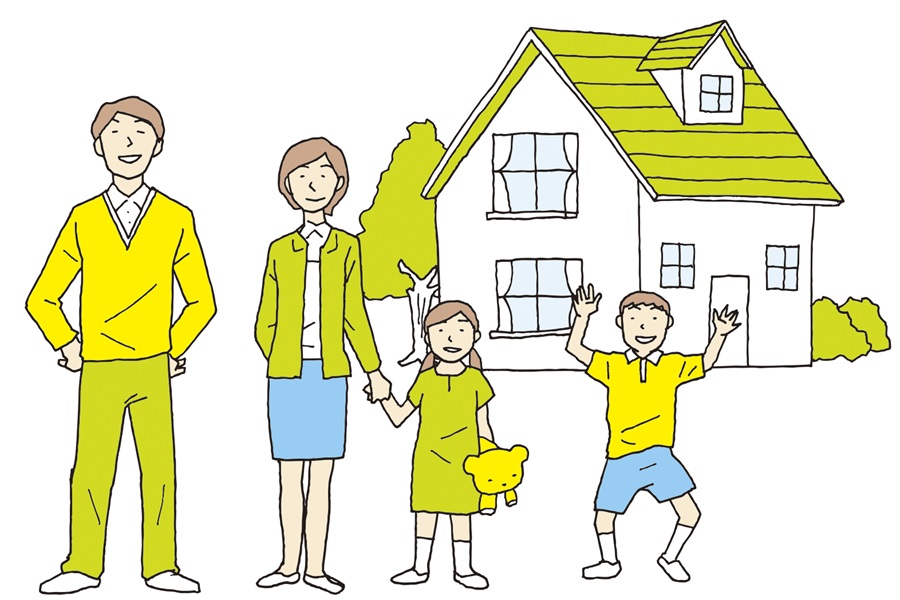
子育て世代の家族にとって、最優先事項は安全な地域での暮らしです。子供が自由に外で遊べる公園や学校が近くにある場所を選ぶことが大切です。近隣のコミュニティが家族向けのイベントや活動を提供しているかどうかも考慮しましょう。
家族の安全を守るために、犯罪率の低い地域を選びましょう。地元の警察署や自治体のウェブサイトで犯罪統計を確認すれば、犯罪率が低く安心して暮らせるエリアを見つけることができます。
子供の安全を考える上で、交通の便や学校の近さも重要な要素です。通学路が安全で、自宅から学校や公園へのアクセスが容易な場所を選びましょう。通勤や通学の利便性は生活の質を左右します。
近くに学校や公共交通機関があることで、家族の移動がスムーズになります。学校の評判や教育水準も確認しましょう。子供たちの将来にかかわります。
家そのものが安全であることも子育て世代にとって不可欠な条件です。耐震性の高い建物やセキュリティシステムが整った住宅を選びましょう。幼い子供がいる場合は、階段や窓の安全対策も見逃せません。
家の建築や設備が安全かどうかを確認し、耐震性の高い建物やセキュリティシステムが整った住宅を選ぶことで、家族の安全を守ることができます。
子供の健康を考える上で、周辺環境の騒音や環境状況も重要なポイントです。交通量の多い道路や工場の近くなど、騒音や大気汚染が気になる場所は避けるようにしましょう。
緑豊かなエリアや静かな住宅地を選ぶことで、子供たちは家周辺で安心して遊べます。騒音や大気汚染の少ない静かな地域を選びましょう。
建築できる建物の種類や用途の制限を定めた用途地域は「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分かれ、さらに13種類のエリアに分かれます。まずは「住居系」から探しましょう。用途地域は自治体窓口で確認できます。
子育て世代にとって、近くに子供向けの施設やアクティビティがあるかどうかも重要な要素です。公園や遊び場、図書館やレクリエーションセンターなど、家族で楽しめる場所が近くにあることで、子供たちの成長や交流を促進できます。
近くに公園や図書館、スポーツ施設があるかどうかを確認し、子供たちの成長をサポートする環境を整えましょう。
子供が成長するにつれて家のニーズも変わってきます。将来的に子供部屋や書斎が必要になるかもしれませんので、将来の拡張やリフォームがしやすい間取りを選ぶといいでしょう。
子供が成長するにつれて家族のニーズも変化します。将来的な子供部屋や家庭オフィスなどのスペースを考慮し、将来の拡張やリフォームがしやすい間取りを選びましょう。
子育て世代にとって理想的な住環境を見つけるためには、安全性や快適性を重視することが重要です。安全な地域の選択や交通の便、住宅の安全性、周辺環境の騒音や汚染、子供向けの施設やアクティビティ、そして将来のニーズに対応できる間取りなどの要素を考慮しましょう。これらの条件を満たす家を見つけることで、子育て世代の家族が安心して暮らせる環境を実現できます。
子育て世代の皆様、安心して子供たちを育てられる住環境を求めていますか。理想の住まいとして、安全な地域にあり、学校や公園にも近く、家族が快適に暮らせる空間が欲しいですよね。
弊社ではお客様からご相談いただいた物件に対して、安全性を重視した設計やセキュリティシステムが整った住宅であるかについて、アドバイスさせていただいています。さらに、周囲の環境も静かで犯罪率の低い地域か否かもお調べして情報提供しています。家族のニーズに合わせた物件や間取りや設備もご提案するほか、将来的な拡張やリフォームも考慮した間取りプランで、家族が成長しても快適に暮らせる空間を提供し、リフォームのアドバイスも行っております。
子育て世代の皆様、安心して子供たちを育てられる理想の住環境探しを弊社でサポートさせていただきますので、ぜひ一度ご相談くださいませ。
公開日:2024年3月6日
理想の住まいを手に入れることは、多くの人々にとって重要な目標です。しかし、予算の制約や貯金の必要性に直面すると、現実との乖離に悩むこともあるでしょう。しかし、可能な限りお金をかけずに理想の住まいを手に入れる方法はあります。今回はその方法を6つ紹介します。
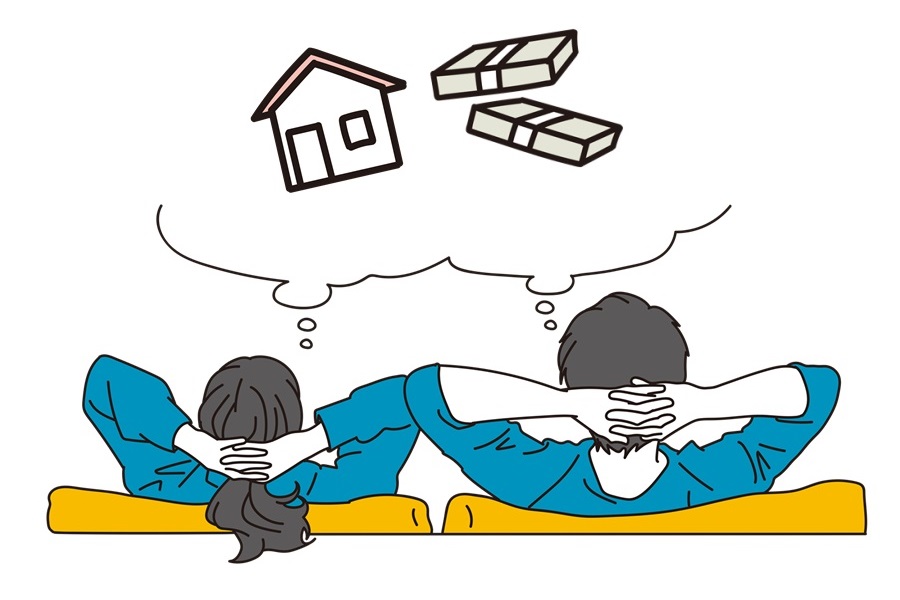
最初に、予算を明確にすることが重要です。ご自身の財政状況を理解し、購入可能な物件の価格帯を把握することで、無駄な時間や労力を省くことができます。予算を明確にすることは、理想の住まいを手に入れるための最初のステップです。
まず、自分の収入と支出を詳細に把握しましょう。月々の収入から生活費やその他の支出を差し引いた残額が、住宅ローンの支払いに充てることができる金額です。金利や返済期間などの条件も考慮に入れて予算を立てることで、自分にとって購入可能な物件の価格帯を特定することができます。
理想の住まいを手に入れるためには、十分な貯金(現金)が必要です。特に頭金や諸費用に充てるための貯金は欠かせません。頭金を多く用意することで、住宅ローンの借入額を抑えることができ、返済負担を軽減することができます。
諸費用とは不動産取引に伴う手数料や税金、保険料などのことです。物件価格の5~10%程度とされ、これらの費用も事前に準備しておく必要があります。
理想の住まいといっても、結局は予算の範囲内で選ぶことになります。広すぎる物件や設備が豪華すぎる物件は、予算オーバーとなる可能性があります。必要なスペースや設備を考慮し、無駄のない物件を選ぶことが重要です。
自分のニーズやライフスタイルに合った物件を選ぶために、まず希望条件を明確にしましょう。例えば、広さや間取り、立地条件など優先すべきことから決めます。また、物件の価格だけでなく、管理費や修繕積立金などの維持費も忘れずにチェックしましょう。
購入したい物件が決まったら価格交渉をすることも重要なステップです。不動産市場では物件の価格に交渉の余地があることが一般的ですので、積極的に交渉を行いましょう。
まず、同じエリアや条件の物件の価格を調査し、市場相場を把握することが大切です。そして、物件の状態や需要供給のバランスなどを考慮しながら、適切な価格で交渉を行います。付帯条件や引き渡し時期などの条件も含めて、細かく交渉することも成功のポイントです。
新築物件だけでなく、中古物件やリノベーション物件も検討してはいかがでしょうか。リノベーションやDIYによって、予算内で自分好みの住まいを作り上げることができるからです。中古物件やリノベーション物件は、新築物件に比べて価格が安く、自分好みにカスタマイズすることができます。
コストや手間、時間などのデメリットもありますが、予算や好みに合わせて自由に改装することができる魅力があります。リノベーションやDIYに興味がある場合は、プロのアドバイスや技術を活用しましょう。
不動産エージェントは市場動向や物件情報に精通しており、理想の住まいを見つけるための貴重なパートナーです。エージェントの助言を活用し、予算内で購入者のニーズに沿った最適な物件を探すサポートを受けることが重要です。価格交渉や契約の手続きなどの面でもアドバイスしてくれるでしょう。
不動産エージェントの専門知識と経験を活用することで、効率的に予算内で最適な物件を見つけることができます。信頼できる不動産エージェントは必ずしも大手の不動産会社ばかりにいるとは限りません。相談に対する返答の内容やレスポンスの早さ、的確さなどから判断しましょう。不信感を持った場合は早めにチェンジしたほうがいいでしょう。
これらの方法を組み合わせることで、お金をかけずに理想の住まいを手に入れることができるでしょう。しっかりと計画を立て、慎重に行動することが必要です。まずは予算を明確にし、貯金を活用しましょう。住まいに求める自分のニーズが何かを明確にしないことには物件の選定ができません。
価格交渉やリノベーションを検討することで、予算内でよりよい物件を手に入れるチャンスが広がります。信頼できる不動産エージェントのアドバイスを積極的に取り入れることで、よりスムーズに物件探しを進めることができます。前向きなアプローチで、理想の住まいを手に入れるために一歩ずつ進んでいきましょう。
公開日:2024年1月27日
REDSエージェント、宅建士の畑中隼一郎です。
住宅ローンの選定と返済計画は、長期的な視点と慎重な計画が求められる重要なテーマです。この記事では、住宅ローンの選び方から賢い返済戦略まで、詳細かつ誰でも理解しやすい内容で解説します。

住宅ローン選びの基本は、慎重な比較と将来を見据えた計画です。まず考慮すべきなのが金利です。金利は借入期間中に支払う利息を左右します。固定金利は一定期間内で一定の金利が適用され、変動金利は金融市場の変動に応じて金利が変わります。選ぶ際には、将来の金利の動向や自身の経済状況を考慮し、最も適したものを選びましょう。
次に注目すべきは借入期間です。借入期間が短いほど返済総額は少なくなりますが、月々の返済額は増えます。一方で、借入期間が長い場合は月々の負担は軽減されますが、返済総額は増加します。ライフスタイルや将来のライフプランに合わせて、返済期間を選定しましょう。
返済額も重要なポイントです。月々の返済が適切でないと、生活に支障をきたす可能性があります。返済能力を正確に把握し、無理のない範囲での返済プランを立てることが必要です。返済額の計算には、元本と金利の分割払いを含めた総返済額を考慮し、適切な月々の支払いプランを組み立てましょう。
最後に、住宅ローンの基本を押さえることは、将来の生活の安定に大いに寄与します。金利や借入期間、返済額を丁寧に比較し、自身のライフプランに合わせた選択を行うことが、住宅ローン契約の成功への第一歩です。
住宅ローン契約を締結する前に、徹底的な返済計画を立てることが成功の鍵です。この計画はご自身が返済できる範囲を理解し、将来にわたって安定した生活を維持するための基盤となります。
最初に行うことは、現在の収入と支出を洗い出すことです。定期的な収入や生活費、急な支出などをリストアップし、実際の返済にどれだけの余裕があるかを確認します。これにより、生活の中でどこまでローン返済に回せるかを具体的に把握できます。
将来の変動にも備えるため、計画には柔軟性を持たせましょう。予想外の出費や急激な生活の変化にも対応できるよう、緊急時の備えを計画に組み込んでおくことが重要です。また、計画においては返済期間や月々の返済額、金利の変動に対するリスクを考慮することも重要です。
専門家や金融アドバイザーに相談することもおすすめです。彼らは市場動向や金利変動に精通しており、最適な返済計画を提供してくれるでしょう。専門家の意見を取り入れつつ、自分自身でも計画を練ることで、返済に対する不安を軽減し、より安心して住宅ローンに取り組むことができます。
住宅ローンの返済は家計への負担が大きいため、月々の支払いが収入の30%未満になるように工夫することが重要です。こうすることで、生活に余裕をもたせ、非常時にも対応しやすくなります。返済に使う収入だけでなく、将来のキャリアの変動や家族構成の変化にも注意を払いましょう。
最も効果的な方法は、収入と支出の管理を徹底することです。家計簿をつけ、何にどれだけのお金がかかっているのかを明確にしましょう。節約の余地があれば検討し、無駄な支出を見直すことで、返済に充てる資金を確保できます。支出を見直す際には、食費や光熱費、通信費などを重点的にチェックし、ムダを省く工夫をすると効果的です。
住宅ローン減税をうまく活用することで、住宅購入の初期コストを軽減し、返済負担を軽くすることができます。例えば、利子控除や住宅取得資金の特例などが該当します。
利子控除は通常、住宅ローンの支払いに対して適用されます。支払った利息額が一定の範囲内に収まる場合、その金額を所得税の計算から差し引くことができます。ただし、地域ごとに規定が異なるため、具体的な条件や上限額を確認することが不可欠です。
住宅取得資金の特例も検討する価値があります。これにより、住宅購入時に必要な資金を節約できることがあります。ただし、これらの減税制度は継続的な居住や条件の遵守が求められることが一般的ですので、詳細をよく理解した上で適用することが肝要です。
住宅ローンの選び方は金利、借入期間、返済額を慎重に比較し、将来を見据えた計画が鍵です。返済計画では現在の収支だけでなく、将来の変動やライフイベントも考慮し柔軟な計画を立てましょう。
公開日:2023年12月19日
REDSエージェント、宅建士の畑中隼一郎です。
近年、不動産市場において注目されているのが、新たな補助金制度です。これは不動産や住宅の購入者にとって絶好のチャンス。この記事では、取得しないと損するかもしれない新しい補助金に焦点を当て、その詳細な内容や効果的な取得方法について解説します。

新しい補助金は、住宅取得者に対して提供されるもので、その目的は多岐にわたります。例えば、エコフレンドリーな住宅を選ぶことや、再生可能エネルギーを導入する場合など、持続可能な選択を促進することが狙いです。補助金の種類によって異なりますが、住宅ローンの支援や税制優遇などが含まれます。
省エネルギー住宅を選ぶことでエネルギー効率向上補助金が得られたり、初めて住宅を購入をしたらファーストタイムホームバイヤー補助金を得られたりします。
補助金を利用することで得られるメリットは多岐にわたります。例えば、住宅ローンの金利軽減や返済期間の猶予、税制上の優遇措置などが挙げられます。これらの特典は、購入者にとって負担を軽減し、将来的な経済的な安定をもたらす要因となります。
補助金を取得するためには、いくつかの手続きや条件があります。補助金の申請書類の提出し審査をクリアしましょう。不明点があれば、専門家の助言を仰ぐことも重要です。
令和5年度に住宅購入を促進するための「こどもエコすまい支援事業」が行われました。こちらはすでに9月時点で予算に達しており、終了しております。新たに発表された補正予算案は「住宅省エネ2024キャンペーン」の一環として、同支援事業の後継事業として発表されました。これから家づくりを検討される方、参考にしてください。
まず、対象となる方は下記のいずれかの方になります。
①子育て世帯:18歳未満の子を有する世帯
②若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが39歳以下の世帯
つまり、例を挙げると以下のようになります。
・夫35歳、妻42歳、子供なし→〇
・夫43歳、妻45歳、子供1人(3歳)→〇
・夫42歳、妻41歳、子供なし→×
次に対象となる住宅(新築)は下記の2つです。
①長期優良住宅→100万円
②ZEH住宅(強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20%に適合するもの)→80万円
②が少々難しいですが、簡単に言うとZEH住宅と言っても必ず太陽光パネルを設置しなければいけないわけではありません。性能レベルがZEH基準を満たしていれば、OKということです。
ただし、下記が注意点となります。
・対象となる住宅の延べ面積は、50㎡以上240㎡以下とする。
・土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に立地している住宅は原則除外とする。
・「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、3戸以上の開発又は1戸若しくは2戸で規模1000㎡超の開発によるもので、都市再生特別措置法に基づき立地を適正なものとするために行われた市町村長の勧告に従わなかった旨の公表に係る住宅は原則除外とする。
補助金の将来的な展望や変遷についても触れましょう。政府の方針や社会の変化に伴い、補助金の内容や提供条件は変動する可能性があります。将来の変更点に備え、賢明な不動産投資戦略を構築できるようになります。この情報は、長期的な視点で不動産取引に携わるので特に重要です。
新しい補助金は、不動産購入者にとっては見逃せない機会となっています。その多様な種類や詳細な内容を理解し、適切な取得方法を選ぶことで、将来的な住宅購入において大きなメリットを享受できるでしょう。
損をしないためにも、補助金について十分な調査を行い、賢明な不動産取引を進めてください。補助金の多様なメリットや取得プロセス、専門家のアドバイス、成功事例を踏まえつつ、将来を見据えた展望を理解することで、より戦略的かつ持続可能な不動産取引を実現できるでしょう。
情報をどれだけ早く取り入れるかどうかで何百万と損をしていることにつながるので、今後も最新情報をチェックしたいと思います。
公開日:2023年11月12日
REDSエージェント、宅建士の畑中です。「賃貸と購入、どちらがいいのか」は住まいについての永遠のテーマですね。
住宅を購入するならさまざまな観点から決断しなければなりません。今回は住宅を購入する7つのメリットを紹介します。この中から3つ以上に納得した、もしくは当てはまっていたという方は、早い段階で住宅購入を実行していただいたほうがいいと思います。決断は早いほど、その後の人生をより豊かに送れるでしょう。

住宅を購入するとメリットがいくつかありますが、主なものを7つ紹介します。
住宅購入の最大の魅力は、資産を構築できることです。住宅の中には時間の経過とともに価値が上昇するものもあります。不動産市場が安定的に成長すれば、マイホームが資産の一部として成長し、将来的には売却することで利益を上げられるでしょう。
例えば、ある都市で住宅を購入し、数年後に売却すると、市場価値が上昇している場合、差額を利益として受け取ることができます。これは、将来の不測の事態に備えるための重要な手段となり、次世代への投資にもなります。
住宅を所有することにより、生活の安定性とセキュリティが向上します。住宅ローンを通じて自宅を購入すると、定期的なローン返済が必要ですが、安心感も得られます。賃貸にはありがちな家賃の増加や突然の転居のリスクから解放され、家族にとって帰る場所が与えられるからです。
マイホームでは自己表現とカスタマイズが自由です。賃貸住宅では居室のカスタマイズには制限が多いですが、マイホームでは壁の色やデザイン、庭の配置などを自分の好みに合わせてカスタマイズできます。個性を反映した居住空間での暮らしは、人生もより楽しく魅力的になるでしょう。
マイホームを所有すると、以下のような税制上の優遇措置が受けられることがあります。
●住宅ローン控除:住宅ローンを利用してマイホームを購入すると、「年末時点での住宅ローンの残高の0.7%」が、入居時から最長13年間にわたって、給与などから納めた所得税や住民税から控除されます。
●不動産税の優遇:不動産を所有すると不動産税が課されますが、住宅所有者は税金の面で優遇を受けることがあります。これにより、不動産にかかる税金が削減されます。脱税は犯罪ですが、賢く節税をするのはいいことです。
●キャピタルゲイン税の免除:キャピタルゲイン税とは、資産の売却によって生じる利益に対して課せられる税金のことです。これは、資産の売却益が資産を取得した時の価格(取得原価)よりも高い場合に課されます。住宅の売却益が一定の金額以下の場合、キャピタルゲイン税が免除されることがあります。これにより、住宅の売却による利益を最大化できます。
住宅ローン金利は通常、他の種類の借入金よりも低く抑えられています。低金利を利用することで、住宅購入がより手頃になり、月々の支払いが抑えられます。
自宅を所有すると、将来の退職したあとの生活設計に役立ちます。住宅ローンの返済を完了すると、退職後に家賃を支払う必要がないため、生活費の軽減につながります。一方、賃貸はある意味で無制限の支払いです。働けなくなって収入がなくなると支払いができないリスクがあることを考え、早めに住宅を購入し老後の居場所を確保しておきましょう。
自宅を所有することは、家族の成長と未来の計画をサポートすることでもあります。自宅の庭で家族の時間を過ごすことは、絆を深める素晴らしい機会となるでしょう。子供が成長する過程をゆっくりと見届けられ、転居の心配などせずに家族との時間をゆっくり過ごすことができます。住居を変更する必要が少ないことは、子供たちに安心感と安定感をもたらします。
住宅購入は、あなたの未来に向けた重要な一歩です。資産の構築、生活の安定性、自己表現の機会、税制上の優遇、低金利のローン、退職資産の一部構築、そして家族の成長をもたらしてくれるでしょう。あなたのライフスタイルをカスタマイズし、将来の退職後の老後生活を強化できます。
ただし、住宅購入には検討すべき多くの要因があり、慎重な計画が必要です。個人の状況に合わせて、住宅購入が最善の選択であるかどうかを検討し、将来の成功に備えましょう。
公開日:2023年10月8日
REDSエージェント、宅建士の畑中です。不動産会社を訪問する際、お客様が事前の準備をされていると話がスムーズに進み、取引の進行が迅速になり、ご自身のニーズに合った物件を見つけるチャンスが高まるなど、お客様にとってメリットがあることばかりです。では、どんな準備をしておけばいいのか、簡単に解説します。

まずは、不動産に対する目的と要件を明確にしましょう。住宅を購入するのか、賃貸物件を探すのか、不動産投資を検討しているのか、土地を買って家を建てたいのかなど、どのような目的があるのかを再確認しましょう。必要な部屋の数、設備、立地条件、予算などの要件をリストアップしておくことも重要です。
それでは、準備する内容を深く見ていきましょう。
購入予定の物件や賃貸料金を決めるために、ご自身の予算を明確にしておきましょう。いくらが許容できる範囲か明確に線を引き、またいくらであれば検討外なのか、考えをしっかり持っているかいないかで、不動産探しに影響が出ます。
予算の設定がないと、営業マンの都合で話が進み、取引後に後悔しても手遅れになることもあります(REDSではそういうことはありませんが)。だからこそ、予算は明確にしておくことをお勧めします。明確なほど、不動産会社は情報を素早く、適切に提供してくれます。
不動産会社に訪れる前に、希望する地域や立地条件を考慮しましょう。学校、仕事場、交通手段など、重要な施設が近くにあるかに加えて、不動産市場の状況を把握するために、インターネットや不動産ポータルサイト、地元の新聞や雑誌から情報を収集し、相場や特定の物件について価格を調査しておきます。これにより、不動産会社はサポートしやすくなりますし、売主様との交渉にも自信を持つことができます。
みなさんもイメージをお持ちのように、不動産会社にはよいところもあれば悪いところもあります。口コミやオンラインの評判を参考に、不動産会社の信頼性、経験、評判を確認し、信頼できるパートナーを選びましょう。気をつけたいのが、ネットに書いてあることは全てではないということ。また、知人や友人から紹介された会社はなにより大切にすべきです。
準備した内容を踏まえ、物件に関する情報、価格交渉、契約条件、手数料など、不明確な点を解明するための質問を用意しておきます。これにより、不動産会社との対話が効果的に進行します。
聞き漏れを防ぎ、取引後の後悔を少しでもなくすために、細かくメモとり、質問表などを用意しておくようにしましょう。
価格交渉や契約条件の交渉が不可欠な場合、事前に交渉戦略を検討しましょう。予算や要件に合う物件を見つけた場合、どのように交渉するかを考え、自分の立場を強化するための戦略を練ります。
適正価格かどうかの見極めは大変難しいですが、見積もりの表記について事細かく質問をすることで、本当に必要なのか、営業マンの反応でわかる場合があります。また相見積もりを取ればよくわかることがありますので、必ず取りましょう。
不動産会社を訪問する前には十分な準備が不可欠です。自分の目的、予算、要件を明確にし、信頼性のある不動産会社を選び、質問事項や書類を用意することで、効果的な不動産取引を進めることができます。
皆様の不動産取引を少しでも後悔のない、納得がいくものにしていただければ幸いです。最後まで読んでいただきありがとうございます。
最終更新日:2023年9月7日
公開日:2023年9月5日
REDSエージェント、宅建士の畑中です。住宅用の土地を購入する際は、慎重な計画と注意が必要です。
土地の購入は一生に一度の大きな買い物であり、将来の家庭生活や資産価値に大きな影響を与える重要な要素です。失敗しないためにも、土地購入の際には以下の重要なポイントをしっかりと理解しておきましょう。

まず、自身の経済状況を正確に把握し、土地購入に充てることのできる予算を決めます。
土地の購入価格だけでなく、登記費用、仲介手数料、固定資産税、住宅ローン手数料などの諸経費も考慮して、全体の費用を把握しましょう。無理のない範囲内で土地を購入できるように資金計画を立てましょう。
購入しようとしている土地の治安状況や近隣の学校、医療施設、商業施設などが住みやすいかどうかを確認します。家族が快適に生活できる環境かどうかを考慮しましょう。
また、通勤や通学の交通アクセスも重要な要素です。駅やバス停、高速道路などへのアクセスが便利であるかどうかをチェックし、移動がスムーズにできるかを確認しましょう。
地盤が強固で地震や洪水などの自然災害に耐えられるかを調べましょう。地盤が安定していることは建物の安全性に直結しますので、地盤調査の結果を確認することは非常に重要です。地震リスクが低い土地を選ぶことで、万が一起きたときの被害を最小限に抑えることができます。
地域の都市計画や建築基準法によって、建物の高さや容積率、用途などに制約がある場合があります。建物を建てる際にトラブルを避けるためにも、規制に違反しないよう注意しましょう。
地域の不動産市場を把握することで、購入しようとしている土地の適正な価格が分かります。同じ条件の土地の取引価格や相場情報を比較検討しましょう。相場を知ることで、無理な値引き交渉を避け、土地購入を円滑に進めることができます。
土地に関する権利が明確でない場合、将来的なトラブルの原因となる可能性があります。特に、土地の所有権の移転手続きや登記に関しては、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
購入しようとしている土地を実際に訪れ、周辺環境を見ることで、騒音や景観、近隣の建物などを判断することができます。写真や動画だけではわからない細部のチェックや実際の雰囲気を確認することで、土地の印象が変わることもあります。そのため、現地調査は土地購入の重要なステップとなります。
土地購入は一般の人にとってはなかなか経験が少ない大きな取引ですので、土地購入に関するアドバイスを受けることが重要です。専門家の意見を参考にすれば、よりよい判断ができるでしょう。特に、契約書や書類のチェック、土地の評価など専門的な知識が必要な場面では、不動産会社の担当者のほかに、不動産の専門家のサポートを得ることが安心です。
不動産取引にはさまざまなトラブルが潜んでいるため、事前のリサーチが重要です。問題のある土地を購入してしまうと、後々解決が難しいことになります。過去の失敗例を学び、同じ過ちを繰り返さないようにすることが賢明です。

以上のポイントを踏まえて、土地購入を検討しましょう。家を建てるための土地選びは大きな決断であり、慎重な計画と専門家のサポートを得ながら進めることが成功へのカギとなります。将来の家庭生活を豊かにするためにも、理想的な住宅用地を見つけることを心掛けましょう。
土地を購入する決断は大きな一歩ですが、それは素晴らしい未来を築くための重要なステップです。夢の家や理想の生活の実現に向けて、勇気を持ち前進しましょう。自分の将来を自分で描き、その土地に込める想いを大切にしてください。
困難や不安もあるかもしれませんが、その先には成長と充実が待っています。チャンスをつかみ、自分の価値を信じて進んでください。土地を購入することで、新たな一歩を踏み出し、素晴らしい未来を手に入れることができるのです。自分を信じ、背中を押す勇気を持ち、未来への扉を開きましょう!
公開日:2023年7月31日
REDSエージェント、宅建士の畑中です。
中古の戸建て住宅購入を検討されている方にとって「この家を買う」と決めることは、人生にとって非常に大きく重要な決断となります。以下に、注意事項や気をつけるべきポイント10箇条を分かりやすくまとめました。ぜひこれらの情報を参考に、ご自身にとって最適な住宅を見つけてください。

最初に、予算を明確に設定しましょう。住宅ローンの返済や維持費など、将来にわたって必要となる負担も考慮に入れて慎重に計画しなければなりません。
気をつけなければいけないことは「借入できる金額≠返済できる金額」です。月々の返済額が家計に負担をかけすぎないように、収入や将来の変動要素(転職や家族の増減など)を考慮しましょう。また、住宅購入に伴う初期費用(登記費用や仲介手数料)や維持費(修繕や税金)も予算に含めることを忘れないでください。
返済を継続できる範囲で計画することが何より大切です。
理想的な住宅の条件を具体的に決めておきましょう。必要な部屋の数や広さ、立地条件、駐車場の有無など、自分の生活スタイルに合わせて考えましょう。
条件を具体的に設定することで、自分に合った物件を見つけやすくなります。必要な部屋の数や間取り、広さ、収納スペースの充実度、駐車場の有無、庭やバルコニーの希望など、自分のライフスタイルや将来の計画に合った条件を明確にしましょう。
中古住宅は建物の老朽化や劣化箇所をチェックし、修繕やリフォームの必要性を見極める必要があります。内部の設備や配管の老朽化、外部の劣化や傷み、防水性能、断熱性能など状態を詳しく確認する必要がありますが、個人で難しい場合は専門業者に建物の検査を依頼することも検討しましょう。
中古住宅の構造や耐震性も重要なポイントです。木造なのか鉄骨なのか、基礎や柱の強度、地震に対する耐震性能などを確認しましょう。特に地震が多い地域に住む場合は、耐震性が高い建物を選ぶことが重要です。
住宅の周辺環境も重要な要素です。近隣の施設や公共交通機関のアクセス、商業施設や学校の有無などを確認し、生活の利便性を考慮しましょう。
住宅の周辺環境も生活の利便性に影響します。近隣には学校や医療機関、公園やレジャースポットなど、必要な施設が適切な距離にあるか確認しましょう。さらに公共交通機関のアクセスや道路状況も考慮し、通勤や外出の利便性をチェックしましょう。
前の所有者からの建物や設備トラブルの有無を確認しましょう。法的な問題や建物の瑕疵(かし)がないか、不動産会社にも確認してトラブルを未然に防ぎましょう。建物の法的問題や隠れた瑕疵などがある場合、後に大きな問題となる可能性があります。
購入前の建物のチェックや価格交渉、将来のリフォーム計画に関することは、不動産の専門家や建築士に相談することをおすすめします。プロは市場動向や物件の評価方法に精通しており、役立つアドバイスを提供してくれます。
購入したい物件が見つかったら、物件の評価や査定結果を確認しましょう。複数の不動産業者や鑑定士に査定を依頼し、相場価格を把握しておくことで、交渉がしやすくなります。
自身で市場の相場価格を調査することもできます。不動産ポータルサイトや不動産広告、地域の不動産取引情報などを参考にしましょう。売出価格が妥当なものかどうかを判断することができます。
住宅購入は将来にわたる長期的なプロジェクトとなります。将来のライフスタイルや家族構成の変化を考慮し、購入する住宅が長く快適に暮らせるかを見極めましょう。子供が増える予定や、介護の必要がある場合など、自分の将来の見通しを持ちながら物件を選びましょう。
購入した中古住宅は将来、なんらかの理由で手放す可能性もあります。将来的な需要や地域の発展性などを考慮し、価値を見極めることも重要です。需要が高まる見込みのある地域や、交通インフラの整備が進んでいる地域などを選ぶことで、売却時により高い価値を期待できるかもしれません。
これらの注意事項とポイントを踏まえながら、中古戸建て住宅を検討していただくといいでしょう。専門家や周囲の人々からのアドバイスを積極的に受け入れ、納得のいく住まいを、そして自分にとって理想的な住まいを見つけることをお祈りします。