大西 進(宅建士・リフォームスタイリスト)
キャリアを生かした質の高い仕事をさせていただきます。
CLOSE
公開日:2024年4月16日
こんにちは、REDSエージェント、宅建士の大西進(おおにし すすむ)です。私のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は、「令和6年能登半島地震」に学ぶ建物に関する注意点について解説します。

2024年1月1日16時10分に発生した能登半島を震源とした地震から4カ月が過ぎました。石川県によると、死者は輪島市106人、珠洲市103人、穴水町20人、能登町8人、七尾市5人、志賀町2人、羽咋市1人の計245人で、うち災害関連死は15人。住宅被害は7万6125棟にのぼります。
一方、台湾の東部沖で4月3日に起きた地震では、これまでに13人の死亡が確認され、6人と連絡が取れなくなっています。お亡くなりになった皆さまのご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方やそのご家族の方にお悔やみを申し上げます。
過去の経験から、地震による被害の多くは、建物の倒壊そのものや倒壊した建物によるものです。今回の地震では、住宅用建物の3分の2が倒壊し、その多くは老朽化した木造の建物でした。
この地震から、以下の2つの点に注意すべきことがわかりました。
伝統的な木造建築や土壁、瓦屋根は、鉄筋コンクリート造りなどに比べて倒壊しやすい傾向があります。
商業や工業用建物の多くは鉄骨造りで高い耐震性を持っているため、被害は比較的少なかったといえます。一方、住宅用建物の多くは木造で、耐震性が低いため、多くが倒壊するという結果となりました。石川県の住宅の3分の1は、1981(昭和56)年以前に建てられた建築物で老朽化したものが多く、これが被害拡大の一因となりました。
日本経済新聞の調査によると、能登半島北部では、1970(昭和45)年以前に建てられた木造建築の割合が、全国平均の7%に対し、珠洲市で40.6%、輪島市で34.6%、能登町で32%と、非常に高いことがわかりました。
地震によって、地盤の孔隙水圧(こうげきすいあつ:土や岩石に含まれている隙間にある流体の圧力)が上昇し、土が液体状になる現象を地盤液化といいます。
地震発生時に、SNSなどで地面が隆起したり、道路が割れたり、水が噴き出したりする映像が拡散されたのをご覧になった方もいるでしょう。これは地盤液化によって、地面が沈下したり、地盤が弱くなったりしたために起こったと考えられています。
東日本大震災では、震源から遠く離れた東京都内や千葉県内でも、地盤液化が発生し、多くの建物が倒壊しました。能登半島地震では新潟県内でも地盤液化が発生し、900棟以上の建物が倒壊しました。
NHKが1月9日に地震による地盤液化のリスクを予測する調査を行いました。首都直下地震で液状化リスクが起こりやすいのは以下の場所だということです。
東京都建設局の「東京都の液状化予測図」ウェブサイトも参考にすることができます。土壌液化リスクが高い地域がすべて危険な場所であるとは限りません。
専門家によりますと「リスクの高い場合、100パーセントの安全性は達成できませんが、より強固な鉄柱を深く地面に打ち込んだり耐震技術を利用したりなどの対策を講じることで、倒壊後も修復が容易になり、被害の深刻さを軽減することができます」と指摘しています。
軟弱な地盤だからといって、建物を建てることができないわけではありません。土壌の特性や地質状況を考慮して、より強固な改良工事が行われているかどうかにかかっています。
地震による建物の倒壊は、防災において重要なリスクです。建物の建造や購入に際しては、建築構造や築年数に注意することをおすすめします。鉄筋コンクリート造りなどの耐震性に優れた構造の建物を選ぶことで、地震による被害を軽減することができます。
また、土壌液化リスクが高い地域で建物を取得した場合でも、過度に心配する必要はありません。不動産仲介業者や建て主に、建物の耐震性や地震保険の加入などを確認しておくことで、万が一の際には保険金の支払いを受けることができ、被害を最小限に抑えることができます。
もちろん、何よりも大切なのは「命を守ること」です。地震はいつ、どこで、どんな時に起こるかわかりません。いざというときの一瞬の行動が生死に関わります。あらかじめ、家や外出時、職場などシーン別での避難方法を知っておくことで緊急時でも心に余裕をもって避難できます。このページをご覧いただき、ご自身がどれだけ避難場所や避難方法を理解しているか確認していただけましたら幸いです。
参考:地震発生時の行動から生活再建までのポイント|東京都防災ホームページ
公開日:2024年3月9日
こんにちは、REDSエージェント、宅建士の大西進(おおにし すすむ)です。私のブログをご覧いただきありがとうございます。
このブログをご覧いただいた方で「原野商法」とは何かご存知の方はいらっしゃいますか? 値上がりの見込みがほとんどないような山林や原野を、「将来、開発計画があるので高く転売できる」「リゾート・別荘地の誘致が進んでいるので価値が上がる」などと騙して売りつける悪徳商法のことです。1960年代から1980年代が全盛期であり、新聞の折り込み広告や雑誌の広告などを使った勧誘が盛んに行われていました。
結局は、道路の整備がされることがなければ、電気・上下水道の生活インフラも整備されることもなく、そして建築を目的で購入したにもかかわらず建築許可も取得できず、タダでも売れないような土地だけが残り、お荷物財産になっています。そのような処分に困っているような購入者を、もう一度ターゲットとした「原野商法」の二次被害トラブルの話題は、ドラマ『正直不動産』でもしっかり描かれていました。
今回はこの「原野商法」について徹底解説します。

近年、この「原野商法」によって取得した土地をめぐる二次被害トラブルの相談件数が急増、被害額が高額化しています。特に「売却勧誘下取り型」という巧妙で複雑な手口が目立っています。
この手口では、まず不動産業者を名乗り、電話や訪問して「あなたの土地を高く買い取ります」などといった電話勧誘が行われます(売却勧誘)。その後、業者は契約内容の詳細を説明せずに「節税対策」などといった名目でお金を請求してきます。しかし、この説明は適切ではなく、実際は土地の売却と同時により高い金額で新たに別の土地をさせる手法です(下取り)。
また、原野商法で買ってしまった土地を子供が相続してしまったら、子供に負担を押しつけてしまうことになると考える人も多いでしょう。「自分が元気なうちに清算したい」との気持ちにつけこんで、業者は勧誘を行っていることも考えられます。
最近、どのような原野商法トラブルが起きているのか、実際の例をご紹介します。
宅地建物取引業の免許を持つ見知らぬ業者から電話があり、相続した雑木林の売却話を持ちかけられた。この雑木林は両親が昔400万円で購入した土地。最初は断っていたが、「オリンピックまでにその土地一帯に複合レジャー施設を造る予定」「約5,000万円で買い取る」と何度も電話で勧誘され、根負けし喫茶店で話を聞いた。
その際、「他の土地を購入すれば節税になる」「購入費用は税金対策処理後に返す」などと勧められた。よく分からなかったが、買い手のつかない雑木林が売れるならなどと思い、約400万円を支払って契約書にサインした。その後、期日になってもお金は支払われず、業者は電話に出ない。改めて売買契約書を確認したところ、雑木林を約1,200万円で売り、原野を約1,600万円で購入する契約になっていた。(60歳代・女性)
40年前に30坪と100坪の山林を購入し所有している。先日、「30坪の方の土地を欲しがっている人がいる」と不動産業者から電話があり、了解した。その後、不動産業者から、売るに当たり調査や整地が必要と言われ、請求されるままに合計190万円を支払った。
30坪の土地の売却代金が入ると思っていたが、今度は「同じ人が100坪の土地も欲しがっているので調査費を80万円払ってほしい」と言われた。「先に30坪の土地を売ってからにしたい」と伝えたが、「まとめて売れば3カ月以内にお金が入る」と言われた。子供に相談したところ、原野商法の二次被害に手口が似ていると言う。(60歳代・男性)
覚えのない管理業者から、約25年前に購入した別荘地について「管理費を滞納しているので支払え」との通知が届いた。その後、その管理業者から電話があり、「購入した別荘地の管理を担当している。管理費用が20年前から滞納となっている」として、管理費約70万円と滞納金約50万円の合計約120万円を請求された。しかし、購入当初の管理サービスについてはすでに解約しているし、業者名も違う。あやしいので支払いたくない。(50歳代・男性)
(参考:国民生活センター「より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル-原野や山林などの買い取り話には耳を貸さない!契約しない!-」)
「原野商法の二次被害」トラブルでは、契約後は業者と連絡がつかなくなることがほとんどであり、一度お金を支払ってしまうと、取り戻すことは非常に困難です。以前購入した原野の買い取り話を不用意に聞いてしまうと、さらなるトラブルに遭ってしまう恐れがありますので、「土地を買い取る」といった勧誘には、耳を貸さずきっぱりと断りましょう。
そもそも、購入した「原野」はこれまで値上がりもせず、開発することもできなかった土地です。「値上がりする」「買いたい人がいる」といったうまい話ほど、まずは疑ってかかりましょう。業者の説明に少しでも不審な点があったり、不安を感じることがあったりした場合は、決してすぐにお金を支払わず、お近くの消費生活センターなどに相談しましょう。
昔買ってしまった原野を処分したいと思っても、その場で話を聞いたり判断したりせず、家族など周囲の人に相談することが大事です。
また、70歳代、80歳代と特に高齢者が被害に遭いやすくなっています。ご本人が用心するだけでなく、ご家族や地域の方々が高齢者の方を見守ることが重要です。口数が減る、買い物をあまりしなくなる、借金を申し込んでくるなど、高齢者の生活に変化がないか気を配りましょう。不審な勧誘を受けている、お金を支払ってしまったなど、困っているときは、消費生活センターなどへ相談するよう勧めましょう。
不動産業者を名乗り、電話や訪問で「あなたの土地を高く買い取ります」といった勧誘には警戒しましょう。契約書をよく読み、売却する土地と購入する土地の差額分を支払う契約になっていないか確認しましょう。疑問や不安があれば、専門家に相談することをお勧めします。
公開日:2024年1月18日
こんにちは、REDSエージェント、宅建士の大西 進(おおにし すすむ)です。私のブログをご覧いただきありがとうございます。
中古住宅のご購入を検討していらっしゃるお客様は「リフォーム済物件」や「新規リノベーション物件」といった表記の物件を目にすることがあると思います。私も、中古戸建・中古マンションの売買業務をたくさん行ってまいりました。
同マンション内の同じ間取りのお部屋でも、「手の入れ方によってこんなに違うのか」と思うこともが多々あります。「自分だったらどちらのお部屋を購入しようかな」等々考えながら内見することもあります。そこで、今回は「リノベーション物件とリフォーム物件との違い」「リノベーション物件のメリット・デメリット」「リノベーションを前提に家を探すときのポイント」について解説いたします。

近年人気が高まっているリノベーション物件とは、一体どのような物件なのでしょうか。リフォーム物件との違いやメリットと併せて解説します。
リノベーション物件とは、中古住宅に手を加えて資産価値(付加価値)を高めた物件のことです。たとえば、現代のライフスタイルに合わせた間取りの物件、最新の設備が整った使い勝手のよい物件、スタイリッシュでデザイン性の高い物件などがあります。
リノベーション物件は、先述したように大規模な改修などで住宅を新築時よりもレベルアップさせた住宅です。それに対して、リフォーム物件は壊れた個所を修繕したり古くなった設備を取り換えたりして、新築と同じレベルに回復させた住宅を指します。
リノベーションを行うと、どんなメリットがあるのでしょうか。以下で主な5つを紹介します。
統計的に、エリアや間取りなどの条件が同じであれば、新築の物件よりも内装や設備が新築同様のリノベーション物件のほうが、価格や費用が安く抑えられる傾向にあります。費用だけでなく、周辺環境やアクセスを気にする方にも、選択肢が広がるのでおすすめです。
一般向けに売り出されている分譲住宅や分譲マンションは、無難な間取りやデザインになる傾向があります。しかし、リノベーションを行えば、家族構成に合わせた部屋の配置や人の目を引くデザインなど思いのままに決められます。
新しい家に生まれ変わらせるのがリノベーションの役割ですが、あえて元の家の特徴を残すことも可能です。たとえば、古民家なら全体の趣を残しつつ最新の設備を導入することで、古いものの味わいと新しいものの便利さを兼ね備えた住まいが形にできるでしょう。
建物自体の築年数が古くても、リノベーションによって資産価値を上げることができます。一般的に住宅は、年数がたつと資産としての価値も減少していきますが、古くなった設備を最新式に交換したり外観や内装をきれいにしたりすることで、古い物件にも新しい価値が生まれるのです。
自分好みにリノベーションするのもよいですが、すでにリノベーション済みとして販売されている物件が近年増加しています。趣向を凝らしていたりこれまでにはない個性的なデザインだったり、物件によっては購入費用だけで手に入れることが可能です。また、リノベーション済みなので、すぐに入居できる点もメリットと言えるでしょう。
リノベーション済み物件もメリットばかりではありません。ただ、デメリットを知っておけば、あらかじめ対応策を考えることもできます。リノベーション済みの物件は、一見きれいに見えますが、見えにくいところにキズや汚れがあるので気を付けましょう。
一言にリノベーションといっても工事内容はさまざまです。目に見える表面的な部分はきれいでも、床下の状態や排水管に不備が見つかることもあります。どの範囲までリノベーションしたのか、元のオーナーや不動産会社にしっかり確認しておくことが大切です。
現在の耐震基準(新耐震基準)は、1981年6月1日に施行されたものです。それ以前に建てられた物件には適用されていません。たとえリノベーションされていても、古い物件では現在の耐震基準を満たしていない可能性があります。築年数を確認して、1981年5月以前に建てられていた場合、耐震補強がされているかを確認するようにしましょう。
中古住宅には天井や外壁に使用されている断熱材が薄く、断熱性能の低い窓やサッシが使用されている物件もあります。断熱性が不十分であれば、実際に住んでみたら予想以上に寒かったということになりかねません。
時代の変化とともに住みやすい家の間取りは変わっていきます。リノベーション済みであっても、建物の構造上、間取りを変えられなかった物件では、間取りが古く使いにくいと感じるかもしれません。
マンションなどの集合住宅では、建物全体で使える電気の容量が決まっているため、各戸の電気契約に上限があります。リノベーション工事だけでは解決できない問題なので、事前に確認しておきましょう。
中古物件を購入する際は、以下の3点に注意しましょう。
中古物件では、老朽化による床下の水漏れや腐敗など、見えない部分を補修する費用についても考慮しておかなければなりません。再利用するはずだったドアや柵が使えなくなったり、電気や下水道の整備費用を想定していなかったりと、当初の予算だけではまかなえなくなるケースが多いので、プランニングの際には十分検討してください。
リノベーションの工事期間は工事の内容によりますが、1~3か月ほどが多い傾向です。物件探しやローン審査などを含めるとさらに数か月が必要で、天災などで工事が遅れるケースもあります。入居希望日から逆算して、余裕をもったスケジュールを組みましょう。
リノベーションができるのは占有部分のみで、共用廊下など共用部分には手を加えることはできません。また、床材変更禁止などマンションごとの管理規約によって制約を受けるケースもあります。
都市計画法・建築基準法によって、容積率・建ぺい率に上限があり、増築などができないケースに注意しましょう。
リノベーションをする前提で物件を探す場合、以下の2点を確認しましょう。
物件の購入では、物件本体の取得費用のほかに、不動産取得税や火災・地震保険料など10種類を超える諸費用がかかります。リノベーションでは、工事費以外に設計料や現場管理費などの費用も必要です。総額が大きな金額になるので、見積もりの段階でしっかり確認しておいてください。
リノベーション工事後に契約した内容と異なる施工箇所が見つかった場合、民法で定められた「契約不適合責任」により、売主が責任を負わなくてはなりません。契約不適合責任の期間は、原則として購入者が契約不適合を知ってから1年以内です。加えて、リノベーションを行なった業者による独自の保証もあります。保証内容と期間は個別に定められているため、契約前に保証制度について確認しておきましょう。
以上のような注意点を確認しながら、お客様にとって良い住宅をご購入できるようお手伝いさせていただきます。
ご購入・ご売却の際には、不明点がございましたら、株式会社不動産流通システム、REDSエージェント 大西 進(おおにし すすむ)まで、何なりとご質問ご相談くださいませ。
MOBILE:080-3316-8123
E-MAIL:su.ohnishi@red-sys.jp
公開日:2023年12月24日
こんにちは、REDSエージェント、宅建士の大西 進(おおにし すすむ)です。私のブログをご覧いただきありがとうございます。
マイホームを購入されるお客様には、住宅ローンとセットで加入する保険「団体信用生命保険」についてお話をさせていただいています。すると、今月はこれまで以上に「団体信用生命保険」の商品内容を重要視して借入金融機関を選ばれるお客様が増えた印象です。
確かに、各金融機関は住宅ローン金利にセットされる「団体信用生命保険」の商品にとても力を入れており、低金利+団体信用生命保険商品で「掛け金のお得感」を打ち出しています。そこで、住宅ローンを利用して保険に加入する中、今現在加入している「生命保険」と保険が重複してしまうのではお考えになられる方も多いようです。
今回のブログは「団体信用生命保険に加入したとき、生命保険の見直しが必要か?」についてご説明します。最後までご一読下さいませ。

団体信用生命保険とは、マイホームを購入する際、住宅ローンとセットで加入する保険です。省略して「団信(だんしん)」とも呼ばれています。契約者が死亡したり、高度障害状態になったりした場合に、住宅ローンの残債が団体信用生命保険から保険金として支払われるため、その後の住宅ローンの返済が免除されます。
民間金融機関の住宅ローンでは、ほとんどの場合、団体信用生命保険への加入が義務付けられていますが、「フラット35(※1)」は団体信用生命保険への加入は任意となっています。
※1 民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供している住宅ローン
「団体信用生命保険」は、その名のとおり、万が一に備える「生命保険」の一種です。団体信用生命保険は住宅ローン返済の保障に特化している保険ですが、契約者に万が一のことが起こってしまった場合に、ご遺族、ご家族が生活に困らないように保障を準備するという目的は同じです。
マイホームを購入して住宅ローンを組むと、毎月の返済によって家計収支に変化が生じるため、すでに加入している生命保険があれば見直しを検討されることをおすすめします。下記に理由を説明します。
住宅ローン契約時に団体信用生命保険に加入すると、すでに加入している生命保険の保障内容と重複することがあります。団体信用生命保険に加入すれば、万が一の場合、住宅ローンの支払い義務はなくなりますので、ご遺族やご家族は住宅ローンを返済することなく、その後も同じ家に住み続けることができます。
すでに加入している生命保険で、将来の住宅費用のための保障額などを多めに見積もっている場合、団体信用生命保険で保障される部分は重複する場合もありますので、減額できる可能性があります。
マイホームを購入すると、家賃の支払いの代わりに、住宅ローンの返済が始まるなど、住宅にかかる費用の内容が変わるのはもちろんですが、購入物件の地域や生活スタイルが変わって家計の支出が増減する可能性があります。
生命保険は定期的に見直すことが大事ですが、特に大きなライフイベントの1つである住宅購入の際は、生命保険の見直しは欠かせません。マイホーム購入のタイミングで生命保険を見直すことで、ライフプランに合った保障に近づけることができ、保障の重複を解消することで保険料負担を軽減し、家計支出を減らせる可能性もあります。
死亡保険を見直す際にはいくつかポイントがあります。具体的な見直し方法も解説します。
まずは、現在加入している死亡保険の種類と保険金額を確認してみましょう。死亡保険は、一生涯にわたって保障が継続する終身保険と、契約した一定期間のみの保障を目的とした定期保険に分かれます。
終身保険は、貯蓄性がある保険で、一般的に、葬儀費用やお墓代を準備する目的で加入することが多いので、住宅ローン返済の保障に特化した保険である団体信用生命保険と保障が重複する可能性は低いと思われます。
定期保険は、必要な期間のみの保障を準備するのに適した保険で、お手頃な保険料で大きな保障を備えることができます。基本的に掛け捨て型で貯蓄性はありませんので、ライフプランの変化に合わせて、見直しをしやすいという特徴があります。保障に重複している部分がないかチェックしてみましょう。
住宅購入することで発生してくるお金についても考えておく必要があります。例えば、マンションを保有する場合には、住宅ローンの支払いのほかに管理費や修繕積立金などが必要です。戸建てを保有する場合には、維持・メンテナンス費やリフォーム費用などが必要になります。このほか、固定資産税・都市計画税など賃貸住宅に住んでいた時にはかからなかった税金の支払いも発生します。
さらに、住まいに見合った内容の火災保険や地震保険への加入が必要となるので、賃貸住宅の時よりも火災保険料の負担が大きくなる場合があります。
生命保険の保障に重複している部分があれば、すでに加入している保険の解約や見直しを検討しましょう。
例えば、住宅購入前に賃貸住宅に住んでいた人が、将来にわたって賃貸住宅に住み続けることを前提として必要保障額を算出していた場合、住宅購入時に団体信用生命保険に加入することで、将来の家賃支払いのために備えていた保障部分は重複となり減額できる可能性があります。
ただし、いくつか注意点もあります。死亡保険に医療特約などを付加している場合、主契約である死亡保険を解約すると、特約も消滅してしまいます。また、今契約している保険をいったん解約し、必要な分だけ別の保険に加入をするという選択肢もありますが、団体信用生命保険を含め、保険に新規加入する際は、健康状態についての告知が必要になります。健康状態によっては加入できない可能性もあるので、解約や見直しは慎重に行うべきでしょう。
また、住宅ローンを組む際に検討したいのが「就業不能保険」です。「就業不能保険」とは、病気やケガで働けない状態になった場合に、毎月給付金を受け取ることができる保険です。通常の団体信用生命保険の場合、死亡に対する保障はありますが、働けなくなったときの保障はありません。住宅ローンの返済プランに合った「就業不能保険」に加入することで、病気やケガによって働けなくなったり、収入が減少したりしてもカバーすることが可能です。
団体信用生命保険には、医療保障などの特約が付加された「特約付き団体信用生命保険」というものもあります。現在加入中の保険を解約、または見直しを行い「特約付き団体信用生命保険」を活用することで、死亡保障や高度障害保障に加え、ガンや病気などのリスクに備えることも可能です。
「特約付き団体信用生命保険」には、3大疾病特約付き団体信用生命保険(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中)のほか、7大疾病特約付き、8大疾病特約付きや、生活習慣病について保障する団体信用生命保険などもあります(※2)。
これらは、死亡や高度障害などの通常の団信の保障に加え、所定の疾病が原因で一定の要件に該当した場合に、住宅ローンの返済が免除(全額または一部)されたりする特約です。住宅購入後、病気になって就労ができず収入が減る可能性を考えると、「疾病特約付き団体信用生命保険」は心強い保険ともいえます。
このほかにも、がんと診断された場合のがん診断給付金や、入院や先進医療に対して給付金がでる特約もあります。特約保険料は、無料のものや、住宅ローン金利に上乗せされるもの、別途保険料を支払うタイプなど、商品によって様々ですので、ご自身に合うタイプを選択するようにしましょう。
※2 疾病特約の具体的な要件は、金融機関や保険商品によって異なります。
住宅ローンの代表的なものとして「フラット35」があります。民間金融機関と住宅支援機構が提携して販売しているローンで、返済期間が最長35年間で全期間固定金利という特徴があります。民間金融機関の住宅ローンは団体信用生命保険を付加することが前提になっていますが、「フラット35」は機構団信(※3)をつけない選択ができます。
平成29(2017)年10月より、「フラット35」の仕組みが変わり「団信付きのローン」という形態になっていますが、金利マイナス0.2%で機構団信を付加せずに利用することができるので、実質的には任意加入といえます。
※3 フラット35の付加する団体信用生命保険は「機構団信」と呼びます。
フラット35を利用しマイホームを購入する際、機構団信に加入せず生命保険で備える方法もあります。機構団信の保険料は年齢に関係なく一定ですが、一般的に生命保険は年齢が若いほど保険料がお手頃になりますので、若年層の場合は生命保険で備えるほうが保険料は低くなる可能性があります。
お手頃な保険料で一定期間大きな保障を得ることができる保険です。住宅ローンの返済プランに合わせて見直しをしやすい、更新型の定期保険がお勧めです。
「収入保障保険」とは、被保険者の死亡後、遺族が毎月の給与のように保険金を受け取ることができる保険です。毎月の住宅ローン返済額と同額程度を受け取ることができる「収入保障保険」に加入することで、万が一のことが起こってしまった後、保険金をローン返済に充当することができます。
機構団信の保険料は借入金額や借入時の金利、生命保険の保険料は契約時の年齢や健康状態などによって異なりますので、機構団信か生命保険のいずれを選ぶかは、しっかりシミュレーションして決めるようにしましょう。
団体信用生命保険の仕組みと生命保険との関係について解説しました。生命保険と保障内容が重複する可能性も考えて、住宅購入時にはご自身に合った保険を検討されるといいのではないでしょうか。生命保険の見直しには、お近くの保険相談窓口などを上手に利用してみてください。
ご購入・ご売却の際には、不明点がございましたら、株式会社不動産流通システム、REDSエージェント 大西 進(おおにし すすむ)まで、何なりとご質問ご相談くださいませ。
公開日:2023年11月11日
こんにちは、REDS不動産流通システムエージェント、宅建士の大西(おおにし)進(すすむ)です。私のブログをご覧いただきありがとうございます。少し時間がたちましたが、2020年4月1日に施行された改正民法によりこれまでの不動産の「瑕疵担保責任」という言葉は、契約不適合責任に置き換えられました。しかしながら、不動産取引をしている中で、売買仲介の相手方「業者」には「見えないキズに対して、売主側が責を負う保証」という意味で「瑕疵担保」というの言葉を当たり前のように話す「残念な業者」が多くみられます。
もしかすると、物件のご案内中やご購入を申し込む際に誤った説明を行い、その後お客様は重要事項説明を聞き、売買契約書に「瑕疵担保責任=契約不適合責任」と勘違いしたまま、署名押印をしているお客様もいらっしゃるのでは、とすら思います。
今回はこれまでの「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に置き換えられて何がどう変わったのかについて解説します。
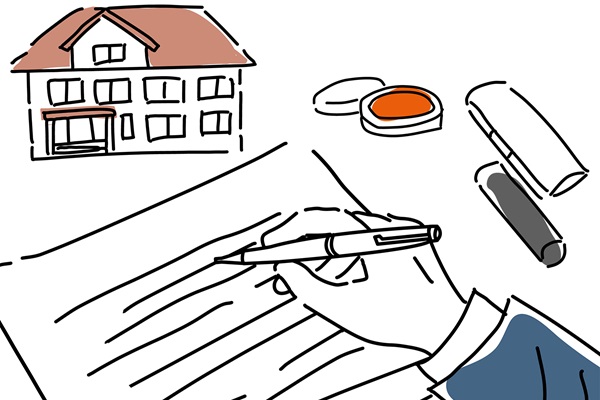
瑕疵担保責任と契約不適合責任についてそれぞれ解説します。
■瑕疵担保責任
売買や請負などの契約に基づき引き渡された目的物に欠陥があった場合に、売主や施工業者が負う法的責任でした。欠陥が「隠れた」ものであること、すなわち契約締結時点において、買主や施主が欠陥の存在について善意無過失であったことを要求していました。
■契約不適合責任
目的物の種類・品質・数量が契約の内容と適合していない場合に、売主や施工業者が負う法的責任です。欠陥が隠れていても、隠れていなくても「契約内容に適合しているかどうか」という点が重要になります。
具体的に瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いは、以下のような点が挙げられます。
・契約不適合責任では、契約責任説を明示的に採用し、目的物が特定物・不特定物のいずれである場合にも適用されます。瑕疵担保責任では、法定責任説が一応の通説とされ、目的物が特定物である場合にのみ適用されていました。
・契約不適合責任では、買主や施主が利用できる救済手段が増えました。瑕疵担保責任では、損害賠償請求と契約の解除のみが可能でしたが、契約不適合責任ではこれに加えて履行の追完請求と代金減額請求が認められています。
・契約不適合責任では、「隠れた瑕疵」の要件が撤廃されました。契約不適合責任が発生するかどうかは、専ら目的物が契約内容に適合しているかどうかによって判断されますので、買主や施主の善意無過失は要件となりません。
では、契約不適合責任と瑕疵担保責任のどちらが有利なのか、という問いについては一概に答えることはできません。売主と買主の立場や契約の内容によって、有利不利は異なるからです。しかし、一般的に、以下のような点が考えられます。
・契約不適合責任では、買主が行使できる権利が増えました。瑕疵担保責任では、損害賠償請求と契約の解除のみが可能でしたが、契約不適合責任では、これに加えて履行の追完請求と代金減額請求が認められています。これは、買主にとっては有利な変更といえます。
・契約不適合責任では、損害賠償の範囲が広くなりました。瑕疵担保責任では、損害賠償の範囲は信頼利益に限られていましたが、契約不適合責任では、履行利益も含まれます。これも、買主にとっては有利な変更といえます。
・契約不適合責任では、責任追及できる期間が延長されました。瑕疵担保責任では、瑕疵があることを知った時から1年以内に損害賠償や解除をしなければなりませんでしたが、契約不適合責任では、不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知すれば責任を追及できます。これも、買主にとっては有利な変更といえます。
以上のように、契約不適合責任は、瑕疵担保責任に比べて、買主の「救済手段を強化する」内容となっているといっていいでしょう。したがって、売主は契約不適合責任を免除する特約を結ぶことでリスクを回避しようとするかもしれませんが、その場合は無効になる可能性があります。
また、売主もしくは買主のいずれかが宅建業者なのかによっても異なりますので、売主も買主も、契約内容とその条項や約款の意味をよく理解しておく必要があります。
当社では、ご契約いただく際にはその条項や約款もご理解いただくことに努めており、説明が漏れることはありません。また、新築住宅以外の中古戸建て、中古マンション、土地については、売主様にご協力いただき現状を説明した「物件状況報告書」「付帯設備表」といった書類も作成し添付することにより、後々の「契約不適合責任」のトラブルにならないようにしております。
ご購入・ご売却の際には、不明点がございましたら、株式会社不動産流通システム、REDSエージェント 大西 進(おおにし すすむ)まで、何なりとご質問ご相談くださいませ。
公開日:2023年10月20日
こんにちは、REDSエージェント、宅建士の大西進(おおにしすすむ)です。私のブログをご覧いただきありがとうございます。
10月初旬、日本の長期金利が大きく上昇し、一時10年ぶりの高水準となりました。理由としてはアメリカでの長期金利の上昇を受け、その影響で日本でも長期金利上昇の圧力が強まったからだと思われます。食費だけでなく光熱費、ガソリン代など日常生活すべてにかかわるあらゆる物の値上がりも続く状況で、変動金利型住宅ローンを契約されて、毎月の住宅ローンのご返済をしていらっしゃる方の中には、今後の返済について不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
こういったタイミングで再度理解しておきたい、変動金利型住宅ローンのポイントを解説いたします。

元利均等方式の変動金利の住宅ローンは後述するいわゆる「5年ルール」により、たとえ金利が上昇しても5年間の返済額は変わらず、6年目にその時点の適用金利によって返済額が見直されます。このとき、その時点での適用金利がどれだけ高くなっていても、返済額の上限は125%までに抑えられる仕組みです。これを「125%ルール」と言います。
従前の毎月返済額が10万円だった場合、6年目の見直しの際の上限は月12万5000円。適用金利が大きく上がった場合でも家計への影響を抑えるための仕組みです。とはいえ、返済額がそれまでの25%増に抑えられるにしても家計への影響は必ずしも軽くはないのではないでしょうか。
例えば、月10万円の返済額であれば返済額が2万5,000円増えることになりますから、場合によっては教育費やその他の生活費などに影響が出る可能性もあると考えられます。対応するためには、変動金利で返済額が低いからといって目一杯の返済にするのではなく、あらかじめ家計にゆとりをもっておくことも大切です。
元利均等方式の変動金利で借りた場合、半年ごとの金利見直しにより適用金利が上がったとしても、5年間は毎月の返済額は変わりません。これは、金利が上がっても家計への影響が抑えられることを目的に設けられた仕組みで、「5年ルール」と呼ばれています。
金利には短期金利と長期金利の2種類ありますが、基本的に変動金利型住宅ローンは短期金利に連動した金利が適用されています。具体的には、日銀が発表する「短期プライムレート(通称:短プラ)」を指標とするものが多いですが、その他の市場金利を指標とするものもあります。短期金利は、長期金利と比較してめったに動かないという特徴がありますが、動く局面も確かにあります。
一般的に変動金利型住宅ローンの金利見直しは半年ごとです。仮に半年ごとに金利が変動し、返済額も都度増減すればどうなるでしょうか。おそらく金融機関の事務手続き負担は増大し、家計は混乱することでしょう。そこで、金利変動時にも返済額の変動頻度が増えすぎないよう、導入されているのがこの「5年ルール」です。
5年ルールにより返済額は5年間変わらないものの、適用金利が変われば、返済額に占める元金と利息の割合は変わります(返済は利息が優先されます)。
例えば、毎月の返済額の合計が10万円で、元金返済額9万5000円、利息が5000円だったとします。適用金利が上がって支払利息が増えると、月10万円の返済額は変わらなくても、内訳が「元金9万円+利息1万円」などと変わる可能性があります。返済額の内訳について通知などはないため、借りている本人は気づいていないこともあります。
変動金利で急激な金利上昇が続いた場合、「5年ルール」や「125%ルール」が裏目に出て、返済額に占める元金と利息の割合が逆転して返済額がほぼ利息、となってしまうこともあり得ます。
最も悪いケースとして、返済額がすべて利息になってしまうこと。さらには、返済額では返しきれない利息が発生すると、「未払利息」として払いきれない利息分、翌月以降の返済に繰り延べされることがあります。多くの場合、最終回の返済日に、未払利息分は残りの元金とともに全額を一括で返済しなくてはなりません。このことも心に留めておかなくてはなりません。
一部の金融機関では、「5年ルール」や「125%ルール」がなく、適用金利が上がればその時点で返済額がアップするタイプの変動金利を扱っているところもありますので、ご自身の住宅ローン商品をどのタイプか理解しておくことも大切です。
住宅購入時に以上のような説明を、金融機関や取引にかかわった不動産業者から受けていらっしゃると思いますが、購入当時は住宅を購入することに精一杯で、うろ覚えの方も多いかもしれません。
変動金利を利用している場合、半年に一度と年末に残高証明が金融機関からの通知(圧着はがきやメールなど)が届いていると思います。住宅ローンのことばかり考えて生活するわけにはいきませんが、半年か年に一度程度で住宅ローンの内容を見直してみるのもよいかもしれません。ご一読いただきありがとうございました。
購入前に住宅ローンについて詳しく知りたい方は、お気軽に大西までご相談ください。
AFP 2級ファイナンシャルプランナー
住宅ローンアドバイザー
REDSエージェント 大西 進
公開日:2023年10月13日
こんにちは、REDSエージェント、宅建士の大西進(おおにしすすむ)です。私のブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は、お隣さんからの竹木の越境について、少しお話したいと思います。

夕方のニュースなどで、管理が行き届いていない住宅(空き家や廃墟も含む)の竹木が伸び放題になっていて、道路の通行に支障をきたしているようなケースが紹介されているのを、ご覧になったことがあるかもしれません。お隣さんの木の枝がのびて、自分の敷地内に越境している場合、声かけさえすれば「自分の敷地内に入っているのだから、切ってもよいのでは?」と思っていらっしゃる方も多いと思います。
ところが、これまで隣家から越境した枝に関しては「お隣さんに枝を切ってもらうようお願いをして切ってもらう」しか方法はなく、越境された土地の所有者が自ら枝を切ることはできなかったことはご存じでしょうか。
民法改定前は、隣の土地にある樹木の枝や根が、境界を越えてこちらに入ってきた場合、法的にどうだったのでしょうか? 当時の規定では「根っこは勝手に切ってもよいが枝は切れない」とされていました。枝に関しては隣家の所有者に「切ってください」と請求することができるだけで、どうしても応じてくれない場合は裁判で勝訴して強制執行を行うしかありませんでした。

この規定が2023(令和5)年4月1日に改正され、一定の場合にはこちらが勝手に切ってもよいことになりました。
この改正では、民法のほか不動産登記法など関連法令の改正による、所有者不明土地管理制度の新設、相続登記の義務化、相続した土地の国庫帰属(相続土地国庫帰属法の新設)などが大きく話題となりました(前回のブログを参照ください)。
実はそのかたわらで、民法の相隣関係(お隣さん同士の法律関係)に関する規定も少し変わりました。その一つである、枝や根の越境に関する民法233条の改正について解説します。
改正前の民法の規定(~2023年)では、隣地の樹木の枝や根がこちらに越境してきた場合、通常は、まずは隣地側に何とかするようお願いすることが必要でした。では、相手がそれに応じない場合は法的にはどのような手段があるのでしょうか。
適用されていた民法の規定は、次のとおりです。
【改正前】
民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2、隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
隣地の樹木(条文上は「竹木」)の枝や根がこちらに越境してきた場合、2項により根についてはこちらが(勝手に)「切り取ることができる」とされています。
これに対し1項によれば、枝については隣地側に「切除させることができる」となっています。といっても、この規定は「お隣さんを無理やり引っ張り出してきてノコギリやナタを持たせて切らせることができる」という意味ではなく、あくまで「相手に枝を切ってもらう権利がある」ということにすぎません。
他の権利と同様、強制的に実現するには勝訴判決を得たのち、強制執行手続を経なければならないのです。具体的には、隣地側に対して「この範囲で枝を切除せよ」という訴訟を起こしてその旨の判決を得た後に、強制執行により枝を切除します。
※強制執行は、具体的には代替執行(民法414条1項、民事執行法171条)という方法により行います。裁判所が手配した業者が枝を切り落とし、その費用を隣地所有者から取り立てることになります。
それにしても、木の枝を切り落とすだけなのに、訴訟や強制執行を行う必要があるとは、何とも迂遠な話です。とはいえ、法律上こちらには(根と違い)枝を切り落とす権利はないわけですから、勝手に切り落とせば器物損壊罪(刑法261条、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)に問われかねませんでした。
2023(令和5)年4月1日に改正され、次のとおり変更されました。上記233条の規定はほぼそのまま残し(改正前の2項は4項に移動)、新たに2項と3項が加わりました。
【改正後】
民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1、⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2、前項の場合において、⽵⽊が数⼈の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3、第⼀項の場合において、次に掲げるときは、⼟地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 ⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 ⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。
(現地調査に加え、不動産登記簿・立木登記簿・住民票など公的な記録を確認して調査を尽くす必要がある)
三 急迫の事情があるとき。
(台風によって折れた枝が建物を破損する恐れがある場合など)
4、隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
改定前の「根っこは勝手に切ってもよいが、枝は勝手には切れない」という大枠は基本的に残しつつも、枝については若干緩めた(例外を認めた)内容になっています。
すなわち、3項により、催告したが相当期間内に切除されない場合、竹木の所有者が不明あるいは所有者の所在が不明の場合、または急迫の事情がある場合には、裁判を起こさずとも勝手に枝を切除してよいこととなりました。この場合、切除費用は原則として隣地側に請求できる(※)ものと考えられます。
※不法行為に基づく損害賠償請求として。
もちろん(今までと同様に)1項に基づき裁判で切除請求をする(※)ことも可能です。
※隣地が共有の場合
細かいですが、隣地が共有の場合(※)、3項1号の催告は共有者全員にしなければなりません。ただし、一部の共有者が所在不明の場合には、3項2号によりその不明者に対しての催告は不要となります。
※正確には「竹木が」共有の場合ですが、多くは土地所有者が竹木の所有者なのでこのように表記しました。
要するに、判明している共有者全員には催告をする必要があるということです。
一方、裁判で切除請求をする場合(1項で請求する場合)には、共有者全員を相手にしなくともOKです。少し分かりづらいですが、2項の規定により共有者は誰でも切除することができると明記されたので、誰か一人に対し「切除せよ」という判決を取ればそれで強制執行ができることになります。
ご所有の不動産も定期的に確認が大切です。まずは所有地と隣地の状況が改正後の状況に当てはまるかどうか確認しましょう。
隣地との越境物に関する事件としては、令和3年9月に、東京都港区で発生した火災事故で、隣地から越境していた木の枝が燃え広がり、建物や車などに被害が出ました。この事故では、越境していた木の枝を切除するように隣人から求められていたものの、所有者が応じなかったことが原因とされています。
意外と自分の敷地から枝が越境していることに気づいていない土地の所有者も少なくありません。不要なトラブルを避けるためには、隣地だけではなく自身の庭木も越境していないか、自宅以外に所有している土地建物なども、定期的に確認することが大切です。
最終更新日:2023年9月8日
公開日:2023年9月7日
こんにちは、REDSエージェント、宅建士の大西進(おおにしすすむ)です。私のブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は相続登記の義務化(相続人申告登記制度)について、お話ししたいと思います。

相続登記とは、不動産を相続したことを登記簿に記録する手続きのことです。相続登記は、相続人の権利を明確にし、不動産の所有者を正しく把握するために重要なものです。しかし、現在は相続登記をしなくても罰則がないため、多くの人が相続登記を怠っています。その結果、所有者不明土地と呼ばれる問題が深刻化しています。
所有者不明土地とは、不動産を相続したことを登記簿に記録しなかったり、登記簿上の所有者と実際の所有者が一致しなかったりすることで、土地の所有者が分からなくなってしまった土地のことです。所有者不明土地ができる原因はいくつかありますが、主なものは以下のとおりです。
不動産の所有者が亡くなったときに、その土地や建物の名義を相続人に変更する手続きを怠ると、登記簿上の所有者と実際の所有者が一致しなくなります。
不動産の所有者が転居したときに、その住所を登記簿に反映させる手続きを怠ると、所有者の所在が不明になります。
相続人が多数いるときは、全員の同意が必要な場合があります。そのため、相続人同士の話し合いや連絡が困難になると、土地の処分や管理ができなくなります。
固定資産税や管理費用などの負担を避けるために、土地に価値を見出さない所有者や相続人が、登記や管理を放棄することもあります。
以上のように、登記や管理が不十分になることで、所有者不明土地が発生します。
近年、所有者不明土地は、日本では深刻な問題になっています。所有者不明土地は、公共事業や復旧・復興事業の妨げになったり、土地の利活用や取引の阻害要因になったりしています。また、所有者不明土地は、適切な管理がされずに荒れ果てたり、雑草やゴミが溜まったり、災害の危険が高まったりします。
私の取り扱ったケースでは、私道の相続未登記が数件、調整区域の荒れた雑種地の放置などがありました。私道は、一般に複数の土地所有者が共有しています。しかし、相続登記や住所変更登記がされなかったり、相続人が多数であったりすることで、私道の所有者が不明になることがあります。
このほか、所有者不明私道は、舗装やライフラインの設置・管理などに支障をきたします。また、所有者不明私道に隣接する土地の利用や取引も困難になります。

このような問題に対処するために、法務省は民法と不動産登記法などの一部を改正し、相続登記の義務化を決定しました。相続登記の義務化とは、以下の3点を意味します。
■相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
■遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
■過去の相続分も義務の対象です。
いずれの場合も、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科せられます。相続登記の義務化は2024年(令和6年)4月1日から施行されます。ただし、2024年4月1日より前に相続が開始している場合も、2027年(令和9年)3月31日までに相続登記をする必要があります。
ただし、相続登記義務化には、以下のような特例もあります。
相続人が相続登記をしないで死亡した場合や、法務大臣指定の土地を相続した場合には、登録免許税が免税となります。これは、2025(令和7)年3月31日までの間に限ります。
相続人が不明であるか、相続人が相続放棄をした場合には、その土地が国庫に帰属することになります。これは2023(令和5)年4月から施行されました。
所有者不明土地の利用や管理を裁判所が選任する財産管理人に委ねることができます。これは、2022(令和4)年11月から施行されました。
所有者不明土地を災害対策や再生可能エネルギー発電などの公益性の高い施設として活用することができます。これは、2022(令和4)年11月から施行されました。
以上の特例も検討しながら、皆さんのご家族が相続された土地についてどのように対応するのかもお考えになってみてはいかがでしょうか。
相続登記の義務化は、不動産の所有者情報を正確に更新し、所有者不明土地を解消することで、次世代への財産移転や土地活用を促進することを目的としています。相続登記は、家族をつなぐ大切な手続きです。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。