片岡 慎太郎(宅建士・リフォームスタイリスト)
安心できる住まいのご提案をします。
CLOSE
公開日:2024年7月5日
こんにちは。仲介手数料が必ず割引、最大無料の不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士の片岡慎太郎と申します。
金融機関で住宅ローンを組むときは、団体信用生命保険(団信)に加入するのが一般的です。そもそも団体信用生命保険とはなんなのでしょうか。
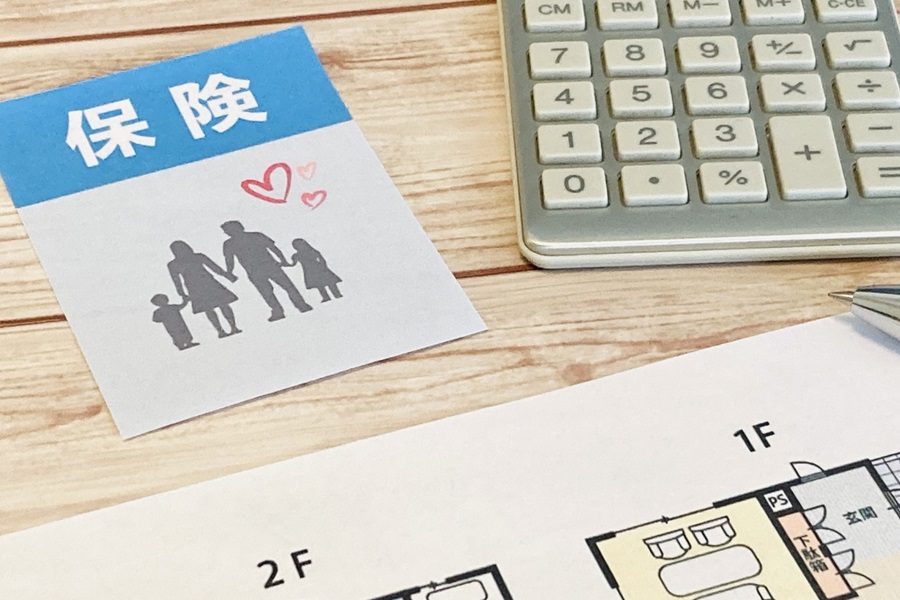
団体信用生命保険(団信)とは住宅ローンの契約者に万が一のことがあった際に、保険会社が住宅ローンの残債に相当する保険金で住宅ローンを完済するという仕組みの保険です。保険契約者は金融機関、被保険者は住宅ローン契約者となり、住宅ローンの契約者が死亡や高度障害状態となった場合に保険金が支払われます。
多くの金融機関では、住宅ローンの契約時に団信への加入が必須となります。加入に際しては生命保険会社が独自に審査をしているため、健康状態によっては団信に加入できず、住宅ローンの審査に落ちてしまうこともあります。
団信の保険料は、金融機関が負担するのが一般的です。しかし、多くの場合は住宅ローンの金利に団信の保険料相当額が上乗せされているため、間接的に契約者が保険料を負担しているともいえます。
団信の保障範囲は金融機関や加入するプランによって異なりますが、一般的な団信では、契約者死亡または所定の高度障害状態に当てはまった場合に保険金が支払われます。
高度障害状態とは、生命保険会社が指定する以下のような状態を指します。
団信に加入する最大のメリットは、住宅ローンの契約者に万が一のことが起こった際に、残された家族が返済を負う義務がなくなり、家族に経済的な負担をかけてしまう心配をせずに済むことです。
住宅ローンの残高に相当する生命保険に加入するのと同様の効果を得られるため、団信以外に加入する生命保険の保険料を抑えやすいという点も魅力です。
一般的な生命保険は、契約内容や金額に応じて一定額を所得から控除できますが、団信は生命保険料控除の対象外となるため、所得控除が受けられないことはデメリットかもしれません。
団信に加入する際は、契約者の健康状態の告知が必要です。健康状態に問題がある場合は、団信に加入できず、住宅ローンが組めない可能性もあります。団体生命保険の加入ができない場合、団信加入が必須ではない「フラット35」などの住宅ローンを利用するといいでしょう。
団信なしで住宅ローンを組むメリットは、適用金利よりも若干低く抑えられることです。そのため、返済期間が短かったり、借入金額が少なかったりする場合は、団信なしでの住宅ローンも選択肢に入るかもしれません。
ただし、団信なしで住宅ローンを組む場合は、返済期間中に契約者が死亡・高度障害状態となったとしても、その後の支払いは免除されないというデメリットがあります。団信に加入せずに万が一のリスクに備えるためには、別の生命保険や貯蓄などで準備しておくことが重要になります。
健康状態に不安がある場合は、金利が若干上がりますが、引き受け基準を緩和したワイド団信に加入するのもひとつの方法です。
最近では、各銀行も特約を付加することで、死亡や高度障害状態以外の病気なども保障できる3大疾病、8大疾病、全疾病保障など、保障が手厚い商品があります。将来を考えて選択するのもいいでしょう。
不動産流通システムREDSでは、「JR山手線の主要ターミナル駅および横浜駅からおおむね30分圏内」の不動産の売買仲介を専門にお取り扱いしております。多少前後してもお取り扱い可能の場合もありますのでお気軽にご相談ください。
常に顧客目線で考え、お客様の満足を最優先に業務に取り組んでいます。その一環として、弊社ではお客様がエージェントを指名できるように対応しております。不動産売買で大切なのは会社よりも、対応する担当者ともいわれております。お客様と相性のよさそうなエージェントがいましたらぜひ、ご指名をいただけたら幸いです。
《不動産仲介手数料が無料もしくは割引》の不動産流通システム【REDS】では、引き続きみなさまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
公開日:2024年5月27日
こんにちは。「仲介手数料が必ず割引、最大無料」の不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士の片岡慎太郎と申します。
お客様に物件をご紹介していく中で、借地権の物件をご紹介することがあります。物件が借地権と分かると毛嫌いするお客様が多く、理由を尋ねると「借りてまで住みたくない」「自分のものにならないから嫌だ」「住宅ローンとは別に地代がかかるから嫌だ」などというお客様が全体の8~9割です。
借地権はそんなに嫌な仕組みなのでしょうか。簡単にですが、借地権について解説します。

借地権とは土地の持ち主から土地を借りて建物を建てる権利のことです。
借地権は大きく分けて2種類で、「旧法借地権」と「借地借家法」があります。
「旧法借地権」は、借地人の権利が強く、期限は決まっているものの、更新することにより半永久的に借りることができます。木造などの場合は、存続期間は30年(最低20年)で、更新後の期間は20年。鉄骨造、鉄筋コンクリートは60年(最低30年)で、更新後の期間は30年となっています。旧法借地権は、土地の返還が難しいなど地主に不利な部分がありました。
1992年8月以降に借り始めた場合は、「借地借家法」が適用されます。
「借地借家法」には5種類あります。大きくは普通借地権と定期借地権です。
1.普通借地権:契約期間は決まっているが、更新することにより半永久的に借りることが可能。存続期間は構造に関係なく当初30年。合意の上の更新なら1回目は20年、以降は10年となっている。
2.定期借地権:定期借地権付き一戸建て、定期借地権付きマンションともに住宅用として土地を賃借する。契約期間は50年以上。契約終了後は、更地にして返還。
3.事業用定期借地権:事業用(店舗や商業施設など)で土地を借りる場合、契約期間は10年以上50年未満。契約終了後は更地にして返還。
4.建物譲渡特約付借地権:契約から土地所有者が建物を相当額にて買い取る決まりがある。契約期間は30年以上。
5.一時使用目的の借地権:工事の仮設事務所やプレハブ倉庫などで一時的に土地を借りる。
借地権には主に以下のようなメリットとデメリットがあります。
建物には固定資産税と都市計画税がかかりますが、土地にはかからないため税金面で安く抑えられるというメリットがあります。
借地権の物件は、所有権に比べて好条件がそろっていても、デメリットを上回るメリットが必要になります。
私が接客してきた中で、借地権を購入されているお客様は、先ほどご説明させていただきましたように立地などの利便性を考慮されたというお客様や、所有権に比べ安いので購入されたというお客様が多数です。
借地権の地主様で多いのが、お寺や神社でした。中には、法人で所有している土地、個人で貸している地主様もいます。
購入されるお客様で、トラブルが多いから嫌だと言う方もいますが、相手がお寺の場合は一律で、地代、名義変更料、更新料、建て替え承諾料が決まっているため、安心できるかと思います。また、更新時は20年後とかになるので、状況はそのときの社会情勢により変わってきますので、今の価格を把握しても先のことは分からないのが正直なところです。
お寺などが所有している土地は、お布施として寄付された土地なので、底地を売るということはほとんどないそうです。個人の地主の場合は、更新のタイミングで「(お金に困ったから)底地を買わない?」と持ちかけてくることもあります。借地権者としては千載一遇のチャンスなので、底地を買えるお金があれば絶対、購入をお勧めします。実は、個人の地主の場合は意外に底地を買えるケースが多く、私も数回、お手伝いいたしました。
あと、借地権は相続ができないと思っているお客様もいますが、借地権は相続できます。一般的には、地主の承諾は必要なく、土地の賃貸借契約書の名義変更をする必要もありません。地主に対して相続したことを通知すれば十分です。名義変更料も不要です。
法定相続人以外の第三者に売却する場合は、地主の承諾と譲渡承諾料が必要になります。名義変更料、譲渡承諾料などは、地主によってさまざまなので、売却前には一度、確認しておきましょう。
駆け足でご説明させていただきましたが、借地権でお困りの際は、ぜひ、片岡までご一報いただけますと幸いです。
不動産流通システムREDSでは、「JR山手線の主要ターミナル駅および横浜駅からおおむね1時間圏内」の不動産の売買仲介を専門にお取り扱いしております。多少前後してもお取り扱い可能の場合もありますのでお気軽にご相談ください。
常に顧客目線で考え、お客様の満足を最優先に業務に取り組んでいます。その一環として、弊社ではお客様がエージェントを指名できるように対応しております。不動産売買で大切なのは会社よりも、対応する担当者ともいわれております。お客様と相性のよさそうなエージェントがいましたらぜひ、ご指名をいただけたら幸いです。
《不動産仲介手数料が無料もしくは割引》の不動産流通システム【REDS】では、引き続き皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
公開日:2024年4月19日
こんにちは。仲介手数料が必ず割引、最大無料の不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士の片岡慎太郎と申します。
少し前ですが、2017年12月に不動産経済研究所が発表したデータによると、首都圏一都三県で、震度5強レベルには耐える力を持つ「旧耐震基準」で建築されたマンションは、6746物件で、45万1560戸あるそうです。その中でも東京都は、4840物件、26万7623戸と約6割を占めています。
23区別にみると、最も多かった港区の480物件2万5337戸を含め、世田谷区の456物件1万9005戸、新宿区338物件1万8091戸、渋谷区374物件1万7736戸、品川区270物件1万5931戸、大田区269物件1万5072戸、板橋区215物件1万2989戸、江東区145物件1万2174戸、杉並区253物件1万1172戸、目黒区241物件1万618戸と計10区が1万戸を上回っているとのこと。
東京都で物件探しをすると、結構な確率で旧耐震のマンションを選んでしまうことになってしまいます。できることなら震度6強~震度7レベルでも倒壊しない設計の新耐震基準のマンションを選びたいもの。旧耐震と新耐震基準の違いについてご説明します。
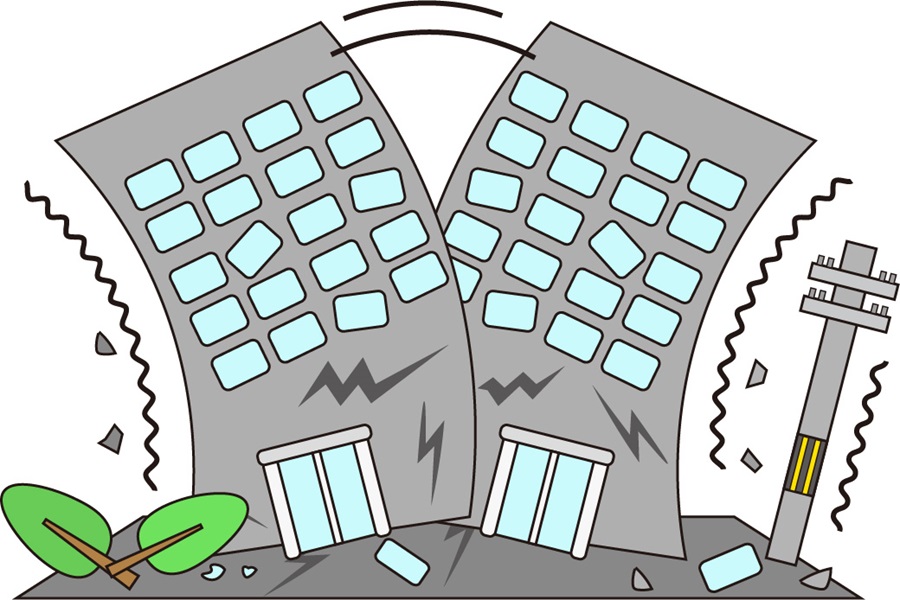
耐震基準は、1978年宮城県沖地震をきっかけに大きく改正され、1981年5月31日までの耐震基準を「旧耐震基準」、1981年6月1日以降の耐震基準を「新耐震基準」と呼んで区別しています。
これは、建物が新築された日ではなくて、建築確認完了日になります。1981年5月31日以前の建築確認完了日が「旧耐震基準」、1981年6月1日以降が「新耐震基準」です。
木造住宅の耐震性向上を目的として新耐震基準をさらに強化した「2000年基準(現行耐震基準)」もありますが、こちらは改めてお話しさせていただきます。
旧耐震基準は「震度5程度の中規模地震を受けたとしても、建物が倒壊・崩壊しないと考えられる」という基準です。中規模しか考慮されていないため、それ以上の大地震では倒壊の恐れがありました。震度5程度の地震では倒壊しないものの、建物に損傷が生じる可能性も少なくありませんでした。
1978年宮城県沖地震マグニチュード7.4(震度5)が発生し、建物やブロック塀の倒壊により甚大な被害がもたらされたのをきっかけに耐震基準が見直され、新耐震基準ができました。
新耐震基準は耐震性に関する規定がより厳格化され、震度6強程度の大地震でも建物が倒壊・崩落せず、人命や財産を守れることが基準となっています。
新耐震基準では、大地震に耐えられるよう、「一次設計(許容応力度計算)」と二次設計(保有水平耐力計算)」の二段階にわたって耐震チェックが行われます。一次設計とは、震度5程度の中規模な地震でも建物が倒壊しないという検証です。二次設計とは、震度6強から7の大規模な地震でも建物が倒壊・崩落せず、内部の人命や財産を守れることを検証するものです。
東京都の場合は、「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」により耐震化の状況の報告義務と耐震診断が義務化されています。次のいずれにも該当する建築物が対象です。
旧耐震基準のマンションは、二次設計を行っていませんので、改めて耐震検査をした場合、ほぼ、新耐震基準を満たしてないことになります。満たしていない場合は、基本的に東京都、市区町村から助成制度を利用して耐震補強を行わなければなりません。
旧耐震のマンションは、住宅ローンの融資も厳しくなり、耐震補強をしていないマンションは、融資すらしない銀行も多いのが現状です。弊社では、旧耐震のマンションでも融資できる金融機関はご紹介できますのでご安心ください。
耐震補強をすることで、新耐震基準を満たしていることが条件になりますが、住宅ローン控除も受けられますし、資産価値も上がります。住宅ローン控除については、内容がコロコロ変わりますので、国税庁の公式サイトにてご確認ください。
マンションを購入する際には、旧耐震、新耐震どちらも条件に入れて探すのもいいかもしれません。
不動産流通システムREDSでは、「JR山手線の主要ターミナル駅および横浜駅からおおむね1時間圏内」の不動産の売買仲介を専門にお取り扱いしております。多少前後してもお取り扱い可能の場合もありますのでお気軽にご相談ください。
常に顧客目線で考え、お客様の満足を最優先に業務に取り組んでいます。その一環として、弊社ではお客様がエージェントを指名できるように対応しております。不動産売買で大切なのは会社よりも、対応する担当者ともいわれております。お客様と相性のよさそうなエージェントがいましたらぜひ、ご指名をいただけたら幸いです。
《不動産仲介手数料が無料もしくは割引》の不動産流通システム【REDS】では、引き続き皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
公開日:2024年3月12日
こんにちは。仲介手数料が必ず割引、最大無料の不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士の片岡慎太郎と申します。
最近、「リノベーション済みマンション」という物件が増えています。この「リノベーション済みマンション」とは何なのか、リフォーム済みとはどう違うのか、解説します。

まず「リフォーム」と「リノベーション」の違いってご存じでしょうか。
リフォームとは、リビングや部屋の壁紙を張り替えたり、キッチンのカウンタートップや水洗金具、キャビネットなどをモダンな設備に変更したり、バスルームを改装したり、古くなった設備などを新しくしたりなど、部分的な修繕を指します。
一方、リノベーションとは、現代的な生活をスタイルやニーズに合わせて改装することが目的とされ、新しい機能や設備を追加したり、給湯器や暖房システムを交換したり、スマートホームテクノロジーを導入したり、屋根や壁、基礎などの修復や補強を行うことで、耐久性を向上させ、長期的な価値を確保したりするなど、包括的な改修をすることを指します。
明確な定義がないので難しいところですが、床材のフロアータイルを例に取ると、へこみを直すことをリフォーム、天然木材のフローリングに変えることをリノベーションだと考えると分かりやすいのではないでしょうか。
リノベーションマンションとはどのようなマンションでしょうか。
多くのリノベーションマンションは、中古マンションのフローリング、壁、天井といった目に見える部分が新品に交換されており、見た目は新築並みに綺麗です。キッチンやお風呂、トイレ、配管(横引き)など住宅設備も新品に変更されている物件もあります。最近では、専門のデザイナー監修が付いてハイセンスな洗練されたマンションとなっている物件も存在します。
中古マンションを購入後にご自身で工事する場合は、入居まで時間がかかってしまいますが、理想の条件に合ったリノベーションマンションは、契約から入居まで円滑に進めることができます。
リノベーションマンションは、買い取り再販業者といわれる専門の不動産業者が売主となっている物件がほとんどです。不動産業者が売主の場合は、契約不適合責任が最低2年以上課されており、買主様が安心して購入しやすくなっています。
契約不適合責任とは、買主に引き渡された不動産が、種類、品質、数量に関して契約内容に適合しない場合に売主が負う責任のことであり、売主が適合しないものを引き渡した場合、買主が売主に対して補修または、代金減額、契約解除、損害賠償などを追及できる制度のことです。
一般個人の売主の場合は、買主が同意すれば、一部免責されます。仮に個人の売主が契約不適合責任を負うとしても3カ月程度であり、2年より短い場合が多く、負わない場合もあります。
リノベーションマンションにはどんなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
まず、自分でリフォーム、リノベーションをしようとするとリフォーム会社の手配、見積もりの確認、設備仕様の選定など、かなり手間がかかります。一方、新規で探す場合は、きちんと施工してくれるのかという不安も残ります。
リノベーションマンションは、中古マンションをそのまま使うのに比べて前入居者の生活感を感じない点もメリットです。リフォームのように一部修繕するのではなく、全体的な雰囲気や見た目が変わっているので、前入居者の生活感がほぼ消えています。
もちろんデメリットもあります。専有部分(お部屋の中)はリノベーションできても、構造躯体や共用部分(バルコニー、玄関ドア、窓、郵便ポスト)などには個人が手を加えることはできません。
また、23区では、リノベーションマンションは旧耐震基準で建てられたマンションも多く、こうしたマンションには住宅ローンが使えないことがあります。最近では、例外もありますが、旧耐震の物件(1981年6月1日以降に建築確認を受けた物件)には、融資しない銀行が増えつつあるためです。同様の理由で、火災保険に加入できる保険会社も限定される場合もあります。
メリットの多いリノベーションマンションですが、ポイントをまとめてみました。
●住宅ローンの確認:住宅ローン以外にも融資事務手数料、印紙代金、登記費用など諸経費がかかりますのであらかじめ理解しておきましょう。
●アフター保証:リノベーションマンションは、施工会社独自の保証がある場合があります。どういった保証が含まれているか、また保証範囲や保証期間を確認しておきましょう。
●耐震基準:築年数が古いと耐震基準を満たしていないマンションもありますが、中には、築年数が古くても補強工事を行い、耐震基準を満たしているマンションもあります。住宅ローンが使えない場合もありますので、事前に確認しておくことが重要です。
不動産流通システムREDSでは、「JR山手線の主要ターミナル駅および横浜駅からおおむね1時間圏内」の不動産の売買仲介を専門にお取り扱いしております。多少前後してもお取り扱い可能の場合もありますのでお気軽にご相談ください。
常に顧客目線で考え、お客様の満足を最優先に業務に取り組んでいます。その一環として、弊社ではお客様がエージェントを指名できるように対応しております。不動産売買で大切なのは会社よりも、対応する担当者ともいわれております。お客様と相性のよさそうなエージェントがいましたら是非、ご指名をいただけたら幸いです。
《不動産仲介手数料が無料もしくは割引》の不動産流通システム【REDS】では、引き続き皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
公開日:2024年2月3日
こんにちは。仲介手数料が必ず割引、最大無料の不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士の片岡慎太郎と申します。
2024年1月3日のドラマ『正直不動産special』のテーマになりそうで取り上げられていなかった「個人間売買」について解説したいと思います。
『正直不動産special』の後半の部分に、お父さんが息子のために所有している不動産(畑)に担保を付けて銀行からお金を借りるお話があったかと思います。
個人間売買において、実は、ここが一番難しいところだと思います。まずは、個人間売買のメリット・デメリットについてご説明いたします。

個人間売買の主なメリットは以下の3点です。
(1)仲介手数料(売買価格の3%+6万円+消費税)が不要。
(2)契約内容を自由に決められる。
(3)契約・引き渡しのスケジュールを自由に決められる。
一方、主なデメリットは以下の3点です。
(1)契約内容など自由に決められる分、手間がかかってしまう。
(2)思わぬところで、トラブルに発展してしまう。
(3)住宅ローンが利用できない場合がある。
私が経験したお客様は、個人間売買について事前にご相談をいただきましたが、不動産業者が仲介しない契約は、契約内容などについて売主、買主に偏ってしまう箇所があり、売買価格が相場以下との理由で住宅ローンが使えないケースがありました。
結局、そのお客様は不動産業者に契約書の作成を依頼して価格も私が調べた周辺相場にてご納得していただき、個人間売買を締結していただきました。
住宅ローンも利用でき問題はありませんでしたが、個人間売買は受け付けてくれない金融機関も多いので、住宅ローンを組む場合は、あらかじめ銀行に確認したほうがいいと思います。私も金融機関を探すのに苦労した記憶があります。
『正直不動産special』では、金融機関の融資について詳しく取り上げていませんでしたが、お父さんは、息子のために高い利息で、お金を借りたのだろうなぁ~と思いながら見ていました。
売買価格も市場の相場からあまりにも安すぎると贈与とみなされてしまい、贈与税が加算されてしまうケースもあります。個人間売買は、価格についてもお互いに自由に決められますので、どちらも納得していれば問題ないのですが、税務署はしっかりチェックしていますので、不動産屋さんに相場の確認はしたほうがいいと思います。
主人公の永瀬は、仲介手数料をもらったと言っていたので、個人間売買ですが、仲介手数料をもらう形で業者が仲介する契約を行ったと思います。仮に現実の話なら両手仲介なので、仲介手数料はいい金額だったかもしれませんが、担当者は、融資する銀行を探したり、現在借入している保証会社など期日の相談をしたりなど相当な苦労があったと思います。
今回は、親子間だったという事情もあり、住む人が変わらない形のリースバック契約だったので、近隣トラブルなどはなさそうな感じでしたが、親戚やご近所さんが購入した場合は、入居後の建物の不具合、地中埋設物、塀の所在、越境などの問題からトラブルに発展することは、十分考えられます。
我々プロからしてみれば、越境などは事前に確認して、売主様から覚書の取得を取るように依頼をしますが、個人間売買の場合は、その辺もあいまいなケースが多いと思います。
また、昔の測量と今の測量では、土地面積の誤差が生まれるケースが多いです。昔は「縄伸び」「縄縮み」と言って縄で測っていました。登記所にある測量図が古い場合は、要注意です。家を買ったはいいけど、土地が登記面積より小さいため、違反建築になってしまうケースも考えられますので、仮測量で構いませんので、あらかじめ行っておくといいかもしれません。
土地、建物に抵当権が付いている場合も要注意です。売却金額で住宅ローンの抵当権が解除されればいいですが、固定資産税などの税金滞納のために付いた抵当権、仮登記など、借金がいくらあるのかも売主様に確認しておくことも必要です。

『正直不動産special』では、「抵当権」という言葉は、話が難しくなるので、あえて使っていないそうです。抵当権が消えないと買主様に引き渡しできなくなってしまうので、私が経験した任意売却のときも住宅ローン、税金の滞納、他の借金をすべて教えていただきました。
他にも権利書、登記簿謄本、契約時の印紙代、固定資産税などの金額が分かる評価証明書なども用意しなくてはなりませんので、私でも面倒に感じます。あとあとトラブルにならないためにも、個人間売買でも不動産仲介会社を入れて契約の締結をすることをお勧めします。
弊社の個人間売買でもREDSでは仲介手数料は割引にて対応しますので、お気軽にご相談くださいませ。不動産流通システムREDSでは、常に顧客目線で考え、お客様の満足を最優先に業務に取り組んでいます。その一環として、弊社ではお客様がエージェントを指名できるように対応しております。
不動産売買で大切なのは会社よりも、対応する担当者ともいわれております。お客様と相性のよさそうなエージェントがいましたら是非、ご指名をいただけたら幸いです。《不動産仲介手数料が無料もしくは割引》の不動産流通システム【REDS】では、引き続き皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
公開日:2023年12月27日
こんにちは。仲介手数料が必ず割引、最大無料の不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士の片岡慎太郎と申します。
最近テレビCMでも「リースバック」に耳にする機会が増えました。メリットだらけのように聞こえますが、デメリットはないのでしょうか。今回は、リースバックについて、その仕組みなどを解説します。

リースバックとは、自宅を売却し、まとまった資金を手に入れる一方で、買主に家賃を支払うことで同じ家に住み続けることができるサービスです。
まず、自宅を売却すると買主(不動産会社や投資家)から一括で現金を受け取れます。資金の使い道の制限はなく、住宅ローンの返済や老後資金、事業資金などに充てることができます。そのうえで、買主と「賃貸借契約」を締結し、同じ家に家賃を払って住み続けることができるシステム、これがリースバックです。
つまり、リースバックは、不動産の売却と賃貸借契約を組み合わせた仕組みといえるでしょう。
リースバックのメリット・デメリットについて説明します。
最大のメリットは、売却後も自宅に住み続けられることです。引っ越しの手間や費用をかけることなく、ライフスタイルの変化も少なく抑えられます。また、近所に自宅を売却しようとしていることを知られずに済みます。
また、自宅を賃借りして住むようになることで、これまでかかっていたランニングコストを軽減できるというメリットもあります。ランニングコストとは住宅ローンの返済、固定資産税・都市計画税、マンションの場合は管理費と修繕積立金が該当します。リースバックでは、これらの費用の支払いがなくなる代わりに家賃が発生します。家賃は、ランニングコストより安くなる場合が多い傾向です。
リースバックのデメリットとして、売却価格が相場よりも安くなることです。リースバックでは、不動産会社が直接買主となるため、仲介会社を利用した通常の売却方法と比べて、競争原理が働きにくく、価格交渉の余地が少ないためです。また、リースバックを利用する人は、資金が必要な状況にあることが多く、どうしても売却価格を優先することができない場合もあります。
また、賃貸期間が無期限ではないこともあります。定期借家契約の場合、契約期間が満了すると退去しなくてはなりません。契約期間の更新や買戻しは、売主の意向によって異なりますが、必ずしも保証されるものではありません。このため、リースバックを利用する場合は、将来的に別の住居を探す必要があることを覚悟しておく必要があります。
家賃が相場よりも高い場合もあります。リースバックを利用する人は、自宅に住み続けたいという希望が強い人が多く、家賃の高さに目をつぶる傾向があります。また、不動産会社は、リースバックで買取した物件を将来的に第三者に売却することを目的としている場合が多いため、家賃を高めに設定することで、物件の収益性を高めようとする傾向にあります。
以上が表面的な内容です。
不動産会社に勤めている私が言うのは何ですが、リースバックはほとんどの場合、お金に困った高齢者の方が「同じ家に住み続けられる」という殺し文句で、深く考えることもなく契約してしまうのが現実のようです。リースバックによって自分名義ではなくなった家に住み続けられますが、近い将来、大損することも考えられます。
リースバックを手掛ける業者は、利回り約7~12%を家賃収入として毎年受け取れるそうです。いまどき、ワンルーム、一棟アパートなどの不動産投資で表面利回り最低利回り7%以上ってありますか? 23区の平均利回りは、5%前後かと思います。
個人的な意見ですが、大々的に広告するくらい、儲かるシステムになっているのですね。さらに契約者側から見ると相場とおりの価格で売却できたとしても家賃を払い続けられる期間は、8~15年程度らしいです。
「老い先短いから」と安易に考えると、家をなくしてしまうリスクのある契約です。契約する前に信用のある不動産業者に必ず、相談することをお勧めします。
不動産流通システムREDSでは、常に顧客目線で考え、お客様の満足を最優先に業務に取り組んでいます。その一環として、弊社ではお客様がエージェントを指名できるように対応しております。不動産売買で大切なのは会社よりも、対応する担当者ともいわれております。お客様と相性のよさそうなエージェントがいましたら是非、ご指名をいただけたら幸いです。
《不動産仲介手数料が無料もしくは割引》の不動産流通システム【REDS】では、引き続き皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
公開日:2023年11月17日
こんにちは。仲介手数料が必ず割引、最大無料の不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士の片岡と申します。
マイホームを売却したときに、売却益が出れば通常、譲渡所得税を払う必要があります。しかし、条件が当てはまれば「3,000万円特別控除」で譲渡所得税がゼロになる可能性もあるのです。それはどういうことなのか、詳しく解説します。

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。ただし、3,000万円特別控除には適用要件があります。
●自分が住んでいる家屋、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。
●マイホームを売った年の前年および前々年にこの特例や、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
●マイホームを売った年とその前年および前々年にマイホームの買い替えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
●売った家屋や敷地などについて、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
●マイホームが地震や災害により家屋が滅失した場合は、その敷地に住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却すること。
●売主様と買主様が、親子や夫婦などの関係でないこと。
以上の条件を全て満たす必要があります。
※以前住んでいたマイホームについて、転勤などを理由に住まなくなってから売却する場合、住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却すれば適用を受けることが可能です。また、マイホームが建っていた土地を、家屋を解体してから売却する場合、家屋解体から1年以内に売買契約を締結し、かつ住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却すれば適用を受けられます。ただし、家屋を取り壊してから売買契約を結ぶ日までの間に、貸駐車場などにして貸し付けていた場合は適用を受けられません。
相続や遺贈により取得した物件を売却する場合、必要な条件を満たせば3,000万円特別控除の適用を受けられます。これを「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」(別名空き家に係る譲渡所得の特別控除)といい、被相続人がマイホームとして居住していることなどが要件となります。詳しい適用要件に関しては後ほど解説します。
マイホームであった物件を賃貸に出している場合でも、条件を満たせば3,000万円特別控除の適用を受けることが可能です。
ただし、売却時点においてマイホームでない物件を売却する場合、住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却しなければなりません。また、自宅兼貸家を売却する場合には、自宅部分のみ、3,000万円特別控除の適用要件を満たせば控除を受けることが可能です。
店舗併用住宅を売却する場合、自宅部分に該当する部分のみ、3,000万円特別控除の適用要件を満たせば、控除を受けることが可能です。なお、全体の90%以上を居住用として使っていた場合には、建物全体について3,000万円特別控除の適用を受けられます。
複数の人間で共有していたマイホームを売却する場合、適用要件に合致する全員が3,000万円分の特別控除を受けることができます。
例えば、持分が2分の1ずつだったとしても、条件を満たせばそれぞれ3,000万円の特別控除を受けることが可能なのです。敷地のみを所有しており、家屋の所有権がない方は、控除の適用を受けることができません。
マイホームを解体した後に敷地だけ売却する場合、以下の要件を満たすことで3,000万円特別控除の適用を受けることが可能です。
●建物解体から1年以内に敷地を売る契約を結ぶこと。
●住まなくなってから3年後の年の12月31日までに売却すること。
●建物解体から売買契約締結の日までに駐車場などとして第三者に貸し付けていないこと。
まず、マイホームを売ったときにかかる税金の額を計算してみましょう。まず、売却によって得られる利益(譲渡所得)を計算します。
●譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)
譲渡所得がプラス(売却益が出た)の場合、下記税率にて情緒所得税の金額を計算します(復興特別所得税含む)。
・長期譲渡所得(5年超)の場合は、20.315%
・短期譲渡所得(5年以下)の場合は、36.93%
例えば、購入価格が5,000万円、取得費が300万円、売却金額が8,000万円で税額を計算してみましょう。
●譲渡所得:8,000万円-(5,000万円+300万円)=2,700万円
これが課税譲渡所得になります。ここから納税額を求めます。
・所有期間が5年超:2,700万円×20.315%=548万5,050円
・所有期間が5年以下:2,700万円×39.63%=1,070万0,100円
通常はこうなりますが、3,000万円特別控除を適用すると、以下のようになります。
●譲渡所得:譲渡価格8,000万円-(取得費5,000万円+譲渡費用300万円)-特別控除3,000万円=0円
つまり、特別控除の適用を受けることで、短期譲渡所得、長期譲渡所得の両方で、税金が控除されます。
マイホームの3,000万円特別控除を受ける場合、不動産を売却した年の翌年2月16日~3月15日の間に申告書を作成し、管轄の税務署に提出する必要があります(e-Taxを利用すれば、自宅から申告できます)。
●10年超所有軽減税率の特例
●被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除
●相続財産譲渡時の取得費加算特例
●10年超所有軽減税率の特例
10年超所有軽減税率の特例とは、売却したマイホームの所有期間が10年超だった場合、軽減税率の適用を受けられる特例です。
●住宅ローン控除
●居住用財産の買い替え等に係る特例
※住宅ローン控除
住宅ローンを組んで購入した際に、住宅ローンの年末残高の0.7%について13年間(既存住宅の場合は10年間)控除を受けられる制度です。ただし、現在所有しているマイホームを売却して新しくマイホームを購入する場合、売却時に3,000万円特別控除の適用を受けていると、新しくマイホームを購入する際に住宅ローン控除の適用を受けられなくなります。
住宅ローン控除と3,000万円控除が併用できると思っているお客様は多いので、ご注意ください。
以上、マイホーム3,000万円特別控除についてお伝えしました。不動産流通システムREDSでは、常に顧客目線で考え、お客様の満足を最優先に業務に取り組んでいます。その一環として、弊社ではお客様がエージェントを指名できるように対応しております。
不動産売買で大切なのは会社よりも、対応する担当者ともいわれております。お客様と相性のよさそうなエージェントがいましたら是非、ご指名をいただけたら幸いです。
《不動産仲介手数料が無料もしくは割引》の不動産流通システム【REDS】では、引き続き皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
公開日:2023年10月20日
こんにちは。仲介手数料が必ず割引、最大無料の不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士の片岡と申します。
不動産を売却するご相談を頂きますが、購入時の金額が不明の場合がよくあります。「親からの相続で契約書がない」や「購入時の売買契約書を紛失した」などの理由がよくあります。買ったときの金額がわからない場合は、どうなるのでしょうか。
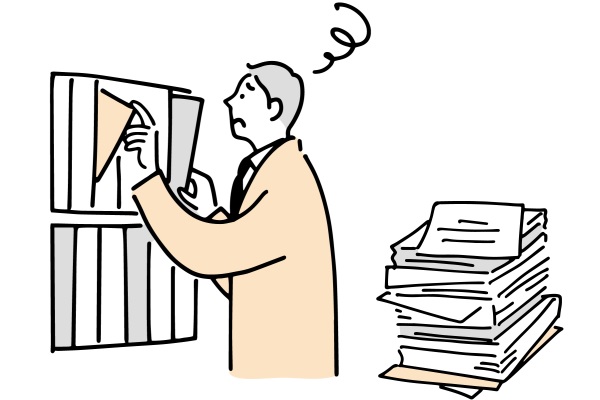
結論から申し上げますと「売却金額の5%」が取得費とみなされます。実際の取得費が5パーセント相当額を下回る場合も、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。
例えば、5,000万円で売却した場合、売った金額の5%の250万円が取得費になります。以前、目黒区のお客様で120㎡(約40坪)200万円で購入したそうですが、当時は土地だけで1億円でしたので、契約書を探すよりも1億円の5%の500万円とするほうがいいので、売買価格の5%を選んでいた記憶があります。
もし購入時の売買契約書がない場合は、次のような対処法があります。
●まずは購入時の不動産屋さん(仲介業者)に連絡して、売買契約書のコピーをもらうか、再発行をお願いする。
●不動産屋さんと連絡が取れない場合や、対応してくれない場合は、売主様に連絡して、売買契約書のコピーをもらうか、再発行をお願いする。
●どちらも難しい場合は、購入金額がわかる書類をできるだけ多く集めて、代用書類として認めてもらう。例えば、購入時パンフレット、残代金領収書、入金した通帳の取引履歴、住宅ローン借り入れ書類、抵当権設定登記などがあげられます。
ない場合は、売却価格の5%を取得費とするしかありません。ですが、売却費用については以下のようなものも含まれます。
(1)土地や建物を売るために支払った仲介手数料
(2)印紙税で売主が負担したもの
(3)貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
(4)土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
(5)すでに売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で売るために支払った違約金(土地などを売る契約をした後、その土地などをより高い価額で他に売却するために既契約者との契約解除に伴い支出した違約金)
(6)借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料などのように、譲渡費用とは売るために直接かかった費用
したがって、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取り立てのための費用などは譲渡費用になりません。
不動産を購入したときは、権利書(登記識別情報)と合わせて大事に保管しておくことが大事ですね。私も購入当時は、ほとんど不動産素人だったので、何が何だか分からないまま、購入した際のの契約書類はまとめて保管しております。
その教訓を生かし、お客様には、売却するようなことがあった場合、大事な書類などを分かりやすくご説明させて頂いております。
一都三県では、ここ7、8年前に不動産を所有した方は、購入当時よりも高く売却されているお客様が多いかと思います。イコール売却益が出てしまう形になります。
居住用財産につきましては、3,000万円控除などの制度もありますが、こちらについては、後日触れたいと思います。一般的には、居住用財産も、収益物件も譲渡所得の税額は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分され、分離課税制度が適用されます。
長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるもので、税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税が0.315%)です。
短期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下のもので、税率は39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)になります。
例えば、所有期間の5年以上の区分は、譲渡して利益を得た日ではなく、譲渡した年の1月1日時点で経過した年数を基準にして判断します。
令和5年12月25日に購入した不動産を、5年後の令和10年12月26日に譲渡すると、日付だけ見れば5年超ですが、譲渡年である令和10年の1月1日時点では5年以下なので「短期譲渡所得」になってしまいます。もう少し待って令和11年の1月2日以降に譲渡すれば、前日の1月1日時点で5年を超えたことになるので「長期譲渡所得」になります。
不動産流通システムREDSでは、常に顧客目線で考え、お客様の満足を最優先に業務に取り組んでいます。その一環として、弊社ではお客様がエージェントを指名できるように対応しております。 不動産売買で大切なのは会社よりも、対応する担当者ともいわれております。お客様と相性のよさそうなエージェントがいましたらぜひ、ご指名をいただけたら幸いです。
《不動産仲介手数料が無料もしくは割引》の不動産流通システム【REDS】では、引き続き皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
公開日:2023年10月12日
こんにちは。仲介手数料が必ず割引、最大無料の不動産流通システム、REDSエージェント、宅建士の片岡と申します。このたび、REDSに入社し、不動産営業マンとして新たなスタートを切りました。みなさま、どうぞよろしくお願いします。

ところで、みなさまは自分が住んでいるところの地名の由来を調べたことはございますか。私は、大田区出身なので、「大田区」について簡単にですが調べてみました。大田区で不動産を検討されている方のご参考になればと思います。

昭和22(1947)年3月15日に、当時の「大森区」と「蒲田区」が一緒になって誕生したのが大田区です。その際、両方の一字ずつを取って命名されました。大田区の前身である大森・蒲田の両区は、ともに昭和7年10月に、当時の東京市へ隣接する郡町村が編入された際に設置されました。
「馬込、東調布、池上、入新井、大森の5つの町が大森区に、矢口、蒲田、六郷、羽田の4つの町が蒲田区になりました」と大田区HPに記載されておりますが、他にも諸説あるようで、「森田」や「大蒲」ではなく「大田」になった理由は、この地が江戸城を築城した太田道灌の領地で、「太田」を連想させることから「大田」になったとの見方もあるそうです。
大田区は海苔の養殖地としても有名でした。歴史は、今から300年ほど前、江戸時代の享保年間(1716〜1736)にさかのぼります。その頃、大森から品川にかけての沿岸部で、日本で初めて本格的に海苔の養殖が始まりました。このあたりの海は、潮の干満があり、養分が含まれた川の水と海水が適度に混じって波も静か。海苔の生育には最適な環境だったのです。
延享3(1746)年から、幕府に「海苔の営業税」を納めるようになり、将軍家などへも献上される最上品の海苔の産地と成長していきました。
そして、大森で発展した養殖技術と乾海苔(ほしのり)加工技術は全国へと伝播し、大森は、明治から昭和初期まで日本一の海苔生産地として最盛期にあった農漁村で、特に海岸の大森・糀谷・羽田地区では海苔の養殖(昭和38年まで存続)が盛んに行われました。また、東海道の街道筋にあたっていたため、人馬の往来でにぎわったそうです。
しかし、港湾整備計画などのさまざまな理由から、昭和37年に漁業権放棄が決定し長きにわたる海苔養殖の歴史の幕を閉じました。かつて産地として品質の良い海苔を量的に扱っていた伝統、技術、経験を活かし、現在の大森の海苔問屋で選別・加工される海苔が「大森海苔」とのことです。今では、少なくはなりましたが、海苔の問屋さんは、多いです。大森海苔ふるさと館がありますので、お近くにお越しの際は、ぜひ寄ってみてください。
大田区の特徴として外せないのが、昭和時代に栄えた小規模な町工場です。下町ロケットの撮影場所になった「株式会社 桂川精螺製作所」が有名です。
これらの工場は、地域経済に根差し、地元の人々に雇用を提供する役割を果たしました。多くの町工場は、家族経営で、親から子へと職業が受け継がれ、長い間にわたって地域経済を支え、地域の活性化や経済発展に寄与しました。
また、町工場は、職人技術が重要な役割を果たしていました。製造のほとんどが手作業に頼っており、熟練した職人が製品の生産を担い、高品質な製品が生み出されました。このような職人文化は、製品に独自の技術やクオリティを持たせる一因となりました。
しかし、近年の産業構造の変化や都市再開発の影響、後継者不足により、町工場の存在感は徐々に減少しています。2014年に大田区が実施した調査では1983年に約9200社あった同区の町工場は、3400社程度にまで減少。発注側の大手企業の海外生産シフトを受けて量産の仕事が減り、廃業が相次ぎました。マンションなどの住宅地が増え、操業にやりにくいと感じる企業も少なくないそうです。
そういった大田区の町工場を絶やさないよう、「大田区では創業支援施設『六郷BASE』や工場アパート『テクノFRONT森ケ崎』などを整備し、『共創』がより推進される場づくりを行っているそうです。
学生の頃、FAXの紙を出すローラーを磨く研磨屋さんでバイトをしておりました。検品する際、髪の毛1本分の0.08mmを誤差がないか確認するので、かなりシビアでした。私の友人も町工場を経営しているぐらい身近な存在です。他にも大田区の魅力は紹介し切れないくらいたくさんありますが、今日はここまでになります。
不動産流通システムREDSでは、常に顧客目線で考え、お客様の満足を最優先に業務に取り組んでいます。その一環として、弊社ではお客様がエージェントを指名できるように対応しております。不動産売買で大切なのは会社よりも、対応する担当者ともいわれております。お客様と相性のよさそうなエージェントがいましたら是非、ご指名をいただけたら幸いです。
《不動産仲介手数料が無料もしくは割引》の不動産流通システム【REDS】では、引き続き皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。