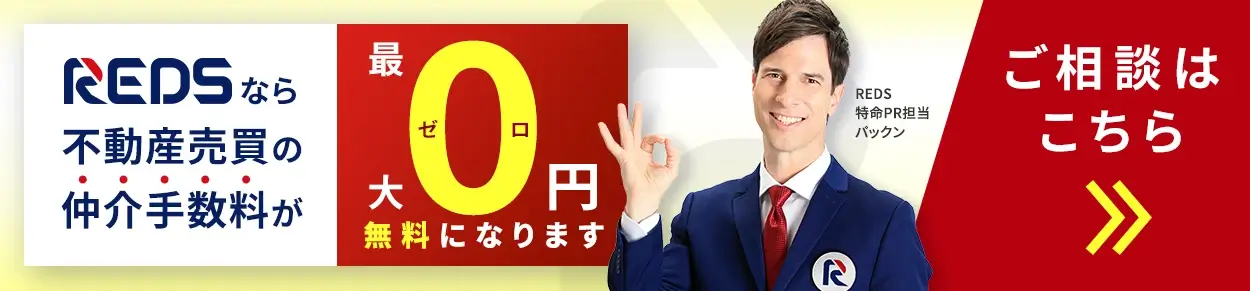住宅ローン残高の1%を10年にわたって所得から控除することで知られる住宅ローン控除(減税)制度。どんな場合に住宅ローン控除の対象になるのか、控除額の計算方法はどのようにすればいいのかを解説します。実例を挙げてシミュレーションもしてみますので、ぜひみなさまもご自身の数値を当てはめて計算してみましょう。

(写真はイメージです)
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除制度の要件や金額、さらに対象となる住宅ローン対象や物件について紹介します。
住宅ローン控除の概要
住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで住宅を購入した人を対象に、金利負担の軽減を図ることを目的とした制度です。基本は下記のうち、最も低い金額が10年間にわたり所得税額から控除されます。所得税から控除しきれない額が生じた場合は、住民税からも一部を控除可能です。
控除額は「毎年末の住宅ローン残高」または「住宅の取得対価」のうち、いずれか少ない方の金額の1%です(通常は「住宅の取得対価」の範囲内で住宅ローンを組むため、以降は「毎年末の住宅ローン残高」として考えていきます)。最大控除額は原則4,000万円ですので、10年間で400万円(4,000×1%×10年)です。ただし認定長期優良住宅であれば最大控除額が5,000万円に引き上げられます。
住宅ローン控除の対象となるローンや物件
住宅ローン控除の対象となるのは、新築住宅や中古住宅のほか、増築や一定規模以上の修繕、リフォーム、省エネ・バリアフリー改修なども含まれます。
住宅は原則として床面積が50㎡以上であることが要件です。ただし令和3(2021)年1月1日から令和4(2022)年12月31日までの間に入居するとき、要件が「40㎡以上」に緩和されます。
中古物件の場合は、築年数が要件に入ります。木造などの耐火建築物以外の建物であれば「20年以内」、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造など耐火建築物の場合は「25年以内」に建築された住宅でなくてはなりません。ただし、所定の耐震基準に適合していることが証明できれば、築年数要件を満たしていなくとも住宅ローン控除を受けられます。
その他、住宅ローン要件として「借入金の償還期間が10年以上であること」、つまりローンの返済期間が10年以上あることが必要です。また、住宅ローン控除には所得制限があり、利用できるのはその年の合計所得金額が3,000万円以下に限られます。
※住宅ローン控除の要件はさらに細かく規定されています。利用の際は、すまい給付金事務局や国税庁のサイトで要件をご確認ください。
参照サイト
住宅ローン減税制度の概要|すまい給付金
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
住宅ローン控除の計算に必要な書類は
住宅ローン控除の計算に必要な書類と、申請方法を紹介します。
住宅ローン控除の計算に欠かせない2つの書類
住宅ローン控除の計算をするには借入先金融機関から受け取る「年末残高証明書」と勤務先から受け取る「源泉徴収票」が必要です。
「年末残高証明書」は、特別に手続きをしなくても、借入先金融機関から送られてきます。金融機関によって差がありますが、だいたい年末前か年始明けです。ただし、秋口以降に住宅ローン契約を組んだり繰上返済を行ったりした場合は年明けになることが多くなります。
「源泉徴収票」は勤務先から年末ごろに受け取れます。源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄の数字が収めた税額です。確定申告の際には他にも、建物・土地の「登記事項証明書」や建物・土地の「不動産売買契約書(請負契約書)の写し」など複数の書類が必要ですが、控除額を計算するためにはこの2つの書類で大丈夫です。
住宅ローン控除の申請をすると、初年度は確定申告が必要です。2年目以降は勤務先の年末調整で済みます。住宅購入時から、翌年の確定申告を見越して書類を整理しておくと、その後のやり取りがスムーズになるでしょう。所得税から控除しきれない額が生じた場合は、翌年の「個人住民税」から所定の額が控除されます。この処理は税務署と自治体間のやり取りで手続きが完了するため、必要な手続きはありません。
住宅ローンの特例措置
令和元年10月に消費税率が8%から10%に引き上げられたのを受け、住宅ローン控除も控除期間が10年から13年に延長されました。この特例措置に該当する場合も、当初10年間は従来の住宅ローン控除と同じ要領です。11~13年目については、次のように控除額を計算します。
以下のうち、いずれか少ない方の金額が3年間にわたり所得税額から控除されます。
・「住宅ローン残高」または「住宅の取得対価(上限4,000万円)」のうちいずれか少ない方の金額×1%
・「建物の購入価格(上限4,000万円※)」×2%÷3
※ここでも認定長期優良住宅であれば最大控除額が5,000万円に引き上げられます。
住宅ローン控除 控除額計算のシミュレーション
では、実際に控除額をシミュレーションしてみましょう。以下の条件で住宅を購入したとします。
〈ローン借入額5000万円/金利1.5%(全期間固定)/返済期間35年〉
住宅ローン残高による住宅ローン控除額
返済開始10年までのローン残高と、控除額は以下の表のとおりです。
| 住宅ローン年数 |
住宅ローン残高(円) |
住宅ローン控除額
(住宅ローン残高×1%) |
| 1年目 |
4,890万5,386 |
48万9,054 |
| 2年目 |
4,779万4,238 |
47万7,942 |
| 3年目 |
4,666万6,309 |
46万6,663 |
| 4年目 |
4,552万1,343 |
45万5,213 |
| 5年目 |
4,435万9,083 |
44万3,591 |
| 6年目 |
4,317万9,270 |
43万1,793 |
| 7年目 |
4,198万1,639 |
41万9,816 |
| 8年目 |
4,076万5,920 |
40万7,659 |
| 9年目 |
3,953万1,836 |
39万5,318 |
| 10年目 |
3,827万9,115 |
38万2,791 |
住宅ローン控除 10年合計額
※100円未満切り捨て |
約436.9万円 |
所得税の概算
次に、上記の住宅を購入した人の所得税を年収別で求めてみましょう。計算方法の手順を示します。
A:年収1,000万円
(1)控除するもの:社会保障・厚生年金・健康保険(15%として計算)→1,000万円×15%=150万円
(2)控除するもの:給与控除+基礎控除
・給与所得控除:収入金額×10%+120万円=220万円
・基礎控除 48万円
→220万円+48万円=268万円
(3)課税所得額→1,000万円-150万円(社会保障)-268万円(控除)=582万円
(4)税計算(所得税)
所得税は所得の金額によって税率、控除額が以下のように変わります。
・1,000~194万9,000円→5%/0円
・195万~329万9,000円→10%/9万7,500円
・330万~694万9,000円→20%/42万7,500円
・695万~899万9,000円→23%/63万6,000円
・900万~1,799万9,000円→33%/153万6,000円
・1,800万~3,999万9,000円→40%/279万6,000円
・4,000万円以上→45%/479万6,000円
課税対象額528万円の場合、税率20%、控除42万7,500円)ですので所得税額→582万円×20%-42万7,500円=73万6,000円となり、所得税が「住宅ローン控除額(住宅ローン残高×1%)」よりも上回っています。ただし、初めの8年は住宅ローン控除額(住宅ローン残高×1%)が40万円を超えるため、住宅が長期認定住宅でなければ「最大控除額」による制限を受けます。
B:年収700万円
(1)控除するもの:社会保障・厚生年金・健康保険(15%として計算)→700万円×15%=105万円
(2)控除するもの:給与控除+基礎控除
・給与所得控除:収入金額×10%+120万円=190万円
・基礎控除 48万円
→190万円+48万円=238万円
(3)課税所得額→700万円-105万円(社会保障)-238万円(控除)=357万円
(4)税計算
課税対象額357万円の場合、税率20%、控除42万7,500円ですので所得税額→357万円×20%-42万7,500円=28万6,500円となります。
「住宅ローン残高」「所得税」「最大控除額」の3つの上限があるため注意が必要です。3つの金額を計算したうえで、どの金額が適用されるのか把握しておきましょう。
住宅ローンの組み方と住宅ローン控除
夫婦で住宅ローンを組む場合、どのように組めば住宅ローン控除を最適化できるでしょうか。3つのケースを紹介します。
(1)収入合算
夫婦のうちどちらか一方が単独で住宅ローンを申し込む際に、配偶者の収入を合算すると審査が通りやすくなります。ただ、住宅ローン控除においては住宅ローン申込者(契約者)のみの適用です。
(2)連帯債務
住宅金融支援機構のフラット35で取り扱いのある「連帯債務」。連帯債務者は住宅ローン申込者ではありませんが、住宅ローン控除の対象となります。住宅ローン控除の割合は原則として夫婦間の返済割合に準じます。仮に連帯債務者の所得がゼロになると、住宅ローン控除の適用はなくなります。
(3)ペアローン
一つの住宅に対して、夫婦がそれぞれに住宅ローンを申し込むのがペアローンです。夫婦それぞれが自身の借入額に応じて住宅ローン控除の適用を受けることが可能です。
住宅ローン控除の計算を行い、家計に生かそう
住宅ローン控除の効果は人や世帯によって異なります。借入額だけでなく、所得税や住宅ローンの組み方によっても控除額が変わってくるので注意が必要です。大切なことは控除額を把握しておくことです。控除額を貯蓄として家計に還元しておけば、いざというときに役に立ちます。より家計に役立てていきたいものです。
横山晴美 ライフプラン応援事務所
2013年にFPとして独立してから一貫して「家計」と向き合い、マネーリテラシーの向上でお金の不安が軽減することを実感。お金の不安を抱える人が、自分自身で問題を解決できるよう、お金の基礎知識を底上げするための啓発活動を行う。WEBコラム・セミナーなどで家計や住宅ローンなどお金について幅広い情報を発信している。
嬉しい口コミも
 40代男性(マンション売却)
40代男性(マンション売却)
 50代女性(マンション購入)
50代女性(マンション購入)
 40代男性(中古マンション購入)
40代男性(中古マンション購入)
 40代女性(住み替え:購入・売却)
40代女性(住み替え:購入・売却)
 50代男性(マンション売却)
50代男性(マンション売却)
 30代女性(マンション購入)
30代女性(マンション購入)
 60代男性(戸建て購入)
60代男性(戸建て購入)