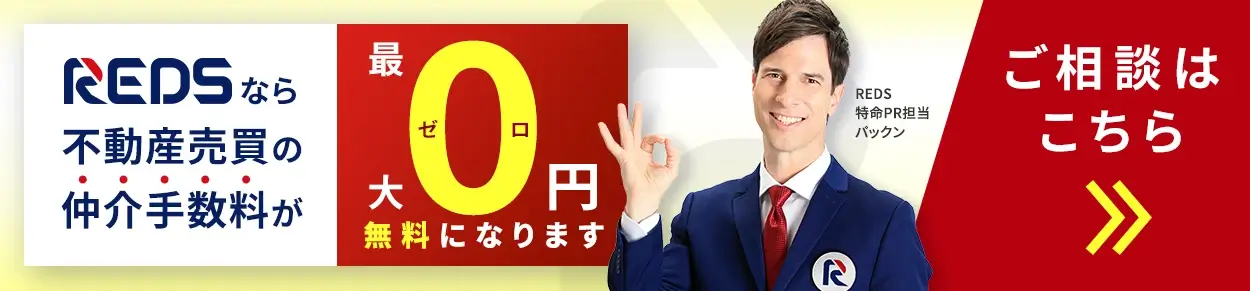前回は、全国の地価公示について見てみましたが、今回は東京23区の住宅地、特に都心区を中心に地価公示を深読みします。
23区の地価下落は、昭和の不動産バブルが崩壊したことにより、1989年(平成元年)から2005年までの17年間続きました。その後上昇に転じましたが、リーマンショックによって再び地価が下落したのが2008年から2013年までの6年間。しかし2014年からは反転して、現在は上昇傾向が続いています。
では、今年の地価公示について、「区別」と「路線別」の2つの視点から23区の住宅地を見ていきましょう。

(写真はイメージです。本文の内容とは関係がありません。)
その1 区別の平均価格はどうなっているのか?
まずは各区の平成27年~29年の平均価格(円/㎡)を、対前年変動率とあわせて表にしました。
参照
平成29年地価公示 区市町村別用途別平均価格表
平成28年地価公示 区市町村別用途別平均価格表
平成27年地価公示 区市町村別用途別平均価格表
(単位:円/㎡)
|
2015年
(H27年) |
変動率
(対前年) |
2016年
(H28年) |
変動率
(対前年) |
2017年
(H29年) |
| 千代田区 |
2,113,300 |
11.6% |
2,358,600 |
7.6% |
2,537,100 |
| 港区 |
1,475,400 |
2.3% |
1,508,900 |
11.5% |
1,682,700 |
| 中央区 |
1,013,900 |
9.4% |
1,108,700 |
4.5% |
1,159,100 |
| 渋谷区 |
1,046,600 |
0.7% |
1,054,000 |
3.6% |
1,092,100 |
| 目黒区 |
797,900 |
1.6% |
811,000 |
4.1% |
844,100 |
| 文京区 |
775,400 |
1.7% |
788,800 |
4.2% |
821,600 |
| 台東区 |
718,300 |
3.0% |
740,000 |
3.8% |
768,200 |
| 品川区 |
654,300 |
1.0% |
661,000 |
9.0% |
720,400 |
| 新宿区 |
640,000 |
3.3% |
661,100 |
3.1% |
681,300 |
| 世田谷区 |
534,900 |
1.7% |
544,100 |
4.0% |
566,000 |
| 区部全域 |
518,600 |
1.1% |
524,100 |
4.8% |
549,100 |
| 中野区 |
497,100 |
0.1% |
497,500 |
5.4% |
524,300 |
| 豊島区 |
484,700 |
3.0% |
499,200 |
4.1% |
519,500 |
| 大田区 |
472,200 |
1.2% |
478,000 |
2.2% |
488,600 |
| 杉並区 |
460,200 |
1.6% |
467,600 |
3.4% |
483,700 |
| 北区 |
414,900 |
-2.0% |
406,600 |
6.7% |
433,700 |
| 江東区 |
392,200 |
2.2% |
400,900 |
3.1% |
413,500 |
| 荒川区 |
382,800 |
0.8% |
385,800 |
4.9% |
404,600 |
| 墨田区 |
372,000 |
-1.0% |
368,300 |
2.7% |
378,100 |
| 板橋区 |
359,300 |
1.4% |
364,500 |
3.2% |
376,300 |
| 練馬区 |
348,100 |
1.1% |
351,800 |
1.9% |
358,600 |
| 江戸川区 |
308,700 |
1.0% |
311,900 |
2.5% |
319,700 |
1㎡あたりの地価が100万円を超えている区は、千代田区・港区・中央区・渋谷区の4区。50万円以上100万円未満の区は、目黒区・文京区など8区。35万円以上50万円未満の区は、大田区・杉並区など8区:となり、35万円以下は江戸川区など3区です。
また、区部全体の住宅地の平均価格は、1㎡あたり54万9,100円です。
23区内の住宅地(902地点)ごとに見ると、最も高い価格が千代田区六番町(千代田-3、四ツ谷駅330m)の1㎡あたり375万円、最も低い価格が足立区入谷8丁目(足立-65、舎人駅1.5㎞)の1㎡あたり17万円。両者の価格の開きは22倍にもなります。
区部で1㎡あたり100万円(330万円/坪)を超えている地点は、全部で73地点あります。
千代田区7(7)、港区27(29)、中央区7(10)、目黒区5(32)、渋谷区16(26)、品川区5(31)、文京区3(24)、台東区1(6)、大田区2(57)
※( )内は、各区内の住宅地の地点総数
千代田・港・中央の都心3区で、区部の半分以上を占めていることが分かります。
その2 路線別での価格はどうなっているのか?
次に、23区内の各路線別での価格について検証してみます。
前章の通り、区部全域での平均価格は1㎡あたり54万9,100円。また、この平均価格以上の地点は全部で293地点あります。ここで各路線を、平均価格以上の地点が多い順に並べ、またその平均価格と平均変動率(対前年比)、価格の最高値と最低値を表にしました。
参照:29地価公示地点データ一覧
※「所在区」は、路線が通っている区を表示
※「最高価格」と「最低価格」で表示される「最寄り駅」は、複数路線が交差する場合、代表的な路線名を表示
同じ路線内でも、価格差の大きい路線と小さい路線があります。路線別で見てみると、区別で見るのとはまた違ったイメージを持たれるのではないでしょうか。
ちなみに、SUUMO住みたい街ランキング2016「路線別ランキング」では、1位が山手線、2位が東急東横線、3位が中央線(吉祥寺駅を含む)となっています。
(単位:円/㎡)
| 路線名 |
地点数 |
所在区 |
平均価格
(平均変動率%) |
最高価格
所在・最寄り駅・距離 |
最低価格
所在・最寄り駅・距離 |
| JR山手線 |
33 |
港・品川・
目黒・渋谷・
新宿・文京・
北・豊島・
台東 |
926,485
(3.7%) |
1,820,000
東五反田1丁目
五反田530m |
563,000
北大塚1丁目
大塚駅550m |
| 東急東横線 |
23 |
渋谷・目黒・
太田・世田谷 |
804,783
(4.0%) |
1,860,000
恵比寿西2丁目
代官山駅200m |
573,000
中町1丁目
祐天寺駅1,200m |
| 東急田園都市線 |
23 |
世田谷・目黒 |
677,783
(4.0%) |
935,000
三軒茶屋2丁目
三軒茶屋駅740m |
564,000
野沢4丁目
駒沢大学前600m |
| 小田急線 |
17 |
世田谷・渋谷 |
666,059
(3.0%) |
1,010,000
代々木5丁目
参宮橋駅600m |
557,000
経堂5丁目
経堂駅740m |
| 京王井の頭線 |
17 |
目黒・渋谷・
世田谷・文京・
杉並 |
844,706
(3.8%) |
1,860,000
青葉台5丁目
神泉駅590m |
549,000
松原5丁目
東松原駅400m |
| 地下鉄丸ノ内線 |
15 |
文京・新宿・
中野・杉並・
豊島 |
699,667
(3.6%) |
905,000
湯島4丁目
本郷三丁目駅550m |
551,000
成田東4丁目
南阿佐ヶ谷駅470m |
| 地下鉄日比谷線 |
15 |
港・渋谷・
目黒・荒川・
足立 |
1,358,867
(5.4%) |
2,750,000
南麻布4丁目
広尾駅630m |
681,000
千住寿町
北千住駅640m |
| JR中央・総武線 |
13 |
杉並・中野・
新宿 |
619,308
(4.0%) |
619,308
中野4丁目
中野駅490m |
553,000
高円寺北2丁目
高円寺駅450m |
| 東急大井町線 |
13 |
世田谷・目黒・
大田 |
654,692
(3.1%) |
840,000
等々力6丁目
尾山台駅700m |
556,000
南千束2丁目
北千束駅270m |
| 地下鉄千代田線 |
12 |
台東・港・
渋谷・文京・
足立 |
877,083
(3.8%) |
1,450,000
池之端1丁目
湯島駅380m |
570,000
綾瀬1丁目
綾瀬駅80m |
| 地下鉄有楽町線 |
11 |
千代田・中央・
文京・江東 |
1,024,818
(5.8%) |
1,880,000
紀尾井町3丁目
麹町駅350m |
600,000
豊洲4丁目
豊洲駅550m |
| 地下鉄南北線 |
10 |
港・文京・
北 |
1,392,600
(3.7%) |
2,600,000
南麻布1丁目
麻布十番駅350m |
638,000
本駒込3丁目
本駒込駅150m |
| 東急目黒線 |
10 |
目黒・世田谷・
品川 |
675,600
(3.8%) |
775,000
目黒本町3丁目
武蔵小山駅650m |
586,000
目黒本町3丁目
武蔵小山駅600m |
JR中央線総武線
(山手線内側) |
8 |
千代田・文京・
渋谷・新宿 |
1,371,875
(4.7%) |
3,750,000
六番町6番
四ツ谷駅330m |
684,000
三栄町15番
四ツ谷駅550m |
| 地下鉄大江戸線 |
8 |
港・中央・
新宿 |
1,056,250
(4.5%) |
1,660,000
三田2丁目
赤羽橋駅560m |
630,000
西新宿5丁目
西新宿5丁目駅500m |
| 地下鉄銀座線 |
7 |
港・渋谷 |
2,050,000
(6.1%) |
3,680,000
赤坂1丁目
溜池山王駅420m |
1,370,000
渋谷4丁目
表参道駅500m |
| 地下鉄三田線 |
7 |
港・文京・北 |
1,090,429
(4.2%) |
3,100,000
白金台3丁目
白金台駅180m |
655,000
滝野川5丁目
西巣鴨駅300 |
| 東急世田谷線 |
7 |
世田谷 |
571,429
(3.1%) |
606,000
赤堤3丁目
松原駅340m |
554,000
上馬5丁目
松陰神社前駅570m |
| 地下鉄新宿線 |
6 |
中央・新宿・
渋谷 |
796,667
(4.0%) |
1,120,000
日本橋浜町3丁目
浜町駅480m |
625,000
本町2丁目
初台駅520m |
| 東急池上線 |
6 |
大田・品川・
世田谷 |
603,500
(3.4%) |
650,000
南雪谷2丁目
雪が谷大塚駅190m |
570,000
西中延2丁目
荏原中延駅310m |
| JR京浜東北 |
6 |
大田・品川 |
720,833
(3.5%) |
1,140,000
大森北1丁目
大森駅380m |
550,000
山王2丁目
大森駅620m |
| 地下鉄浅草線 |
5 |
港・品川 |
848,000
(3.6%) |
1,090,000
高輪2丁目
泉岳寺駅270m |
580,000
戸越3丁目
戸越駅120m |
| 地下鉄半蔵門線 |
5 |
千代田・中央 |
2,382,000
(7.8%) |
2,880,000
三番町
半蔵門駅480m |
1,140,000
日本橋中洲
水天宮前駅320m |
| 地下鉄東西線 |
4 |
新宿 |
645,000
(3.0%) |
735,000
矢来町
神楽坂駅350m |
550,000
赤城下町
神楽坂駅350m |
| 京急線 |
4 |
品川 |
761,000
(3.8%) |
1,090,000
北品川1丁目
北品川駅380m |
549,000
南品川4丁目
新馬場駅430m |
| 地下鉄副都心線 |
3 |
渋谷・新宿 |
866,333
(3.2%) |
1,150,000
千駄ケ谷3丁目
北参道駅450m |
596,000
西早稲田2丁目
西早稲田駅260m |
| 京王線 |
2 |
世田谷 |
616,500
(1.8%) |
663,000
上北沢3丁目
上北沢駅390m |
570,000
粕谷1丁目
千歳烏山駅1.1㎞ |
| 西武新宿線 |
1 |
新宿 |
559,000
(2.0%)
|
|
下落合4丁目
下落合駅650m |
| JRりんかい線 |
1 |
品川 |
794,000
(3.8%) |
|
東品川1丁目
天王洲アイル駅850m |
| JR湘南新宿ライン |
1 |
品川 |
611,000
(4.3%) |
|
大井5丁目
西大井駅920m |
今後の地価動向と注目すべき点
私見として、今後の地価動向は、下落基調に入ると見ています。問題は、それが東京オリンピック後なのか、前なのか。また、その引き金は金利か、外国人投資家の売却か。さらに下落は急落か、徐々にか、といったことです。
前回も触れましたが、現在の銀座の土地価格は昭和のバブル期を超えた価格となっています。
この背景には、訪日外国人の消費以上に、日銀の「黒田バズーカ」と言われた金融緩和政策による影響が大きいと考えます。
日銀の発表によると、国内銀行の不動産業への貸出額が12兆円を超えています。これは、昭和のバブル期(平成元年10.4兆円)を大きく超えています。昭和のバブル期と違う点は、地価上昇エリアが大都市圏の、ごく一部の地域が中心となっていることです。前章の通り23区内でも地価上昇率には大きな格差があります。
土地価格の変動は、金融政策(金利や金融機関への指導)の動向とリンクしています。ここへきて、銀行の不動産業に対する貸出額の増加率(対前年同期比)に大きな変化が出てきました。
平成28年の四半期別では16.4%、25.0%、11.1%、9.7%と二桁台の増加率でしたが、平成29年第1四半期(1月~3月)は0.7%と大きく減少。不動産業への貸出額の縮小が始まったと見えます。
また、「アパートの作りすぎ」がニュースでも取り上げられていますが、既に、日銀の「金融システムレポート(2015年10月)」では、「貸家業向け貸出と与信管理」と題した囲み記事を掲載しています。これは、金融機関に対しての注意アナウンスとも受け取れます。
参照:金融システムレポート/日本銀行HP
さらに新築分譲マンションも、地価の上昇と建築費の高止まりで、分譲価格が高止まりしています。デベロッパーは分譲価格を低く抑えるために専有面積の縮小化をしており、これも昭和のバブル期と同じ手法です。
今回、地価下落が起きた時の怖さは、負のスパイラルです。すなわち地価下落の影響が、地価が上昇しなかった地域にまで及ぶことです。既に首都圏でも、人口減少や空き家問題で売却できない不動産が増えている中、地価下落の影響を受け、さらに売れない不動産が増える恐れがあります。不動産を「負動産」としないよう、注意をしていく時代に入りました。
三浦雅文(みうら まさふみ)米国国際資産評価士・不動産鑑定士
土地家屋調査士・行政書士・宅地建物取引主任士の資格も保有。1954年北海道生まれ。大学卒業後、測量、登記、鑑定、総合不動産会社を経て独立。多分野での経験を活かした不動産のアドバイスとオールラウンドの鑑定評価の業務を中心に活動中。
嬉しい口コミも
 40代男性(マンション売却)
40代男性(マンション売却)
 50代女性(マンション購入)
50代女性(マンション購入)
 40代男性(中古マンション購入)
40代男性(中古マンション購入)
 40代女性(住み替え:購入・売却)
40代女性(住み替え:購入・売却)
 50代男性(マンション売却)
50代男性(マンション売却)
 30代女性(マンション購入)
30代女性(マンション購入)
 60代男性(戸建て購入)
60代男性(戸建て購入)