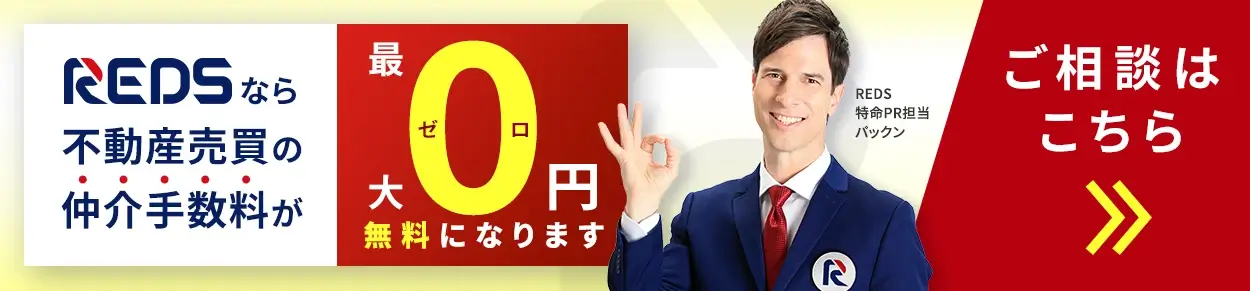不動産会社が売買仲介をしたときの報酬は「物件価格の3%+6万円」が上限と法律で定められています。2020年度の主要不動産流通会社の売買仲介実績(住宅新報社発表、主要不動産会社33社)によると、それを上回る数値が出ています。
その理由と不動産の仲介手数料の実態、コロナ禍に見舞われた2020年度の仲介業界の事情について解説します。

全体の7割超が減収、第1四半期の落ち込みが響く
アンケート結果によると、前年同期比で手数料収入が前年を上回ったのは、33社中9社しかなく、7割以上の会社は減収となっています。取扱高も同じく9社が、取扱件数は10社が前年よりも増加したにとどまっていて、不動産仲介の業界にとって2020年は厳しい一年となったようです。
2020年第1四半期(4~6月)は、コロナ禍により初の緊急事態宣言が発令され、多くの不動産会社が2カ月近くの休業や時短営業を実施しました。そのため減収減益の要因を「主に第1四半期の休店の影響」「外出自粛や営業自粛の影響」とする会社も多かったようです。
一方で、下期には各社とも回復傾向に転じました。第2四半期(7~9月)以降は、第3四半期(10~12月)で前年比プラス。コロナ禍によって在宅時間が増えたことから、住まいに対する関心が高くなり、新たな需要が喚起されました。テレワークの普及から、郊外や地方にある床面積が広い物件の需要が高まったことも特徴です。
上期にコロナ禍で仕入れを抑えていたことと、持ち家志向の高まりで、在庫不足・供給不足が顕著となったといわれています。
(レインズ マーケットウォッチ 2021年1-3月期 サマリーレポートより)
首都圏中古マンション *首都圏⇒東京・神奈川・埼玉・千葉
| 項目 |
成約 |
新規登録 |
| 件数 |
前年比 |
件数 |
前年比 |
| 2020年4-6月 |
6,428 |
66% |
45,020 |
89% |
| 2020年7-9月 |
9,537 |
101% |
44,044 |
86% |
| 2020年10-12月 |
9,789 |
112% |
41,004 |
84% |
| 2021年1-3月 |
11,295 |
112% |
40,320 |
78% |
| 2020年度計 |
37,049 |
98% |
170,388 |
84% |
首都圏中古戸建て
| 項目 |
成約 |
新規登録 |
| 件数 |
前年比 |
件数 |
前年比 |
| 2020年4-6月 |
2,638 |
78% |
15,356 |
85% |
| 2020年7-9月 |
3,664 |
108% |
15,264 |
85% |
| 2020年10-12月 |
3,711 |
124% |
14,586 |
81% |
| 2021年1-3月 |
4,207 |
126% |
13,340 |
70% |
| 2020年度計 |
14,220 |
109% |
58,546 |
80% |
首都圏中古市場 計
| 項目 |
成約 |
新規登録 |
| 件数 |
前年比 |
件数 |
前年比 |
| 2020年4-6月 |
9,066 |
69% |
60,376 |
88% |
| 2020年7-9月 |
13,201 |
103% |
59,308 |
86% |
| 2020年10-12月 |
13,500 |
115% |
55,590 |
84% |
| 2021年1-3月 |
15,502 |
116% |
53,660 |
76% |
| 2020年度計 |
51,269 |
101% |
228,934 |
83% |
上記の表は、東日本不動産流通機構(レインズ)により公表されている首都圏1都3県の中古住宅市場の動向を、筆者が作表したものです。マンション・戸建てともに、成約件数および新規登録数が4~6月に急落、その後7~9月以降は新規登録件数(販売在庫戸数)は伸び悩んだものの、成約件数はV字回復していて、不動産会社の収益分析がおおむね正しいことを示しています。
トップ3は健在、取扱高、件数、手数料も突出
2020年度もトップ3といわれる「三井不動産リアルティグループ(以下リハウス)」「住友不動産販売(スミフ)」「東急リバブル(以下リバブル)」の牙城は健在でした。4位以下を圧倒的に引き離しています。取扱高はトップ3が1兆円を大きく超えるのに対して、4位の野村不動産は約8,934億円にとどまり、5位のセンチュリー21グループは約6,417億円と、3位のスミフの約1兆2,260億円の約半額となっています。
この取扱高の差は、1件当たりの金額の差から生まれているのではありません。1件当たりの取扱高はトップ3平均4,061万円で、その他30社の平均4,510万円よりもむしろ約500万円も低いのです。それでなぜ突出して稼いでいるのかというと、取引量が段違いだからです。トップ3の合計年間取扱件数は9万9,264件で、全体の取扱件数の45%超。圧倒的な成約数でもって、その高い売り上げを支えているのです。
2020年度(21年3月期)主要不動産会社 売買仲介実績 集計表
| 企業・グループ名 |
トップ3 合計
(リハウス・スミフ・リバブル)
|
その他30社 計 |
合計 |
| 手数料収入 |
金額
(百万円) |
196,968 |
226,467 |
423,435 |
前期比
(%) |
▲8.1% |
▲3.2% |
▲5.5% |
1件当たり
手数料
(百万円) |
1.98 |
1.88 |
1.93 |
取扱高比
(%) |
4.89% |
4.16% |
4.47% |
| 取扱高 |
金額
(百万円) |
4,031,399 |
5,443,834 |
9,475,233 |
前期比
(%) |
▲8.1% |
▲6.0% |
▲6.9% |
1件当たり
取扱高
(百万円) |
40.61 |
45.10 |
43.08 |
| 取扱件数 |
件数 |
99,264 |
120,702 |
219,966 |
前期比
(%) |
▲7.2% |
▲1.0% |
▲3.9% |
大手不動産は取引の半分で欧米ではタブーの両手仲介?
2020年度の不動産会社の仲介手数料率(上記表では「手数料収入」の「取扱高比」で表示されています)は、33社平均で4.47%となっています。
不動産の仲介手数料は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」)により、取扱高が400万円以上の場合、その上限額は取扱高の「3%+6万円」と決まっています。
それなのにトップ3の手数料率は4.89%、その他の30社の手数料率平均も4.16%と、宅建業法の上限額を超えてしまっているように見えます。
この料率が成り立つ理由は、不動産取引の売買の仲介手数料は、売主と買主の双方から上限値までもらうことができるからです。これを「両手仲介」といいます。両手仲介に対して、売主または買主のどちらか一方の依頼者からのみ報酬を受け取る場合は「片手仲介」といいます。
欧州の一部の国の法律や米国の州法では、不動産会社は売主もしくは買主のどちらか一方の依頼しか受けることができず、両方から依頼を受けることは禁止されています。売主の利益と買主の利益は相反すると考えられるからです。当事者の両方の代理になっても当事者の利益を追求することができないため、禁止されているのです。日本の民法でも108条で「双方代理」は禁止されています。
しかし、日本の不動産取引を規定する宅建業法では「仲介業務は当事者の法律行為の代理ではなく、その成立を手助けする行為であるから、双方から依頼を受けることができる」という解釈がなされています。このため、多くの不動産会社は効率を上げるため、両手仲介を目指すようになります。
売買当事者の両方から仲介手数料をもらえる「両手仲介」を実現できると、不動産会社は最大で「6%+12万円」を報酬として受け取ることができます。単純に全取引の半分が「両手仲介」だとすれば「4.5%+9万円」の報酬を受け取ることができるという計算になり、上記の大手不動産会社が受け取った手数料率とほぼ一致しています。
コロナ禍で両手仲介が増え、不動産取引の荒廃が進んだ?
| |
トップ3 |
その他30社 |
合計 |
| 取扱高 |
2020年度 |
4,031,399 |
5,443,834 |
9,475,233 |
| 2019年度 |
4,386,682 |
5,794,019 |
10,180,701 |
| 前年比 |
92% |
94% |
93% |
| 手数料収入 |
2020年度 |
196,968 |
226,467 |
423,435 |
| 2019年度 |
214,309 |
233,938 |
448,247 |
| 前年比 |
92% |
97% |
94% |
| 手数料率 |
2020年度 |
4.89% |
4.16% |
4.47% |
| 2019年度 |
4.89% |
4.04% |
4.40% |
| 前年比 |
0.00% |
0.12% |
0.07% |
2020年度の不動産仲介実績を2019年度と比較すると、取扱高はトップ3もその他の会社も前年割れとなりました。一般に取扱高・成約件数がともに振るわないときには、会社としては少しでも収益減少の穴埋めをすることが求められます。その場合、唯一の収入減である手数料を少しでも上げるために、両手仲介を達成することを営業目標としてノルマ化していると考えられます。
トップ3の手数料率はすでに高い水準であるため上昇は見られませんでしたが、その他の30社では手数料率が前年比で0.12ポイント上昇しています。上昇幅は小さく見えますが、金額で見ると6,532億円も上昇しています。片手取引では手数料率は3%+6万円で頭打ちになるはずですから、両手取引が促進されたと推測できます。
しかし、不動産会社が自社の収益を重視しすぎると、多くの弊害を生みます。その一つが「囲い込み」という商慣習です。これは売却を依頼された物件を、他の不動産会社による問い合わせなどには応じずに非公開とし、自社の情報網・顧客網でのみ買い手を探してマッチングさせることをいいます。
こうすると、他の不動産会社経由の顧客の購入希望は門前払いとなり、売主にとっては売却機会が損なわれることになります。売主・買主双方の利益を損ない、公正な市場も形成されません。客に迷惑をかけて平然としているのです。
さらに、こうして囲い込みを極端に実施して意図的に売れ残りにしてしまい「売れ残ったので値下げしましょう」と売主に持ちかけ、物件の価格を下げさせることすらやるのが不動産会社です。これを業界内では「値こなし」といいます。
買い取り業者に、業者がリフォームして売り出すときにまた仲介を専任で依頼してもらう「専任返し」を条件として、物件を「こなし」て安く買いとってもらう、というように両手仲介から端を発してどんどんアコギな手口が行われています。残念ながら、こうした用語がはびこるくらい、不動産業界では両手仲介にまつわる不透明な手口が蔓延しているといえます。
不動産仲介の問題に意識の高い会社を選ぼう
大手不動産会社は、全国ネットで駅前の一等地に支店を設け、独自の顧客管理システムと物件検索サイトを構築し、テレビや雑誌、ネットでイメージ広告を打ち、優秀な人材を確保し、人事労務体制も整備しています。2020年はウイズコロナ時代のために率先して新たなVR技術を導入した内覧システムやテレワークも洗練させていかなければなりませんでした。
要するに、大手はコストが高いのです。もろもろのコストを手数料収入の上限額が定められているなかで可能な限り回収するためには、不動産市場の寡占化を進め、手数料率向上のために両手仲介の比率を高めるほかないのでしょう。しかし、それでは「囲い込み」や「値こなし」が横行する一方です。
一般消費者が安心できる不動産の取引環境を形成するためにも、どういった手法が適切なのか、常に問題意識を持って取り組み続けることが、不動産市場に身を置く業者の責任であると思えます。消費者のみなさんも、こうした問題意識を持った不動産業者に仲介を任せたほうが後悔のない取引ができることでしょう。
早坂 龍太(宅地建物取引士)
龍翔プランニング代表取締役。北海道大学法学部卒業。石油元売会社勤務を経て、北海道で不動産の賃貸管理、売買・賃貸仲介、プランニング・コンサルティングを行う。
嬉しい口コミも
 40代男性(マンション売却)
40代男性(マンション売却)
 50代女性(マンション購入)
50代女性(マンション購入)
 40代男性(中古マンション購入)
40代男性(中古マンション購入)
 40代女性(住み替え:購入・売却)
40代女性(住み替え:購入・売却)
 50代男性(マンション売却)
50代男性(マンション売却)
 30代女性(マンション購入)
30代女性(マンション購入)
 60代男性(戸建て購入)
60代男性(戸建て購入)