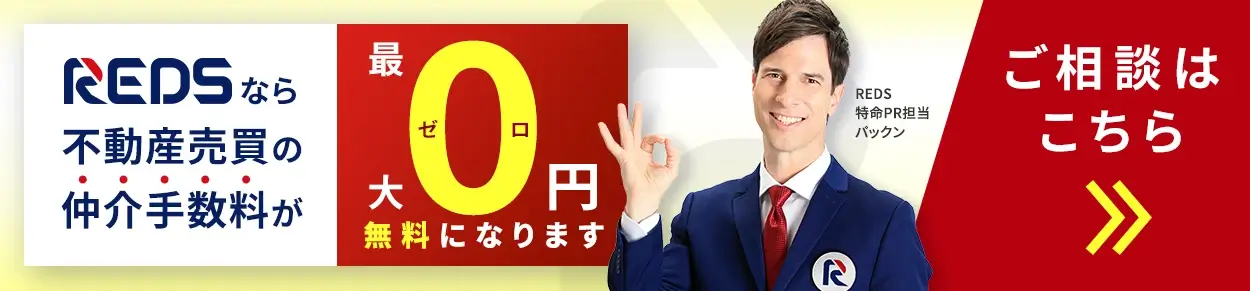時代を読み、常に一歩先を行くマンション選びの視点について、不動産事業プロデューサーの牧野知弘氏に引き続き話をうかがいました。
(取材・構成 不動産のリアル編集部)

牧野知弘氏
2020年代には交通利便性は重視されなくなる
――現時点では交通利便性が重視された住まい選びが進んでいますが、先生はご著書で「働き方改革が進み、やがて交通利便性を考えなくていい時代が来る」とのご見解です。それはいつごろになりそうでしょうか。
牧野 難しい質問ですが、意外と遠くない将来だと思います。2020年代にはそうなるかもしれません。というのも、職場に集まって仕事をしなくてもよいという流れがここ数年でも急速に進んでいるからです。いちばん典型的な例が、多くの大企業で導入されているフリーアドレス制。社員1人に机が1つ用意されているというスタイルがなくなってきました。私がいる最も保守的な不動産業界であってもその傾向は進んでいて、中堅不動産会社の役員が多数集まった会合で聞いたところ、半数以上の役員がフリーアドレスだとお答えになりました。ある専務取締役は、専務なのに机がなく、タイミングによっては座るところがないと嘆いていました。
ほかにも名だたる大企業のほとんどで、営業系のセクションはすでにフリーアドレスです。また副業を認めたり、残業規制をしたり、有休取得を義務化したりを進めています。これは、社員を会社に縛り付けるのではなく、むしろ、生産性を高めるためのものです。取引先の近くで仕事をして、会社にネットで報告を済ませたら、そのまま自宅に帰るほうが、拘束時間の短縮になりますね。
これを後押しするのがアメリカ企業『WeWork』に代表されるコワーキングスペースです。会社はサテライトオフィスを構えなくても、WeWorkの会員になれば、そこを自由に使って仕事ができます。埼玉県担当の人は、これまでのように本社のある大手町にわざわざ行かなくても、埼玉県の中のWeWorkで仕事をしてそのまま帰る。こんな仕事のやり方はもう2020年代後半には主流になるのではないでしょうか。
――それでは将来、都心にオフィスが余るようになりませんか
牧野 私は余るのではないかと悲観しています。現在、大手デベロッパーは都心にオフィスビルを大量に作っていますが、「大丈夫かな?」と感じますね。もちろん職種や業種によって事情は違うでしょう。でも私も小さな会社を経営していますが、オフィスのコストというものは実に大きく張り付いた固定費なんですね。今までは1人あたり3坪目安で借りなければいけなかったのが、フリーアドレスだと3分の1で済んでしまうようになる。そうなると、経営者は必ず経費削減の方向で考えます。WeWorkの会員になって、会費として処理すると、固定費ではなく変動費として処理できるのも大きいでしょう。
「会社に社員がいないと不安」というのはオールド世代そのもので、今の30代から40代の人が会社の要職につくころには「別にこれでいい」となるはずです。今だってスカイプで会議できますからね。2年前に仕事でベトナムに行ったときに、チーフリーダーが香港で飛行機に乗り損ねたことがあります。彼がいなかったら仕事にならないのではと思いましたが、スマートフォンのスカイプで会議ができましたし、資料も送ってもらいました。こんなトラブルがあっても大丈夫なようになっています。
こういう仕事のやり方に慣れて、違和感を覚えない社員が管理職になった瞬間、大手町や日本橋にある企業はホールディングスの一部機能だけを残して、社員を放し飼いにするようになるのではないでしょうか。出版大手の「KADOKAWA」は所沢に本社を移転します。「所沢なんて通えない」という人もいましたが、一部の部署を除き、本社に通わなくてもよいそうです。
こうなるとサラリーマンにとって、通勤時間や会社との往復の時間は大幅に削減され、そうなればなるほど、会社への交通利便性は関係なくなります。そうなると、ムーミンパークのある埼玉県飯能市が意外と暮らしやすい、なんてことになるかもしれませんね。
私の知人が神奈川県三浦市に住んでいたことがあり、新橋まで通うのは2時間もかかって大変だと話していました。でもネット機器を駆使すれば、月に1回だけ新橋にきてあとは三浦で働く、なんてこともできるようになります。そうなると、三浦のあの環境のいい海沿いの地域で、朝サーフィンしてからコワーキングスペースで働いて、保育園へ子供を迎えに行って帰る、なんていう若い夫婦が出てきても不思議ではない。
交通利便性がすべてという住まいの選び方は、あと4~5年くらいで変わってくるのではないでしょうか。
今後の地方都市に求められるもの
――住まい選びの基準が交通利便性でなくなったとき、ライフスタイルの変化とともに、街のあり方も変わってくることになりますね
牧野 それぞれの地域に求められることが「会社に通いやすいですか?」から「一日いても楽しいですか?」となるでしょう。通勤がなくなるほどフリータイムが増え、買い物が楽しめるか、ちょっとしたエンターテイメントがあるか、子育てによいかなどに関心が向かうからです。歩いていて楽しいとか、店がいっぱいあるかとか。これまではイトーヨーカドーのような大型店舗が1つあればよかったかもしれませんが、これからはそれだけでは満足されません。
たとえば逗子は完全に通勤圏から外れた都市ですが、これまで述べてきたような生活が成り立つようになると、「24時間滞在して住むにはとってもいい街」との評価に変わります。海が近くて空気がきれい。朝起きてサーフィンしてから地元で仕事をして、なんて生活になると逗子の評価は上がるでしょう。
そうなったとき、埼玉県では大宮や浦和とはまた別に、思いもつかなかったようなところが人気になるかもしれませんね。
一般人にはお勧めしない資産アップ狙いのマンション選び
――マンションを買うときに、資産価値が上がること、もしくは下がらないことを最優先する人も多いと思います。東京という都市は、かつては膨張し、東京から多摩へと広がっていったのですが、今後は人口が減って収縮するのではないでしょうか。そんなとき、東京からあまりに離れたところに買ってしまうと、売るに売れない「負動産」になってしまうのではないかという懸念を持つ人も多いと思われます。どのあたりに買うのが適正なのでしょうか。みなさんそれぞれの事情があり、答えは一つではないことは百も承知でうかがいます
牧野 まず、マンションの資産性を語ることができるエリアというのは、非常に限られています。たとえば東京の「3A地区」と言われる青山、麻布、赤坂。ここには投資用のマネーが入りますので、資産性の議論をしてもいいと思います。
このほか、たとえば大宮の駅前のタワーマンションとか、浦和の文教地区にある低層の高級マンションは資産性が保たれます。ところが半端なエリアのマンションや、東京でも投資用のマネーが入らないところ、例えば多摩などは相当に厳しいと思います。多摩の中で唯一資産性がいいのは立川の近辺くらいですね。それ以外はちょっと厳しくなると思います。
資産性だけに着目してマンションを買うことを検討されるなら、ヒントは投資マネーが来るか来ないかです。投資マネーは国内外から流れ込みます。でも投資マネーは移り気なので、引くときはいっせいに引きます。近い記憶だとリーマンショックのときですね。このように価格が乱高下しますので、それにお付き合いができるためには、当たり前ですけど、過剰に借金をせずに、しっかりした資金計画の中で持っていれば、市況が軟化したときにもあわてて売らずにすむでしょう。また、そのうちに投資マネーが入ります。投資マネーは世界中で循環しているので、また数年後に入ってきたら上がります。そういうエリアだったら資産性重視で買われた方がいいと思います。
そういうマネーが入ってくるエリアと入ってこないエリアは、調べれば分かります。昔のように首都圏の人口がどんどん増えて、実需で資産価値が上がるなんてことは、今後はありません。投機マネーや投資マネーの流れを見て、「資産性が上がったね」と楽しめるでしょう。
ただ、一般の方がやってはいけません。難しいんですよ。不動産を商売にしている自分でも、できるかどうか分からないくらいですから。
たとえば2013年ごろにマンションを買った人の多くが、「今売るとキャピタルゲインが出る」と言います。しかし、それは単なる結果論ですよ。全体の相場が上がっていったのと、建築費が4~5割アップしたので、新築につられて中古の相場も上がった結果、たまたま得したというだけの話です。また、一部の湾岸エリアで中国をはじめとするアジアマネーが2015年くらいから大量に入ったためで、たまたま運がよかっただけ。でも、そういう方にも私は「東京五輪の前には売りなさい」とアドバイスしています。そこから先は本当の実力が出てきてしまいますので。
そういった意味で、私はマンションを買う人に必ずこう言います。「目的は投資ですか、生活ですか」と。答えが生活なら、「会社に通いやすい」というのが重要な要素でしょう。大宮や浦和は首都圏でも割安で、通勤圏としては利便性が高い。しかも街にいろんな機能が全部備わっているので、もっと評価されていい。その中で、将来的に倍になるとかいう期待感で買うことは算数と理科くらい違うことです。
=(下)に続く
■牧野知弘氏(オラガ総研株式会社 代表取締役)
東京大学経済学部卒業。第一勧業銀行(現:みずほ銀行)、ボストンコンサルティンググループを経て1989年、三井不動産入社。数多くの不動産買収、開発、証券化業務を手がけたのち、三井不動産ホテルマネジメントに出向し、ホテルリノベーション、経営企画、収益分析、コスト削減、新規開発業務に従事する。2006年、日本コマーシャル投資法人執行役員に就任しJ-REIT(不動産投資信託)市場に上場。2009年、株式会社オフィス・牧野設立およびオラガHSC株式会社を設立、代表取締役に就任。2015年にオラガ総研株式会社を設立、代表取締役に就任する。著書に『なぜ、町の不動産屋はつぶれないのか』『空き家問題』『民泊ビジネス』(いずれも祥伝社新書)『老いる東京、甦る地方』(PHPビジネス新書)『こんな街に「家」を買ってはいけない』(角川新書)『2020年マンション大崩壊』『2040年全ビジネスモデル消滅』(ともに文春新書)、『街間格差 オリンピック後に輝く街、くすむ街』(中公新書ラクレ)などがある。
嬉しい口コミも
 40代男性(マンション売却)
40代男性(マンション売却)
 50代女性(マンション購入)
50代女性(マンション購入)
 40代男性(中古マンション購入)
40代男性(中古マンション購入)
 40代女性(住み替え:購入・売却)
40代女性(住み替え:購入・売却)
 50代男性(マンション売却)
50代男性(マンション売却)
 30代女性(マンション購入)
30代女性(マンション購入)
 60代男性(戸建て購入)
60代男性(戸建て購入)